存在することの真理――「ストーリー・ストーリー」の霧子を読む
初出:2020年5月4日Privatterに投稿
初出時より一部修正
◇はじめに
この文章は、アンティーカのイベントシナリオ「ストーリー・ストーリー」の中の、霧子の発言を読解するものです。
読解するのは、主に2箇所の発言です。1つ目は家出中のマイクロバスの中での発言。そして2つ目は、エンディングコミュで「生きてることは物語じゃない」「わたしたちがわたしたちならどこにも嘘なんて」と言った発言。この2つが主題になります。
読解するにあたって、イベントsSR【ドゥワッチャラブ!】での千雪の言葉の読解を参照します。そして、家出までの経緯を簡単に要約し、アンティーカが陥った問題を明らかにします。その後で霧子の発言を読解します。そこで明らかになるのは、霧子の「存在」(するということ)に対する独特の感度です。
よろしければお付き合いください。
目次
◇はじめに
◇シネマじゃなくても
◇経緯と問題
◇霧子の提案
◇物語じゃない
◇わたしたちがわたしたちなら
◇存在することの真理
◇存在論者幽谷霧子
◇おわりに
◇シネマじゃなくても
まずは【ドゥワッチャラブ!】の1つめのコミュを見てみたいと思う。このコミュでは、現実の生活とフィクションとの関係の問題が描かれており、リアリティショーに関する物語である「ストーリー・ストーリー」を読む際に参考になると思われるからである。
千雪は書かれた記事をそらんじることができるほど、雑誌アプリコットに憧れていた。その記事にはこう書かれていた。
「エンドロールが夕焼けのように去って音楽が最後の吐息をもらした後も続いていたら素敵じゃない? シネマの中で見ていた恋が」
これは、シネマの中で描かれていた恋みたいな恋を、シネマの外側の現実世界でもできたとしたら素敵じゃない?と言っているように読める。私たちは現実世界に生きているが、特に恋愛などについては、どのようにそれをすればいいのかフィクションから学ぶことが少なくない(フィクションのあの恋みたいな恋がしたい、と憧れるように)。私たちは現実世界を生きながら、フィクションの物語に憧れ、フィクションの物語を引用し、フィクションの物語を真似るようにして生きているのである。現実はすでにフィクション化されている。
けれども、千雪はあれほど憧れたアプリコットの世界から「卒業」して飛び出していく。そして千雪はこう言う。
「――エンドロールは流れないし、音楽も終わらない――私たちは、続いていく。でも。素敵だね。シネマじゃなくても……――」
エンドロールは流れない。終わりがないというのはアルストロメリアにつきまとうイメージだ。シネマなどのフィクションにはいずれ終わりがくる(エタらなければ)。けれど現実は続いていく。シネマみたいにエンドロールが流れることはない。千雪はこうして、フィクション化された現実から、現実そのものへと抜け出したのだ。見ていた夢から覚めるように。
シャニマスは過去にこのように現実とフィクションの問題について書いていた。ここではフィクションの外へと飛び出す、という方向性になる。
(詳しくはふせったーに投稿した記事を見てください → 「幸福よりもっと幸福であること――アルストロメリアの幸福論について」https://fusetter.com/tw/CKkPGret#all)
◇経緯と問題
それではアンティーカの「ストーリー・ストーリー」の話に移ろう。ここではまずアンティーカが陥った問題までの経緯を要約し、それからその問題がどんな問題だったかを確認したい。
アンティーカの「ストーリー・ストーリー」は、いわゆるリアリティショーと呼ばれる種類の番組のお仕事のお話だった。メンバーはちょっとしたルールのもとで生活し、カメラは生活する5人を追いかける。
「リアリティ」とは言うが、これはテレビ番組なので面白くなければならないから、ただただ生活するさまを映して放映する、というわけにはいかない。しかしただの普通の生活が、テレビ番組として成立するほど面白くなるわけではない。そこで番組制作側が要求するのが、テレビ番組として放映するに耐える物語である。「リアリティ」は「リアル」ではないということを思い起こすべきかもしれない。
番組制作側は、カメラに収められたアンティーカの生活の様子を恣意的に編集し、ある物語を作り出した。その番組自体は視聴者に好評だったが、その物語はアンティーカの実際の生活の内容からは乖離しており、アンティーカのメンバーが意志したものとは全く異なっていた。編集して作り出された物語は、事実と異なる虚偽だったのである。
アンティーカメンバーは窮地に立たされる。番組制作側は、視聴に耐えうる物語を求めている。物語がなければ、視聴者が満足するような番組として成立しない。しかし番組制作側が編集する物語は現実から乖離した虚偽のものとなりうる。だがアンティーカメンバーとしてはこのまま番組を終わらせたくはない。
これがアンティーカが陥った問題だった。
◇霧子の提案
その打開策を提示したのが霧子だった。「ストーリーをつくる」、これが霧子の出した打開策である。番組制作側に物語を作られるくらいなら、自分たちの手で先に物語を作ればいい。
だが咲耶は、それでも「勝手に作り替えられるリスクは消えないと言う」。それに対して霧子は、こう答えた。
「どこかに…… 嘘じゃないお話が……なきゃ…… 嘘のアンティーカが…… 作られる……ことより…… 本当のアンティーカが…… ない……方が……」
これが今回読解したい1つ目の霧子の発言である。
本当のアンティーカがない」というのは、番組制作側の恣意的な編集によって物語を作られて、カメラの前でいつも通りの振る舞いができなくなってしまったメンバーの様子を指す。霧子はここで2つのことを提案している。
1つ目は、番組制作側が物語を要求してるなら、自分たちで作ってしまえばいい。それが番組制作側を満足させられれば、問題はクリアできる。
2つ目は、たとえ番組制作側を満足させられず、恣意的な編集をされてしまうとしても、自分たちがいつも通りの「本当の」アンティーカでいられることが大事だ。そもそも誰が物語をつくるとしても、「嘘じゃないお話」がどこかに必要である。カメラの前で何もできなくなって普段通りの「本当の」自分たちを失ってしまったら、番組制作側や視聴者に伝わるべきものも何もなくなってしまう。
1つ目の提案は、番組制作側が作る物語に対して、別の物語をこちらで提示しようということだ。物語の外側へと出ようというのではなく、別の物語を自ら提示するのである。
そして2つ目の提案は、物語にかかわらず、普段通りの「嘘じゃないお話」の「本当の」アンティーカが必要だということだ。
◇物語じゃない
この2つ目の「本当の」の意味が問題になる。それはどういう意味なのだろうか。
霧子は後日こう言っている。
「生きてることは…… 物語じゃ…… ないから…… わたしたちがわたしたちなら…… ほんとは…… どこにも嘘なんて……」
これが今回読解したい2つ目の発言である。
番組制作側が恣意的に編集した初回放送のあの物語は、事実と異なっている。虚偽である。それに対し、虚偽にならない物語を、真実の物語をアンティーカの5人は自らで提供しようとした。
それは自らが描いた物語に、自らを合わせるような部分もある。そのためにカメラがないところでも摩美々はパンをくわえて走ろうとする。「カメラの外でも嘘じゃないストーリーにする」と摩美々は言う。それに対する応答が上の霧子の言葉だ。
「生きてることは物語じゃない」。生きるということはただ人間として存在しているということだ。そしてそれは物語ではない。つまり存在するということはただ存在するというだけであって、そこには物語はないのである。
物語であるならば、そこには真偽の問題が発生する。事実と対応しているかどうかという問題だ。物語は、あるものがどんなものであるか、それにはどんな背景があるか、それはどんなことをするか、そういったことを伝える。それは事実と対応していて正しい(真)かもしれないし、事実と対応しておらず間違っている(偽)かもしれない。だから物語には真偽の問題が発生する。
だが、生きていること、存在しているということは、物語ではない。ただ存在しているということは、それが何であるかなどを伝えない。それはただ存在するのみである。だから存在しているということには真偽の問題が介入しないのだ。真偽の問題とは無関係なのである。ただそれは存在している、そのことは真でも偽でもない。ただ存在しているのみである。
「存在」に対する霧子の独特の感覚がここにもうかがえる。
◇わたしたちがわたしたちなら
しかし真偽の問題が介入しない、真偽とは無関係なのだとすると、「本当の」アンティーカをどこで担保するのか?
霧子の発言の続きが重要だ。霧子は、「わたしたちがわたしたちなら、ほんとはどこにも嘘なんて(ない)」と言っている。これを普通に解釈すると、「わたしたちが〈いつも通りの〉わたしたちなら」という風に〈 〉の部分を補って読みたくなってしまう。
確かに、家出のときの霧子の発言には、「いつも通りのアンティーカ」といったニュアンスが感じられた。だがここで霧子は、〈 〉の中の言葉を言っていない。それに、「ほんとは」と言って、以前の自分の発言を改めようとしているように読める。
そのため、霧子の言葉をここでは文字通り読んでみたい気持ちに駆られる。その駆り立てに従って文字通りに読んでみよう。それは、「わたしたちがわたしたちならどこにも嘘なんて(ない)」と言っている。これは、「AがAであるということは偽ではない」、というようなことを言っているように読めるのだ。「わたしたちがわたしたちであるということは偽ではない」。ここに「本当の」の「ほんと」の意味があるのではないかと思う。
◇存在することの真理
霧子は、「存在するということは物語じゃない」と言った(と私は読む)。存在そのものは、物語に左右されない。ある存在はただ存在するだけだ。それはいつも通りかどうかとか、いつもと違っているとか、そういうこととは関係がない。いつも通りだろうと、いつも通りじゃなかろうと、演出されていようと、素でやっていようと、ある存在はただその存在である。
そしてその存在そのものの同一性は、どうであったとしても全く変わらない。霧子の「どこにも」は、恣意的に編集された虚偽の物語でも、自分たちが提示する真実の物語でも、どれであったとしても、という風に読める。
「わたしたちがわたしたちなら」というのは、そういう風に読める言葉だと思う。いつも通りだろうと、いつも通りじゃなかろうと、恣意的に編集されて物語を作られようと、意図した通りに映像が作られようと、「わたしたち」は「わたしたち」である。それによって存在の同一性が変わるわけではない。
それゆえ霧子は「どこにも嘘なんて(ない)」と言ったのである。「わたしたちがわたしたちなら」、それは「嘘」ではない。「嘘」ではありえない。たとえ恣意的に編集された物語であったとしても。そうだとしても、AがAであるという同一性が真でないはずがない。そこに真理が開かれる。
この真理は、事実と対応しているという真理とは違うタイプの真理である。事実と対応していようといなかろうと、AはAであるという同一性は真理だからだ。
だからこそ霧子は「どこにも」(嘘なんてない)と言えたのである。番組制作側が恣意的に編集して作り出した物語も、アンティーカが自ら提示する物語も、それらは物語という点では同列に置かれる。それらは共に物語であり、それゆえ共通に真偽の問題にさらされる。番組制作側が恣意的に編集した物語が虚偽であるとして、実はアンティーカが自ら提示する物語も、それが真実であるとは限らないのである。
そのことに気がつくとき、霧子の言う「どこにも」(嘘なんてない)という言葉が効果を発揮し始めるのである。それは、真偽が問題になる物語とは無関係なところで、ちゃんと真理を見出すことができるのだ、という意味なのだ。どんな物語であっても、ちゃんと「本当の」アンティーカを示すことができるのである。
大胆に、霧子の言葉を置き換えてみよう。「ある存在者が存在するということは物語ではない。ある存在者が当のその存在者であるといいう同一性は偽ではなく真である」というわけである。
このようにして、アンティーカそのものの存在の真理性を見出すことができた。「本当の」アンティーカは、ただそこに存在しているのだ。アンティーカがアンティーカとして存在するということ、ただそれだけで、そこにアンティーカの存在の真理が開かれるのである。
◇存在論者幽谷霧子
霧子の「存在」に対するこうした感度には、哲学的なセンスが感じられる。ただし、「霧子は哲学をしている」とはっきり言うつもりはない。けれども、哲学が始まるところにある感度と、霧子のこうした感度には、共通しているものが感じられるのだ。一般に「哲学」とされているものではなく、生の〈哲学〉とでも言うべきなにか。そうしたものならば霧子はしていると言えるかもしれない。
そして実は幽谷霧子は存在論者である、と大胆に言ってみたくなるのである。私の中のイメージでは少なくともそうである。この話題についてはいずれどこかで書けたらいいなと思う。
◇おわりに
千雪の場合は、自分の生活を枠づけていたアプリコットから「卒業」することで、現実へと抜け出した。フィクションに憧れて、フィクションのように生きるのではなく、その外側で現実そのものの中で生きることを選んだ。
霧子(とアンティーカ)は、現実がフィクション化されようとも、アンティーカがアンティーカであるという同一性が偽になりえないというところから真実を開く。
一方は、フィクションの外側へと出る方向で現実を目指し、他方は、フィクションの中においても存在者の同一性を見出すことで真実の点を開く。前者が夢から覚めることと類比的なら、後者は夢の中であったとしても真実を開くことで夢と現実の差異を超えてしてしまうのである。
シャニマスという一つの作品の中で、フィクションと現実に対してこれほどまでに異なるアプローチを描き出すことができるという点に、驚愕しないではいられない。いったいどうやってイベントストーリーを作っているんだ……
*Privatterの投稿は削除済み
初出時より一部修正
◇はじめに
この文章は、アンティーカのイベントシナリオ「ストーリー・ストーリー」の中の、霧子の発言を読解するものです。
読解するのは、主に2箇所の発言です。1つ目は家出中のマイクロバスの中での発言。そして2つ目は、エンディングコミュで「生きてることは物語じゃない」「わたしたちがわたしたちならどこにも嘘なんて」と言った発言。この2つが主題になります。
読解するにあたって、イベントsSR【ドゥワッチャラブ!】での千雪の言葉の読解を参照します。そして、家出までの経緯を簡単に要約し、アンティーカが陥った問題を明らかにします。その後で霧子の発言を読解します。そこで明らかになるのは、霧子の「存在」(するということ)に対する独特の感度です。
よろしければお付き合いください。
目次
◇はじめに
◇シネマじゃなくても
◇経緯と問題
◇霧子の提案
◇物語じゃない
◇わたしたちがわたしたちなら
◇存在することの真理
◇存在論者幽谷霧子
◇おわりに
◇シネマじゃなくても
まずは【ドゥワッチャラブ!】の1つめのコミュを見てみたいと思う。このコミュでは、現実の生活とフィクションとの関係の問題が描かれており、リアリティショーに関する物語である「ストーリー・ストーリー」を読む際に参考になると思われるからである。
千雪は書かれた記事をそらんじることができるほど、雑誌アプリコットに憧れていた。その記事にはこう書かれていた。
「エンドロールが夕焼けのように去って音楽が最後の吐息をもらした後も続いていたら素敵じゃない? シネマの中で見ていた恋が」
これは、シネマの中で描かれていた恋みたいな恋を、シネマの外側の現実世界でもできたとしたら素敵じゃない?と言っているように読める。私たちは現実世界に生きているが、特に恋愛などについては、どのようにそれをすればいいのかフィクションから学ぶことが少なくない(フィクションのあの恋みたいな恋がしたい、と憧れるように)。私たちは現実世界を生きながら、フィクションの物語に憧れ、フィクションの物語を引用し、フィクションの物語を真似るようにして生きているのである。現実はすでにフィクション化されている。
けれども、千雪はあれほど憧れたアプリコットの世界から「卒業」して飛び出していく。そして千雪はこう言う。
「――エンドロールは流れないし、音楽も終わらない――私たちは、続いていく。でも。素敵だね。シネマじゃなくても……――」
エンドロールは流れない。終わりがないというのはアルストロメリアにつきまとうイメージだ。シネマなどのフィクションにはいずれ終わりがくる(エタらなければ)。けれど現実は続いていく。シネマみたいにエンドロールが流れることはない。千雪はこうして、フィクション化された現実から、現実そのものへと抜け出したのだ。見ていた夢から覚めるように。
シャニマスは過去にこのように現実とフィクションの問題について書いていた。ここではフィクションの外へと飛び出す、という方向性になる。
(詳しくはふせったーに投稿した記事を見てください → 「幸福よりもっと幸福であること――アルストロメリアの幸福論について」https://fusetter.com/tw/CKkPGret#all)
◇経緯と問題
それではアンティーカの「ストーリー・ストーリー」の話に移ろう。ここではまずアンティーカが陥った問題までの経緯を要約し、それからその問題がどんな問題だったかを確認したい。
アンティーカの「ストーリー・ストーリー」は、いわゆるリアリティショーと呼ばれる種類の番組のお仕事のお話だった。メンバーはちょっとしたルールのもとで生活し、カメラは生活する5人を追いかける。
「リアリティ」とは言うが、これはテレビ番組なので面白くなければならないから、ただただ生活するさまを映して放映する、というわけにはいかない。しかしただの普通の生活が、テレビ番組として成立するほど面白くなるわけではない。そこで番組制作側が要求するのが、テレビ番組として放映するに耐える物語である。「リアリティ」は「リアル」ではないということを思い起こすべきかもしれない。
番組制作側は、カメラに収められたアンティーカの生活の様子を恣意的に編集し、ある物語を作り出した。その番組自体は視聴者に好評だったが、その物語はアンティーカの実際の生活の内容からは乖離しており、アンティーカのメンバーが意志したものとは全く異なっていた。編集して作り出された物語は、事実と異なる虚偽だったのである。
アンティーカメンバーは窮地に立たされる。番組制作側は、視聴に耐えうる物語を求めている。物語がなければ、視聴者が満足するような番組として成立しない。しかし番組制作側が編集する物語は現実から乖離した虚偽のものとなりうる。だがアンティーカメンバーとしてはこのまま番組を終わらせたくはない。
これがアンティーカが陥った問題だった。
◇霧子の提案
その打開策を提示したのが霧子だった。「ストーリーをつくる」、これが霧子の出した打開策である。番組制作側に物語を作られるくらいなら、自分たちの手で先に物語を作ればいい。
だが咲耶は、それでも「勝手に作り替えられるリスクは消えないと言う」。それに対して霧子は、こう答えた。
「どこかに…… 嘘じゃないお話が……なきゃ…… 嘘のアンティーカが…… 作られる……ことより…… 本当のアンティーカが…… ない……方が……」
これが今回読解したい1つ目の霧子の発言である。
本当のアンティーカがない」というのは、番組制作側の恣意的な編集によって物語を作られて、カメラの前でいつも通りの振る舞いができなくなってしまったメンバーの様子を指す。霧子はここで2つのことを提案している。
1つ目は、番組制作側が物語を要求してるなら、自分たちで作ってしまえばいい。それが番組制作側を満足させられれば、問題はクリアできる。
2つ目は、たとえ番組制作側を満足させられず、恣意的な編集をされてしまうとしても、自分たちがいつも通りの「本当の」アンティーカでいられることが大事だ。そもそも誰が物語をつくるとしても、「嘘じゃないお話」がどこかに必要である。カメラの前で何もできなくなって普段通りの「本当の」自分たちを失ってしまったら、番組制作側や視聴者に伝わるべきものも何もなくなってしまう。
1つ目の提案は、番組制作側が作る物語に対して、別の物語をこちらで提示しようということだ。物語の外側へと出ようというのではなく、別の物語を自ら提示するのである。
そして2つ目の提案は、物語にかかわらず、普段通りの「嘘じゃないお話」の「本当の」アンティーカが必要だということだ。
◇物語じゃない
この2つ目の「本当の」の意味が問題になる。それはどういう意味なのだろうか。
霧子は後日こう言っている。
「生きてることは…… 物語じゃ…… ないから…… わたしたちがわたしたちなら…… ほんとは…… どこにも嘘なんて……」
これが今回読解したい2つ目の発言である。
番組制作側が恣意的に編集した初回放送のあの物語は、事実と異なっている。虚偽である。それに対し、虚偽にならない物語を、真実の物語をアンティーカの5人は自らで提供しようとした。
それは自らが描いた物語に、自らを合わせるような部分もある。そのためにカメラがないところでも摩美々はパンをくわえて走ろうとする。「カメラの外でも嘘じゃないストーリーにする」と摩美々は言う。それに対する応答が上の霧子の言葉だ。
「生きてることは物語じゃない」。生きるということはただ人間として存在しているということだ。そしてそれは物語ではない。つまり存在するということはただ存在するというだけであって、そこには物語はないのである。
物語であるならば、そこには真偽の問題が発生する。事実と対応しているかどうかという問題だ。物語は、あるものがどんなものであるか、それにはどんな背景があるか、それはどんなことをするか、そういったことを伝える。それは事実と対応していて正しい(真)かもしれないし、事実と対応しておらず間違っている(偽)かもしれない。だから物語には真偽の問題が発生する。
だが、生きていること、存在しているということは、物語ではない。ただ存在しているということは、それが何であるかなどを伝えない。それはただ存在するのみである。だから存在しているということには真偽の問題が介入しないのだ。真偽の問題とは無関係なのである。ただそれは存在している、そのことは真でも偽でもない。ただ存在しているのみである。
「存在」に対する霧子の独特の感覚がここにもうかがえる。
◇わたしたちがわたしたちなら
しかし真偽の問題が介入しない、真偽とは無関係なのだとすると、「本当の」アンティーカをどこで担保するのか?
霧子の発言の続きが重要だ。霧子は、「わたしたちがわたしたちなら、ほんとはどこにも嘘なんて(ない)」と言っている。これを普通に解釈すると、「わたしたちが〈いつも通りの〉わたしたちなら」という風に〈 〉の部分を補って読みたくなってしまう。
確かに、家出のときの霧子の発言には、「いつも通りのアンティーカ」といったニュアンスが感じられた。だがここで霧子は、〈 〉の中の言葉を言っていない。それに、「ほんとは」と言って、以前の自分の発言を改めようとしているように読める。
そのため、霧子の言葉をここでは文字通り読んでみたい気持ちに駆られる。その駆り立てに従って文字通りに読んでみよう。それは、「わたしたちがわたしたちならどこにも嘘なんて(ない)」と言っている。これは、「AがAであるということは偽ではない」、というようなことを言っているように読めるのだ。「わたしたちがわたしたちであるということは偽ではない」。ここに「本当の」の「ほんと」の意味があるのではないかと思う。
◇存在することの真理
霧子は、「存在するということは物語じゃない」と言った(と私は読む)。存在そのものは、物語に左右されない。ある存在はただ存在するだけだ。それはいつも通りかどうかとか、いつもと違っているとか、そういうこととは関係がない。いつも通りだろうと、いつも通りじゃなかろうと、演出されていようと、素でやっていようと、ある存在はただその存在である。
そしてその存在そのものの同一性は、どうであったとしても全く変わらない。霧子の「どこにも」は、恣意的に編集された虚偽の物語でも、自分たちが提示する真実の物語でも、どれであったとしても、という風に読める。
「わたしたちがわたしたちなら」というのは、そういう風に読める言葉だと思う。いつも通りだろうと、いつも通りじゃなかろうと、恣意的に編集されて物語を作られようと、意図した通りに映像が作られようと、「わたしたち」は「わたしたち」である。それによって存在の同一性が変わるわけではない。
それゆえ霧子は「どこにも嘘なんて(ない)」と言ったのである。「わたしたちがわたしたちなら」、それは「嘘」ではない。「嘘」ではありえない。たとえ恣意的に編集された物語であったとしても。そうだとしても、AがAであるという同一性が真でないはずがない。そこに真理が開かれる。
この真理は、事実と対応しているという真理とは違うタイプの真理である。事実と対応していようといなかろうと、AはAであるという同一性は真理だからだ。
だからこそ霧子は「どこにも」(嘘なんてない)と言えたのである。番組制作側が恣意的に編集して作り出した物語も、アンティーカが自ら提示する物語も、それらは物語という点では同列に置かれる。それらは共に物語であり、それゆえ共通に真偽の問題にさらされる。番組制作側が恣意的に編集した物語が虚偽であるとして、実はアンティーカが自ら提示する物語も、それが真実であるとは限らないのである。
そのことに気がつくとき、霧子の言う「どこにも」(嘘なんてない)という言葉が効果を発揮し始めるのである。それは、真偽が問題になる物語とは無関係なところで、ちゃんと真理を見出すことができるのだ、という意味なのだ。どんな物語であっても、ちゃんと「本当の」アンティーカを示すことができるのである。
大胆に、霧子の言葉を置き換えてみよう。「ある存在者が存在するということは物語ではない。ある存在者が当のその存在者であるといいう同一性は偽ではなく真である」というわけである。
このようにして、アンティーカそのものの存在の真理性を見出すことができた。「本当の」アンティーカは、ただそこに存在しているのだ。アンティーカがアンティーカとして存在するということ、ただそれだけで、そこにアンティーカの存在の真理が開かれるのである。
◇存在論者幽谷霧子
霧子の「存在」に対するこうした感度には、哲学的なセンスが感じられる。ただし、「霧子は哲学をしている」とはっきり言うつもりはない。けれども、哲学が始まるところにある感度と、霧子のこうした感度には、共通しているものが感じられるのだ。一般に「哲学」とされているものではなく、生の〈哲学〉とでも言うべきなにか。そうしたものならば霧子はしていると言えるかもしれない。
そして実は幽谷霧子は存在論者である、と大胆に言ってみたくなるのである。私の中のイメージでは少なくともそうである。この話題についてはいずれどこかで書けたらいいなと思う。
◇おわりに
千雪の場合は、自分の生活を枠づけていたアプリコットから「卒業」することで、現実へと抜け出した。フィクションに憧れて、フィクションのように生きるのではなく、その外側で現実そのものの中で生きることを選んだ。
霧子(とアンティーカ)は、現実がフィクション化されようとも、アンティーカがアンティーカであるという同一性が偽になりえないというところから真実を開く。
一方は、フィクションの外側へと出る方向で現実を目指し、他方は、フィクションの中においても存在者の同一性を見出すことで真実の点を開く。前者が夢から覚めることと類比的なら、後者は夢の中であったとしても真実を開くことで夢と現実の差異を超えてしてしまうのである。
シャニマスという一つの作品の中で、フィクションと現実に対してこれほどまでに異なるアプローチを描き出すことができるという点に、驚愕しないではいられない。いったいどうやってイベントストーリーを作っているんだ……
*Privatterの投稿は削除済み
投稿したあとで公開範囲を変更することができるよ。マイページから、投稿したやつの右下にある「編集」をポチッとしてね
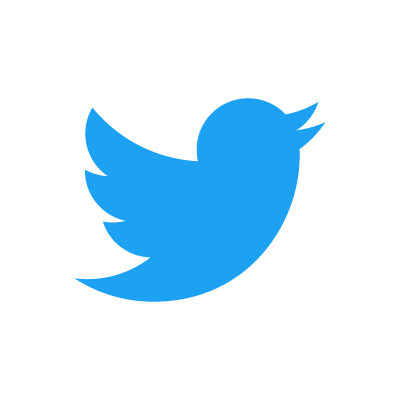 元ツイート
元ツイート