本日の一次創作短編です。
お題は「意地っ張りな人」「オレが謝る必要なんて」です
お題は「意地っ張りな人」「オレが謝る必要なんて」です
カルセドニー
「どうしてそんなこと言うの?!」
恋人の龍驤 八千代にそう責められて、俺は反感を覚えた。
「なにイキってんだよ、お前にああだこうだ言われる筋合いねえから」
「あの子、泣いてたじゃない!!なんとも思わなかったの!?」
「お前に非人間扱いされる覚えはねーよ!!お前の方がよっぽど人でなしだ!!」
「はあ?!」
「ヘタに子供に夢を見せて何になるんだよ!!夢と現実が違った時にも責任なんて取らねえくせに!!
根本が無責任なんだよ!!正義の味方ぶっていい子ぶりやがって、てめえがいい人に見られたいだけだろ!!」
思ったままに叫べば、八千代はひどく傷ついた顔をした。俺の怒りはおさまらなかった。彼女は俯いて、絞り出すように言った。
「…………勇斗がそんな人だとは、思わなかったわ」
「そうかよ」
俺は吐き捨てた。そのまま帰路について、八千代のことは置いていった。彼女はついてこなかった。
俺、蒼鷹 勇斗と龍驤 八千代は、中学にあがって以来の恋人同士だ。
もともと小学校の頃からの幼馴染だった。ケンカもたくさんしたが、なんだかんだ言って放っておけなくて、俺から告白した。その時八千代は、目に涙を浮かべて、心から幸せそうに笑った。うれしさのあまり抱きついてきて、彼女の身体の柔らかい体温を感じたことを、今でも覚えている。
恋人同士となってからも、様々なケンカをしたが、ある時は俺が謝ったり、ある時は八千代が謝ったりして、それなりに関係を修復して、恋人付き合いを続けていた。
でも今回ばかりは、修復できるような気がしなかった。
いつもの帰り道。八千代と一緒に帰路について、少し腹が減ったのでコンビニでおやつを買う。公園で食べようと思って寄っていくと、ベンチで小さな男の子が泣いていた。八千代はその子が放っておけなくて、男の子に話しかけた。男の子は泣きながら言った。
「ポチが死んじゃったんだ。もう戻ってこないって」
それに対して、八千代は言った。
「悲しいわね。つらかったわね。
でも、大丈夫よ。ポチはきっと生まれ変わって、あなたのもとに帰ってきてくれるわ」
「…………本当?」
顔をあげた男の子に、俺は言った。
「んな訳ねえだろ。死んだ奴は二度と戻ってこない。そんな幻想にすがったところで、あとから絶望するだけだ。忘れた方がずっといい」
男の子はそれを聞いて、再び泣きだしてしまった。俺はその子を置いて帰路についた。八千代は男の子に「ごめんね」と言って、俺を追いかけてきた。
「どうしてあんなこと言ったの」
半ば苛立ちを覚えたように、八千代は言った。俺は素直に答えた。
「そのまんまだよ。ヘタに夢なんか見てたところで、どうせ現実はやってくる。変な夢を見てキラキラするより、まっすぐ現実見てた方が、ずっと傷が少なくて済むだろ」
「どうしてそんなこと言うの?!」
そうして、今に至る。
真っ向から否定してきた八千代に謝るつもりなんか、毛頭ない。夢を語るやつは無責任なのだ。語った夢が現実と違って、相手を苦労させても、責任は取らない。信じたやつが悪いと言う。夢や前向きな言葉なんていうものは、ぜんぶ詐欺師が使う言葉だ。そんな確証のないものを信じてキラキラしているやつはもれなくバカだし、付き合っていられない。しかも厄介なことに、夢を語る奴らはその夢を他人に押し付けてくる。八千代がそんな行動をとるのは不愉快でたまらなかった。吐き気がした。もう八千代の顔なんて見たくなかった。
(そんなやつだとは思わなかった)
翌日。俺たちは別々に登校した。いつもは一緒に登校していたが、俺はいつもの待ち合わせ場所に行かなかった。
八千代に会いたくなくて、早めに家を出た。八千代はいつもより遅れて、教室に入ってきた。顔は見なかった。
淡々と授業をこなし、休み時間に友達としゃべくり、友達と昼食をとる。俺は一切、八千代に関わらなかった。八千代からの視線は感じたが、俺は全て無視した。八千代が近寄ってきたり、話しかけそうになった時は、その場を離れたり、友達に声をかけたりした。とにかく話しかけるなオーラを出し続けた。とにかく、近づいてほしくなかった。
そんな日々が数日続き、ある昼食時、友達が言った。
「最近、龍驤と一緒じゃないな」
「ケンカでもしたか?仲いいよなあ」
俺は聞きたくない名前に心底顔をゆがめた。
「やめてくれ。もうあいつの名前は聞きたくない」
そう言うと、友達は言葉を詰まらせた。
「…………なんかあったのか?」
「別に」
「龍驤、お前のこと気にしてるみたいだよ。話しかけてやったら?」
「やだね」
「…………」
友達は気まずそうに、互いに顔を見合わせた。付き合ってた時はからかってたのに、いざケンカするとこれだ。こいつらも所詮、俺たちのことは消費するものとしか思っていないんだろう。
「…………龍驤と、別れる?」
友達のひとりが、遠慮がちにそう言った。別れる、か。
「そうだな、その方がいいかもな。
別れるか」
友達の顔を見ずに、弁当の中身をかき込んだ。
帰り道。八千代のいない帰り道。ひとりで気楽に歩いていると、ふと子供の頃を思い出した。
音を立てて空を飛ぶ飛行機を見ていた。俺は両親と手をつないでいた。俺は飛行機を見上げて言った。
「おおきくなったら、パイロットになりたい!!」
あのカッコいい飛行機に乗りたい。そんな純粋な夢だった。しかし、両親は言った。
「お前にできるわけないだろ。パイロットは難しいんだぞ」
それから、パイロットになるのがいかに難しいことかを延々と語られた。何を語られたかは覚えていない。子供には難しい話だった。俺は夢を打ち砕かれたことが悲しくて、泣き出した。うるさいと母に叩かれた。それからどうやって家に帰ったか、覚えていない。ずっと、ぐずっていたような気がする。
人間はみんな卑怯者だ。調子のいいことばかり言って夢を語って、いざそれを信じた途端に信者を裏切る。そうして遊んでいるのだ。愉悦に浸っているのだ。人間など履いて捨てるほどいるのだからと、周りの人間で遊んでいるのだ。
(そんな詐欺師どもに、付き合ってられるか)
あの日から俺の心はぐちゃぐちゃと乱されるばかりだった。苛立ちを隠しきれなかった。
(卑怯者のウソつきども、みんなに天罰が下ればいいのに)
数日後。八千代が隣にいない日にも慣れた頃、担任が重い顔をして言った。
「バスが横転し、川に投げ出された。横転したバスに龍驤が乗っていた。龍驤は今、行方不明だ」
クラス全体がざわついた。俺に向けられた視線も感じた。俺はなんとも思わなかった。
その日から、学校に警察が出入りするようになった。生徒にも話を聞いているらしい。俺のところにもやってきた。
「君は、龍驤さんと付き合っていたようだね。最近、ケンカをしたとか」
「そうですね。あいつが悪いんで、俺はもう別れたと思ってます」
「そうか。どんなケンカだったか、教えてもらってもいいかな」
「別に、構いませんけど…………」
俺は素直に、警官に話した。夢を語る奴なんて、みんな詐欺師と一緒だ。吐き捨てるようにそう言ったら、警官はそうか、と頷いた。そして言った。
「今の君に必要なのは、夢を傷つけられた悲しみや痛みが癒されることだ。
人は、夢を持つから希望が持てる。生きるのが楽しくなる。明るくなれる、キラキラできる。
子供のころの君も、そうなりたいと願ったはずだ。だから、パイロットになりたいと願ったんだ。
それを傷つけられれば、誰だって悲しいし、怒りを感じる。その傷がケアされることこそ、君に真に必要なものだ。
だから、その悲しみで他人を傷つけることは、してはいけない。
君には悲しみを癒してもらう権利はあるが、悲しみで他人を傷つける権利はない。
夢を持って君に寄り添っていた龍驤さんになら、それができたんじゃないのかな」
警官は、小さなコピー用紙を俺に差し出した。そこには、1枚の領収証が印刷されていた。
「龍驤さんは事故に巻き込まれる直前、このお店に行っていたらしい。
店主も龍驤さんのことはよく覚えていたよ。よかったら、話を聞きに行ってみてはどうかな」
店に向かうバスに乗っている間、俺の脳内は警官の言葉で埋め尽くされていた。
なんとも言えず、腑に落ちた。そうだ。俺は悲しかったんだ。
夢を持つ心を親に否定されたのが悲しかったんだ。だからあんなに泣いたんだ。親に共感してほしかった。「いいね!」って言ってもらいたかった。もう傷つきたくなくて、夢を信じるのをやめたんだ。
それをもしも、八千代にきちんと話していたら。八千代なら、どうしただろう。
考えるまでもなかった。八千代なら、きっと俺の気持ちに寄り添ってくれただろう。伊達に付き合いも長くないのだ、それくらいは想像がついた。冷静になってきちんと話せば、あるいはケンカもしなくて済んだだろうか。それでも俺はなんとなく、「それでも八千代に謝ってほしい」という意地が抜けなかった。
最寄りのバス停を降りて少し歩く。領収証に書かれた住所は、一軒のアクセサリーショップだった。パワーストーンや、それで作ったアクセサリーを売るお店。俺と八千代でよく行った、俺たちの大好きな店だった。
店に入ると、俺を見つけた店主が俺のもとまで飛んできた。
「ああっ、お客さん!彼女さんは大丈夫だったかい?!」
その心から心配した顔に、俺の胸がちくりと痛んだ。
「…………わかりません」
「ああ…………あの事故であのお客さんがバスに乗っていたと聞いて、もう気が気じゃなくて…………
警察の人から聞いたんだね。あのお客さんはね、君のために、プレゼントを買っていったんだよ」
その言葉に、俺は顔をあげた。
「俺に?」
「そうとも。お客さんは彼女さんとケンカしたらしいね。
それを話してくれてね、君に贈るために、これと同じものを買っていったんだよ」
店主はそう言って、陳列棚からペンダントをひとつ取って、俺に見せた。
以前俺がほしいと呟いた、ブルーのカルセドニーをあしらったペンダントだった。
それを手に取ると、店主は言った。
「君と話がしたい、と言っていたよ。
君の気持ちにも、何か理由があったんだろうって。彼女さんは君が優しい人だということを知っていたから、なんとかして仲直りして、話がしたいと思って、これを買っていったんだ。
カルセドニーは『社交性』『思いやり』ブルーのカルセドニーは『博愛』の石だからね」
外から、大きな声がした。
「号外!号外!!この先の橋のバス落下事件の被害者が全員見つかりました!」
そのペンダントはサービスするよ、と店主は言った。
「彼女さんを、迎えにいってあげな」
俺は橋まで一直線に走った。八千代に会いたくてたまらなかった。今まで意地を張っていた自分がバカらしくて、恥ずかしさすら覚えた。八千代はいつでも、俺を想ってくれていたんだ。それを俺は、全てはねのけてしまっていた。カルセドニーのペンダントが手の中で温まっていく。カルセドニーは人と人を紡ぐ石。八千代は俺との縁をずっと紡いでいたかったんだ。だから、これを買いに行ったんだ。走りながら、視界が歪んでいく。気付けば俺は走りながら、大粒の涙を零していた。俺は自分の悲しみを八千代にぶつけて、傷つけていただけだった。夢なんて信じなければいいと、カッコつけていたのは俺の方だ。八千代の方が、ずっと現実を見ていたんだ。
(本当の卑怯者は、俺だったんだ)
事故現場の橋は封鎖こそ解けていたが、橋のそばでは警官や救助隊員たちがせわしなく行き交っていた。
今もなお、救助が行われていた。布をかけられて運ばれていく担架の姿もあちこちにあった。野次馬たちがたかって見物し、記者が野次馬に号外を配る。そのうちのひとつ、地面に打ち捨てられた号外に、俺ははっきりとその字を目にした。
被害者名 一覧
龍驤 八千代(14)
+++
「カルセドニー」4,721字
お題
「意地っ張りな人」
「オレが謝る必要なんて」
(ああ、意地なんて張らなきゃよかった)
「どうしてそんなこと言うの?!」
恋人の龍驤 八千代にそう責められて、俺は反感を覚えた。
「なにイキってんだよ、お前にああだこうだ言われる筋合いねえから」
「あの子、泣いてたじゃない!!なんとも思わなかったの!?」
「お前に非人間扱いされる覚えはねーよ!!お前の方がよっぽど人でなしだ!!」
「はあ?!」
「ヘタに子供に夢を見せて何になるんだよ!!夢と現実が違った時にも責任なんて取らねえくせに!!
根本が無責任なんだよ!!正義の味方ぶっていい子ぶりやがって、てめえがいい人に見られたいだけだろ!!」
思ったままに叫べば、八千代はひどく傷ついた顔をした。俺の怒りはおさまらなかった。彼女は俯いて、絞り出すように言った。
「…………勇斗がそんな人だとは、思わなかったわ」
「そうかよ」
俺は吐き捨てた。そのまま帰路について、八千代のことは置いていった。彼女はついてこなかった。
俺、蒼鷹 勇斗と龍驤 八千代は、中学にあがって以来の恋人同士だ。
もともと小学校の頃からの幼馴染だった。ケンカもたくさんしたが、なんだかんだ言って放っておけなくて、俺から告白した。その時八千代は、目に涙を浮かべて、心から幸せそうに笑った。うれしさのあまり抱きついてきて、彼女の身体の柔らかい体温を感じたことを、今でも覚えている。
恋人同士となってからも、様々なケンカをしたが、ある時は俺が謝ったり、ある時は八千代が謝ったりして、それなりに関係を修復して、恋人付き合いを続けていた。
でも今回ばかりは、修復できるような気がしなかった。
いつもの帰り道。八千代と一緒に帰路について、少し腹が減ったのでコンビニでおやつを買う。公園で食べようと思って寄っていくと、ベンチで小さな男の子が泣いていた。八千代はその子が放っておけなくて、男の子に話しかけた。男の子は泣きながら言った。
「ポチが死んじゃったんだ。もう戻ってこないって」
それに対して、八千代は言った。
「悲しいわね。つらかったわね。
でも、大丈夫よ。ポチはきっと生まれ変わって、あなたのもとに帰ってきてくれるわ」
「…………本当?」
顔をあげた男の子に、俺は言った。
「んな訳ねえだろ。死んだ奴は二度と戻ってこない。そんな幻想にすがったところで、あとから絶望するだけだ。忘れた方がずっといい」
男の子はそれを聞いて、再び泣きだしてしまった。俺はその子を置いて帰路についた。八千代は男の子に「ごめんね」と言って、俺を追いかけてきた。
「どうしてあんなこと言ったの」
半ば苛立ちを覚えたように、八千代は言った。俺は素直に答えた。
「そのまんまだよ。ヘタに夢なんか見てたところで、どうせ現実はやってくる。変な夢を見てキラキラするより、まっすぐ現実見てた方が、ずっと傷が少なくて済むだろ」
「どうしてそんなこと言うの?!」
そうして、今に至る。
真っ向から否定してきた八千代に謝るつもりなんか、毛頭ない。夢を語るやつは無責任なのだ。語った夢が現実と違って、相手を苦労させても、責任は取らない。信じたやつが悪いと言う。夢や前向きな言葉なんていうものは、ぜんぶ詐欺師が使う言葉だ。そんな確証のないものを信じてキラキラしているやつはもれなくバカだし、付き合っていられない。しかも厄介なことに、夢を語る奴らはその夢を他人に押し付けてくる。八千代がそんな行動をとるのは不愉快でたまらなかった。吐き気がした。もう八千代の顔なんて見たくなかった。
(そんなやつだとは思わなかった)
翌日。俺たちは別々に登校した。いつもは一緒に登校していたが、俺はいつもの待ち合わせ場所に行かなかった。
八千代に会いたくなくて、早めに家を出た。八千代はいつもより遅れて、教室に入ってきた。顔は見なかった。
淡々と授業をこなし、休み時間に友達としゃべくり、友達と昼食をとる。俺は一切、八千代に関わらなかった。八千代からの視線は感じたが、俺は全て無視した。八千代が近寄ってきたり、話しかけそうになった時は、その場を離れたり、友達に声をかけたりした。とにかく話しかけるなオーラを出し続けた。とにかく、近づいてほしくなかった。
そんな日々が数日続き、ある昼食時、友達が言った。
「最近、龍驤と一緒じゃないな」
「ケンカでもしたか?仲いいよなあ」
俺は聞きたくない名前に心底顔をゆがめた。
「やめてくれ。もうあいつの名前は聞きたくない」
そう言うと、友達は言葉を詰まらせた。
「…………なんかあったのか?」
「別に」
「龍驤、お前のこと気にしてるみたいだよ。話しかけてやったら?」
「やだね」
「…………」
友達は気まずそうに、互いに顔を見合わせた。付き合ってた時はからかってたのに、いざケンカするとこれだ。こいつらも所詮、俺たちのことは消費するものとしか思っていないんだろう。
「…………龍驤と、別れる?」
友達のひとりが、遠慮がちにそう言った。別れる、か。
「そうだな、その方がいいかもな。
別れるか」
友達の顔を見ずに、弁当の中身をかき込んだ。
帰り道。八千代のいない帰り道。ひとりで気楽に歩いていると、ふと子供の頃を思い出した。
音を立てて空を飛ぶ飛行機を見ていた。俺は両親と手をつないでいた。俺は飛行機を見上げて言った。
「おおきくなったら、パイロットになりたい!!」
あのカッコいい飛行機に乗りたい。そんな純粋な夢だった。しかし、両親は言った。
「お前にできるわけないだろ。パイロットは難しいんだぞ」
それから、パイロットになるのがいかに難しいことかを延々と語られた。何を語られたかは覚えていない。子供には難しい話だった。俺は夢を打ち砕かれたことが悲しくて、泣き出した。うるさいと母に叩かれた。それからどうやって家に帰ったか、覚えていない。ずっと、ぐずっていたような気がする。
人間はみんな卑怯者だ。調子のいいことばかり言って夢を語って、いざそれを信じた途端に信者を裏切る。そうして遊んでいるのだ。愉悦に浸っているのだ。人間など履いて捨てるほどいるのだからと、周りの人間で遊んでいるのだ。
(そんな詐欺師どもに、付き合ってられるか)
あの日から俺の心はぐちゃぐちゃと乱されるばかりだった。苛立ちを隠しきれなかった。
(卑怯者のウソつきども、みんなに天罰が下ればいいのに)
数日後。八千代が隣にいない日にも慣れた頃、担任が重い顔をして言った。
「バスが横転し、川に投げ出された。横転したバスに龍驤が乗っていた。龍驤は今、行方不明だ」
クラス全体がざわついた。俺に向けられた視線も感じた。俺はなんとも思わなかった。
その日から、学校に警察が出入りするようになった。生徒にも話を聞いているらしい。俺のところにもやってきた。
「君は、龍驤さんと付き合っていたようだね。最近、ケンカをしたとか」
「そうですね。あいつが悪いんで、俺はもう別れたと思ってます」
「そうか。どんなケンカだったか、教えてもらってもいいかな」
「別に、構いませんけど…………」
俺は素直に、警官に話した。夢を語る奴なんて、みんな詐欺師と一緒だ。吐き捨てるようにそう言ったら、警官はそうか、と頷いた。そして言った。
「今の君に必要なのは、夢を傷つけられた悲しみや痛みが癒されることだ。
人は、夢を持つから希望が持てる。生きるのが楽しくなる。明るくなれる、キラキラできる。
子供のころの君も、そうなりたいと願ったはずだ。だから、パイロットになりたいと願ったんだ。
それを傷つけられれば、誰だって悲しいし、怒りを感じる。その傷がケアされることこそ、君に真に必要なものだ。
だから、その悲しみで他人を傷つけることは、してはいけない。
君には悲しみを癒してもらう権利はあるが、悲しみで他人を傷つける権利はない。
夢を持って君に寄り添っていた龍驤さんになら、それができたんじゃないのかな」
警官は、小さなコピー用紙を俺に差し出した。そこには、1枚の領収証が印刷されていた。
「龍驤さんは事故に巻き込まれる直前、このお店に行っていたらしい。
店主も龍驤さんのことはよく覚えていたよ。よかったら、話を聞きに行ってみてはどうかな」
店に向かうバスに乗っている間、俺の脳内は警官の言葉で埋め尽くされていた。
なんとも言えず、腑に落ちた。そうだ。俺は悲しかったんだ。
夢を持つ心を親に否定されたのが悲しかったんだ。だからあんなに泣いたんだ。親に共感してほしかった。「いいね!」って言ってもらいたかった。もう傷つきたくなくて、夢を信じるのをやめたんだ。
それをもしも、八千代にきちんと話していたら。八千代なら、どうしただろう。
考えるまでもなかった。八千代なら、きっと俺の気持ちに寄り添ってくれただろう。伊達に付き合いも長くないのだ、それくらいは想像がついた。冷静になってきちんと話せば、あるいはケンカもしなくて済んだだろうか。それでも俺はなんとなく、「それでも八千代に謝ってほしい」という意地が抜けなかった。
最寄りのバス停を降りて少し歩く。領収証に書かれた住所は、一軒のアクセサリーショップだった。パワーストーンや、それで作ったアクセサリーを売るお店。俺と八千代でよく行った、俺たちの大好きな店だった。
店に入ると、俺を見つけた店主が俺のもとまで飛んできた。
「ああっ、お客さん!彼女さんは大丈夫だったかい?!」
その心から心配した顔に、俺の胸がちくりと痛んだ。
「…………わかりません」
「ああ…………あの事故であのお客さんがバスに乗っていたと聞いて、もう気が気じゃなくて…………
警察の人から聞いたんだね。あのお客さんはね、君のために、プレゼントを買っていったんだよ」
その言葉に、俺は顔をあげた。
「俺に?」
「そうとも。お客さんは彼女さんとケンカしたらしいね。
それを話してくれてね、君に贈るために、これと同じものを買っていったんだよ」
店主はそう言って、陳列棚からペンダントをひとつ取って、俺に見せた。
以前俺がほしいと呟いた、ブルーのカルセドニーをあしらったペンダントだった。
それを手に取ると、店主は言った。
「君と話がしたい、と言っていたよ。
君の気持ちにも、何か理由があったんだろうって。彼女さんは君が優しい人だということを知っていたから、なんとかして仲直りして、話がしたいと思って、これを買っていったんだ。
カルセドニーは『社交性』『思いやり』ブルーのカルセドニーは『博愛』の石だからね」
外から、大きな声がした。
「号外!号外!!この先の橋のバス落下事件の被害者が全員見つかりました!」
そのペンダントはサービスするよ、と店主は言った。
「彼女さんを、迎えにいってあげな」
俺は橋まで一直線に走った。八千代に会いたくてたまらなかった。今まで意地を張っていた自分がバカらしくて、恥ずかしさすら覚えた。八千代はいつでも、俺を想ってくれていたんだ。それを俺は、全てはねのけてしまっていた。カルセドニーのペンダントが手の中で温まっていく。カルセドニーは人と人を紡ぐ石。八千代は俺との縁をずっと紡いでいたかったんだ。だから、これを買いに行ったんだ。走りながら、視界が歪んでいく。気付けば俺は走りながら、大粒の涙を零していた。俺は自分の悲しみを八千代にぶつけて、傷つけていただけだった。夢なんて信じなければいいと、カッコつけていたのは俺の方だ。八千代の方が、ずっと現実を見ていたんだ。
(本当の卑怯者は、俺だったんだ)
事故現場の橋は封鎖こそ解けていたが、橋のそばでは警官や救助隊員たちがせわしなく行き交っていた。
今もなお、救助が行われていた。布をかけられて運ばれていく担架の姿もあちこちにあった。野次馬たちがたかって見物し、記者が野次馬に号外を配る。そのうちのひとつ、地面に打ち捨てられた号外に、俺ははっきりとその字を目にした。
被害者名 一覧
龍驤 八千代(14)
+++
「カルセドニー」4,721字
お題
「意地っ張りな人」
「オレが謝る必要なんて」
(ああ、意地なんて張らなきゃよかった)
公開範囲を「すべて」にしたときは、Twitter認証をしなくても伏せ字が読めるよ
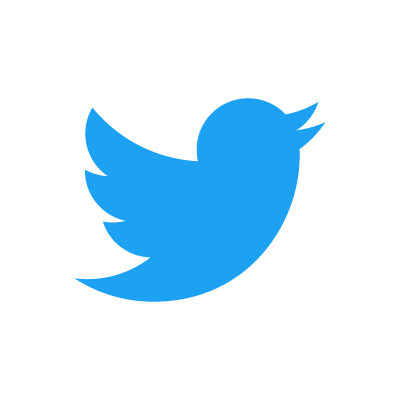 元ツイート
元ツイート