桑山千雪と読むラカン――ラカンのまなざしの概念について
初出:2022年6月10日Privatterに投稿
◇はじめに
この文章は、大胆にもシャニマスを読むことを通してラカンの概念について考えてみようということを企図しています。そこで取り上げたいのは、「#283をひろげよう」の企画においてTwitterで千雪の上げた写真と、それに関する話、すなわち千雪の寮の部屋の壁のひびにまつわる話です。ここに、ラカンの考えるまなざしの概念を読み取ることができるのではないか、と私は考えています。ここではそれにトライしてみます。
セミネール11巻『精神分析の四基本概念』においてラカンはまなざしの概念について議論を展開しているのですが、それは簡単なものではありません。ですが、ラカンはその概念を理解するための補助としていくつも例を挙げており、そうした例に千雪の部屋の壁のひびを並べることができるのではないかと思われます。
まずは千雪が投稿していた部屋の壁のひびの写真を見ていきましょう。
https://twitter.com/imassc_official/status/1479094401699885197?s=20&t=h0eWLnor6wyD3vmpRnlWrg
こちらが壁のひびの写真です。この投稿に続けて、千雪は次のように述べています。
「初めてこのお部屋に来た頃は、どうにかしてふさげないかなって思ったんですが
すぐに忙しくなっちゃって、いつの間にかそのままになって
……もし、このひびを向こう側から覗いたら、あの頃の私が、あの頃の日々が見えるかもしれません
教えてあげたいな
どんな顔をしているかわからないけど、こっち側にいる未来の私は、とっても幸せだぞって」
この壁のひびにはいくつかポイントがあります。まずは、この壁のひびは最初は「どうにかしてふさげないか」と思ったものだということです。千雪の部屋は、コミュの背景にも登場しますが、小物などが並べられており、世界観が構築されています。しかもそれは雑誌『アプリコット』によって作られたものだということが推察できます(千雪の部屋がどのように作られていったかは、「薄桃色にこんがらがって」のサポートSSR【ドゥワッチャラブ!】の「卒業」の中で語られています)。ひびは、そうした世界観にそぐわないものであったはずで、それゆえ「ふさげないか」と考えられたのだと思われます。
2つ目のポイントは、ひびは覗き穴のようになって向こう側が見えるものであるということです。しかもそれは、こちら側から覗くのではなく、「向こう側から」覗くようになっているのです。
そして3つ目のポイントは、投稿された写真では、ひびは壁に映った千雪の影に重なるようにして写されているということです。
以上から、結論を先取りすると、かつての千雪にとって壁のひびは、ラカンが考えるまなざしという対象として現れていたのではないかと考えられるわけです。(ラカンの議論においては、まなざしは対象(objet)の1つです。)
それではこれからこのことを、ラカンが実際にまなざしという対象をどのようなものとして考えていたかをラカンの挙げた例を見ることによって確認していきましょう。
以下ラカンの『精神分析の四基本概念』の引用は、2020年に岩波文庫から上下巻で出版された小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭の翻訳から行います。
◇海に浮かぶ缶
ラカンが挙げている例の中で個人的に一番わかりやすい例が、この海に浮かんだ缶の話です(上206-210頁)。これは若い頃(20代)のラカンが実際に体験したという話で、要約するとこうです。
パリに生まれて育ったラカンは、医学部に入って精神科医になりました。精神分析家であるラカンのキャリアは精神科医として出発しています。ラカン自身が言っているように、これから話す体験をしたころのラカンは「若いインテリ」でした。
若いインテリであったラカンは、小さな漁港で漁師の家族とともに漁をしていました。当時ラカンが体験した漁は産業化される前のもので、小さな船に乗って危険を賭して行われるものでした。ラカンはある日、一緒に船に乗っていたプチ・ジャンという青年から、波間に漂う何かを指しながらこんなことを言われます。「あんたあの缶が見えるかい。あんたはあれが見えるだろ。でもね、やつの方じゃあんたを見ちゃいないぜ」(上207頁)。波間に浮かんだ缶は鰯の缶詰の缶で、太陽の光を浴びてキラキラ光っていました。
プチ・ジャンはこの話を面白がったそうですが、ラカンは全く面白くなかったようです。ラカンはここで、「それでもやはり缶は私を眼差しているからです。その缶は光点という意味で私を眼差しているのです」と言っています(上208頁)。どういうことでしょうか。ラカンはもう少し説明していますので、それを引用してみましょう。
「私の相棒が思いついたこのちょっとした話、この話が彼にはひどく面白く、私にはそれほどでもなかった理由は次の点にあります。つまり、彼がこんな話をしたのは、やはりこのときの私、つまり厳しい自然の中でやっとの思いで生きているこれらの人々に混じってすっかりその気になっていた私は、実に不調和な絵(タブロー)をなしていた、ということです。要するに、私は絵の中にあって多少ともシミとなっていたのです。それをどこかで感じていたからこそ、自分が不意に呼びかけられたと思っただけで、このユーモラスな、そして皮肉な話を別にそれほど面白いとは感じなかったのです」(上208頁)。
ラカンは漁師たちに混じって小さな漁港で小さな船に乗って、一緒に漁をしていたわけですが、その漁師たちの光景の中にそぐわない、浮いた存在となっていたわけです。ラカン自身は、漁師たちと一緒になって自分もそこに参加している気になりつつも、どこかで自分がそぐわない存在であるということを感じており、そのことを缶を通して指摘されたかたちになって、ラカンはこれを面白く感じなかったのです。
さて、この話の中で、波間に浮かんでキラキラ光る缶のところのところに、まなざしという対象があります。この話の中でラカンは、「絵(タブロー)」ということを言っていますが、これはラカンが混じっていた漁師たちの姿、その光景を指しています。そうした絵、光景を作るための視点、あるいは光点として現れてくるのが、波間に浮かんでキラキラ光る缶です。そうした缶のもとから見える光景の中においてラカンは、プチ・ジャンが「やつの方じゃあんたを見ちゃいない」と言うように、光景の中に見える存在として適切に位置づけられていないのであり、全くそぐわない存在として浮いている、ということになります。松本卓也(『享楽社会論』、人文書院、2018年)によれば、「ラカンは、自分がその場にそぐわない存在であることを、缶によって教えられた」のです(186頁)。
松本(2018)は次のようにまとめています。
「私たちはふつう、世界に対して、自分が何か(対象)を見ていると思っている。しかし、まさにそのとき、世界の中の何か(対象)から、むしろ自分が見られている。そして、そのような〈他者〉の眼差しによって、実は私たち自身のことが告げられてしまっている。その眼差しが私たち自身の「場違いさ」を示すとき、私は居づらさを感じる。そして、その眼差しによって、私たち自身の異様さが示されるからこそ、私たちは恥ずかしさを感じるのである」(松本 2018:186頁)
ラカンの考えるまなざしという対象は、こういうものです。
・自分が対象を見るのではなく、対象の方が私を見ている。
・自分の方を見る対象は、波間に浮かんでキラキラ光る缶のように、人格的な存在の視線であるとは限らない。
・自分を見る対象=まなざしのもとで、自分のいる光景が絵(タブロー)となる。
・自分の外部にあって自分の方を見る対象が、自分が何者であるかを示してくる。
・しかもそこで明らかにされることは、どちらかといえば居心地の悪いものである。
◇まなざしとしての部屋のひび
まなざしという対象がこのようなものであるとすると、千雪の部屋のひびというのは、まさに千雪にとってはまなざしという対象だったのではないか、と考えたくなってくるわけです。
千雪は山口県出身で、東京で一人暮らしをしながら雑貨屋に勤めていました。そこでアイドルにスカウトされ、当初は雑貨屋勤務とアイドル業の両方を務めています。WING編の途中で千雪はアイドル一本に絞ることを決意し、雑貨屋を辞めています。寮にいつ引っ越したのかは定かではないのですが(分かる方がいたら教えてください)、雑貨屋を辞めてアイドル一本に絞ることを決めたことよりも後に位置づけられるのではないかと思います。
千雪の寮の部屋は、コミュの背景で描かれているように小物がたくさん置かれています。この部屋の世界観はおそらく、千雪が愛読していた雑誌『アプリコット』の影響下にあったことが考えられます。部屋のひびは、そうして作り上げる世界観にそぐわないものとして存在していたと思われます。千雪はだからこそ、このひびをふさぐことを考えていました。作り上げる世界観を完全なものにするためです。
ここで部屋の世界観にそぐわないものとして現れてくるひびは、漁の小舟に乗っているときラカンの前に現れた波間に光る缶と同じものだったのではないでしょうか。つまり壁のひびは、自分をその場の光景にそぐわないものとして開示するまなざしという対象だったのではないか。
また「薄桃色にこんがらがって」のサポートSSR【ドゥワッチャラブ!】の「卒業」では、寮の自分の部屋を作り上げることを「まっさらな場所に絵を描くみたい」だったと語っています。それゆえ壁のひびは「絵」に現れたシミであったと考えられるのです。
このことを示すかのように、壁のひびの写真には千雪自身の影がひびに重なるように写されています。千雪という人物の姿(=影)は部屋の絵(タブロー)の中の一部となっており、しかもひびは千雪自身の姿に重なっているわけです。千雪という姿の中にひびが現れているようであり、部屋のひびの場所にこそ千雪という人物の存在が現れているというようにも見えます。またあるいは、ひびは自分の外部に存在するものであるが、しかし自分が何者であるのかを開示するような自分自身にとって重要な一部であるということを示しているかのようです。
そして千雪はこのひびに対してこう言っています。「向こう側から覗いたら、あの頃の私が、あの頃の日々が見えるかもしれません」。重要なのは、ひびを通してこちらから向こう側を覗くのではなく、「向こう側から」覗くということです。千雪はひびの向こう側からまなざされるわけです。まなざすのはこちらではなく、向こう側なのです。
このように、壁のひびは千雪にとってのまなざしという対象として現れていたのではないかと考えられるのです。
ではこのひびが開示する「その場の光景にそぐわないもの」としての千雪自身とはどういうことだったのでしょうか。
まず最初に考えられるのは、これは推測ですが、アイドルになりたての頃の自分自身ということです。アイドルになりたての頃、自分は「アイドル」をちゃんとやれているだろうか、と自分自身に問うということはありそうなことです。そういう意味で、壁のひびにおいて自分が「その場の光景にそぐわないもの」として開示されていると考えることができます。
もう一つ、より突っ込んだこととして考えられることがあります。それはイベントシナリオ「薄桃色にこんがらがって」で描かれたことです。つまり、『アプリコット』という世界観の中にそぐわないものとしての自分自身が開示されていたのではないか、という解釈です。
千雪は雑誌『アプリコット』の愛読者でした。『アプリコット』の世界観に憧れ、記事の一節を諳んじることができるほど読み込んでいました。その『アプリコット』が復刊する際の雑誌のモデルとして、出版社から甘奈が推薦されます。しかしそれは、甘奈が優勝することが内定したオーディションを公募で行う形式とするというものでした。千雪は、ユニットメンバーである甘奈の抜擢を喜ばしく思う一方、自分が『アプリコット』のモデルをやりたいという気持ちを高ぶらせていきます。
このときの千雪の心情の危機は、自分も『アプリコット』のオーディションに出たいと夜の大崎家を訪問して甘奈に伝えたとき、頂点に達したように見えます。夜に大崎家を突然訪問してしまうというところに千雪の行動の衝動性がうかがわれ、それほど切迫していたのだということが感じられるのです。そして千雪から『アプリコット』のオーディションに出たいということを聞いた甘奈は千雪を恐れており、千雪はそれほど鬼気迫るものだったと考えられるのです。
『アプリコット』のモデルを自分はやれるのか。大好きな『アプリコット』の世界観の中に自分自身の居場所はあるのか。千雪の問いはこうだったはずです。まさにこの場所にこそ、部屋の壁のひびは位置づけられるのであり、構築された世界観に存在しているひびは、『アプリコット』の世界観に自分そぐわないのではないかという千雪自身を開示していたと考えられるのです。
このひびについて千雪は「すぐに忙しくなっちゃって、いつの間にかそのままになって」という風に言っていますが、この部屋のひびが気にならなくなった時期は、「薄桃色にこんがらがって」の後日談を描いたサポートSSR【ドゥワッチャラブ!】のコミュの時期なのではないかと考えたくなります。
【ドゥワッチャラブ!】1つ目のコミュ「シネマじゃなくても」は、千雪が諳んじる『アプリコット』の記事の一節から始まります。これは次のような一節でした。
「この春は、映画のような恋にフォーカス! -シネマみたいに想って-
ねぇ、どうしてこんなにため息ばかり出ちゃうんだろう。だめだめ、ダーリン。カメラが回っているあいだは、ゴキゲンな天使でいて。エンドロールが夕焼けのように去って、音楽が最後の吐息を漏らしたあとも、続いていたら素敵じゃない? シネマの中で見ていた恋が」
ここでは、映画(の物語)という枠組みが、映画の終わった後にも続いていくことが示唆されます。映画を見終わった後でも、映画の中で見ていた物語の中で生きていくことができるというわけです。このことを実際に示すかのように、千雪はこの記事で特集されていた映画の中のため息のような、魅力的なため息をして見せています。またさらに、この特集の中に登場するブルベ―リータルトを実際に注文します。千雪は『アプリコット』の世界観の中に生きています。
しかしそこからの逸脱も同時に描かれます。『アプリコット』のモデルのオーディションに落ちたことの悔しさや悲しみを思い起こしつつ、それを乗り越えるようにしてブルーベリータルトを口にします。これは『アプリコット』の特集で取り上げられていた映画の中の場面を模したものですが、千雪はそのとき心の中でこうつぶやきます。「エンドロールは流れないし、音楽も終わらない」「私たちは続いていく。でも、素敵だね。シネマじゃなくても……」
『アプリコット』の記事が書いていたことは、映画にエンドロールが訪れ、その後にも映画の枠組みが続いていくということでした。しかし「シネマじゃなくても」における千雪にとっては、もはやそうではないのです。エンドロールは訪れません。なぜならこれは「シネマじゃな」いからです。「シネマじゃなくても」「素敵」なのです。『アプリコット』の描く世界観から足を踏み出し、その世界観の中にいないとしても、「素敵」であると、肯定的に受け止めることができているのです。
2つ目のコミュ「卒業」では、千雪の部屋について甜花と話しています。甜花は、この部屋自体が千雪のようであると言っていました。そして千雪は『アプリコット』を実家に送ろうと決意しているのです。千雪は『アプリコット』から「卒業」しようというのです。
この2つのコミュには、千雪が『アプリコット』の世界観から飛び出そうとしていることが分かります。部屋の世界観に対するシミとして存在するひびが気にならなくなったのは、この時期なのではないかと考えたくなるのです。
◇まなざしの侵襲性について
プチ・ジャンに波間に浮かぶ缶の話をされたときに面白くない気持ちになったように、あるいは千雪が壁のひびをふさぎたいと考えたように、まなざしという対象の出現は居心地の悪さを感じさせます。
しかしラカンは、通常まなざしは「姿を現さない」ものであり「省略」されていると言います(上166頁)。またラカンはまなざしという対象は「捉えられないという特徴」を持っており、「他のすべての対象にもまして無視され」るとも言っています(上183頁)。このようにまなざしという対象は通常では気づかれないものであり、それが現れてくるときには居心地の悪さを感じさせるものであるということが分かります。千雪は『アプリコット』のオーディションに出たいという衝動にかられ、夜に大崎家を訪問するということをしてしまいました。それほど切迫した状態にあったと考えられます。
このように、まなざしという対象が現れるということは、単に居心地の悪さを感じさせるだけでなく、侵襲的なもので精神の安定を揺さぶるものでありえます。そのことを示すためにはもっと深入りしなければならないのですが、ここではそこまでせず、文献を紹介することで替えさせてください。文献は3つです。
松本卓也、2018、「「恥の死滅」としての現代――羞恥の構造を読む」『享楽社会論――現代ラカン派の展開』人文書院: 179-200。
福田大輔、2021、「ラカンによるフロイトの欲望への問いかけ」『筋肉のメランコリー――ラカンとともに読む三島由紀夫』晃洋書房: 1-40。
春木奈美子、2015、「デュラスの描くふたりの女」『現実的なものの歓待――分析的経験のためのパッサージュ』創元社: 27-53。
松本卓也の「「恥の死滅」としての現代」は、今回引用したものです。このテキストは、ラカンのまなざしについて分かりやすく解説しつつ、まなざしという対象が現れるとき人は居心地の悪さを感じたり恥を感じたりするということをラカンに従って論じています。そして現代社会においては、居心地の悪さを感じさせたり恥を感じさせたりすることを抜きにまなざしが利用されているのではないかということが主張されています。リアリティショーなどにも触れられており、アイドルとして見る/見られるということが主題となることの多いシャニマスを読むにあたって参考になることの多いテキストであると思います。
福田大輔の「ラカンによるフロイトの欲望への問いかけ」は、フロイトの五大症例の1つである狼男症例についてのラカンによる批判を取り上げながら、症例の中で問題になるまなざしについて論じられています。このテキストを読むと、狼男症例の中でまなざしという対象が侵襲的なものとして現れてきており、その病理に深く関与しているということがよく分かります。そしてまた、フロイトから狼男の臨床を引き継いだブランスウィックの分析とそのラカンによる評価を参照しながら、治療の中でまなざしを鎮静化する道が探られています。
春木奈美子の「デュラスの描くふたりの女」では、マルグリット・デュラスの小説『ロル・V・シュタインの歓喜』が分析されており、小説の中で不気味なまなざしが現れて主人公のロルをまなざすところが取り上げられています。
◇おわりに
今回は千雪のひびについて見ていくことでラカンのまなざしについて理解を深めようということを企図しました。ラカンのまなざし概念は簡単なものではなく、その議論の全てを解説することは私にはできませんが、その入門くらいの役割が果たせていれば幸いです。
文献紹介のところでも書きましたが、シャニマスでは見る/見られるということが繰り返し主題に上がってきます。リアリティショーを取り上げた「ストーリー・ストーリー」や、見るということを直接問いかけるノクチルのシナリオ群などに顕著にそれらは現れています。まなざしの概念を挿入することで、これらのシナリオをさらに味わうことができるのではないかと考えています。特にこの点に関しては、松本卓也の「「恥の死滅」としての現代」はかなり参考になります。松本は次のように言います。
「眼差しもまた、ごくありふれたものになってしまった。かつて、眼差しは、人が神を観ることを可能にする存在論的な機能をもっていたし、ひとを辱めるような――エロスと結びつくような――暴力性をもっていた。ところが、眼差しがもつそのような機能がほとんど意識されないようになった現代においても、私たちはいまだに眼差しの機能をつかっている。眼差しによって他者を辱めるようなエロスは、いまだに私たちにある種の享楽をもたらしてくれるようである。しかし、私たちは徐々に眼差しの暴力性を忘れつつあるようだ。眼差しの暴力性を認識することなしに、眼差しの恩恵に預かるような「眼差しのフリーライド」が生じている場面も多々みられる[……](松本 2018: 199)。
「眼差しのフリーライド」という言葉は強烈ながら重要なワードであるように思います。たとえば、リアリティショーの中でまなざしにさらされている登場人物たちを、私たちはまなざし返される恐れを抱くことなく一方的に見て消費ことができます。またあるいは、バズを目的としたSNSのセルフィ―などを、私たちはいくらでも見て消費することができます。リアリティショーや、SNSのセルフィ―などは、まなざしの機能のもとで存在する(誰かに見られるという位置において自分自身を開示する)ものですが、それを見て消費する私たちは、逆にまなざし返されるおそれはなく、そうしたまなざしの機能について気付かないままに消費できてしまうわけです。
サルトルの『存在と無』の中に有名な覗きの場面があります。ラカンも『精神分析の四基本概念』(上183‐186頁)で参照していました。サルトルはこうした場面を描いています。ある人が廊下でドアの鍵穴から部屋の中を覗いています。そのとき廊下の階段から人が現れ、鍵穴を覗いているところを見られてしまいます。覗きをしていた人は、突然現れたそのまなざしに不意打ちを喰らい、羞恥を感じる、というのです。
しかしテレビやSNSの中の映像や画像を見るとき、私たちは誰かに見返される(まなざされる)ことなくそれらを見ることができてしまいます。そして日々SNSに入り浸っていると、見返される(まなざされる)ということがないとき映像や画像を見て消費する際の暴力性は増していくように思えてなりません。
シャニマスはこうした「眼差しのフリーライド」ということに対して問いを突き付けてきているのではないか、と私はずっと感じています。作中においても、アイドルを見て消費する人たちの意識的・無意識的な暴力性を描いており、さらにそれだけでなくシャニマスというゲームをプレイしシナリオを読む私たちに向かってもそうした問いを投げかけているように思えるのです。
暴力的なまなざしを告発する動画として、2013年のインドの映画祭で公開されたものが非常に分かりやすく、最後にこちらを紹介して終わろうと思います。動画の中で、男性たちは女性をじろじろと見つめています。そのまなざしは女性を視覚的に消費しようとするものです。しかし男性がまなざしている女性の身体のその場所に、男性のまなざしを反射して返すものが出現します。ここにラカン的な意味でのまなざしが現れていると見ることができるのです。
つまり、対象を見ているつもりであっても、対象の方こそがこちらを見ているというわけです。そしてその対象の方に現れるまなざしが、こちらが何者であるか(何をしているか)を開示するのです。
https://www.youtube.com/watch?v=SDYFqQZEdRA
◇はじめに
この文章は、大胆にもシャニマスを読むことを通してラカンの概念について考えてみようということを企図しています。そこで取り上げたいのは、「#283をひろげよう」の企画においてTwitterで千雪の上げた写真と、それに関する話、すなわち千雪の寮の部屋の壁のひびにまつわる話です。ここに、ラカンの考えるまなざしの概念を読み取ることができるのではないか、と私は考えています。ここではそれにトライしてみます。
セミネール11巻『精神分析の四基本概念』においてラカンはまなざしの概念について議論を展開しているのですが、それは簡単なものではありません。ですが、ラカンはその概念を理解するための補助としていくつも例を挙げており、そうした例に千雪の部屋の壁のひびを並べることができるのではないかと思われます。
まずは千雪が投稿していた部屋の壁のひびの写真を見ていきましょう。
https://twitter.com/imassc_official/status/1479094401699885197?s=20&t=h0eWLnor6wyD3vmpRnlWrg
こちらが壁のひびの写真です。この投稿に続けて、千雪は次のように述べています。
「初めてこのお部屋に来た頃は、どうにかしてふさげないかなって思ったんですが
すぐに忙しくなっちゃって、いつの間にかそのままになって
……もし、このひびを向こう側から覗いたら、あの頃の私が、あの頃の日々が見えるかもしれません
教えてあげたいな
どんな顔をしているかわからないけど、こっち側にいる未来の私は、とっても幸せだぞって」
この壁のひびにはいくつかポイントがあります。まずは、この壁のひびは最初は「どうにかしてふさげないか」と思ったものだということです。千雪の部屋は、コミュの背景にも登場しますが、小物などが並べられており、世界観が構築されています。しかもそれは雑誌『アプリコット』によって作られたものだということが推察できます(千雪の部屋がどのように作られていったかは、「薄桃色にこんがらがって」のサポートSSR【ドゥワッチャラブ!】の「卒業」の中で語られています)。ひびは、そうした世界観にそぐわないものであったはずで、それゆえ「ふさげないか」と考えられたのだと思われます。
2つ目のポイントは、ひびは覗き穴のようになって向こう側が見えるものであるということです。しかもそれは、こちら側から覗くのではなく、「向こう側から」覗くようになっているのです。
そして3つ目のポイントは、投稿された写真では、ひびは壁に映った千雪の影に重なるようにして写されているということです。
以上から、結論を先取りすると、かつての千雪にとって壁のひびは、ラカンが考えるまなざしという対象として現れていたのではないかと考えられるわけです。(ラカンの議論においては、まなざしは対象(objet)の1つです。)
それではこれからこのことを、ラカンが実際にまなざしという対象をどのようなものとして考えていたかをラカンの挙げた例を見ることによって確認していきましょう。
以下ラカンの『精神分析の四基本概念』の引用は、2020年に岩波文庫から上下巻で出版された小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭の翻訳から行います。
◇海に浮かぶ缶
ラカンが挙げている例の中で個人的に一番わかりやすい例が、この海に浮かんだ缶の話です(上206-210頁)。これは若い頃(20代)のラカンが実際に体験したという話で、要約するとこうです。
パリに生まれて育ったラカンは、医学部に入って精神科医になりました。精神分析家であるラカンのキャリアは精神科医として出発しています。ラカン自身が言っているように、これから話す体験をしたころのラカンは「若いインテリ」でした。
若いインテリであったラカンは、小さな漁港で漁師の家族とともに漁をしていました。当時ラカンが体験した漁は産業化される前のもので、小さな船に乗って危険を賭して行われるものでした。ラカンはある日、一緒に船に乗っていたプチ・ジャンという青年から、波間に漂う何かを指しながらこんなことを言われます。「あんたあの缶が見えるかい。あんたはあれが見えるだろ。でもね、やつの方じゃあんたを見ちゃいないぜ」(上207頁)。波間に浮かんだ缶は鰯の缶詰の缶で、太陽の光を浴びてキラキラ光っていました。
プチ・ジャンはこの話を面白がったそうですが、ラカンは全く面白くなかったようです。ラカンはここで、「それでもやはり缶は私を眼差しているからです。その缶は光点という意味で私を眼差しているのです」と言っています(上208頁)。どういうことでしょうか。ラカンはもう少し説明していますので、それを引用してみましょう。
「私の相棒が思いついたこのちょっとした話、この話が彼にはひどく面白く、私にはそれほどでもなかった理由は次の点にあります。つまり、彼がこんな話をしたのは、やはりこのときの私、つまり厳しい自然の中でやっとの思いで生きているこれらの人々に混じってすっかりその気になっていた私は、実に不調和な絵(タブロー)をなしていた、ということです。要するに、私は絵の中にあって多少ともシミとなっていたのです。それをどこかで感じていたからこそ、自分が不意に呼びかけられたと思っただけで、このユーモラスな、そして皮肉な話を別にそれほど面白いとは感じなかったのです」(上208頁)。
ラカンは漁師たちに混じって小さな漁港で小さな船に乗って、一緒に漁をしていたわけですが、その漁師たちの光景の中にそぐわない、浮いた存在となっていたわけです。ラカン自身は、漁師たちと一緒になって自分もそこに参加している気になりつつも、どこかで自分がそぐわない存在であるということを感じており、そのことを缶を通して指摘されたかたちになって、ラカンはこれを面白く感じなかったのです。
さて、この話の中で、波間に浮かんでキラキラ光る缶のところのところに、まなざしという対象があります。この話の中でラカンは、「絵(タブロー)」ということを言っていますが、これはラカンが混じっていた漁師たちの姿、その光景を指しています。そうした絵、光景を作るための視点、あるいは光点として現れてくるのが、波間に浮かんでキラキラ光る缶です。そうした缶のもとから見える光景の中においてラカンは、プチ・ジャンが「やつの方じゃあんたを見ちゃいない」と言うように、光景の中に見える存在として適切に位置づけられていないのであり、全くそぐわない存在として浮いている、ということになります。松本卓也(『享楽社会論』、人文書院、2018年)によれば、「ラカンは、自分がその場にそぐわない存在であることを、缶によって教えられた」のです(186頁)。
松本(2018)は次のようにまとめています。
「私たちはふつう、世界に対して、自分が何か(対象)を見ていると思っている。しかし、まさにそのとき、世界の中の何か(対象)から、むしろ自分が見られている。そして、そのような〈他者〉の眼差しによって、実は私たち自身のことが告げられてしまっている。その眼差しが私たち自身の「場違いさ」を示すとき、私は居づらさを感じる。そして、その眼差しによって、私たち自身の異様さが示されるからこそ、私たちは恥ずかしさを感じるのである」(松本 2018:186頁)
ラカンの考えるまなざしという対象は、こういうものです。
・自分が対象を見るのではなく、対象の方が私を見ている。
・自分の方を見る対象は、波間に浮かんでキラキラ光る缶のように、人格的な存在の視線であるとは限らない。
・自分を見る対象=まなざしのもとで、自分のいる光景が絵(タブロー)となる。
・自分の外部にあって自分の方を見る対象が、自分が何者であるかを示してくる。
・しかもそこで明らかにされることは、どちらかといえば居心地の悪いものである。
◇まなざしとしての部屋のひび
まなざしという対象がこのようなものであるとすると、千雪の部屋のひびというのは、まさに千雪にとってはまなざしという対象だったのではないか、と考えたくなってくるわけです。
千雪は山口県出身で、東京で一人暮らしをしながら雑貨屋に勤めていました。そこでアイドルにスカウトされ、当初は雑貨屋勤務とアイドル業の両方を務めています。WING編の途中で千雪はアイドル一本に絞ることを決意し、雑貨屋を辞めています。寮にいつ引っ越したのかは定かではないのですが(分かる方がいたら教えてください)、雑貨屋を辞めてアイドル一本に絞ることを決めたことよりも後に位置づけられるのではないかと思います。
千雪の寮の部屋は、コミュの背景で描かれているように小物がたくさん置かれています。この部屋の世界観はおそらく、千雪が愛読していた雑誌『アプリコット』の影響下にあったことが考えられます。部屋のひびは、そうして作り上げる世界観にそぐわないものとして存在していたと思われます。千雪はだからこそ、このひびをふさぐことを考えていました。作り上げる世界観を完全なものにするためです。
ここで部屋の世界観にそぐわないものとして現れてくるひびは、漁の小舟に乗っているときラカンの前に現れた波間に光る缶と同じものだったのではないでしょうか。つまり壁のひびは、自分をその場の光景にそぐわないものとして開示するまなざしという対象だったのではないか。
また「薄桃色にこんがらがって」のサポートSSR【ドゥワッチャラブ!】の「卒業」では、寮の自分の部屋を作り上げることを「まっさらな場所に絵を描くみたい」だったと語っています。それゆえ壁のひびは「絵」に現れたシミであったと考えられるのです。
このことを示すかのように、壁のひびの写真には千雪自身の影がひびに重なるように写されています。千雪という人物の姿(=影)は部屋の絵(タブロー)の中の一部となっており、しかもひびは千雪自身の姿に重なっているわけです。千雪という姿の中にひびが現れているようであり、部屋のひびの場所にこそ千雪という人物の存在が現れているというようにも見えます。またあるいは、ひびは自分の外部に存在するものであるが、しかし自分が何者であるのかを開示するような自分自身にとって重要な一部であるということを示しているかのようです。
そして千雪はこのひびに対してこう言っています。「向こう側から覗いたら、あの頃の私が、あの頃の日々が見えるかもしれません」。重要なのは、ひびを通してこちらから向こう側を覗くのではなく、「向こう側から」覗くということです。千雪はひびの向こう側からまなざされるわけです。まなざすのはこちらではなく、向こう側なのです。
このように、壁のひびは千雪にとってのまなざしという対象として現れていたのではないかと考えられるのです。
ではこのひびが開示する「その場の光景にそぐわないもの」としての千雪自身とはどういうことだったのでしょうか。
まず最初に考えられるのは、これは推測ですが、アイドルになりたての頃の自分自身ということです。アイドルになりたての頃、自分は「アイドル」をちゃんとやれているだろうか、と自分自身に問うということはありそうなことです。そういう意味で、壁のひびにおいて自分が「その場の光景にそぐわないもの」として開示されていると考えることができます。
もう一つ、より突っ込んだこととして考えられることがあります。それはイベントシナリオ「薄桃色にこんがらがって」で描かれたことです。つまり、『アプリコット』という世界観の中にそぐわないものとしての自分自身が開示されていたのではないか、という解釈です。
千雪は雑誌『アプリコット』の愛読者でした。『アプリコット』の世界観に憧れ、記事の一節を諳んじることができるほど読み込んでいました。その『アプリコット』が復刊する際の雑誌のモデルとして、出版社から甘奈が推薦されます。しかしそれは、甘奈が優勝することが内定したオーディションを公募で行う形式とするというものでした。千雪は、ユニットメンバーである甘奈の抜擢を喜ばしく思う一方、自分が『アプリコット』のモデルをやりたいという気持ちを高ぶらせていきます。
このときの千雪の心情の危機は、自分も『アプリコット』のオーディションに出たいと夜の大崎家を訪問して甘奈に伝えたとき、頂点に達したように見えます。夜に大崎家を突然訪問してしまうというところに千雪の行動の衝動性がうかがわれ、それほど切迫していたのだということが感じられるのです。そして千雪から『アプリコット』のオーディションに出たいということを聞いた甘奈は千雪を恐れており、千雪はそれほど鬼気迫るものだったと考えられるのです。
『アプリコット』のモデルを自分はやれるのか。大好きな『アプリコット』の世界観の中に自分自身の居場所はあるのか。千雪の問いはこうだったはずです。まさにこの場所にこそ、部屋の壁のひびは位置づけられるのであり、構築された世界観に存在しているひびは、『アプリコット』の世界観に自分そぐわないのではないかという千雪自身を開示していたと考えられるのです。
このひびについて千雪は「すぐに忙しくなっちゃって、いつの間にかそのままになって」という風に言っていますが、この部屋のひびが気にならなくなった時期は、「薄桃色にこんがらがって」の後日談を描いたサポートSSR【ドゥワッチャラブ!】のコミュの時期なのではないかと考えたくなります。
【ドゥワッチャラブ!】1つ目のコミュ「シネマじゃなくても」は、千雪が諳んじる『アプリコット』の記事の一節から始まります。これは次のような一節でした。
「この春は、映画のような恋にフォーカス! -シネマみたいに想って-
ねぇ、どうしてこんなにため息ばかり出ちゃうんだろう。だめだめ、ダーリン。カメラが回っているあいだは、ゴキゲンな天使でいて。エンドロールが夕焼けのように去って、音楽が最後の吐息を漏らしたあとも、続いていたら素敵じゃない? シネマの中で見ていた恋が」
ここでは、映画(の物語)という枠組みが、映画の終わった後にも続いていくことが示唆されます。映画を見終わった後でも、映画の中で見ていた物語の中で生きていくことができるというわけです。このことを実際に示すかのように、千雪はこの記事で特集されていた映画の中のため息のような、魅力的なため息をして見せています。またさらに、この特集の中に登場するブルベ―リータルトを実際に注文します。千雪は『アプリコット』の世界観の中に生きています。
しかしそこからの逸脱も同時に描かれます。『アプリコット』のモデルのオーディションに落ちたことの悔しさや悲しみを思い起こしつつ、それを乗り越えるようにしてブルーベリータルトを口にします。これは『アプリコット』の特集で取り上げられていた映画の中の場面を模したものですが、千雪はそのとき心の中でこうつぶやきます。「エンドロールは流れないし、音楽も終わらない」「私たちは続いていく。でも、素敵だね。シネマじゃなくても……」
『アプリコット』の記事が書いていたことは、映画にエンドロールが訪れ、その後にも映画の枠組みが続いていくということでした。しかし「シネマじゃなくても」における千雪にとっては、もはやそうではないのです。エンドロールは訪れません。なぜならこれは「シネマじゃな」いからです。「シネマじゃなくても」「素敵」なのです。『アプリコット』の描く世界観から足を踏み出し、その世界観の中にいないとしても、「素敵」であると、肯定的に受け止めることができているのです。
2つ目のコミュ「卒業」では、千雪の部屋について甜花と話しています。甜花は、この部屋自体が千雪のようであると言っていました。そして千雪は『アプリコット』を実家に送ろうと決意しているのです。千雪は『アプリコット』から「卒業」しようというのです。
この2つのコミュには、千雪が『アプリコット』の世界観から飛び出そうとしていることが分かります。部屋の世界観に対するシミとして存在するひびが気にならなくなったのは、この時期なのではないかと考えたくなるのです。
◇まなざしの侵襲性について
プチ・ジャンに波間に浮かぶ缶の話をされたときに面白くない気持ちになったように、あるいは千雪が壁のひびをふさぎたいと考えたように、まなざしという対象の出現は居心地の悪さを感じさせます。
しかしラカンは、通常まなざしは「姿を現さない」ものであり「省略」されていると言います(上166頁)。またラカンはまなざしという対象は「捉えられないという特徴」を持っており、「他のすべての対象にもまして無視され」るとも言っています(上183頁)。このようにまなざしという対象は通常では気づかれないものであり、それが現れてくるときには居心地の悪さを感じさせるものであるということが分かります。千雪は『アプリコット』のオーディションに出たいという衝動にかられ、夜に大崎家を訪問するということをしてしまいました。それほど切迫した状態にあったと考えられます。
このように、まなざしという対象が現れるということは、単に居心地の悪さを感じさせるだけでなく、侵襲的なもので精神の安定を揺さぶるものでありえます。そのことを示すためにはもっと深入りしなければならないのですが、ここではそこまでせず、文献を紹介することで替えさせてください。文献は3つです。
松本卓也、2018、「「恥の死滅」としての現代――羞恥の構造を読む」『享楽社会論――現代ラカン派の展開』人文書院: 179-200。
福田大輔、2021、「ラカンによるフロイトの欲望への問いかけ」『筋肉のメランコリー――ラカンとともに読む三島由紀夫』晃洋書房: 1-40。
春木奈美子、2015、「デュラスの描くふたりの女」『現実的なものの歓待――分析的経験のためのパッサージュ』創元社: 27-53。
松本卓也の「「恥の死滅」としての現代」は、今回引用したものです。このテキストは、ラカンのまなざしについて分かりやすく解説しつつ、まなざしという対象が現れるとき人は居心地の悪さを感じたり恥を感じたりするということをラカンに従って論じています。そして現代社会においては、居心地の悪さを感じさせたり恥を感じさせたりすることを抜きにまなざしが利用されているのではないかということが主張されています。リアリティショーなどにも触れられており、アイドルとして見る/見られるということが主題となることの多いシャニマスを読むにあたって参考になることの多いテキストであると思います。
福田大輔の「ラカンによるフロイトの欲望への問いかけ」は、フロイトの五大症例の1つである狼男症例についてのラカンによる批判を取り上げながら、症例の中で問題になるまなざしについて論じられています。このテキストを読むと、狼男症例の中でまなざしという対象が侵襲的なものとして現れてきており、その病理に深く関与しているということがよく分かります。そしてまた、フロイトから狼男の臨床を引き継いだブランスウィックの分析とそのラカンによる評価を参照しながら、治療の中でまなざしを鎮静化する道が探られています。
春木奈美子の「デュラスの描くふたりの女」では、マルグリット・デュラスの小説『ロル・V・シュタインの歓喜』が分析されており、小説の中で不気味なまなざしが現れて主人公のロルをまなざすところが取り上げられています。
◇おわりに
今回は千雪のひびについて見ていくことでラカンのまなざしについて理解を深めようということを企図しました。ラカンのまなざし概念は簡単なものではなく、その議論の全てを解説することは私にはできませんが、その入門くらいの役割が果たせていれば幸いです。
文献紹介のところでも書きましたが、シャニマスでは見る/見られるということが繰り返し主題に上がってきます。リアリティショーを取り上げた「ストーリー・ストーリー」や、見るということを直接問いかけるノクチルのシナリオ群などに顕著にそれらは現れています。まなざしの概念を挿入することで、これらのシナリオをさらに味わうことができるのではないかと考えています。特にこの点に関しては、松本卓也の「「恥の死滅」としての現代」はかなり参考になります。松本は次のように言います。
「眼差しもまた、ごくありふれたものになってしまった。かつて、眼差しは、人が神を観ることを可能にする存在論的な機能をもっていたし、ひとを辱めるような――エロスと結びつくような――暴力性をもっていた。ところが、眼差しがもつそのような機能がほとんど意識されないようになった現代においても、私たちはいまだに眼差しの機能をつかっている。眼差しによって他者を辱めるようなエロスは、いまだに私たちにある種の享楽をもたらしてくれるようである。しかし、私たちは徐々に眼差しの暴力性を忘れつつあるようだ。眼差しの暴力性を認識することなしに、眼差しの恩恵に預かるような「眼差しのフリーライド」が生じている場面も多々みられる[……](松本 2018: 199)。
「眼差しのフリーライド」という言葉は強烈ながら重要なワードであるように思います。たとえば、リアリティショーの中でまなざしにさらされている登場人物たちを、私たちはまなざし返される恐れを抱くことなく一方的に見て消費ことができます。またあるいは、バズを目的としたSNSのセルフィ―などを、私たちはいくらでも見て消費することができます。リアリティショーや、SNSのセルフィ―などは、まなざしの機能のもとで存在する(誰かに見られるという位置において自分自身を開示する)ものですが、それを見て消費する私たちは、逆にまなざし返されるおそれはなく、そうしたまなざしの機能について気付かないままに消費できてしまうわけです。
サルトルの『存在と無』の中に有名な覗きの場面があります。ラカンも『精神分析の四基本概念』(上183‐186頁)で参照していました。サルトルはこうした場面を描いています。ある人が廊下でドアの鍵穴から部屋の中を覗いています。そのとき廊下の階段から人が現れ、鍵穴を覗いているところを見られてしまいます。覗きをしていた人は、突然現れたそのまなざしに不意打ちを喰らい、羞恥を感じる、というのです。
しかしテレビやSNSの中の映像や画像を見るとき、私たちは誰かに見返される(まなざされる)ことなくそれらを見ることができてしまいます。そして日々SNSに入り浸っていると、見返される(まなざされる)ということがないとき映像や画像を見て消費する際の暴力性は増していくように思えてなりません。
シャニマスはこうした「眼差しのフリーライド」ということに対して問いを突き付けてきているのではないか、と私はずっと感じています。作中においても、アイドルを見て消費する人たちの意識的・無意識的な暴力性を描いており、さらにそれだけでなくシャニマスというゲームをプレイしシナリオを読む私たちに向かってもそうした問いを投げかけているように思えるのです。
暴力的なまなざしを告発する動画として、2013年のインドの映画祭で公開されたものが非常に分かりやすく、最後にこちらを紹介して終わろうと思います。動画の中で、男性たちは女性をじろじろと見つめています。そのまなざしは女性を視覚的に消費しようとするものです。しかし男性がまなざしている女性の身体のその場所に、男性のまなざしを反射して返すものが出現します。ここにラカン的な意味でのまなざしが現れていると見ることができるのです。
つまり、対象を見ているつもりであっても、対象の方こそがこちらを見ているというわけです。そしてその対象の方に現れるまなざしが、こちらが何者であるか(何をしているか)を開示するのです。
https://www.youtube.com/watch?v=SDYFqQZEdRA
1週間は長いなーと感じるけど、1ヶ月はすごく早く感じる……
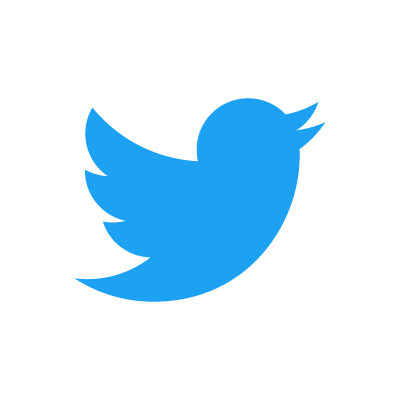 元ツイート
元ツイート