見えるものと見えないもの――幽谷霧子と杜野凛世の「心」について
初出:2019年7月15日Privatterに投稿
◆夢と現実
◇生きていないもの、意識を持っていないもの
幽谷霧子は、普通生きてないとされるもの(「カメラのレンズさん」)、普通意識がないとされるもの(「ゼラニウムさん」)に対して語りかける。子どもがするごっこ遊びのようなものであるのかもしれないが、霧子は17歳であり、そういうごっこ遊びをするのは「子どもっぽい」と思われる年齢だろう。けれど霧子がそれらに語りかけるさまは、こちらにそう茶化すような気を起させない誠実さが感じられる。霧子がするそれは、擬人化であるよりももっと真剣な何かではないかとこちらに思わせる、そういう力がある。
霧子は「カメラのレンズさん」や「ゼラニウムさん」たちが、生きて意識を持っていると真剣に思っているのだろうか。霧子の言葉に耳を傾けると、どうやらそうではないようだということがわかってくる。プロデューサーがゼラニウムやユキノシタの鉢に張り付けたメモを見つけた霧子は、「お花さんから…… お礼、言われてるみたい」と言う。「みたい」ということは、それが本当ではないということを知っている、ということだ。けれどその直後に霧子はユキノシタに向かって「どういたしまして、ユキノシタさん…… これからも……いっぱいお話しようね……」と語りかける。この語りかけが、「みたい」の範疇にあるものなのかどうか、もはや定かではないような気がしてくる。
霧子の中で、何が生きているとされるものなのか、何が意識を持つとされるものなのか、といった常識的なことはふまえられているように思われる。だがその上でなお、そうした生きていないとされるもの、意識を持たないとされるものに対して、生きており意識を持っているようなものとして接している。この二段構えがある。
もっと抽象化すればこうなるだろう。フィクションと現実との区別はついているのだが、その上で、フィクションを現実と同レベルのものとして扱う、ということである。霧子にはそういう節がある。
◇デカルトの夢の懐疑
それがよく表れているのが【我・思・君・思】の二番目のコミュ「かなかな」だろう。「かなかな」では、デカルトの夢の懐疑が取り上げられている。
まずデカルトの懐疑を確認しておこう。
デカルトは、決して疑うことができない、確実な真理を手にしたかった。だから、その疑いえない確実な真理を手に入れるために、全てを疑ってみようと試みたのである。疑わしいものを排除していき、その果てに疑いえない確実なものがあると考えたのである。
さてここでデカルトがまず疑ったのが、自らの感覚であった。自分がいま部屋にいて、椅子に座って、紙を手にもって書かれたものを読んでいるとしよう。でも人間の感覚というのは時に間違うものだ。それに、こうしていま椅子に座って書かれたものを読んでいるということと全く同じことが、夢の中で繰り広げられることがある。現実と間違ってしまうような夢を見てしまうことが、実際にあるのだ。ならば、こうしていま部屋にいるということは、実は夢であるかもしれない。これが夢ではないということのしるしはない。ならばこれは今本当に夢なのではないか。……とデカルトは疑いを進めていく。これが夢の懐疑である。
この夢の懐疑が居座り続ける限り、確実な真理には到達しえない。科学的な事実や、歴史的な事実をいくら発見してみたところで、もし全てが夢だとしたら、それは疑いえない確実な真理ではなくなってしまう。全ては夢かもしれないという可能性があるだけで、確実さは失われる。だから、確実な真理を手にするためには、全ては夢かもしれないという夢の懐疑を退ける必要があるのだ。デカルトが知りたいと願った現実世界について、夢かもしれないという懐疑を一切抜きにして、アプローチできるのでなければならないのだ。
さて、デカルトが夢の懐疑の果てにたどり着いた真理こそ、「われ思う、ゆえにわれあり」にほかならない。これは、あらゆるものに疑いを差し向けたところで、その疑いそのものは疑いえないということである。そうして疑うことで思考する私そのものは、確実に存在するのだ。デカルトはここにたどり着いた。
デカルトはその後、神の存在証明を行い、神は欺かないと考え、明晰な思考に基づく判断は確実であるという確実さにたどり着く。理性に基づいて思考すれば、現実世界について確実な知識を得ることができるのである。
ここで確認しておきたいのは、夢と現実についての、デカルトの疑い方である。デカルトは、ふつう現実とされるものについて、「これは夢かもしれない」と疑った。そしてデカルトにとっては、現実が夢であっては困るのである。
◇霧子にとっての夢
さて、【我・思・君・思】の二番目のコミュでは、デカルトの名前が引用され、「これは夢かもしれない」という夢の懐疑が咲耶によって紹介される。咲耶は霧子に夢の懐疑を投げかける。霧子は、「夢…… かもしれない……」「夢じゃない……って…… 言えない……」と結論づける。
デカルトならば、それは大変困った事態である。デカルトは現実世界について、確実にアプローチする方法が必要だったのだから。
だが、霧子は動じない。
咲耶との話の中で、霧子の瞼は再び重くなる。そこで霧子はこう言う。
「眠っちゃいそう……
あ……――
これから……起きるのかな……」
今は夢であるのかもしれない。そうであるとしたら、これから眠るということは、目が覚めることであるのかもしれない。
現実と夢とを対比するとき、ふつうは、現実世界に生きる人間が、眠っている間に夢を見ている、と考えるだろう。そして眠っている人の身体は、現実世界にずっと横たわって存在し続け、その身体内部の脳が、夢という幻覚を見ている(見せている)のだと。こう考えるとしたら、現実に実在するのは、眠り続けている身体の方だ。そして、「目覚める」ということは、常に、この眠り続けていた身体の方に目覚めるのである。夢は、現実世界の中に存在し続ける身体の中に生じた、一時的なバグのようなものであるとされる。(そうであればこそ、夢の中で見たことや体験したことを、実際に見たものや体験したこととして語るのは変なことであるとされるのだ。)
だが、ここで霧子はこう考えていない。眠るということと、目覚めるということの区別が消えかかっているのである。夢に対して現実が、ずっと存在し続けている土台のような役割を果たせなくなっているのである。夢世界と現実世界とが交互に立ち現れるような状態になっている。そのとき、どちらが本当の「現実」であるのかは、もはや分からなくなっている。胡蝶の夢である。
霧子はさらにこう続ける。
「あのね……
どっちでも……嬉しいな……
今見てるのが……夢でも……
夢でなくても……
この咲耶さんが……
咲耶さんで……
次に会う咲耶さんも……
この咲耶さんなら……」
もはやどちらが本当の「現実」であるのかは、ここの霧子にとっては問題ではなくなっている。デカルトがあれほど確実な現実世界へのアプローチを求めていたのに、荘子が胡蝶の夢に頭を悩ませたのに。その問題は霧子にとっては重要な問題ではない。
霧子にとって重要なのは、目覚め=眠りを繰り返すことで交互に立ち現れる諸世界において、咲耶やみんなが同一であり続けるということだ。これは、夢と現実のふつうの区別のレベルで考えるとすれば、夢の中に登場した人物と、夢から覚めた世界にいる人物との間の同一性を考えるということにほかならない。これは、ふつう、変なことだとされる。
第一に、夢の中でAさんに殴られたとしよう。夢から覚めてAさんに会ったとき、夢の中で殴られたことの責任を、Aさんに帰するようなことは、普通はしない。
第二に、夢の中である人物に出会ったとしよう。この人物のことは、現実世界においてはまったく知らず、夢の中で初めて会ったとしよう。その人物を、夢から覚めた世界において探すようなことは、ふつうはしない。
第三に、夢というのは、ふつうは一人で見るものである。同一の夢を複数人で見るとはふつうは考えられない。もしそれらしきことが起こったとしたら、ふつう考えられるのは、たまたまその複数人が同じ日によく似た夢を見た、ということに違いない。
夢の中に登場した人物に対して、ふつうはこういう風に捉えられるだろう。夢の中の登場人物について、現実世界(とされる世界)に存在するふつうの人間と同等に扱うのは、変なことであるとされるのである。だが、霧子は、「この咲耶さん」にまた会うことを願い、次に会う咲耶さんが「この咲耶さん」であることを願うのだ。
◇虚の仲間たち
霧子にとって、夢の中に登場する人間もまた、現実世界に存在する人間と同等の存在でありうるのではないか、と考えたくなる。夢の中の登場人物は、ふつう現実に実在しない人間であるとされる。それはふつう、現実に存在する人間とは同等に並べられない。この、現実に存在する人間とは同等に並べられないものの系列に、夢の中の登場人物のほか、生きてないとされるもの、意識を持たないとされるものが、加わるのではないかと思う。霧子にとって、そういう者たちも、仲間なのではないか。
教会のステンドグラスの燦めきを目にしたとき、霧子はその場に存在しない無数の人間の祈りを思い浮かべた。そこにいない者たちが、そこで霧子の傍にいる。
ふつう、「われわれ」として考えられるのは、現実に存在し、言語を話す人間だろう。一部の動物もそこに含まれるかもしれない。けれど、おそらく霧子にとっては、「カメラのレンズさん」や「ゼラニウムさん」や夢の中の登場人物や、今その場にはいない過去の無数の人間もまた、「われわれ」の仲間になるのではないかと思う。
デカルトは、確かにいったん、夢と現実を区別するしるしはない、と考えた。この夢の懐疑の一瞬において、夢と現実とは区別ができなくなる。だがデカルトにおいてのそれは、現実とされるものが、実は夢にすぎないかもしれないと疑うことだ。デカルトにおいて、現実は依然として優位に置かれている。その現実を、夢という偽物から救いたい、といった風である。
一方霧子の立場では、夢とされるものが実は現実であるかもしれないと考えていることになる。それはいわば、現実から切り落とされたものたちを、ふたたび現実の元へと連れ戻そうとするかのようだ。霧子はよく、小さなものへと視線を向ける。それはふつうの人ならば見落としてしまうような何かだ。霧子は、ふつうの人がそうやって見落としてしまうもの、ふつうの人が現実でないとして切り落としてしまうものへと、視線を向ける。霧子が探すうさぎ座は、オリオンの下にあるのに見つけられない。霧子はそういう、見えなくなっているものへと視線を向ける。
なぜそういうものたちへと霧子は視線を向けるのか。これは私の仮説にすぎないのだけれども、霧子という存在が、実はすでにしてそういう虚の系列に加わるものだったのではないか。
◆見えないもの
◇「私」というものについて
霧子が、実はそうした虚の系列に加わる存在なのではないか、と考える根拠は、大きく分けて二つある。一つ目は理論的なものであり、二つ目は霧子の特徴に基づくものである。この二つは繋がっている。
まずは一つ目の方から。それは、「私」というもののあり方に基づくものだ。「私」というものは、すでにして「われわれ」にとっての余剰なのではないか。「私」というものは、虚の系列に入るものなのではないか。
ウィトゲンシュタインは、独我論について次のように書いている。
「独我論と我々が呼ぶ人、そしてただ自分の経験のみが本当のものだという人、その人は何もそれで実際的な事実問題について我々と食い違いがあるわけではない。我々が痛みを訴える時、ただそのふりをしているだけだとは彼は言わないし、他の誰に劣らず気の毒に思ってくれる。しかし同時に彼は、「本当の」という、通り名を我々が彼の経験と呼ぶべきものだけ限りそして多分更に我々の経験をどんな意味であれ「経験」とは呼びたくないのである[……]」(ウィトゲンシュタイン,『青色本』大森荘蔵訳,ちくま学芸文庫,p.137)。
ここで取り出しておきたいのは、自分の経験に対してのみ「本当の」という言葉を付けるという言葉遣いである。われわれの多くは独我論ではないかもしれない。けれど、他人が殴られても、その痛みは私には感じられないのである。殴られて本当に痛いのは、私だけなのだ。だから、痛みに関しても、他人が抱く痛みと、私が抱く痛みの間には、超えられない差がある。
Aという他人が痛みを持つということについて独我論者がどう考えるかというと、黒崎宏は「この場合、独我論者は例えば「Aはイダミを持っている」とでも言うかもしれない」と言う(『『青色本』読解』産業図書,p.101)。自分が持つ痛みを「痛み」、他人が持つ痛みを「イダミ」として区別しよう、というわけである。ここには、自分の痛みこそが「本当の痛み」、他人が持つ痛みは「虚構の痛み」という区別がある。永井均は、この区別を「実痛み」「虚痛み」と名付けて整理する(『『青色本』を掘り崩す』ナカニシヤ出版,p.117)。
興味深いのは、自他に対応していた「実痛み」「虚痛み」が、逆転しうると永井が指摘していることである。
「むしろ逆に、他人の痛みはみなごくふつうに正当に「痛み」と呼ばれるべきものであるが、自分のはまったく比類のない不思議なものだから、通常の言葉には存在しない「イダミ」とでも呼んでおこう、と考えても不思議ではない。したがって「実」と「虚」の対比に戻っていえば、他人の側のを「実痛み」と呼んで自分の側のを「虚痛み」と呼びたくなっても、べつに独我論に反するところはない」(『『青色本』を掘り崩す』,pp.120-121)。
殴られて本当に痛いのは、私だけである。けれども、私が殴られたときに感じるこの痛みそのものは、他人たちには全く理解されない。他人に通じるのは、私が殴られたという状況や、表情や振る舞いに現れる痛がっている様子や、「痛い!」という私の言葉だけだ。それしか、他人には伝わらない。そしてそれらは、他人が表出しているものの全てである。
だから、人間たちに「痛み」が生じる状況や、人間たちが「痛み」を抱いているとする表情や振る舞いや、人間たちが「痛い」と発する言葉などにおいて、私が本当に感じる痛みそのもののようなものは、全く機能していないのである。それは他の歯車と噛み合っていない空転する歯車のようなものである。だから、その痛みそのものは、人間たちのコミュニケーションの中では、虚の方に位置付けられると言える。
だから、全ての他人は、私が持つような本当の感覚を持つことがない、ゾンビであるのかもしれないのである。だが、私が持つような本当の感覚というものは、他人たちには絶対に伝わらない。だから、他人たちの方を基準にすれば、私の方こそが余計な何かを持ってしまった、異質な存在だということになる。
「私」という存在は、「われわれ」にとっては余剰となる何かなのだ。その点において、「私」という存在は、「われわれ」に含み入れられない、虚の系列に位置付けられるものに近いのである。「われわれ」から落とされてしまう存在とは、たとえば、生きていないとされるもの、意識を持たないとされるもの、夢の中の登場人物、などである。それはつまり、「カメラのレンズさん」であり、「ゼラニウムさん」であり、「この咲耶さん」である。
◇霧子の「私」
霧子のWING編のプロデュースを始めると、オーディションに合格した霧子と会議室で出会うところから始まる。そこでプロデューサーが霧子の名前を言うと、霧子は「わたしの名前、覚えていてくれたんですね……」と言う。自分の名前を覚えてもらっていない(かもしれない)と思っていたようである。プロデューサーは霧子を「控え目」と評するが、霧子にとって、自分の存在はこの世から消えてしまっている(見えなくなっている)のではないかと思わせる雰囲気があるように思う。
プロデュースの最初のコミュのタイトルは、その名も「みえない献身」である。霧子は普段からレッスン室を掃除していたのだが、それをプロデューサーも気づかないでいた。プロデューサーが霧子を褒めると、霧子は「あんまり…… そんなふうに言ってもらったこと……なくて…… すごく…… う、嬉しい……です!」と言う。
この後で選択肢があるのだが、私がDaでよくプロデュースする都合もあり、よく「それは霧子のためにもなるって思うぞ」を選ぶ。実際この選択肢が好きだ。プロデューサーは「アイドル幽谷霧子が育つ場所なんだってことを覚えておいてほしい」と言う。ここはレッスン室であり、レッスン室を自分から掃除するということ自体が、アイドル幽谷霧子にとっての成長になるということなのだ。プロデューサーはここで、レッスン室の中で成長する人間の中に霧子を数え入れているのである。
さて次のコミュでは、オーディションで様子がおかしかった霧子について語られる。霧子は、パフォーマンスをする中で「ダンスのときは、隣の人の邪魔になったらいけないって……」「自己アピールのときは…… 大きな声を出したら、他の人が驚いてしまうなって……」と言う。ふつうオーディションにおいてはダンスをするために十分な空間があるはずだし、大きな声で自己アピールをするのが当然で、それが誰かを驚かしたりはしないだろう。まるで霧子は、自分が存在するということそのものが他人にとって迷惑になってしまうのではないかと心配しているかのようである。
これに対してプロデューサーは、ダンスをもっと大胆にやってもいいんだよとか、大きな声で自己アピールしてもいいんだよといった風には言わない。そうやって心配してしまう霧子のあり方そのものが霧子の魅力であり、それがアイドル幽谷霧子を作っていくということを言うのだ。ここでプロデューサーは、霧子の心を肯定しているのである。
シーズン4のコミュでは、霧子のファッション誌の撮影のお仕事をしている様子が描かれる。そこで霧子は自分の包帯を見せるような構図を自ら提案する。霧子は包帯や絆創膏をよく身に着けているが、それは身体に傷があるからではない。霧子は、不安や自信がなかったりするとき、包帯や絆創膏を身に着ける。実際オーディションで負けてしまったとき、控室で霧子は絆創膏を貼っている。身体上に付ける絆創膏や包帯は、身体ではなく心の問題を表していると言える。
霧子は絆創膏や包帯の下に「隠している」と言っていたが、シーズン4の頃には、それも「見てもらいたい」と思うようになる。それはつまり、霧子の心の内をみんなに見てもらいたいということだろう。「みんな霧子に夢中になるよ」を選択すると、「霧子がこれまで、大事にしてきたこと……」「そういうことがきっと、包帯の下で眠ってたんだよ」とプロデューサーは言うのである。
◇内面
このように、霧子の控え目さというのは、自分を数に数え入れていなかったり、自分の存在自体が他人の迷惑になってしまうのではないかと考えたりするということでもある。霧子は、自分の存在はふつうの人たちの中では浮いてしまうと思っているのではないか。
だから、ふつうの人間の数を数えようとすれば、そこから浮いてしまうものは数え入れられない。一方で、自分の存在を主張しようとすれば、ふつうの人間の中に適切な居場所がないのだから、余計なものとして周りに影響を与えてしまう。……こう考えているのではないか。つまり霧子は、自分はoddだと思っているのではないか……
なぜ霧子はoddとなってしまうのだろう。そのヒントが、絆創膏や包帯(の下にあるもの)ではないか、と私は思う。
絆創膏や包帯は、霧子にとって内面のよくないものを隠すものであった。だが、絆創膏や包帯は、他人から見えるものでもある。絆創膏や包帯が身に付けられているということは、その裏側に何かがありますよということを他人に伝える。絆創膏や包帯は、隠すものでありながら、明示するものでもあるのだ。
絆創膏や包帯の裏にあるものは、霧子の内面である。つまり霧子は、絆創膏や包帯を身に着けることによって、内面を隠すと同時に、見えるようにしていたのだ。
ここで、虚の方に位置付けられる「「私」の本当の感覚」と結びつく。霧子という存在、および霧子の内面は、ただ存在するだけでは、ふつうの人間たちの間では存在するものとして数え入れられることがない。見えなくなっているのである。(「幽」谷「霧」子という、幽と霧という実体のないものを名に持つところからも、それが感じられるような気さえする。)
◇鏡像段階
幽や霧は、実体がない。実体がないものは、うまく存在するものとして位置づけられない。この現実世界とされる世界において、ふつうの人間として数え入れられるためには、幽や霧ではなく、実体を持つこと、つまり身体を持つことが必要になる。
フランスの精神分析家ジャック・ラカンによれば、人間の赤ちゃんは、鏡に映った像を自分であるとみなすことによって、自我(「私」)が形成される。これを鏡像段階と言う(「〈わたし〉の機能を形成するものとしての鏡像段階」『エクリⅠ』弘文堂)。
生まれたばかりの赤ちゃんは、神経系が未発達であるので、身体感覚が統合されていない。このときの身体を、ラカンは「寸断された身体」と呼ぶ。赤ちゃんにとって身体はばらばらなのである。この状態の赤ちゃんの前に、鏡(の像)が現れる。赤ちゃんはそこに映った像を自分の像として引き受けることで、自分の統一的な自己像を獲得する。それは神経系の発達に先立つのである。
赤ちゃんが自分の姿として引き受ける像は、必ずしも鏡に映った像でなくてもよく、赤ちゃんの兄弟(姉妹)や、他の子どもなどもその像の役割を果たすことができる。つまり鏡像段階とは、自分もほかの他人と同じように身体を持ってこの世に生きている、ということを引き受けるということなのだ。それはまさに、幽や霧のようなものが、実体を持って世界に存在し始めるようなものである。
ラカンの鏡像段階論の興味深いところは、他者こそが自我のモデルであると考えるところにある。自我がまずあって、その似姿として他者を考えるのではない。他者がまずあって、その似姿として自我があるのである。「私」が持つ本当の感覚が虚の系列に落ちてしまうのは、そのためだとも言える。
さらに興味深いのは、そうした自我のモデルとなる他者は、「自動人形」のようなものにすぎないということをラカンが示唆しているということだ。鏡像段階において自我のモデルとなる他者は、理論的には、必ずしも生きているものや、意識を持っているものではないのである。だからその他者はゾンビであってもかまわないのである。だからこの鏡像段階論に従うなら、「私」というものはすでにして、虚の系列に位置付けられるものたちと仲間でありえているはずなのである。
ラカンは、寸断された身体の状態にある赤ちゃんが統一的な自己像を獲得する過程を、「形成外科的」と表現する。あるいは、型の中に飛び込むようなイメージを与える。ここでラカンが注意しているのは、鏡像段階によって統一的な自己像が獲得されたとしても、寸断された身体が消えてなくなるわけではないということだ。精神的な疾患にかかってしまったときや、夜眠っている間に見る夢などに、それは表れるという。
鏡像段階は、他人たちをモデルにして自分を形成することであるが、他人たちをモデルにしても、そこにうまく組み込むことができないものが、鏡の手前に残ってしまうのである。「私」だけが持つ本当の感覚はその一つであると言える。
◇絆創膏と包帯
霧子が、内面の問題であるはずのことを、絆創膏と包帯によって身体上で取り扱おうとしていたということを、鏡像段階の観点から考えることができる。
霧子は、自分がふつうの人間の中に数え入れられないと思っている節があった。まるで他人から見えていないと思っているかのようでもあった。その問題を解決するためには、見えるようになればいい。端的に、身体を持てばいい。鏡像段階によって自分の自己像を獲得するということは、自分もまた他人たちと同様に、目に見える身体を持って生きているということを引き受けるということだ。
だが鏡像段階において、自我のモデルにうまく組み込めないものが鏡の手前に残る。それは霧子の内面の問題である。こうしたものが鏡像段階においてどれほど問題を生み出すかはそれぞれの個人によって異なる。
霧子の場合、それは、統一的な身体像を傷つけてしまうほどのものだったのかもしれない。それが霧子にとって具体的にどんな事態であるのかは分からない。あるいはそれは完全には意識に上らない無意識上での問題だと考えることもできるかもしれない。
これは行き過ぎた仮説かもしれない。しかしこのように考えると、その身体像の傷を癒すために絆創膏と包帯が用いられているのではないかと解釈することができる。
だが絆創膏と包帯によって内面の問題を取り扱おうとすることは、ポジティブな別の効果ももたらしている。
他人から見えなくなっている内面を、絆創膏や包帯として身に着けることによって、他人から認識可能にするのである。少なくとも、その絆創膏や包帯の裏に、何かがあると他人に伝えることができる。そうやって、他人から見えなくなっているものを、見えるようにしているのである。絆創膏や包帯は、すなわち、霧子(の心)がそこに存在している、ということの証になるのだ。
霧子はそうやって絆創膏や包帯を用いることによって、ふつう虚の方に位置付けられるような、見えなくなっているものと、現実に存在するとされる見えるものとの間に立っていると言える。絆創膏や包帯の下に、霧子が霧子だけの心を持ち続ける限り、霧子は虚の系列に位置付けられるものたちと隣人であり続けると、私は思う。そしてきっとそれが、霧子の魅力なのだ。
◆凛世の「心」
◇見えているのに見えない
霧子の内面と、包帯や絆創膏との関係を、見えないものと見えるもの、と考えたとき、凛世の「心」の問題が比較して浮かび上がるような気がした。
凛世の場合は、見えているはずなのに、見えていないというのが問題になる。
【想ひいろは】の一つ目のコミュ「思いぬれど」では、凛世の言葉が伝わらない場面が描かれる。凛世は、仕事の待ち時間に、持参した少女漫画を読んでいた。智代子から借りたものだという。そこには「恋のいろは」が書かれている、と。プロデューサーは「あまり真に受けない方がいいぞ?」と言う。その後で凛世はこう言うのだ。
「……プロデューサーさま」
「……ずっと……お慕いしております
もう、お傍を……
……離れたくありません」
「貴方さまと、
永遠に、添い遂げたいのです……」
これに対してプロデューサーは驚くが、「さっきの少女漫画の台詞か!」と思いいたる。漫画の引用だと思ったのである。仕事の後で「いくら漫画の台詞でもそういうことは不用意に言うもんじゃないぞ」「そういうことは本当に大事な人にだな……」とプロデューサーは言う。凛世は「プロデューサーさまは、凛世の、大切なお人です……」と言うが、「そういう冗談は誤解を招くから、もうちょっと表現を、な」と返される。そこで凛世は、「嘘や、冗談は……申しません」とつぶやくのだが、プロデューサーはそれを聞き逃してしまう。凛世は結局自分の言ったことを明らかにせずに会話は終わる。
◇「心とは」
この凛世のコミュと結びつけて読みたいのが、【ふらここのうた】のTrueコミュ「はちぶく」である。
凛世は今度の模擬試験のために古典の勉強をしている。そこで古語の「はちぶく」という言葉についての話になる。「はちぶく」とは「蜂吹く」、「口をとがらせ不満げな顔をすること」だという。古語辞典を見ていると思わぬ言葉に出会うことがある。プロデューサーは凛世の辞書を手に取ってめくり始め、ある言葉にマルがつけられているのに気づく。
「うらごい」。凛世が慌てる。「心恋」と書いて「うらごい」と読む。「慕っている人を心の中に想うこと」という意味。凛世は目を背けている。「漫画で……見かけましたので……」。「「心」って、「うら」って読むんだな」とプロデューサー。
「……きっと、見通せぬもの……だからでしょう」
「見通せぬもの……それで、裏か」
「……プロデューサーさまには……
隠しておられるものが……
ございますか……?」
「俺か? うーん……
……あんまり隠してるつもりもないけど……」
「…………」
「……凛世はどうなんだ?
あるのか、隠してるもの」
「……
凛世は…………」
……
……見えないでしょうか?」
「……え?」
「…………いえ――
…………
――ぶぅ……」
「……!
…………蜂吹いた」
「……ふふっ…………」
「や、すまん……
なんか……変なこと聞いちゃったかな……?」
「いえ……
ですが……
隠さなくても……見えぬもののようです……」
「……凛世?」
「心とは……」
【ふらここのうた】の「はちぶく」でも、【想ひいろは】の「思いぬれど」と同様に、見せているのに見えていないということが描かれている。「はちぶく」のコミュで興味深いのは、心の特徴をこう言い表していることだ。「心とは、隠さなくても見えぬもの」。
◇手元に残ってしまう
ここで、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』を思い出さないではいられない。ウェルテルは、自分の能力ではなく、自分の心を評価してもらいたいと思っている。しかしそれが叶わない。
「公爵は私の知性と才能とを、私の心情よりも高く評価している。しかし、この心情こそは私が誇る唯一のものであり、力も、浄福も、悲惨も、すべてはこの泉から湧く。ああ、私が知っていることは何人も知ることができる。――ただ、私の心は私だけのものだ」(『若きウェルテルの悩み』竹山道雄訳,岩波文庫,p.105)。
公爵が評価するのはウェルテルの能力だ。だがウェルテルにとって、それは重要ではない。なぜなら、そうした能力は、ウェルテル以外の誰か別の人も持つことができるものだからだ。ウェルテルだけが持つことができるもの、それはウェルテルの心である。その心をこそ、評価してほしい。ウェルテルはそう願う。
このウェルテルの嘆きについて、ロラン・バルトは次のように書いている。
「こころこそ、わたしが与えたいと思っていたものなのだ。ところが、この贈り物が送り返されてくる。そのとき、ウェルテルのように、人がこのわたしに認める才気、わたし自身は望みもせぬ才気など、すべてとり除かれてしまったあとにも、こころだけはなおもわたしのものでありつづける、などと言ってみたところでどうにもなりはしない。こころとは、わたしの手元に残ってしまったもの、なのだ。そして、わたしのこころに残されたままのこのこころは、重く悲しい。引き潮の思いに満たされて重い(恋する者と子供だけが重い心をもつのだ)」(ロラン・バルト『恋愛のディスクール・断章』三好郁郎訳,みすず書房,p.81)。
心とは、「私の手元に残ってしまったもの」なのである。これは凛世の言う「隠さなくても見えぬもの」と共鳴し合う。
自分の思いを言葉にして伝えてみたところで、それは言葉でしかない。その言葉は、思いそのものではない。自分の痛みが他人とのコミュニケーションの中では虚痛みでしかないのと同じように、伝えたい思いそのものは他人にとっては存在しないことになってしまうのである。
それに、言葉は、それを言う人が誰であるかと言うことを限定しない。「お慕いしております」という言葉を、凛世以外の誰でも言うことができてしまう。そうであるならば、凛世の言葉を少女漫画からの引用だとプロデューサーが思ったように、どんなに自分の思いを本当に言葉にしたところで、それはどこかからの引用的な発言でしかなくなってしまい、凛世の本当の発話は受け取られなくなってしまう。
こうして凛世は、自分の思いを伝えるにあたって二重の問題に立ち塞がれることになる。心とはやはり、手元に残ってしまうものなのであり、隠さなくても見えぬものなのである。
(だが凛世にとって引用そのものが障壁になるわけではない。たとえば【凛世花伝】のTrueコミュ「序破急」においては、引用そのものがプロデューサーとの出会いをもたらした偶然が描かれている。「引用」は、凛世にとって重要なテーマであると思われる。「想いは…… それに乗って……時を超えるのでしょう……」と凛世が言っているように、凛世の想いの永遠さを、引用された古い言葉に託しているのかもしれない。風鈴の硝子も長い時を渡るものである。)
◆霧子と凛世
以上、主に霧子について考えながら、凛世の「心」(こころ/うら)についても考えてみた。二人を比較してみることができると思う。
両者に共通しているのは、心がうまく他者に認知されないということである。心は、他人とのコミュニケーションにおいて、この現実世界において、適切に取り扱うことができない。心は虚の方に落ちて存在しないものとされてしまう。
霧子は、そのことを引き受けた上で、そうした心の存在を絆創膏や包帯によって示す。それは心の中身そのものをこの現実世界の中に位置づけようとするというよりは、心がありますよということを見えるようにしているだけである。だがそれでも、その絆創膏や包帯の裏側にある内面は、虚の系列に落ちるものたちと仲間であり続けている。生きていないとされるものたち、意識を持たないとされるものたち、夢の中に登場するものたちである。霧子は、それらを自分の仲間であるとする。
一方の凛世は、恋をしている。恋は、自分の思い人に、自分の思いを伝えたくさせる。自分の恋心を伝えられずに、手元に思いを持ち続けるのはしんどい。ロラン・バルトは、そうした心を「重い」と書いている。だが、伝えたいという願いとは裏腹に、思いを伝えるということは容易ではない。自分の思いは、他人とのコミュニケーションにおいてはむしろ、虚の方に落ちてしまうからだ。伝えたいものこそが上手く伝えられないというパラドックスが立ちはだかるのである。
*Privatterの投稿は削除済み
◆夢と現実
◇生きていないもの、意識を持っていないもの
幽谷霧子は、普通生きてないとされるもの(「カメラのレンズさん」)、普通意識がないとされるもの(「ゼラニウムさん」)に対して語りかける。子どもがするごっこ遊びのようなものであるのかもしれないが、霧子は17歳であり、そういうごっこ遊びをするのは「子どもっぽい」と思われる年齢だろう。けれど霧子がそれらに語りかけるさまは、こちらにそう茶化すような気を起させない誠実さが感じられる。霧子がするそれは、擬人化であるよりももっと真剣な何かではないかとこちらに思わせる、そういう力がある。
霧子は「カメラのレンズさん」や「ゼラニウムさん」たちが、生きて意識を持っていると真剣に思っているのだろうか。霧子の言葉に耳を傾けると、どうやらそうではないようだということがわかってくる。プロデューサーがゼラニウムやユキノシタの鉢に張り付けたメモを見つけた霧子は、「お花さんから…… お礼、言われてるみたい」と言う。「みたい」ということは、それが本当ではないということを知っている、ということだ。けれどその直後に霧子はユキノシタに向かって「どういたしまして、ユキノシタさん…… これからも……いっぱいお話しようね……」と語りかける。この語りかけが、「みたい」の範疇にあるものなのかどうか、もはや定かではないような気がしてくる。
霧子の中で、何が生きているとされるものなのか、何が意識を持つとされるものなのか、といった常識的なことはふまえられているように思われる。だがその上でなお、そうした生きていないとされるもの、意識を持たないとされるものに対して、生きており意識を持っているようなものとして接している。この二段構えがある。
もっと抽象化すればこうなるだろう。フィクションと現実との区別はついているのだが、その上で、フィクションを現実と同レベルのものとして扱う、ということである。霧子にはそういう節がある。
◇デカルトの夢の懐疑
それがよく表れているのが【我・思・君・思】の二番目のコミュ「かなかな」だろう。「かなかな」では、デカルトの夢の懐疑が取り上げられている。
まずデカルトの懐疑を確認しておこう。
デカルトは、決して疑うことができない、確実な真理を手にしたかった。だから、その疑いえない確実な真理を手に入れるために、全てを疑ってみようと試みたのである。疑わしいものを排除していき、その果てに疑いえない確実なものがあると考えたのである。
さてここでデカルトがまず疑ったのが、自らの感覚であった。自分がいま部屋にいて、椅子に座って、紙を手にもって書かれたものを読んでいるとしよう。でも人間の感覚というのは時に間違うものだ。それに、こうしていま椅子に座って書かれたものを読んでいるということと全く同じことが、夢の中で繰り広げられることがある。現実と間違ってしまうような夢を見てしまうことが、実際にあるのだ。ならば、こうしていま部屋にいるということは、実は夢であるかもしれない。これが夢ではないということのしるしはない。ならばこれは今本当に夢なのではないか。……とデカルトは疑いを進めていく。これが夢の懐疑である。
この夢の懐疑が居座り続ける限り、確実な真理には到達しえない。科学的な事実や、歴史的な事実をいくら発見してみたところで、もし全てが夢だとしたら、それは疑いえない確実な真理ではなくなってしまう。全ては夢かもしれないという可能性があるだけで、確実さは失われる。だから、確実な真理を手にするためには、全ては夢かもしれないという夢の懐疑を退ける必要があるのだ。デカルトが知りたいと願った現実世界について、夢かもしれないという懐疑を一切抜きにして、アプローチできるのでなければならないのだ。
さて、デカルトが夢の懐疑の果てにたどり着いた真理こそ、「われ思う、ゆえにわれあり」にほかならない。これは、あらゆるものに疑いを差し向けたところで、その疑いそのものは疑いえないということである。そうして疑うことで思考する私そのものは、確実に存在するのだ。デカルトはここにたどり着いた。
デカルトはその後、神の存在証明を行い、神は欺かないと考え、明晰な思考に基づく判断は確実であるという確実さにたどり着く。理性に基づいて思考すれば、現実世界について確実な知識を得ることができるのである。
ここで確認しておきたいのは、夢と現実についての、デカルトの疑い方である。デカルトは、ふつう現実とされるものについて、「これは夢かもしれない」と疑った。そしてデカルトにとっては、現実が夢であっては困るのである。
◇霧子にとっての夢
さて、【我・思・君・思】の二番目のコミュでは、デカルトの名前が引用され、「これは夢かもしれない」という夢の懐疑が咲耶によって紹介される。咲耶は霧子に夢の懐疑を投げかける。霧子は、「夢…… かもしれない……」「夢じゃない……って…… 言えない……」と結論づける。
デカルトならば、それは大変困った事態である。デカルトは現実世界について、確実にアプローチする方法が必要だったのだから。
だが、霧子は動じない。
咲耶との話の中で、霧子の瞼は再び重くなる。そこで霧子はこう言う。
「眠っちゃいそう……
あ……――
これから……起きるのかな……」
今は夢であるのかもしれない。そうであるとしたら、これから眠るということは、目が覚めることであるのかもしれない。
現実と夢とを対比するとき、ふつうは、現実世界に生きる人間が、眠っている間に夢を見ている、と考えるだろう。そして眠っている人の身体は、現実世界にずっと横たわって存在し続け、その身体内部の脳が、夢という幻覚を見ている(見せている)のだと。こう考えるとしたら、現実に実在するのは、眠り続けている身体の方だ。そして、「目覚める」ということは、常に、この眠り続けていた身体の方に目覚めるのである。夢は、現実世界の中に存在し続ける身体の中に生じた、一時的なバグのようなものであるとされる。(そうであればこそ、夢の中で見たことや体験したことを、実際に見たものや体験したこととして語るのは変なことであるとされるのだ。)
だが、ここで霧子はこう考えていない。眠るということと、目覚めるということの区別が消えかかっているのである。夢に対して現実が、ずっと存在し続けている土台のような役割を果たせなくなっているのである。夢世界と現実世界とが交互に立ち現れるような状態になっている。そのとき、どちらが本当の「現実」であるのかは、もはや分からなくなっている。胡蝶の夢である。
霧子はさらにこう続ける。
「あのね……
どっちでも……嬉しいな……
今見てるのが……夢でも……
夢でなくても……
この咲耶さんが……
咲耶さんで……
次に会う咲耶さんも……
この咲耶さんなら……」
もはやどちらが本当の「現実」であるのかは、ここの霧子にとっては問題ではなくなっている。デカルトがあれほど確実な現実世界へのアプローチを求めていたのに、荘子が胡蝶の夢に頭を悩ませたのに。その問題は霧子にとっては重要な問題ではない。
霧子にとって重要なのは、目覚め=眠りを繰り返すことで交互に立ち現れる諸世界において、咲耶やみんなが同一であり続けるということだ。これは、夢と現実のふつうの区別のレベルで考えるとすれば、夢の中に登場した人物と、夢から覚めた世界にいる人物との間の同一性を考えるということにほかならない。これは、ふつう、変なことだとされる。
第一に、夢の中でAさんに殴られたとしよう。夢から覚めてAさんに会ったとき、夢の中で殴られたことの責任を、Aさんに帰するようなことは、普通はしない。
第二に、夢の中である人物に出会ったとしよう。この人物のことは、現実世界においてはまったく知らず、夢の中で初めて会ったとしよう。その人物を、夢から覚めた世界において探すようなことは、ふつうはしない。
第三に、夢というのは、ふつうは一人で見るものである。同一の夢を複数人で見るとはふつうは考えられない。もしそれらしきことが起こったとしたら、ふつう考えられるのは、たまたまその複数人が同じ日によく似た夢を見た、ということに違いない。
夢の中に登場した人物に対して、ふつうはこういう風に捉えられるだろう。夢の中の登場人物について、現実世界(とされる世界)に存在するふつうの人間と同等に扱うのは、変なことであるとされるのである。だが、霧子は、「この咲耶さん」にまた会うことを願い、次に会う咲耶さんが「この咲耶さん」であることを願うのだ。
◇虚の仲間たち
霧子にとって、夢の中に登場する人間もまた、現実世界に存在する人間と同等の存在でありうるのではないか、と考えたくなる。夢の中の登場人物は、ふつう現実に実在しない人間であるとされる。それはふつう、現実に存在する人間とは同等に並べられない。この、現実に存在する人間とは同等に並べられないものの系列に、夢の中の登場人物のほか、生きてないとされるもの、意識を持たないとされるものが、加わるのではないかと思う。霧子にとって、そういう者たちも、仲間なのではないか。
教会のステンドグラスの燦めきを目にしたとき、霧子はその場に存在しない無数の人間の祈りを思い浮かべた。そこにいない者たちが、そこで霧子の傍にいる。
ふつう、「われわれ」として考えられるのは、現実に存在し、言語を話す人間だろう。一部の動物もそこに含まれるかもしれない。けれど、おそらく霧子にとっては、「カメラのレンズさん」や「ゼラニウムさん」や夢の中の登場人物や、今その場にはいない過去の無数の人間もまた、「われわれ」の仲間になるのではないかと思う。
デカルトは、確かにいったん、夢と現実を区別するしるしはない、と考えた。この夢の懐疑の一瞬において、夢と現実とは区別ができなくなる。だがデカルトにおいてのそれは、現実とされるものが、実は夢にすぎないかもしれないと疑うことだ。デカルトにおいて、現実は依然として優位に置かれている。その現実を、夢という偽物から救いたい、といった風である。
一方霧子の立場では、夢とされるものが実は現実であるかもしれないと考えていることになる。それはいわば、現実から切り落とされたものたちを、ふたたび現実の元へと連れ戻そうとするかのようだ。霧子はよく、小さなものへと視線を向ける。それはふつうの人ならば見落としてしまうような何かだ。霧子は、ふつうの人がそうやって見落としてしまうもの、ふつうの人が現実でないとして切り落としてしまうものへと、視線を向ける。霧子が探すうさぎ座は、オリオンの下にあるのに見つけられない。霧子はそういう、見えなくなっているものへと視線を向ける。
なぜそういうものたちへと霧子は視線を向けるのか。これは私の仮説にすぎないのだけれども、霧子という存在が、実はすでにしてそういう虚の系列に加わるものだったのではないか。
◆見えないもの
◇「私」というものについて
霧子が、実はそうした虚の系列に加わる存在なのではないか、と考える根拠は、大きく分けて二つある。一つ目は理論的なものであり、二つ目は霧子の特徴に基づくものである。この二つは繋がっている。
まずは一つ目の方から。それは、「私」というもののあり方に基づくものだ。「私」というものは、すでにして「われわれ」にとっての余剰なのではないか。「私」というものは、虚の系列に入るものなのではないか。
ウィトゲンシュタインは、独我論について次のように書いている。
「独我論と我々が呼ぶ人、そしてただ自分の経験のみが本当のものだという人、その人は何もそれで実際的な事実問題について我々と食い違いがあるわけではない。我々が痛みを訴える時、ただそのふりをしているだけだとは彼は言わないし、他の誰に劣らず気の毒に思ってくれる。しかし同時に彼は、「本当の」という、通り名を我々が彼の経験と呼ぶべきものだけ限りそして多分更に我々の経験をどんな意味であれ「経験」とは呼びたくないのである[……]」(ウィトゲンシュタイン,『青色本』大森荘蔵訳,ちくま学芸文庫,p.137)。
ここで取り出しておきたいのは、自分の経験に対してのみ「本当の」という言葉を付けるという言葉遣いである。われわれの多くは独我論ではないかもしれない。けれど、他人が殴られても、その痛みは私には感じられないのである。殴られて本当に痛いのは、私だけなのだ。だから、痛みに関しても、他人が抱く痛みと、私が抱く痛みの間には、超えられない差がある。
Aという他人が痛みを持つということについて独我論者がどう考えるかというと、黒崎宏は「この場合、独我論者は例えば「Aはイダミを持っている」とでも言うかもしれない」と言う(『『青色本』読解』産業図書,p.101)。自分が持つ痛みを「痛み」、他人が持つ痛みを「イダミ」として区別しよう、というわけである。ここには、自分の痛みこそが「本当の痛み」、他人が持つ痛みは「虚構の痛み」という区別がある。永井均は、この区別を「実痛み」「虚痛み」と名付けて整理する(『『青色本』を掘り崩す』ナカニシヤ出版,p.117)。
興味深いのは、自他に対応していた「実痛み」「虚痛み」が、逆転しうると永井が指摘していることである。
「むしろ逆に、他人の痛みはみなごくふつうに正当に「痛み」と呼ばれるべきものであるが、自分のはまったく比類のない不思議なものだから、通常の言葉には存在しない「イダミ」とでも呼んでおこう、と考えても不思議ではない。したがって「実」と「虚」の対比に戻っていえば、他人の側のを「実痛み」と呼んで自分の側のを「虚痛み」と呼びたくなっても、べつに独我論に反するところはない」(『『青色本』を掘り崩す』,pp.120-121)。
殴られて本当に痛いのは、私だけである。けれども、私が殴られたときに感じるこの痛みそのものは、他人たちには全く理解されない。他人に通じるのは、私が殴られたという状況や、表情や振る舞いに現れる痛がっている様子や、「痛い!」という私の言葉だけだ。それしか、他人には伝わらない。そしてそれらは、他人が表出しているものの全てである。
だから、人間たちに「痛み」が生じる状況や、人間たちが「痛み」を抱いているとする表情や振る舞いや、人間たちが「痛い」と発する言葉などにおいて、私が本当に感じる痛みそのもののようなものは、全く機能していないのである。それは他の歯車と噛み合っていない空転する歯車のようなものである。だから、その痛みそのものは、人間たちのコミュニケーションの中では、虚の方に位置付けられると言える。
だから、全ての他人は、私が持つような本当の感覚を持つことがない、ゾンビであるのかもしれないのである。だが、私が持つような本当の感覚というものは、他人たちには絶対に伝わらない。だから、他人たちの方を基準にすれば、私の方こそが余計な何かを持ってしまった、異質な存在だということになる。
「私」という存在は、「われわれ」にとっては余剰となる何かなのだ。その点において、「私」という存在は、「われわれ」に含み入れられない、虚の系列に位置付けられるものに近いのである。「われわれ」から落とされてしまう存在とは、たとえば、生きていないとされるもの、意識を持たないとされるもの、夢の中の登場人物、などである。それはつまり、「カメラのレンズさん」であり、「ゼラニウムさん」であり、「この咲耶さん」である。
◇霧子の「私」
霧子のWING編のプロデュースを始めると、オーディションに合格した霧子と会議室で出会うところから始まる。そこでプロデューサーが霧子の名前を言うと、霧子は「わたしの名前、覚えていてくれたんですね……」と言う。自分の名前を覚えてもらっていない(かもしれない)と思っていたようである。プロデューサーは霧子を「控え目」と評するが、霧子にとって、自分の存在はこの世から消えてしまっている(見えなくなっている)のではないかと思わせる雰囲気があるように思う。
プロデュースの最初のコミュのタイトルは、その名も「みえない献身」である。霧子は普段からレッスン室を掃除していたのだが、それをプロデューサーも気づかないでいた。プロデューサーが霧子を褒めると、霧子は「あんまり…… そんなふうに言ってもらったこと……なくて…… すごく…… う、嬉しい……です!」と言う。
この後で選択肢があるのだが、私がDaでよくプロデュースする都合もあり、よく「それは霧子のためにもなるって思うぞ」を選ぶ。実際この選択肢が好きだ。プロデューサーは「アイドル幽谷霧子が育つ場所なんだってことを覚えておいてほしい」と言う。ここはレッスン室であり、レッスン室を自分から掃除するということ自体が、アイドル幽谷霧子にとっての成長になるということなのだ。プロデューサーはここで、レッスン室の中で成長する人間の中に霧子を数え入れているのである。
さて次のコミュでは、オーディションで様子がおかしかった霧子について語られる。霧子は、パフォーマンスをする中で「ダンスのときは、隣の人の邪魔になったらいけないって……」「自己アピールのときは…… 大きな声を出したら、他の人が驚いてしまうなって……」と言う。ふつうオーディションにおいてはダンスをするために十分な空間があるはずだし、大きな声で自己アピールをするのが当然で、それが誰かを驚かしたりはしないだろう。まるで霧子は、自分が存在するということそのものが他人にとって迷惑になってしまうのではないかと心配しているかのようである。
これに対してプロデューサーは、ダンスをもっと大胆にやってもいいんだよとか、大きな声で自己アピールしてもいいんだよといった風には言わない。そうやって心配してしまう霧子のあり方そのものが霧子の魅力であり、それがアイドル幽谷霧子を作っていくということを言うのだ。ここでプロデューサーは、霧子の心を肯定しているのである。
シーズン4のコミュでは、霧子のファッション誌の撮影のお仕事をしている様子が描かれる。そこで霧子は自分の包帯を見せるような構図を自ら提案する。霧子は包帯や絆創膏をよく身に着けているが、それは身体に傷があるからではない。霧子は、不安や自信がなかったりするとき、包帯や絆創膏を身に着ける。実際オーディションで負けてしまったとき、控室で霧子は絆創膏を貼っている。身体上に付ける絆創膏や包帯は、身体ではなく心の問題を表していると言える。
霧子は絆創膏や包帯の下に「隠している」と言っていたが、シーズン4の頃には、それも「見てもらいたい」と思うようになる。それはつまり、霧子の心の内をみんなに見てもらいたいということだろう。「みんな霧子に夢中になるよ」を選択すると、「霧子がこれまで、大事にしてきたこと……」「そういうことがきっと、包帯の下で眠ってたんだよ」とプロデューサーは言うのである。
◇内面
このように、霧子の控え目さというのは、自分を数に数え入れていなかったり、自分の存在自体が他人の迷惑になってしまうのではないかと考えたりするということでもある。霧子は、自分の存在はふつうの人たちの中では浮いてしまうと思っているのではないか。
だから、ふつうの人間の数を数えようとすれば、そこから浮いてしまうものは数え入れられない。一方で、自分の存在を主張しようとすれば、ふつうの人間の中に適切な居場所がないのだから、余計なものとして周りに影響を与えてしまう。……こう考えているのではないか。つまり霧子は、自分はoddだと思っているのではないか……
なぜ霧子はoddとなってしまうのだろう。そのヒントが、絆創膏や包帯(の下にあるもの)ではないか、と私は思う。
絆創膏や包帯は、霧子にとって内面のよくないものを隠すものであった。だが、絆創膏や包帯は、他人から見えるものでもある。絆創膏や包帯が身に付けられているということは、その裏側に何かがありますよということを他人に伝える。絆創膏や包帯は、隠すものでありながら、明示するものでもあるのだ。
絆創膏や包帯の裏にあるものは、霧子の内面である。つまり霧子は、絆創膏や包帯を身に着けることによって、内面を隠すと同時に、見えるようにしていたのだ。
ここで、虚の方に位置付けられる「「私」の本当の感覚」と結びつく。霧子という存在、および霧子の内面は、ただ存在するだけでは、ふつうの人間たちの間では存在するものとして数え入れられることがない。見えなくなっているのである。(「幽」谷「霧」子という、幽と霧という実体のないものを名に持つところからも、それが感じられるような気さえする。)
◇鏡像段階
幽や霧は、実体がない。実体がないものは、うまく存在するものとして位置づけられない。この現実世界とされる世界において、ふつうの人間として数え入れられるためには、幽や霧ではなく、実体を持つこと、つまり身体を持つことが必要になる。
フランスの精神分析家ジャック・ラカンによれば、人間の赤ちゃんは、鏡に映った像を自分であるとみなすことによって、自我(「私」)が形成される。これを鏡像段階と言う(「〈わたし〉の機能を形成するものとしての鏡像段階」『エクリⅠ』弘文堂)。
生まれたばかりの赤ちゃんは、神経系が未発達であるので、身体感覚が統合されていない。このときの身体を、ラカンは「寸断された身体」と呼ぶ。赤ちゃんにとって身体はばらばらなのである。この状態の赤ちゃんの前に、鏡(の像)が現れる。赤ちゃんはそこに映った像を自分の像として引き受けることで、自分の統一的な自己像を獲得する。それは神経系の発達に先立つのである。
赤ちゃんが自分の姿として引き受ける像は、必ずしも鏡に映った像でなくてもよく、赤ちゃんの兄弟(姉妹)や、他の子どもなどもその像の役割を果たすことができる。つまり鏡像段階とは、自分もほかの他人と同じように身体を持ってこの世に生きている、ということを引き受けるということなのだ。それはまさに、幽や霧のようなものが、実体を持って世界に存在し始めるようなものである。
ラカンの鏡像段階論の興味深いところは、他者こそが自我のモデルであると考えるところにある。自我がまずあって、その似姿として他者を考えるのではない。他者がまずあって、その似姿として自我があるのである。「私」が持つ本当の感覚が虚の系列に落ちてしまうのは、そのためだとも言える。
さらに興味深いのは、そうした自我のモデルとなる他者は、「自動人形」のようなものにすぎないということをラカンが示唆しているということだ。鏡像段階において自我のモデルとなる他者は、理論的には、必ずしも生きているものや、意識を持っているものではないのである。だからその他者はゾンビであってもかまわないのである。だからこの鏡像段階論に従うなら、「私」というものはすでにして、虚の系列に位置付けられるものたちと仲間でありえているはずなのである。
ラカンは、寸断された身体の状態にある赤ちゃんが統一的な自己像を獲得する過程を、「形成外科的」と表現する。あるいは、型の中に飛び込むようなイメージを与える。ここでラカンが注意しているのは、鏡像段階によって統一的な自己像が獲得されたとしても、寸断された身体が消えてなくなるわけではないということだ。精神的な疾患にかかってしまったときや、夜眠っている間に見る夢などに、それは表れるという。
鏡像段階は、他人たちをモデルにして自分を形成することであるが、他人たちをモデルにしても、そこにうまく組み込むことができないものが、鏡の手前に残ってしまうのである。「私」だけが持つ本当の感覚はその一つであると言える。
◇絆創膏と包帯
霧子が、内面の問題であるはずのことを、絆創膏と包帯によって身体上で取り扱おうとしていたということを、鏡像段階の観点から考えることができる。
霧子は、自分がふつうの人間の中に数え入れられないと思っている節があった。まるで他人から見えていないと思っているかのようでもあった。その問題を解決するためには、見えるようになればいい。端的に、身体を持てばいい。鏡像段階によって自分の自己像を獲得するということは、自分もまた他人たちと同様に、目に見える身体を持って生きているということを引き受けるということだ。
だが鏡像段階において、自我のモデルにうまく組み込めないものが鏡の手前に残る。それは霧子の内面の問題である。こうしたものが鏡像段階においてどれほど問題を生み出すかはそれぞれの個人によって異なる。
霧子の場合、それは、統一的な身体像を傷つけてしまうほどのものだったのかもしれない。それが霧子にとって具体的にどんな事態であるのかは分からない。あるいはそれは完全には意識に上らない無意識上での問題だと考えることもできるかもしれない。
これは行き過ぎた仮説かもしれない。しかしこのように考えると、その身体像の傷を癒すために絆創膏と包帯が用いられているのではないかと解釈することができる。
だが絆創膏と包帯によって内面の問題を取り扱おうとすることは、ポジティブな別の効果ももたらしている。
他人から見えなくなっている内面を、絆創膏や包帯として身に着けることによって、他人から認識可能にするのである。少なくとも、その絆創膏や包帯の裏に、何かがあると他人に伝えることができる。そうやって、他人から見えなくなっているものを、見えるようにしているのである。絆創膏や包帯は、すなわち、霧子(の心)がそこに存在している、ということの証になるのだ。
霧子はそうやって絆創膏や包帯を用いることによって、ふつう虚の方に位置付けられるような、見えなくなっているものと、現実に存在するとされる見えるものとの間に立っていると言える。絆創膏や包帯の下に、霧子が霧子だけの心を持ち続ける限り、霧子は虚の系列に位置付けられるものたちと隣人であり続けると、私は思う。そしてきっとそれが、霧子の魅力なのだ。
◆凛世の「心」
◇見えているのに見えない
霧子の内面と、包帯や絆創膏との関係を、見えないものと見えるもの、と考えたとき、凛世の「心」の問題が比較して浮かび上がるような気がした。
凛世の場合は、見えているはずなのに、見えていないというのが問題になる。
【想ひいろは】の一つ目のコミュ「思いぬれど」では、凛世の言葉が伝わらない場面が描かれる。凛世は、仕事の待ち時間に、持参した少女漫画を読んでいた。智代子から借りたものだという。そこには「恋のいろは」が書かれている、と。プロデューサーは「あまり真に受けない方がいいぞ?」と言う。その後で凛世はこう言うのだ。
「……プロデューサーさま」
「……ずっと……お慕いしております
もう、お傍を……
……離れたくありません」
「貴方さまと、
永遠に、添い遂げたいのです……」
これに対してプロデューサーは驚くが、「さっきの少女漫画の台詞か!」と思いいたる。漫画の引用だと思ったのである。仕事の後で「いくら漫画の台詞でもそういうことは不用意に言うもんじゃないぞ」「そういうことは本当に大事な人にだな……」とプロデューサーは言う。凛世は「プロデューサーさまは、凛世の、大切なお人です……」と言うが、「そういう冗談は誤解を招くから、もうちょっと表現を、な」と返される。そこで凛世は、「嘘や、冗談は……申しません」とつぶやくのだが、プロデューサーはそれを聞き逃してしまう。凛世は結局自分の言ったことを明らかにせずに会話は終わる。
◇「心とは」
この凛世のコミュと結びつけて読みたいのが、【ふらここのうた】のTrueコミュ「はちぶく」である。
凛世は今度の模擬試験のために古典の勉強をしている。そこで古語の「はちぶく」という言葉についての話になる。「はちぶく」とは「蜂吹く」、「口をとがらせ不満げな顔をすること」だという。古語辞典を見ていると思わぬ言葉に出会うことがある。プロデューサーは凛世の辞書を手に取ってめくり始め、ある言葉にマルがつけられているのに気づく。
「うらごい」。凛世が慌てる。「心恋」と書いて「うらごい」と読む。「慕っている人を心の中に想うこと」という意味。凛世は目を背けている。「漫画で……見かけましたので……」。「「心」って、「うら」って読むんだな」とプロデューサー。
「……きっと、見通せぬもの……だからでしょう」
「見通せぬもの……それで、裏か」
「……プロデューサーさまには……
隠しておられるものが……
ございますか……?」
「俺か? うーん……
……あんまり隠してるつもりもないけど……」
「…………」
「……凛世はどうなんだ?
あるのか、隠してるもの」
「……
凛世は…………」
……
……見えないでしょうか?」
「……え?」
「…………いえ――
…………
――ぶぅ……」
「……!
…………蜂吹いた」
「……ふふっ…………」
「や、すまん……
なんか……変なこと聞いちゃったかな……?」
「いえ……
ですが……
隠さなくても……見えぬもののようです……」
「……凛世?」
「心とは……」
【ふらここのうた】の「はちぶく」でも、【想ひいろは】の「思いぬれど」と同様に、見せているのに見えていないということが描かれている。「はちぶく」のコミュで興味深いのは、心の特徴をこう言い表していることだ。「心とは、隠さなくても見えぬもの」。
◇手元に残ってしまう
ここで、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』を思い出さないではいられない。ウェルテルは、自分の能力ではなく、自分の心を評価してもらいたいと思っている。しかしそれが叶わない。
「公爵は私の知性と才能とを、私の心情よりも高く評価している。しかし、この心情こそは私が誇る唯一のものであり、力も、浄福も、悲惨も、すべてはこの泉から湧く。ああ、私が知っていることは何人も知ることができる。――ただ、私の心は私だけのものだ」(『若きウェルテルの悩み』竹山道雄訳,岩波文庫,p.105)。
公爵が評価するのはウェルテルの能力だ。だがウェルテルにとって、それは重要ではない。なぜなら、そうした能力は、ウェルテル以外の誰か別の人も持つことができるものだからだ。ウェルテルだけが持つことができるもの、それはウェルテルの心である。その心をこそ、評価してほしい。ウェルテルはそう願う。
このウェルテルの嘆きについて、ロラン・バルトは次のように書いている。
「こころこそ、わたしが与えたいと思っていたものなのだ。ところが、この贈り物が送り返されてくる。そのとき、ウェルテルのように、人がこのわたしに認める才気、わたし自身は望みもせぬ才気など、すべてとり除かれてしまったあとにも、こころだけはなおもわたしのものでありつづける、などと言ってみたところでどうにもなりはしない。こころとは、わたしの手元に残ってしまったもの、なのだ。そして、わたしのこころに残されたままのこのこころは、重く悲しい。引き潮の思いに満たされて重い(恋する者と子供だけが重い心をもつのだ)」(ロラン・バルト『恋愛のディスクール・断章』三好郁郎訳,みすず書房,p.81)。
心とは、「私の手元に残ってしまったもの」なのである。これは凛世の言う「隠さなくても見えぬもの」と共鳴し合う。
自分の思いを言葉にして伝えてみたところで、それは言葉でしかない。その言葉は、思いそのものではない。自分の痛みが他人とのコミュニケーションの中では虚痛みでしかないのと同じように、伝えたい思いそのものは他人にとっては存在しないことになってしまうのである。
それに、言葉は、それを言う人が誰であるかと言うことを限定しない。「お慕いしております」という言葉を、凛世以外の誰でも言うことができてしまう。そうであるならば、凛世の言葉を少女漫画からの引用だとプロデューサーが思ったように、どんなに自分の思いを本当に言葉にしたところで、それはどこかからの引用的な発言でしかなくなってしまい、凛世の本当の発話は受け取られなくなってしまう。
こうして凛世は、自分の思いを伝えるにあたって二重の問題に立ち塞がれることになる。心とはやはり、手元に残ってしまうものなのであり、隠さなくても見えぬものなのである。
(だが凛世にとって引用そのものが障壁になるわけではない。たとえば【凛世花伝】のTrueコミュ「序破急」においては、引用そのものがプロデューサーとの出会いをもたらした偶然が描かれている。「引用」は、凛世にとって重要なテーマであると思われる。「想いは…… それに乗って……時を超えるのでしょう……」と凛世が言っているように、凛世の想いの永遠さを、引用された古い言葉に託しているのかもしれない。風鈴の硝子も長い時を渡るものである。)
◆霧子と凛世
以上、主に霧子について考えながら、凛世の「心」(こころ/うら)についても考えてみた。二人を比較してみることができると思う。
両者に共通しているのは、心がうまく他者に認知されないということである。心は、他人とのコミュニケーションにおいて、この現実世界において、適切に取り扱うことができない。心は虚の方に落ちて存在しないものとされてしまう。
霧子は、そのことを引き受けた上で、そうした心の存在を絆創膏や包帯によって示す。それは心の中身そのものをこの現実世界の中に位置づけようとするというよりは、心がありますよということを見えるようにしているだけである。だがそれでも、その絆創膏や包帯の裏側にある内面は、虚の系列に落ちるものたちと仲間であり続けている。生きていないとされるものたち、意識を持たないとされるものたち、夢の中に登場するものたちである。霧子は、それらを自分の仲間であるとする。
一方の凛世は、恋をしている。恋は、自分の思い人に、自分の思いを伝えたくさせる。自分の恋心を伝えられずに、手元に思いを持ち続けるのはしんどい。ロラン・バルトは、そうした心を「重い」と書いている。だが、伝えたいという願いとは裏腹に、思いを伝えるということは容易ではない。自分の思いは、他人とのコミュニケーションにおいてはむしろ、虚の方に落ちてしまうからだ。伝えたいものこそが上手く伝えられないというパラドックスが立ちはだかるのである。
*Privatterの投稿は削除済み
公開範囲を「すべて」にしたときは、Twitter認証をしなくても伏せ字が読めるよ
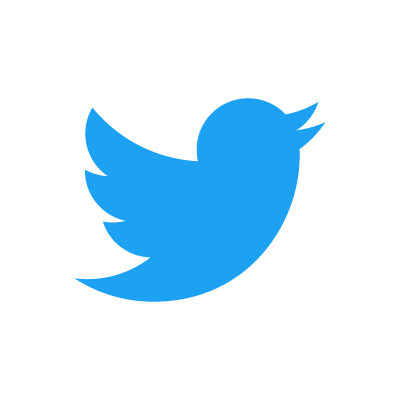 元ツイート
元ツイート