本日の一次創作、短編できました。よろしければ読み物にどうぞ。
お題は「根」です
お題は「根」です
神の森
「あれ」
少女はふと、森を歩く足を止めた。草葉の影に、何か光った気がしたのだ。
「どうしたの?カヤ」
少女の友人が振り返る。カヤは近くの木のそばにしゃがみ込み、その根元に手を伸ばした。
「こんなところに、指輪が落ちてる」
カヤは指輪を拾って立ち上がった。高価そうな指輪だ。リングの素材はホワイトゴールド、そのトップには、遥か異国でよく取れるという青い貴石がはめ込まれていた。友人はそれを見て目を輝かせた。
「あーっ、いいなあ!!ラッキーじゃん!神様の贈り物だよ!売ったらお小遣いいっぱい増えるね!!」
その言葉に、カヤはうれしさで頬を紅潮させた。この村のしきたりで、森で拾った宝物は見つけた人のものになる。この指輪は紛れもなく、見つけたカヤのものだった。よかった、ちょうどほしいものがあったんだ。
「そうだね!!帰ったら屋台に売ってみよう!きっと高く売れるよ!!」
「いいなー、私もなんか見つけられないかなあ」
友人は俄然やる気になって、木の根元に目を凝らし始めた。いいなあ、私もお小遣いほしい。そんな呟きが聞こえてきた。カヤは見つけた指輪を大事にポケットにしまった。あとで忘れないように、ちゃんと売ろう。
とある世界の、とある小さな村。村長の娘であるカヤは、村の工芸である木工が好きな、ごく普通の少女だ。村の余分な木を切り倒し、その木で作った食器や雑貨が都会でそれなりに売れるのだ。繊細な彫刻を施したものほど高く売れる。カヤは食器やペン立てなどに細かな彫刻を施すのが好きだった。キレイに彫れると、いろんな人からほめられた。これは高く売れるぞ、カヤは見事な技術の持ち主だ。そうしてたくさんの人がほめてくれるのが、カヤの何よりの幸せだった。今日もカヤは森へ入り、来週の伐採の日に切り倒す木を見定めていた矢先の幸運だった。村を覆うこの森からは、ときどきこうしてお宝が見つかる。森で見つけたお宝は、見つけた人のもの。これはこの村の決まりだった。これでお小遣いが増えて、ほしいものが買える。ちょっと美味しいものを買うのもいいな。カヤは想像を膨らませ、わくわくと胸を躍らせた。
「もう暗くなっちゃうね。切る木はだいたい目星つけたし、今日はもう帰る?」
「そうだね、さっき見つけた木でいいと思う!じゃあ、今日はもう帰ろっか。
あーあ、私もカヤみたいにお宝見つけられないかなあ」
友人はうらやましそうにため息をつき、カヤに続いて帰路につく。思わぬ幸運を手にしたカヤは、うきうきと軽い足取りで森を引き返していった。
翌日。カヤは2階の自室で、指輪を売ったお金で買った本を嬉々として読んでいた。最近流行りの小説だった。物語の展開に夢中になっていると、ふと部屋の扉がノックされた。
「カヤ。ちょっと、下に降りてきて」
母の声だった。普段どおりの母の声だったが、どこか浮かないような声だった。カヤは物語の続きが気になって仕方がなかったが、母が心配になり、しおりをはさんで本を閉じ、ぱたぱたと階段を降りていった。
リビングの扉を開けると、両親がソファに座っていた。父はカヤをソファに座らせると、ひと呼吸して、カヤに言った。
「カヤ。大事な話がある」
父の顔は真剣だった。カヤは少し肩に力を入れた。父は重い口を開いた。
「カヤ。今年の“神の使い”が、お前に決まった。
来週のお祭りで、カヤは神の御許へ行くことになったんだ。
村のシャーマンの占いで、お前が神に選ばれたんだよ」
カヤは目を見開いた。年に一度、この村で行われる村祭り。そこでは毎年、村が信仰する森の神に誰かひとりが選ばれる。選ばれた者は村祭りを最後にこの村を去り、神の御許へ行くと教えられていた。その選ばれし者のことを、村では「神の使い」と呼んでいた。
「神の使いに選ばれるのは名誉なことだ。選ばれた者は森の神の御許で、永遠に幸せに暮らせるという」
「カヤと一緒にいられるのは、来週のお祭りまで。
さみしいけれど、カヤが幸せになれるなら、お母さんたちも幸せだわ」
「おめでとう、カヤ。別れはさみしいが、神の御許で、幸せに暮らすんだよ」
両親は口々に祝いの言葉をカヤにかける。カヤはいまひとつ、実感がわかなかった。どこかへ引っ越しをするような心地だった。そうか、そうしたら、友達とはもう会えなくなるな。挨拶まわりに行かなくちゃ。カヤは頭の片隅で、そんなことを考えた。
その日の夕食は、カヤの好きなものばかりが並んだ。
友人や世話になった人たちに挨拶まわりへ行くと、全ての人から祝福の言葉をもらった。おめでとう、カヤの日頃の行いだな、さみしくなるけど幸せになれよ。みんな、カヤの幸せを願った。カヤもなんとなく、幸せになれそうな気がした。
一緒に森へ行った友人が、手作りの首飾りをプレゼントしてくれた。カヤの好きな緑色の、キレイなビーズの首飾りだ。お小遣いの中で作った安っぽい首飾り。けれどその一粒一粒に、友人の思いがこもっていた。カヤは大喜びで受け取って、肌身離さず身につけた。
そうして1週間が過ぎ、村祭りがはじまった。広場に火を焚き、炎の周りで村人たちがうれしそうに踊っている。その様子を、カヤは上座からぼんやりと眺めていた。
今までずっと、あの踊る人々の中のひとりだった。この上座に座る神の使いを、他人事のように見上げていた。それが今は、自分が座っている。まるで現実味を感じなかった。
儀式を終えて、村役場へ通される。禊を行い、身を清めて、儀式用の衣で身を包む。厳かな気を発する儀式の間へ通されると、そこは薄暗い部屋だった。診療台のような人が横になれる台座があり、その周りを、ヴェールで顔を隠した人々が囲んでいた。
カヤは少しばかりの緊張と不安を覚えたが、近くにいた大人が優しい声でカヤに言った。
「大丈夫ですよ。痛くも、つらくもありません。
この薬を飲んで、この台に横になってください」
そう言って、盆の上にのせた2種類の飲み薬をカヤに差し出した。カヤは不安を取り除けなかったが、大人しく薬を飲み干して、台座の上に横になった。薬は少し甘いと感じる程度で、なんのにおいもしなかった。
横になると、すぐに睡魔が襲ってきた。うとうとしていると、視界に入る大人がカヤに言った。
「これから神の御許へご案内します。目が覚めたら、そこで3日間過ごしてください。3日経てば、神がお迎えにいらしてくださるでしょう」
その言葉を最後に、カヤは睡魔に飲まれていった。
何やら温かい。身体がぬくぬくと気持ちがいい。左目に少し違和感がある。そこまで感じて、カヤは目を覚ました。
知らない部屋。見覚えのない内装。木でできたそのインテリアは、辛うじてここが村の中のどこかであることを指していた。窓の外は美しい森。木漏れ日が輝き、外からは鳥の声がする。タンスには清潔な衣服が並び、キャビネットの中には生活用品がキレイに整頓して仕舞われていた。
どうやらここは、小さな小屋のようだった。人1人が生活するのに不自由しない衣類と、食糧、水が用意された小屋だった。退屈しのぎに使えそうな本も、本棚にたくさん納められていた。カヤ以外には誰もいなかった。
部屋を見て回り、ふと脱衣所の壁にかけられた鏡を見た。鏡の向こうの自分の顔には、見覚えのない傷がついていた。左目を囲うように、紋章のような傷があった。左目に感じていた違和感は、どうやらこの傷のようだった。違和感はあるが、痛みやかゆみはとくにない。儀式の際につけられたものだろうか。カヤは眠っていたので、全くなんの記憶もなかった。
外に出てみる。見覚えのない森だった。木々の葉の擦れる音が心地よかったが、全く人の気配も何もないその様相は、どこか少し寂しかった。
カヤは言われた通り、小屋で過ごした。この小屋で3日過ごせば、神が迎えに来るという。神様って、どんな姿をしてるんだろう。どんな声で話すんだろう。私と仲良くしてくれるかな。カヤは少し期待した。
何事もなく、あまりにも何事もなく、1日が過ぎ、2日が過ぎた。左目に違和感を感じる以外は、とても平和な時間だった。
3日目の朝。目が覚めると、何やら頭が重かった。
左目の違和感が強くなり、視界がやけに狭かった。左目が開いていないのだとわかった。左目に触れてみると、何かゴツゴツと固いものと、ふさふさした柔らかいものが当たった。寝室の鏡を覗き込んで、カヤは硬直し、血の気が引いた。
左目が、木になっていた。左目のあったところがそっくりそのまま木の皮のようになり、皮目からみずみずしい新芽が生えていた。それだけではない。その新芽は目に見えてぐんぐんと生長し、にょきにょきとその身を伸ばしていた。
目にした光景のあまりの気味悪さに、カヤは頭がひっくり返るように愕然として、悲鳴をあげた。そして新芽をつかみ取り、指でねじり切ろうとした。新芽は柔らかいはずなのに、どれだけ力をこめても一向に切れることはなかった。それどころか、新芽を切ろうとすると、左目がじくりじくりと痛んだ。まるで新芽に神経が通っているかのようだった。
カヤは絶望し、ハサミを取って木の皮になっている部分を抉り取ろうとした。皮になった左目に刃を当てると、たしかにハサミの冷たい固さが皮を通して伝わってきた。この木になっている部分にも、神経が通ってしまっているように感じた。
鏡越しの自分の顔が真っ青になっていた。ふと手を見れば、手もまるで木の皮のように固くなり、その節々から枝が伸び始めていた。カヤは叫び、枝を切ろうとするも、枝も固くて切れなかった。枝の1本1本に神経が通り、とても痛くて切れなかった。
顔の新芽はどんどん伸びて、茎が細い幹になっていった。カヤは我を忘れて、何か叫びながら全速力で小屋を飛び出した。脳裏に思い出が蘇る。友人の顔、お世話になった先生の顔、両親の顔、みんなの笑顔。みんなにすがりたくてたまらなかった。誰か、誰か助けて!!
どれだけ走っても、森は抜けることがなかった。その木の1本1本に、よくよく見れば人の顔が埋まっているような気がした。ああ、そうだ。そうなのだ。これがこの森の真実なのだ。走りながら、カヤは真実を知ってしまった。この村の森が、何でできているか。私が今まで削ってきた、切ってきた木は、なんだったのか。ときどき見つかるお宝が、いったい誰のものだったのか――――
ふと、足が重くなって、カヤはそれ以上走ることができなくなった。足を見ると、足はすっかり茶色くなり、ごつごつとした分厚い木の皮で覆われていた。木になった足はその下の地に根を張って、カヤはいよいよ動けなくなった。くらくらするほど頭が重い。左目の新芽が、もう立派な木に生長してしまっていることが、その重さで理解できた。
カヤはふと、空を見上げた。もうすっかり夜になっていた。けっきょくずっと走ったけれど、森の出口は見えなかった。静まり返った森の中、カヤは力なく月を見上げた。視界の中央、まん丸に輝く満月は、まるで神の光のように神秘的で、しかし冷たい輝きを放つばかりだった。
私は、木工が好きだ。
代々、この村では木工が盛んだった。余分な木を切って、その木で食器や雑貨を作る。繊細な彫刻を施したものは高く売れた。だから皆、競って腕を振るっていた。
私の作る工芸品は、町でとても高く売れた。私は村いちばんの工芸師として、毎日木を彫っていた。
ある日、来週切る木を見繕いに森へ入ると、ふと木の根元で何かが輝いた。もしや、お宝か。そう思い手を伸ばすと、それは粗末な首飾りだった。
緑色のビーズをつなげただけの、古びた安っぽい首飾り。高く売れるわけもない、森を汚す、ただのゴミだった。こんなものも落ちているのか。私はそれを拾って、森の奥へと進んでいった。この首飾りは、帰ったら捨てよう。頭の片隅にメモをして、私は首飾りをポケットへしまった。
+++
「神の森」4,777字
お題「根」
→「根」:いつまでも痕が残るイメージを形にした漢字。
「艮」は、目の周りに傷をつける情景をあらわしたもの。
「あれ」
少女はふと、森を歩く足を止めた。草葉の影に、何か光った気がしたのだ。
「どうしたの?カヤ」
少女の友人が振り返る。カヤは近くの木のそばにしゃがみ込み、その根元に手を伸ばした。
「こんなところに、指輪が落ちてる」
カヤは指輪を拾って立ち上がった。高価そうな指輪だ。リングの素材はホワイトゴールド、そのトップには、遥か異国でよく取れるという青い貴石がはめ込まれていた。友人はそれを見て目を輝かせた。
「あーっ、いいなあ!!ラッキーじゃん!神様の贈り物だよ!売ったらお小遣いいっぱい増えるね!!」
その言葉に、カヤはうれしさで頬を紅潮させた。この村のしきたりで、森で拾った宝物は見つけた人のものになる。この指輪は紛れもなく、見つけたカヤのものだった。よかった、ちょうどほしいものがあったんだ。
「そうだね!!帰ったら屋台に売ってみよう!きっと高く売れるよ!!」
「いいなー、私もなんか見つけられないかなあ」
友人は俄然やる気になって、木の根元に目を凝らし始めた。いいなあ、私もお小遣いほしい。そんな呟きが聞こえてきた。カヤは見つけた指輪を大事にポケットにしまった。あとで忘れないように、ちゃんと売ろう。
とある世界の、とある小さな村。村長の娘であるカヤは、村の工芸である木工が好きな、ごく普通の少女だ。村の余分な木を切り倒し、その木で作った食器や雑貨が都会でそれなりに売れるのだ。繊細な彫刻を施したものほど高く売れる。カヤは食器やペン立てなどに細かな彫刻を施すのが好きだった。キレイに彫れると、いろんな人からほめられた。これは高く売れるぞ、カヤは見事な技術の持ち主だ。そうしてたくさんの人がほめてくれるのが、カヤの何よりの幸せだった。今日もカヤは森へ入り、来週の伐採の日に切り倒す木を見定めていた矢先の幸運だった。村を覆うこの森からは、ときどきこうしてお宝が見つかる。森で見つけたお宝は、見つけた人のもの。これはこの村の決まりだった。これでお小遣いが増えて、ほしいものが買える。ちょっと美味しいものを買うのもいいな。カヤは想像を膨らませ、わくわくと胸を躍らせた。
「もう暗くなっちゃうね。切る木はだいたい目星つけたし、今日はもう帰る?」
「そうだね、さっき見つけた木でいいと思う!じゃあ、今日はもう帰ろっか。
あーあ、私もカヤみたいにお宝見つけられないかなあ」
友人はうらやましそうにため息をつき、カヤに続いて帰路につく。思わぬ幸運を手にしたカヤは、うきうきと軽い足取りで森を引き返していった。
翌日。カヤは2階の自室で、指輪を売ったお金で買った本を嬉々として読んでいた。最近流行りの小説だった。物語の展開に夢中になっていると、ふと部屋の扉がノックされた。
「カヤ。ちょっと、下に降りてきて」
母の声だった。普段どおりの母の声だったが、どこか浮かないような声だった。カヤは物語の続きが気になって仕方がなかったが、母が心配になり、しおりをはさんで本を閉じ、ぱたぱたと階段を降りていった。
リビングの扉を開けると、両親がソファに座っていた。父はカヤをソファに座らせると、ひと呼吸して、カヤに言った。
「カヤ。大事な話がある」
父の顔は真剣だった。カヤは少し肩に力を入れた。父は重い口を開いた。
「カヤ。今年の“神の使い”が、お前に決まった。
来週のお祭りで、カヤは神の御許へ行くことになったんだ。
村のシャーマンの占いで、お前が神に選ばれたんだよ」
カヤは目を見開いた。年に一度、この村で行われる村祭り。そこでは毎年、村が信仰する森の神に誰かひとりが選ばれる。選ばれた者は村祭りを最後にこの村を去り、神の御許へ行くと教えられていた。その選ばれし者のことを、村では「神の使い」と呼んでいた。
「神の使いに選ばれるのは名誉なことだ。選ばれた者は森の神の御許で、永遠に幸せに暮らせるという」
「カヤと一緒にいられるのは、来週のお祭りまで。
さみしいけれど、カヤが幸せになれるなら、お母さんたちも幸せだわ」
「おめでとう、カヤ。別れはさみしいが、神の御許で、幸せに暮らすんだよ」
両親は口々に祝いの言葉をカヤにかける。カヤはいまひとつ、実感がわかなかった。どこかへ引っ越しをするような心地だった。そうか、そうしたら、友達とはもう会えなくなるな。挨拶まわりに行かなくちゃ。カヤは頭の片隅で、そんなことを考えた。
その日の夕食は、カヤの好きなものばかりが並んだ。
友人や世話になった人たちに挨拶まわりへ行くと、全ての人から祝福の言葉をもらった。おめでとう、カヤの日頃の行いだな、さみしくなるけど幸せになれよ。みんな、カヤの幸せを願った。カヤもなんとなく、幸せになれそうな気がした。
一緒に森へ行った友人が、手作りの首飾りをプレゼントしてくれた。カヤの好きな緑色の、キレイなビーズの首飾りだ。お小遣いの中で作った安っぽい首飾り。けれどその一粒一粒に、友人の思いがこもっていた。カヤは大喜びで受け取って、肌身離さず身につけた。
そうして1週間が過ぎ、村祭りがはじまった。広場に火を焚き、炎の周りで村人たちがうれしそうに踊っている。その様子を、カヤは上座からぼんやりと眺めていた。
今までずっと、あの踊る人々の中のひとりだった。この上座に座る神の使いを、他人事のように見上げていた。それが今は、自分が座っている。まるで現実味を感じなかった。
儀式を終えて、村役場へ通される。禊を行い、身を清めて、儀式用の衣で身を包む。厳かな気を発する儀式の間へ通されると、そこは薄暗い部屋だった。診療台のような人が横になれる台座があり、その周りを、ヴェールで顔を隠した人々が囲んでいた。
カヤは少しばかりの緊張と不安を覚えたが、近くにいた大人が優しい声でカヤに言った。
「大丈夫ですよ。痛くも、つらくもありません。
この薬を飲んで、この台に横になってください」
そう言って、盆の上にのせた2種類の飲み薬をカヤに差し出した。カヤは不安を取り除けなかったが、大人しく薬を飲み干して、台座の上に横になった。薬は少し甘いと感じる程度で、なんのにおいもしなかった。
横になると、すぐに睡魔が襲ってきた。うとうとしていると、視界に入る大人がカヤに言った。
「これから神の御許へご案内します。目が覚めたら、そこで3日間過ごしてください。3日経てば、神がお迎えにいらしてくださるでしょう」
その言葉を最後に、カヤは睡魔に飲まれていった。
何やら温かい。身体がぬくぬくと気持ちがいい。左目に少し違和感がある。そこまで感じて、カヤは目を覚ました。
知らない部屋。見覚えのない内装。木でできたそのインテリアは、辛うじてここが村の中のどこかであることを指していた。窓の外は美しい森。木漏れ日が輝き、外からは鳥の声がする。タンスには清潔な衣服が並び、キャビネットの中には生活用品がキレイに整頓して仕舞われていた。
どうやらここは、小さな小屋のようだった。人1人が生活するのに不自由しない衣類と、食糧、水が用意された小屋だった。退屈しのぎに使えそうな本も、本棚にたくさん納められていた。カヤ以外には誰もいなかった。
部屋を見て回り、ふと脱衣所の壁にかけられた鏡を見た。鏡の向こうの自分の顔には、見覚えのない傷がついていた。左目を囲うように、紋章のような傷があった。左目に感じていた違和感は、どうやらこの傷のようだった。違和感はあるが、痛みやかゆみはとくにない。儀式の際につけられたものだろうか。カヤは眠っていたので、全くなんの記憶もなかった。
外に出てみる。見覚えのない森だった。木々の葉の擦れる音が心地よかったが、全く人の気配も何もないその様相は、どこか少し寂しかった。
カヤは言われた通り、小屋で過ごした。この小屋で3日過ごせば、神が迎えに来るという。神様って、どんな姿をしてるんだろう。どんな声で話すんだろう。私と仲良くしてくれるかな。カヤは少し期待した。
何事もなく、あまりにも何事もなく、1日が過ぎ、2日が過ぎた。左目に違和感を感じる以外は、とても平和な時間だった。
3日目の朝。目が覚めると、何やら頭が重かった。
左目の違和感が強くなり、視界がやけに狭かった。左目が開いていないのだとわかった。左目に触れてみると、何かゴツゴツと固いものと、ふさふさした柔らかいものが当たった。寝室の鏡を覗き込んで、カヤは硬直し、血の気が引いた。
左目が、木になっていた。左目のあったところがそっくりそのまま木の皮のようになり、皮目からみずみずしい新芽が生えていた。それだけではない。その新芽は目に見えてぐんぐんと生長し、にょきにょきとその身を伸ばしていた。
目にした光景のあまりの気味悪さに、カヤは頭がひっくり返るように愕然として、悲鳴をあげた。そして新芽をつかみ取り、指でねじり切ろうとした。新芽は柔らかいはずなのに、どれだけ力をこめても一向に切れることはなかった。それどころか、新芽を切ろうとすると、左目がじくりじくりと痛んだ。まるで新芽に神経が通っているかのようだった。
カヤは絶望し、ハサミを取って木の皮になっている部分を抉り取ろうとした。皮になった左目に刃を当てると、たしかにハサミの冷たい固さが皮を通して伝わってきた。この木になっている部分にも、神経が通ってしまっているように感じた。
鏡越しの自分の顔が真っ青になっていた。ふと手を見れば、手もまるで木の皮のように固くなり、その節々から枝が伸び始めていた。カヤは叫び、枝を切ろうとするも、枝も固くて切れなかった。枝の1本1本に神経が通り、とても痛くて切れなかった。
顔の新芽はどんどん伸びて、茎が細い幹になっていった。カヤは我を忘れて、何か叫びながら全速力で小屋を飛び出した。脳裏に思い出が蘇る。友人の顔、お世話になった先生の顔、両親の顔、みんなの笑顔。みんなにすがりたくてたまらなかった。誰か、誰か助けて!!
どれだけ走っても、森は抜けることがなかった。その木の1本1本に、よくよく見れば人の顔が埋まっているような気がした。ああ、そうだ。そうなのだ。これがこの森の真実なのだ。走りながら、カヤは真実を知ってしまった。この村の森が、何でできているか。私が今まで削ってきた、切ってきた木は、なんだったのか。ときどき見つかるお宝が、いったい誰のものだったのか――――
ふと、足が重くなって、カヤはそれ以上走ることができなくなった。足を見ると、足はすっかり茶色くなり、ごつごつとした分厚い木の皮で覆われていた。木になった足はその下の地に根を張って、カヤはいよいよ動けなくなった。くらくらするほど頭が重い。左目の新芽が、もう立派な木に生長してしまっていることが、その重さで理解できた。
カヤはふと、空を見上げた。もうすっかり夜になっていた。けっきょくずっと走ったけれど、森の出口は見えなかった。静まり返った森の中、カヤは力なく月を見上げた。視界の中央、まん丸に輝く満月は、まるで神の光のように神秘的で、しかし冷たい輝きを放つばかりだった。
私は、木工が好きだ。
代々、この村では木工が盛んだった。余分な木を切って、その木で食器や雑貨を作る。繊細な彫刻を施したものは高く売れた。だから皆、競って腕を振るっていた。
私の作る工芸品は、町でとても高く売れた。私は村いちばんの工芸師として、毎日木を彫っていた。
ある日、来週切る木を見繕いに森へ入ると、ふと木の根元で何かが輝いた。もしや、お宝か。そう思い手を伸ばすと、それは粗末な首飾りだった。
緑色のビーズをつなげただけの、古びた安っぽい首飾り。高く売れるわけもない、森を汚す、ただのゴミだった。こんなものも落ちているのか。私はそれを拾って、森の奥へと進んでいった。この首飾りは、帰ったら捨てよう。頭の片隅にメモをして、私は首飾りをポケットへしまった。
+++
「神の森」4,777字
お題「根」
→「根」:いつまでも痕が残るイメージを形にした漢字。
「艮」は、目の周りに傷をつける情景をあらわしたもの。
みんなのネタバレふせったーを読みたい!というときは 「fusetter.com キーワード」でTwitter検索してみてね
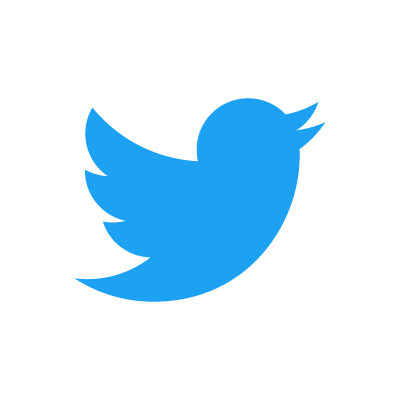 元ツイート
元ツイート