モノのキャラシ(ダブクロ、Life on Edge)(2万字)(ただの短編)
ネタバレはないが、わーい!書ききった!って推敲もしてない。そのうち推敲します。
ネタバレはないが、わーい!書ききった!って推敲もしてない。そのうち推敲します。
※ただのダブクロキャラシ
※とっちらかってる&書きたいことだけ書いてる
※文章力?ゴミ
*
永遠に答えの出ない問いを、投げかけ続けている。
胸に溜まった薄暗い異物を取り除く方法を探していた。
叫び出しそうな、絞り出すしかない“それ”を消す方法を。
机の上で美しく咲く花を見つめ、ひとつ溜息をつく事しかできない。
窓際、一番後ろの席に飾られた白い百合。
見慣れた光景だった。
遠巻きに注がれる奇異の眼を無視して、自身に割り当てられていたその席から、一輪の百合の花が生けられた花瓶を取り上げる。そして教室後ろに設置された合板作りの低い棚の上に乗せるのだ。
その後はただ席の椅子を引き、学生カバンから自身の教科書を机に投げ込む。
いつも通りの朝だ。ここ2カ月、このルーティーンが崩れたことはない。
いじめ、と呼べばそれまで。
だが単純にそう呼ぶには、彼らにはあまりにも害意がなかった。
毎朝飽きもせず花を供えるだけ。それ以上の事は起こらない。いや、起こせないのだろう。
僕に向けられる目線は、怯え、恐れ、そして僅かな好奇心。
花が示す彼らの意図はひとつ。
『学校に来るな』
それだけだ。
物心がつく頃には、父親が塀の中にいた。
母親は『父は必死に組織を抜けようとしていたんだ』と言っていたが、僕にとってはどうでもいい。
どんな綺麗事を並べ立てようと父親が犯罪者であるという事実は変わらず、僕と母親の生活を蝕んだ。
住んでいる場所を転々としたが、数年も経たぬ内にどこからか噂が流れ、周囲の人間はどうあっても僕と母親を忌避した。
ひっそりと生きていく事に慣れ、それを受け入れていてもなお断絶された。
小学校3年生の時、父親が犯した罪が殺人だった事を知った。
母親伝手ではない。その時近所に住んでいた女性が、遠巻きに、しかし大きな声で話していたのが耳に入ったのだ。
何故息子すら知らない事を、赤の他人で、それも僕らを避けている人間が知っているのか。
確かに僕が意識的に父親の罪状を知ることを避けていた節もあっただろう。
だが、それにしても滑稽だった。罪状に対して何の感情も抱くことはなかったが、そのお節介な隣人に対して思わず笑いが込み上げてきた事を覚えている。
その時からだ。喉の奥に薄暗い異物が住み着いたのは。
叫び出しそうな、決して飲み込めないこの違和感は、大きくなることも小さくなることもなく僕の胸と喉の間に居座った。
「怖い」
「恐い」
「今はおとなしいが、怒らせたらきっと殺される」
「いなくなってしまえばいいのに」
「どうしてここに住むんだ」
周りの人間がそう言って僕達を遠ざける事を、僕はちゃんと受け入れていた。
だって、そうしない保証なんてなかったから。
侮辱されたり、殴られたり、あまつさえ殺されかけた時に、相手を殺したいと思ったことは幾度となくあるのだ。
ただ、それをする事に意味を感じず、実行しなかっただけで。
目の前の人間は、自分という害を退けようとしているだけなのだ。
彼らには彼らなりに正義や理由があって、僕を殴っている。
僕はこの世界にとって害でしかない。
けれど、僕はできる限り無害でありたい。
ガラリ、と引き開けられる扉の音。
それまで僕に注がれていた視線が遠のいたと同時に、僕の思考もまた引き戻される。
「一義君!おはよう!!」
その場に人間の視線を一身に受けた人物が、大きな声で僕の名前を呼んだ。その挨拶を僕は当然のように無視する。
ぐんぐんと近づいてくる気配はすぐ真横までやってきた。そして、視界の端でニカリと笑いながら声をあげる。
「お!は!よ!う!」
「……おはようございます」
「なぁ~一義君。いい加減、敬語は取ってくれよ」
「……」
ぐ、と喉を絞る。薄暗い異物が口の中を満たしかけるが、辛うじて飲み込んだ。
彼は僕から反応を得られないと分かると、やれやれと言った様子で前の席の椅子を引く。
僕は鞄から一冊の本を引っ張り出し、挟んであったしおりを頼りにページを繰った。
前方から性懲りもなくかけられる声を延々と無視し続け、朝のホームルームが始まるチャイムが鳴った瞬間に本を閉じる。
眼前に映る少年は、茶色い短髪の生えた頭をポリポリと指でかくと
「なんでそう頑なかな……」
そう呟いた。
と同時に、教室の前方のドアが開く。担任が「おはよー。朝のホームルームはじめるぞー」と間延びした言い方で声をかければ、それまで立ち上がって雑談していた生徒は誰もがおとなしく席に着いた。
担任は前方の席から出席番号をとってゆく。
美月一義と名を呼ばれ、僕は淡々と返事を返す。
名前のような変わった苗字。父親の姓だ。
父親の無実を頑なに信じる母親は、離婚という選択肢を取る事も、姓を変えるという事もしなかった。
このおかげで僕達の素性が周囲にバレる事は数多く、最初は僕も母親の愚行だと思っていた。
けれど、きっと彼女は彼女なりの考えを持ってそれを貫いていたのだろう。
そもそも、僕を放り出すこともせず、義務教育を終えてもなお高等教育機関に通わせてくれている母親には感謝こそすれ、恨みなどあろうはずがない。
この姓が嫌であれば、僕はさっさと母親の元から離れ、就職なりなんなりすればよかったのだ。それを選ばなかったのは僕なのだから、文句を言う筋合いもない。
「ねぇレイジ……いい加減かかわるのやめなよ」
「なんで?」
「いや、なんでッて……」
担任がクラス名簿を読み上げている最中、前方の男子生徒と右斜め前の女子生徒の声が僕の耳に届く。
「一義君は何一つとして悪い事はしていないじゃないか。何もしていない人間を避ける方がおかしくないか?」
「いや……それはそうかもだけどさ」
「おーい、石井。石井零士。遅刻かー?」
「うわっひでえな先生!どう見てもクラス全員そろってんじゃん!!」
名を呼ばれおどける彼に向けて、クラスの数人がくすくすと笑う。
好意に満ちた笑みばかりだ。――そう。分かっている。彼は、石井零士という人物は、確かに善人なのだ。
僕は静かに目を閉じ、喉の奥までせり上がった感情を何とか飲み下す。異物、としか言いようないそれが何の感情を孕んでいるのか、僕には分からなかった。
だが、それが多くの感情を綯交ぜにした黒々としたものであることは確かだ。
そして、彼が近くに寄るたびにその異物は存在を主張し始める。あぁ、なんて煩わしい。近寄らないでほしい。放っておいてほしい。ただ、ただそれだけで良かったのに。
「あー。まぁ、皆も多分知ってると思うんだがな」
律儀に出席を取り終えた担任が、徐に咳ばらいをして切り出した。
その瞬間、それまで教室のいたるところで勃発していた小さな話声が一気に止む。
僕はといえば、一番後ろの席を良い事に先ほどまで開いていた本を再び開き、文字列を目で追う事に忙しい。
文庫カバーがいちいち取れかかるのが煩わしかった。エラリー・クイーンをはじめとした海外の推理小説を読むことは好きだが、あらぬ噂を立てられないためにはブックカバーは必須である。
「今日からクラスに仲間が増えるからな。転校生だ。仲良くするんだぞ」
「うちのクラス、他のクラスより人数1人少ないからクラス対抗戦不利だったもんなー」と続けながら、担任が黒板にチョークを打ち付ける音。
だが、担任が続きの言葉を紡ぐより先に、教室の扉が開く音がした。
「あ、やっべ。タイミングミスった」
そう声が聞こえるや否や、バン!と教室の扉が乱暴に閉められる。
思わず顔をあげるが、そこに『転校生』らしき影はなかった。どうやら先走って扉を開けた癖に入らずに閉めたようだ。
一瞬唖然とした雰囲気に包まれた教室が、誰かが吹き出した事を皮切りに笑い声で包まれる。
「あー……。佐々木。入ってきて良いぞ」
苦笑ともつかない表情の担任が扉に向かって手招きすると、彼はそろりと扉を開け、愛想笑いを浮かべて入ってくる。
短い茶髪に快活とした表情が似合う少年。のように見える。
僕はそれだけを確認して再び本に目を落とした。
「うわー……初手からミスっちまったんでクソはずいんすけど、えっと、佐々木です」
「いや、下の名前」
「あッ、コーヘーです!幸せな平面で幸平!」
「幸せな平面ってなんだよ!!」
前方の人間からヤジが飛ぶ。笑いに包まれる教室。まるでその場の全員が陽だまりに浸かったようだった。
恥ずかしそうに頭をかきながら苦く笑う少年は、そんな笑顔を一身に受けている。
あぁ、きっと彼も『良い人』なんだろう。
少なくとも、他者を笑顔にできる人間だ。僕とは違う。
本に目を落としながらそう思う。そこに感情は特にない。
「んじゃ、佐々木は一番後ろの席な」
「マジすか!?俺目ェめっちゃいいんですよ!」
「だから何なんだよ」
呆れ気味の担任が言葉を返す。脈絡のないそのやり取りがツボに入った人間も多いようだ。
先程まで俺に視線を送っていた人間が変化したわけではない。人間の変わりようは不思議なものだと感嘆さえ漏れる。
転校生の少年は、担任に指定された席に着く。教室の一番後ろ。窓際から数えて二番目。つまりは僕の隣だ。
「あ、よ、よろしくな?」
席に着くと同時に、何故か疑問符の付いた挨拶。
僕が本から顔を上げれば目がしっかと合ってしまった。逸らすタイミングを見失い思わず硬直した途端、目の前に手を差し伸べられる。
「俺、コーヘー。おま、き、あー、なた様は?」
おまえ、きみ、あなた、と探して着地したのが『あなた様』とは、随分言葉選びが下手らしい。
眼前の少し抜けた様子の少年にかけられた問い。僕がそれに答えたのは、ほとんど反射のようなものだった。
「……美月」
瞬間、教室内の空気が凍り付いた。
奇異の視線。だけではない。不信感、驚き、それから、不安だろうか。
あぁ、失敗したのか、僕は。いや、挨拶をされて返す事の何が悪い。僕は何も悪い事をしていない、はずだ。
けれど、自信はなかった。周囲が何を考えてこの空気を作り出しているのか僕には分からない。
胸と喉にあの不安な塊が押し寄せるばかりで息が詰まる。
「へー。ミツキ。良い名前だな!」
差し伸べられた手を引っ込めることなく、彼は僕にそう言って笑いかける。
が、僕にその笑顔を見る余裕などなかった。
――僕は、この手を取るべきなのだろうか。
分からない。分からない。
視線は何を考えているのか。名前を名乗っただけでこの空気になる程だ。手を取ったら、どうなる。
僕は
僕は無害でありたい。それだけだ。どうすればそういられる。
掻き混ぜられる思考がショートするその寸前、不意に横から彼の手を掴むものがあった。
「コーヘーっていうんだね!よろしく!オレは石井零士!」
「え?」
僕の前に座る石井零士が、転校生の手を取って握手をしたのだ。
――助かった。のだろうか。少なくとも僕が彼から視線を逸らす理由はできた。
転校生は突然割って入った石井零士に気を取られたようで、困惑しつつも愛想笑いを浮かべ直している。
「仲良くしろよぉ。じゃ、一時間目の準備をしてください」
そう担任が締めくくると同時に、僕は英語の教材を机から引っ張り出し席を立った。
「あ、ちょい」
転校生は何かを言いたげだったが、聞こえないふりをする。
僕が彼の背後を何も言わず通り過ぎると共に、転校生の周囲にはあっという間に人だかりが出来上がった。
「ねぇねえ!どっから来たの?」
「部活何入るとかあんの?」
「え?あ、えっと、……どっから?トーキョー?」
「東京!都会っ子じゃん!」
「てかウチの学校、3年の修学旅行先東京だよ?里帰りじゃん」
「えっ、マジ!?うわー、沖縄とか行きたかったわ」
――あぁ、良かった。
背後から聞こえてくるそんな言葉を、声を聞いて、僕は安堵する。
転校生に対する対応を僕は少し間違えたかもしれない。けれど、変わらなかった。
ちゃんと、僕は無害でいられた。
僕とさえ関わらなければ、転校生の彼は、これから先きっと明るい高校生活を送る事ができるだろう。
決してこの学校は陰湿な訳ではない。
誰しも他人の机の上に花を置くなんて遠巻きな嫌がらせを好んでやりたい訳がないのだ。
彼らは僕が怖いだけ。僕さえいなければ平穏な生活を送れると信じているだけで。
ごめん。僕は無害でいるから。何も、何もないから。だから、せめて存在する事は許してほしい。
教室を出る僕の背後からは転校生を歓迎する声が絶えず湧く。
明るい光を遮るように、僕はゆっくりと後ろ手に扉を閉めた。
*
朝。
僕はいつも、ホームルーム開始のチャイムが鳴る数分前に教室に入るようにしている。
他の人間に紛れ、できるだけ教室に居座らないようにするためだ。
教室に入ればいつも通り机の上には花瓶があって、数人が怯えた目で僕を見る。
怯えた目をしている人間が恐らくその日の«当番»なのだろう事は、このクラスになって数日で分かった。
そんな顔をするくらいだったら、やらなければいいのに。
僕にこんな安い精神攻撃が効かない事くらい、2ヶ月も経っているのだから分かってほしいものだ。
いちいち避けるのも面倒くさいが、直接暴力を振るわれる“いじめ”よりなら数百倍マシというものである。
僕の直後に、石井零士はやってくる。いつも僕に何かと話しかけてくる、席が近いだけの男。
彼は明るく語り掛けてくるが、僕は無視をする。
それがいつもの日常。
何も変わらない。けれどある意味では【平穏】な日々。
「すいません!!!遅刻しました!!!」
ホームルームが始まった30秒後に飛び込んでくるのは、転校生だ。
担任が軽い口頭注意で済ませ、周囲からは小さな笑いや「またかよ!」という野次が飛ぶ。
恥ずかしそうに頭をかきながら座る転校生。
ここ最近ではお決まりの光景だ。
隣人となった転校生は度々僕に話しかけてこようとしてきたが、無視にならない程度に避け続けた。
クラスの人間とほぼ数日で打ち解けた様で、彼は自然とクラスの輪に入っている。ように思える。
実際の所どうであるかは分からない。知る由がないのだ。
僕はホームルームと授業、それから掃除以外の時間は、ほとんど人目の付かない屋上で過ごしている。
だから彼がクラスメイトとどう過ごしているか、僕は知らない。
けれどそれでいい。
陽だまりの中にいる人間を、僕のせいで日陰に追いやることになったらと思うとぞっとする。
ただ、今は僕に与えられた【平穏】を享受するべきだ。いない者として扱ってくれるならそれで。
僕のその願いが通じたのかは分からない。
だが、確かに僕は【平穏】を享受し続ける事ができたのだ。
*
それは唐突にやってきた。
いつも通り屋上で、家で握ってきたご飯をほおばる。すっかり固くなった米を咀嚼しながら、その日はアガサ・クリスティを読んでいた。
アガサ・クリスティと言えば灰色の脳細胞を持つ名探偵が代名詞かもしれないが、僕は彼女の書く安楽椅子探偵が好きだった。
推理小説ではほとんど必ずと言っていいほど人が亡くなる。そして登場人物は誰しもがその死と向き合うのだ。そこにはどうしても、死に対する『やりきれなさ』が存在する。
その『やりきれなさ』。あるいは『痛ましさ』は、僕の喉の奥にある異物とたまに混ざり合う。そしてその異物が『推理小説による痛ましさ』なのだと考えると、幾分か心が楽になった。
屋上に僅かに存在する日陰に身を寄せ、静かに食事を摂る。
「あ、やっと見つけた」
そんな【平穏】を壊す声に、僕は思わず身を固くした。
本から顔を上げず、平静を装って文字列を追い続ける。さっぱり頭に入ってこないままページを繰る。
そんな動作を続ける僕の元に、声の主はやってきた。
「えっと……。美月……」
「……」
「あれ?美月は覚えてんだけどな?」
壁に背中を預けて座る僕の前に、彼がしゃがみ込んでくる。
少しでも視線を上げれば彼の顔は目に入るだろうが、極力それは避けたかった。
「……関わらない方が良いよ」
「え」
僕が本に目を落としたまま口を開けば、相手は素っ頓狂な声を上げる。
1カ月前にやってきた転校生の声は、もはや聞き慣れたものだ。
「僕の事、聞いてない訳ないだろ。……関わると、貴方まで避けられる」
「避けられる?なんで」
そこで僕は顔を上げた。正面にしゃがむ彼は陽だまりの中でじっと僕を見つめている。
思わず息を飲みこむが、彼の瞳に捉えられた僕の視線はもう外せない。
「何でって……。僕は……」
「俺さ、美月君を探してたんだ」
「……?」
誰かの目を見て話すなどいつぶりの事なのだろう。いや、目を見て話すどころか会話すらままならないのが僕の常だ。近頃は母親とすら話をしていない。
久しぶりの会話に戸惑うばかりで、僕は「探してた……?」と彼の言葉を繰り返す事しかできなかった。
「前から話してみたかったんだよな。隣の席なのに全然話した事ねえじゃん?な、推理小説好きなんだろ?」
「えっ」
何故それを。と続けそうになって、必死に飲み込んだ。
本には常にブックカバーをつけているはずだ。僕が読んでいる本が推理小説だとバレないように。
今ここで声を出せば、僕が推理小説を、『殺人』に関わる本を読んでいる事がバレる。
そうすれば、どうなるのだろうか。怯えるのだろうか。他の皆と同じように。
それは、僕の本意ではない。
ぐ、と自分が本を持つ手に力がこもった。彼はそれを見止めたのか、苦笑を浮かべて僕に笑いかけてくる。
「あー、いや、その。……盗み見たのは悪かったよ。俺、昔っから目が良くて。けどこの前美月君がエラリー・クイーン読んでたの見えて、うわ、読んでる人いるんだと思ってうれしくなってさ」
まるで言い訳のように捲し立てられたその内容を、一拍置きで把握する。
そして、納得した。
あぁ、彼はきっと僕の事を知らないのだ、と。
知らなければ、恐怖もすまい。
僕は彼の言葉には何も返さず、日陰の中立ち上がる。
「佐々木君。僕の事、本当に何も聞いてない?」
「? どうしたんだよ、さっきから」
「なら、知っておいた方が良い。……僕の父親は殺人犯だ」
日向の彼は首を傾げる。
「だから?」
「……だからって」
「いや、何かクラスの奴らも言ってたんだけどさ。え?だから何?」
視線を落とした。しゃがんだまま僕を見上げる彼は、眉をひそめている。
まるで心底意味が分からないとでもいう様に。
咄嗟に歩き出そうとした僕の腕を、彼の手が掴んだ。
「ちょ、おい!そんな逃げなくたっていいだろ!?」
「でも」
「いやいや、俺、別に美月君の親父の話しに来たんじゃなくて、趣味の話しに来たんだって」
「趣味って……」
「え?推理小説好きって訳じゃねえの?」
「いや……好き、ではあるけど」
「やっぱり!そうか!よかった!なぁ、エラリー・クイーン好きなのか!?俺『悲劇4部作』好きでさ!」
呆気にとられた僕の腕をあっさりと離し、彼はエラリー・クイーンだけではなく、コナン・ドイルが、東野圭吾の名作がと目を輝かせて話を始めてしまった。
完全にその場を去るタイミングを計り損ねた僕は、あぁ、とか、うん、とか、へどもどな返事しか返す事ができず、視線を宙に彷徨わせる。
「……って、悪い。……迷惑だったか?」
だが、熱を持って僕に語り掛けていた転校生は、僕の反応を見てすぐに口を閉ざした。
1人で長々と語る趣味は流石にないらしい。彼は恐らく本当に推理小説を語れる人間を探していただけなのだろう。
それがたまたま運悪く僕しか見つける事ができなかった。それだけの話なのだ。
「僕は迷惑じゃないけど。……でも、僕の方が佐々木君に迷惑かけかねないから」
「いやいや、俺がそっちと話したくて探してたんだから、迷惑な訳ないだろ」
「でも、僕と話してたら、クラスの皆に冷たくされるかもしれない」
「はぁ……?マジで意味わかんねーな。じゃぁ、そん時は美月君が俺の相手してくれよ」
そう言って転校生は膝を伸ばし立ち上がる。昼間の日光を浴びた彼は、口元を吊り上げて僕に笑顔を見せた。
「な、美月君が好きな推理小説とかないのかよ」
「え、……」
「あぁ。ほら、何か俺よりずっと小説読んでそうだったし、おすすめとかあればさ!」
屈託のない笑顔だった。
先の反応を見る限り、僕の事をクラスの人間から聞いていない訳ではないのだ。
ただ彼は、僕の父親という存在をを完全に僕から切り離していた。それだけの話で。
今まで、僕に好奇心で近づいてきた人間は少なからずいた。
僕に優しくすることで、自身の優しさを誇示しようとする者もいた。
けれど、それらが見ていたのはあくまでも『殺人犯の父親を持つ美月一義』だ。
「……僕は、『容疑者Xの献身』が好き……かな」
「うっわ、分かる!!やっぱお前分かる奴だった!!」
興奮気味に人差し指で僕を指し、直後「やべ、うっかりお前とか言っちまった」と慌てふためく。
やはり彼は言葉を選ぶことが苦手なのだろう。けれど、それを悪し様に思う事はない。
口から言葉が滑り出した今でも、まだ半信半疑だった。本当に、僕個人に対して好奇心を向ける人間が存在する事があり得るのか。
だがこの場で、この瞬間に答えが出る事はないだろう。
例え裏切られたとしても。目の前で笑う彼がやはり『殺人犯の父親を持つ人間』に興味があっただけだとしても。
それでもかまわないと思えた。
あの不気味な異物が、少しだけ薄まる。この感覚を、もう少し留めていたかった。
そうして僕と彼が共に行動するようになって1ヶ月後。
珍しく彼が僕より先に席について、その日は確か『アヒルと鴨のコインロッカー』を読んでいた。珍しいな、と思ったのを覚えている。
僕の机の上に、花瓶はなかった。
遠巻きに僕を見る視線の中、先に座っていた佐々木幸平が、僕を見て笑ったのだ。
「よ、おはよ」
小さく挨拶を返し、席に座る。
足元が少しだけ砂利ついた。
その日以降、僕の机の上に花瓶が置かれる事は無くなった。
*
転校生――佐々木幸平と趣味を語り合う仲になった。
お互いを苗字に君付けで呼び合うのは流石によそよそしすぎる、ということで、僕は彼を『幸平』と呼び、幸平は僕の事を『カズ』と呼ぶようになっている。
何故僕だけ略されるのかと言えば、「僕の下の名前を呼び間違えたら流石に申し訳ないから」だとか何とか。
致命的に人の名前を覚えることが苦手な幸平は、僕の名前を最初『美月』だと思って珍しい名前として憶えていたらしい。その後ちゃんと自己紹介をしたところ、下の名前がなかなか覚えられず、結果『カズ』呼びが定着した。
今となっては流石にフルネームを覚えてもらっているが、当初は『カズヨシ』『カズヒコ』『カズオ』と呼びたい放題だったのだ。本人には一切の悪気がない点が、僕としては面白かった。
ここ最近でわかったのは、佐々木幸平という男はよく喋り、よく動くという事。
感情表現の豊かな彼の言動や行動は、今まで対話をした人間の中でもずば抜けて分かりやすかった。
僕は自分が他人の機微に疎い事を自覚しているが、それを加味してもなおこの男の考えている事は面白いほどに筒抜けだ。楽しければよく笑うし、気に入らないことがあればすぐに言葉にする。
「自分といて本当に楽しいのか」「気を使っているのではないか」と罪悪感じみたものを僕が抱えた事もあったが、幸平は僕との時間が嫌になったらきっと勝手に離れていくだろう。彼がこうして僕といるのは、あくまでも彼の意志なのだ。
幸平といて楽なのは、そう僕自身が思える事でもあった。
決定的だったのは、僕の机に花瓶が置かれなくなって半年が経った頃。
帰りのホームルーム前に行われる清掃時の事だ。
その週、僕達は男子トイレが担当だった。
掃除場所の担当は、席の近い者を6人で括って割り振られる。席の近い者ということはつまり、幸平と、そして石井零士もいるという事だ。
毎日毎日話しかけてくる石井零士があまりにも煩わしく、僕が学校裏までのゴミ捨てを買って出るのが常だった。
「なあ、どうして君は彼とそんなに仲良くなれたんだ?」
「あ?」
それもあと2日の我慢、と考えながら戻ってきた水曜日。トイレの中から聞こえてきた声に僕ははたと足を止めた。
「彼?」
「一義君だよ。オレはキミが来る前から、よく彼に話しかけてあげてるんだが……。何故か全く相手にしてくれなくて」
その問いに答えとなる声は無かった。
女子トイレの方聞こえてくる楽しげな話声にまぎれて聞き逃してしまったのだろうかと、僕は少し足を踏み出す。が、
「……石井ってさ、カズの事どう思ってんの?」
ああ、機嫌を損ねたな。
耳に届いた低い声に覚えがあるわけではない。普段自分の機嫌を取るのが上手い幸平が僕に怒った事は1度もなかった。
だが、彼ほど感情をストレートに投げる人間もそういない。聴覚でしか状況は探れないが、それはあまりにも分かりやすい空気の変化だった。
「どう、とは?」
「お前、よくカズに話しかけてるじゃん。そんとき、アイツはどんな奴だと思って話しかけてんだ?」
「どんな奴……。彼は大変な思いをしてる人だと思ってる。だから少しでも力になれたらと。彼が悪い事をした訳じゃないから……」
「へぇ。そういうくせに、あの花瓶は放置してたんだな」
幸平の声が鋭さを増した。その剣呑さにあてられてか、石井零士の声が上ずる。
「それは……和義君がクラスに打ち解けてくれたら、自然となくなると思ったんだ。彼がみんなに理解されればきっと」
「……そうかよ」
カラン、と木が固いものに打ちつけられる音。
続けて聞こえてきたのは、静かな怒号だ。
「俺さ、お前のこと嫌いだわ」
「え……」
「お前が最初にクラスの奴らにカズの家の事情バラしたんだろ?『話しかけて“あげてる”』だ?アイツがハブられる理由作ったくせに、どの面下げてそんな偉そうなこと言えんだよ」
「バラした、って……。だって、彼が悪いことをした訳じゃ無いじゃないか!父親がどうとかは、彼が虐げられる理由にならない!それをみんなにも分かってほしくて……」
不意に、喉の奥に違和感が溜まった。
ああ、まただ。最近はあまり出会わなかったのに。
薄暗い異物。胸と喉の奥から音になって出てきそうになるのを押し止め、僕は学生服の裾を握る。
『一義君が悪い事をした訳じゃないんだ!皆にもそれを分かって欲しい!』
高校1年生のクラス委員長決めの日。クラス委員長に就任した石井零士が言い放った言葉。
一体どこでその話を知ったのかとか、そんな事は最早どうでも良かった。少しでも先延ばししたかったのは確かだが、どうせいつかはバレる話だ。忌避される事に慣れきってしまった僕にとっては些細な問題で。
ただ、それでも石井零士は確かに僕の心を蝕んだ。
彼は善意から、良かれと思って僕の事をクラスにバラしたのだ。彼にとっての正義感。呆れるほどに性善説を信じ、彼はクラスの人間へ訴えた。
石井零士という人間は恐らく善人だ。誰がどう見ても。そんな彼を僕は嫌いになりたくない。なってはいけない。
だから、無視をしていた。じっと、喉の奥の違和感に耐えながら。
「それをアイツが望んだのかよ」
「それは……でも、彼を虐げるのは間違ってるだろ?それを理解してもらわないと、いつまでも彼は変われないじゃないか!」
「るっせえな!!」
響き渡った大声に、周囲が水を打ったように静まり返った。。
女子トイレから恐る恐る顔を覗かせた女子が、立ち尽くす僕の姿を見て慌てて引っ込んでいく。興味本位で近付いてくる人間に僕が視線を送れば、彼らもまたそそくさとその場を離れていった。
幸平の低い声は続く。
「お前が言う事も一理はあるぜ。カズが悪い事をした訳じゃねえ。親父のせいでアイツが縮こまって生きるのは違うと俺も思う。けど、その話が先行したらアイツに対する偏見悪化するってなんで考えねえんだよ?俺でも分かるわ。お前がクラスにそれを訴えた結果何が残ったんだ?」
「だから……オレが話しかけて……」
石井零士はぼそぼそと歯切れ悪く反論する。
「『あげてる』か?気色悪ィ。誰がンな事頼んだんだよ。カズの態度見てりゃ分かんだろ?
自己満足のヒーローごっこにアイツを付き合わせんな!!」
吐き捨てた声が、こちらへと向かってくる。
今顔を合わせる事に気まずさもあるが、僕の足は動かない。
とうとうバチリと視線がぶつかって、僕たちの間に沈黙が訪れた。
「……掃除、終わった」
ただしそれはほんの一瞬で、幸平はそんな片言を残し足早に僕の隣を通り過ぎていく。
徐々に喧騒を取り戻し始めたこの場にとどまる意味などない。僕もまた踵を返してそれを追う。
大股でずかずかと進む幸平に、事情を知らない学校の人間は何事かと首を傾げて道を開けていた。
やがてたどり着いたのは、立ち入り禁止の貼り紙がされた屋上だ。
扉を開け放った幸平は、そこから数歩立ち入ってから頭を掻きむしってしゃがみ込んだ。
「あーーーー、ムカつく!!!」
頭上の空は透き通った水色をしていたが、フェンスの奥は赤く染まり上がっている夕方。西日に当てられて長く伸びた幸平の影が、僕の足元に落ちる。
僕が後ろ手に扉を閉めてもなお、幸平はしばらく不満げに喉から絞り出すような息を吐いていた。
「なんで、我慢できんだよお前」
「……」
その声はつっかえ、揺れている。叫び出しそうな声を必死に取り繕う様に、低い声で彼は呻いた。
「全部聞いてたんだろ」
呆然と立ち尽くす僕を振り返る。だが、幸平の背後から当てられた西日のおかげで、彼の顔が上手く見えない。
「まぁ……」
「……嫌じゃねえのかよ。周りの奴らにあんな態度取られてさ。花瓶の件とか、石井の野郎のやり方とか……色々!」
吐き出した言葉に脈絡はなかった。選ぶ余裕が無いほどに感情を高ぶらせて、幸平は声を揺らがせる。
彼が僕のために怒ってくれていると分からない程鈍くはない。
そして、幸平の問いかけに「嫌じゃない」と心から答えられるほど僕は善人ではなかった。
けれど
「駄目なんだ」
「……何がだよ」
喉の奥に声が堰溜まる。もういつから感じていたのか分からない、薄暗い違和感だ。
「僕は……皆にとって無害でありたい。だから、ダメなんだ。嫌だって思ったら」
「……」
「皆は僕を怖がるけど、それは当たり前だ。僕自身ですら今後一生父さんと同じことをしないとは言い切れない。だから、距離を置くのは当然だと思う」
無害でありたい。無害でなければいけない。
叫び出しそうな苦みをかみつぶして、僕はずっとそう思うようにしてきた。
仕方がないんだと。何もかもが僕にはどうしようもないのだと。
クラスの人間の事も理解して、石井零士の行動も理解して、そしてそれを飲み込まなければならないと、ずっと思っていた。
「僕が周りに生きることを許してもらうためには、無害でなければいけないんだ。だから、僕はそうする。それが許されるように」
掌が焼き付くほどに握り込む。
嫌だと、ムカつくと、声をあげられる幸平がうらやましかった。
僕が一度でもそんな姿を誰かに見せたらどうなるか。そんな事は想像に難くない。
「……クソみたいだな」
「……」
ゆっくりと幸平は立ち上がった。膝に手をついて、そして大きく息を吐く。
「カズが生きる事に許すも許さねえもねえだろ」
膝から手を離し、日差しを背に僕をじっと見つめた。
冷たく澄んだ風が僕の頬を撫ぜる。
影になって顔なんて見えない。だが顔を背ける事はできなかった。幸平は確かに僕の目を覗いている。
「なぁ。お前が何をしたってんだよ?」
「何もしてない。けど」
「俺は!」
自分の想像以上に声を張ったのか、幸平は驚いたように肩を震わせトーンを落とした。
「……少なくとも俺は、お前に幸せになってほしいと思うし、お前に笑って生きてくれって思う」
「それも駄目なんだ」
「ダメじゃねえ!!」
影のようだった幸平が、徐々に僕に近づく。
その黒い瞳が、僕を捉えた。
「お前が諦めてんじゃねえよ!嫌だって思う事は悪い事じゃねえんだ。嫌なことがあったら、拒否っても怒ってもいいんだ!」
駄目なんだと、口から出かかった。胸の異物がその言葉をわざと押し出そうとする。
しかし、それを幸平は許さない。
「いいか!これからお前は俺と一緒に色んな楽しい事沢山やって、嫌いなモン忘れるくらい好きなモンつくんだよ!!ダメじゃねえって、今俺が決めたんだ!分かったか!!」
まくしたてるように。矢継ぎ早に。幸平は僕をにらみつけて叫んでいる。顔も目線も逸らす事はできない。
返す言葉は思いつかなかった。本来であれば否定しなければならない言葉も、何故か今はすんなりと自分の中に落ちてくる。
ここで上っ面の返事を返す事だって簡単だ。
「……うん」
――けれど、それをする必要なんてない。
「よし!」
掴みかからんばかりの勢いが、僕の返事で少しだけ収まった。
が、それでもまだ落ち着かないのか頭をガシガシとかいて唸る。
「あーッ、むしゃくしゃする!!とりあえず!今日はめちゃくちゃ美味いモン食って帰るぞ!!」
「……」
拒否する事も、怒る事も、嫌う事も。楽しい事も、好きなものを作る事も、親友がいる今も。
全て『自分がやってはいけない事』だと思っていた。
けれど、目の前で自分の代わりに怒り、全てを許してくれる人間がいる。
怖かった。
あり得ない事だと疑うべきだ。いずれ裏切られるんじゃないかと警戒するべきだ。
けれど、僕のそんな警戒や疑いは飛び越えられてしまった。
「僕、から揚げ食べたい」
「っしゃぁ!!じゃあ岩谷商店いこーぜ!」
これから先、僕はコイツに裏切られたらきっと二度と立ち直れない。自覚ができるその域までコイツは踏み込んだのだ。
それでもいいと思うなんて、どうかしている。
心を許す事はこんなに怖いのか。
怖いけれど、――コイツならいいや。
あの薄暗い違和感は、胸の奥へと解けていた。
*
「石井が帰ってこない?」
ほっとけンなモン、と幸平はそっぽを向きゲーム画面に目を落とす。
が、同室の男子生徒は焦ったように僕らに訴えた。
「そういう訳にもいかねえよ!先生にバレたら俺らだけ明日の自由行動無しだぞ!?」
「あー、それはだりぃ」
「だろ?頼むよ、2人も探すの手伝ってくれ!」
高校3年生にあがってから、僕は幸平の人望に助けられてある程度クラスに受け入れられるようになっていた。
僕に怯える人間がいない訳ではなかったが、あからさまな嫌がらせも格段に減ったのだ。
そのおかげと言えばいいのか、3年の修学旅行も特に仲間外れにされることなく、クラスメイトの班の中に入ることができている。
1つだけ懸念点があるとすれば石井零士も同班だったことだが、彼はあの一件以来僕に対して必要以上に話しかけてくることが無くなった。
「くっそめんどくせえなー、あの野郎迷惑しかかけてきやがらねえ……」
「まぁ、明日遊ぶ下調べがてらって事でいいんじゃないかな」
「お前があっけらかんとしてんの、俺マジで腑に落ちねえんだけど」
都内で闇雲に探すわけにもいかないが、幸い旅行前に班メンバー共通で入れた携帯端末アプリによって、僕たちは過去30分以内に立ち寄った場所がお互いに把握できる。
石井零士はどうやら僕達が泊るホテルの近くをうろついているという事は分かっていたので、2人と3人に別れて捜索する形となった。
「ったく……何してんだ?」
「何だろうね。1時間くらい前から、ずっとここを円状に回ってる」
「とうとう頭でもバグったかアイツ……」
呆れた表情を浮かべながらも、幸平は迷うことなく道を進んでゆく。
その後ろをついて歩くが、都会らしい都会に出てきた事がほぼない僕の目には全てが珍しく映るのだ。きょろきょろと辺りを見渡しては、幸平に「気になんのか?」と問われ立ち止まる。
いつの間にか夜の都内見物と化した僕らの捜索は、別に回っていた3人と合流を果たして強制終了を余儀なくされた。
「あ、コーヘーにカズヨシ!あいつ、いたか?」
「いや、こっちは会ってないぜ。アプリだとこの道順通ってるはずだから、どっかですれ違ってんのかねー……って、うぉ!?」
端末をいじる幸平が、突然声をあげて顎を引いた。
「どうしたんだ?」
幸平はそう問いかける僕に一度目配せをして、自身の端末を耳に当てる。
着信か。そう合点がいくと同時に、胸にチクリと針が刺さるような感覚があった。
「よぉ、石井か?お前何してんだよ?今班の皆でお前の事……」
そこまで口にして、ふと幸平の顔が曇る。幸平は僕たちの顔を一瞥すると、すぐに耳から端末を離した。
全員の前に突き出した彼の端末から聞こえてくるのは、恐らく石井零士の声だ。
「正義を執行しなければならない。正義を執行しなければならない。苦しい思いをしている人間は、オレが救う。オレが救う。救うために、必要なんだ。必要な事なんだ」
スピーカー設定のなされた電話口から流れてくるのは、そんな言葉。
異常。いや、どちらかといえば狂気の方が近い。
端末からは石井零士の声がまるで巻き返した動画のように垂れ流されている。
「先生たちに知らせよう。コイツ、何か変なことに巻き込まれ――」
幸平が顔をあげ僕を見やる。だが、彼がその言葉を最後まで言い切る事はなかった。
徐々に大きく見開かれる目。僕が疑問に思う間もなく、幸平が僕の方へと手を伸ばし
「――カズ!!」
突き飛ばした。
瞬間、轟音が劈く。
吹き飛ばされ、肩から地面に激突した感覚。
僕の視界は何を映す事も無くただ暗転した。
激痛が身を襲い、口から意図せず嗚咽が漏れる。
どれほどの時間気を失っていたのだろう。一瞬だったのかもしれないし、長い時間が過ぎたのかもしれない。
が、辛うじて死んではいない。こうして思考できている事がその証拠だ。
耳に届くのは、悲鳴。それから火が弾ける音に、遠くからのサイレン。
何が、起こったのだろうか。
痛みに耐えながらゆっくりと身を起こせば、焼き切るような頭痛が襲った。右手をあてようと動かして、そこで初めて自らの身体の異常を知る。
破れた服の下からは皮膚が擦り切れて赤黒い肉がのぞいていた。ぼたりと垂れた血液を呆然と見つめ続ければ、徐々に痛みが身を裂いてゆく。どろりと赤い液体が右目に被る。目の上を切ったのかと左腕で拭った。
判然としない僕の視界に映るのは、瓦礫と炎。覚束ない炎から黒い煙が立ち込める。
辺りに落ちている布を纏った肉片が何なのか、それを理解するための処理を僕の脳は拒否していた。
先の一瞬でこの光景が生まれたのか、それとも僕が気を失っている間に作り出されたのか。どちらにせよ、これが現実なのだと激しい頭痛が僕に突き付ける。
霞む意識を奮い立たせ、僕は何とか両膝に力を入れて立ち上がった。
「コウ……」
名前を呼ぼうとして、声がかすれた。火の粉交じりの煙を吸って思わずむせ返る。
どこに向かえばいい。どこに向かえば、アイツはいる。
さっき幸平が僕を突き飛ばしたのは何故なのか、何がこの光景を作り出したのか。何も分からない。分からないが、動かなければならない。
「――ミツキ、カズヨシ」
「!」
不意の声。反射的に振り返って体が軋む。思わず悲鳴が漏れ出そうになりながらも、歯を食いしばって押しとどめた。
「……石井?」
背後から僕の名を呼んだのは、確かに見慣れた顔だった。
つい先ほどまで僕らが探していた人物。石井零士が煙の中から顔を出す。
僕は胸をなでおろした。こんな状況、生きている人間の顔を見て安堵しない人間などいないはずだ。
今まで何をしていたんだ。一体何が起こったんだ。お前は大丈夫なのか。
そう混乱した頭の中で作り上げた疑問は、終ぞ僕の口から問われる事はない。
「……おい」
全身の痛みが止んだ。
煙の中から現れたのは確かに石井零士の顔だ。ただし、その身体は最早人間の姿を保っていない。
狼のような爪が生えた腕に、羆を思わせる体躯。その異常な体は燃え盛る炎をものともせず、そこに立ち尽くしている。
そしてその怪物は、確かに右手に人間を携えていた。
「カズヨシ、くん。オレは、救いたい。オレが、オレが皆を」
一歩後ずさり、瓦礫に足を取られてしりもちをつく。
ざり、と石井零士の顔をした怪物が僕へと歩みを進めた。ゆっくりと、ただし確実に近づいてくるそれを、僕は凝視する事しかできない。
死ぬ、のだろうか。
受け入れがたいはずのその事実は、ただ僕の身体を強張らせるだけだ。恐怖なのかももう自分では判断が付かない。
ただ心臓が何度も跳ね上がり鼓動を繰り返している。
「……石井」
口から転がり落ちたのは、震える自分自身の声だった。
あぁ、なんて情けない声なんだろうと、その場にそぐわない感想が脳裏を過る。その拍子に、僕の意識は怪物の持つ人間へと逸れた。
大きく心臓が脈打つ音が、自分の耳と、そして痛みが続く頭を殴る。
「――幸平」
大きな爪の生えた手に捕まれて引きずられた人間を、見間違えるはずがない。
力が完全に抜けた身体は、――その半身が、引きちぎられて
光景が焼き付いた瞬間、身体が弾けるように前に出た。
助けようとしたのか、それとも怪物に殴りかかろうとしたのか、最早分からない。ただ痛みも何もかもを忘れて、石井零士へととびかかる。
ガツ、と言う音と共に、視界が明滅した。
「がッ……!」
どう吹き飛ばされたのかも分からないまま、背中が叩きつけられる。
衝撃に脳が揺さぶられ、喉の奥から熱いものが湧き上がった。ぬるりとした熱い血液を口から吐き出す。腕をついて身を起こした。内臓が掻き混ぜられる。脳が焼き切れそうなほどの痛みに、意識を手放しそうだ。
明確に横たわる死の怖気。それが僕の身体から発される最後の警告なのだろう。逃げなければ、きっと死ぬ。
しかし、僕の足は地面を蹴った。
殴りかかっても、何も意味はない。助け出そうとしても、僕が死ぬだけ。そんな分かり切った事を前に、ただ僕は右手を振り上げる。
胸がざわついた。こんな感情が自分にあるなどとは知らなかった。
これは、ただ一方的に奪われたことに対する明確な怒りだ。
今まで感じた事が無い訳じゃない。けれど、表にしてはいけないと塞いでいた感情。
何故なのだろうか。何故、突然奪われなければならないのだろうか。
これ以上声をあげれば喉は張り裂ける。それを止める事はできなかった。焼き付くような絶叫をあげ、僕は怪物へと殴りかかる。
その右手が、不意に赤く染まった。全身の血が、いや、場にある僕の血が、形を変えて怪物へと向けられる。
それは、僕が拳を振り下ろすと同時に爆散した。幾重にも折り重なる血液の刃のように、血が怪物に襲い掛かる。
腕が引き裂かれる痛み。耳鳴りがする。心臓の鼓動がうるさい。
いつの間にか瞑っていた目をゆっくりと開けば、目の前には石井零士の顔があった。
「オレはッ、全てを……」
口から大量の血を吐きながら、彼はゆっくりと僕にのしかかる。全体重を預けてくる石井零士を、僕は足に力を入れて抱きかかえた。
再び右腕に激痛が走る。
「……え」
自らの右腕が石井零士の胸を貫通している事に気が付いたのは、僕の膝が折れて地面につくのと同時だった。
肉が引きちぎれる音と共に、ずるりと腕が抜ける。僕の右腕は、石井零士の折れた骨に引っかかり縦に大きく引き裂かれていた。
裂かれた箇所から血が流れているのか、それとも石井零士の血なのか。赤く染まりすぎていて最早分からない。
ただ熱い。まるで腕が鼓動を繰り返すかのようで、焼け爛れる程の温度が襲う。
痛みとも違う熱に耐えながら、抱えていた石井零士の体躯を横たえた。つい先ほどまで怪物然としていたその身体は、いつの間にか僕の知る人間の物へと変化している。
幻覚を見ていたのか。いや、だとしても。
石井零士の手から落とされうつ伏せに倒れた親友まで幻覚だとは到底思えなかった。重い身体を引きずり、幸平の近くへと這いずる。
「……幸平」
名前を呼ぶことに、意味がないと分かっていた。
幸平は、その身体は、下腹部から下が消失している。
確かに横たわるその死に、それでも僕は声をかけることをやめられなかった。どうしてもできなかった。
「――カズ」
やめておけばよかったと後悔したのは、その掠れた声が耳に届いたからだ。
聞きたかった。聞きたかったが、そんな奇跡は望んでない。
「幸、平」
「あぁ……良かった……」
下半身が引き裂かれても、人は生きられてしまうのだろうか。いや、この燃え盛る炎にあぶられて出血が抑えられでもしたのだろうか。
良かったってなんだ。苦しそうな顔で、何を言ってるんだ。
今すぐ人を呼べば間に合うのだろうか。そんな――
「カズ……」
絞り出される声。散らばった思考が停止する。
僕の方に伸ばされていた手はもう動かない。
「――――」
幸平の口は、数文字の言葉をこぼれ落とした。そして、少しずつ僕を映しているのかも分からない瞳が、瞼が落ちる。
必死に這いよった。そして触れる。赤く染まった右手の温度のせいで、幸平を触る感覚が届かない。
この耳を劈く慟哭は、どこから聞こえるのだろうか。
鼓膜が破れる。喉が張り裂ける。胸を焼き切る。
身体の痛みはないはずだった。自分の身体を失ったように、
目の前にかざされたものがただの現実であることを。
どうして受け止められるのだろうか。
挽き潰れたその半身は、もう二度と言の葉を紡がない。
僕はその日、親友を喪った。
*
「前から訊いてみたかったことがあるんだ」
大きな事務机の上には大量の資料。その奥にある座り心地のよさそうな椅子に座り、霧谷雄吾は穏やかに問いかけた。
「……何でしょうか」
「君は何故UGNに協力してくれるのかな」
スケジュールが毎秒刻みの多忙な人物だという事に疑いはない。UGNの日本支部支部長ともなれば致し方のない事だろう。
だが、突拍子の無いその質問をする程度には余裕があるのか、と思ってしまう事に罪はないはずだ。
怪訝な表情を向けてやれば、彼は「はは」と人のよさそうな笑みを零す。
「私も決して興味本位で訊いている訳ではないんだ。君は今、私の依頼を受ける事で各地のFHセルに敵対視されている。こちらとしては君をエージェントとして日本支部に迎え入れ、保護したいところだが……」
「お断りします」
「だろうね」
穏やかな笑みは崩れない。
UGNエージェントへの加入は10年前から何度も断り続けている事柄だ。もう長年の付き合いとなる霧谷が今更確認するものでもないだろう。
霧谷は一度目を伏せるとその続きを口にした。
「君の過去からすれば、UGNを恨んでいてもおかしくはないはずだ。UGNチルドレン『石井零士』がジャーム化し暴走したことによって、君は親友を喪った。」
「……」
何も言わず、彼の言葉を待つ。
「組織内でそんな君を疑う声や、FHセルへの引き抜きを懸念する声が無いわけでもない。だから、君の真意を聞いておきたいと前から思っていた」
「随分明け透けに話をしますね」
「隠し事や陰口は、君にとって有効ではないだろう?」
そう言って彼は軽く肩を竦めた。
霧谷雄吾という男の周到さや理想主義ぶりには度々呆れる面もあるが、一番質が悪いのはそれが彼の美点であるという所だ。憎めないその立ち振る舞いは、残念ながら俺にとっては好ましい。
数枚の報告書を手の中で弄びながら、俺は言葉を返す。
「FHの活動に興味がないんですよ。俺は別にUGNが嫌いなんじゃない。オーヴァードが嫌いなんです」
「なら、オーヴァードを滅ぼそうとするFHセルがあったら加担するかもしれない訳だ」
「そんな自分たちを棚上げにしたセルに入りたいとも思いません。……俺はあくまで中立に立って、正しいと思った方についてるだけです。まぁ、今後貴方からの依頼が図抜けて気に入らなかったら裏切りますけど」
「君も言うね」
ジャームを肯定する立場の多いFHの連中がそんなコミュニティを作るとも思えない。
そもそも本当に霧谷雄吾自身が俺を疑っているのなら、常から2人きりで依頼受諾や報告を行う環境下になるわけがないのだ。
冗談としか思えない発言にこちらも冗談で返してやると、彼はくつくつと笑っていた。
「ああ、おかしなことを聞いてすまなかった。気を悪くしていなければ、今後ともよろしく」
「貴方のスケジュールに組み込んでもらえるだけの仕事はするつもりです。……今後とも御贔屓に」
報告書を彼の机の上に置き、一礼して部屋を出る。
俺が外に出ると、外に立っていた霧谷の護衛と思しき人間がこちらを一瞥してすぐさま視線を外した。
室内の話は聞こえていただろう。
霧谷雄吾という男の細やかさには頭が下がる。日本支部長ともあろう御方が一介のイリーガルに直接依頼を行う事に疑いを持った事もあったが、――このようなことが積み上がった結果、最近では霧谷本人に対する抵抗感は払拭しつつあった。
支部の廊下を歩き、ふと立ち止まる。
窓を雨粒が打っていた。
俺がFHに加担しうると判断されるのは当然だ。
FH側からすればUGNの情報を持っているイリーガルの引き抜きを狙わない手はない。実際に声をかけられる事は度々あるのだから、ある程度疑いは持たれてしかるべき。
だが、例え疑われても、誰にも理解されずとも関係ない。
許せないのは、UGNでも、ジャームでも、オーヴァードでもない。
生かされてしまった。
それは救いだった。いや、救いだと、思わなければならなかった。
喉の奥に堰溜まった薄暗い異物。
叫び出しそうな、絞り出すしかないそれを。取り除く術を俺は知っている。
けれど、もう二度と取り去る事は許されない。
俺が許さない。
『カズ』
どうして人を救えるアイツが死んで、何もできなかった俺が生きているのか。
『――助けて、くれ』
永遠に答えの出ない問いを、投げかけ続けている。
※とっちらかってる&書きたいことだけ書いてる
※文章力?ゴミ
*
永遠に答えの出ない問いを、投げかけ続けている。
胸に溜まった薄暗い異物を取り除く方法を探していた。
叫び出しそうな、絞り出すしかない“それ”を消す方法を。
机の上で美しく咲く花を見つめ、ひとつ溜息をつく事しかできない。
窓際、一番後ろの席に飾られた白い百合。
見慣れた光景だった。
遠巻きに注がれる奇異の眼を無視して、自身に割り当てられていたその席から、一輪の百合の花が生けられた花瓶を取り上げる。そして教室後ろに設置された合板作りの低い棚の上に乗せるのだ。
その後はただ席の椅子を引き、学生カバンから自身の教科書を机に投げ込む。
いつも通りの朝だ。ここ2カ月、このルーティーンが崩れたことはない。
いじめ、と呼べばそれまで。
だが単純にそう呼ぶには、彼らにはあまりにも害意がなかった。
毎朝飽きもせず花を供えるだけ。それ以上の事は起こらない。いや、起こせないのだろう。
僕に向けられる目線は、怯え、恐れ、そして僅かな好奇心。
花が示す彼らの意図はひとつ。
『学校に来るな』
それだけだ。
物心がつく頃には、父親が塀の中にいた。
母親は『父は必死に組織を抜けようとしていたんだ』と言っていたが、僕にとってはどうでもいい。
どんな綺麗事を並べ立てようと父親が犯罪者であるという事実は変わらず、僕と母親の生活を蝕んだ。
住んでいる場所を転々としたが、数年も経たぬ内にどこからか噂が流れ、周囲の人間はどうあっても僕と母親を忌避した。
ひっそりと生きていく事に慣れ、それを受け入れていてもなお断絶された。
小学校3年生の時、父親が犯した罪が殺人だった事を知った。
母親伝手ではない。その時近所に住んでいた女性が、遠巻きに、しかし大きな声で話していたのが耳に入ったのだ。
何故息子すら知らない事を、赤の他人で、それも僕らを避けている人間が知っているのか。
確かに僕が意識的に父親の罪状を知ることを避けていた節もあっただろう。
だが、それにしても滑稽だった。罪状に対して何の感情も抱くことはなかったが、そのお節介な隣人に対して思わず笑いが込み上げてきた事を覚えている。
その時からだ。喉の奥に薄暗い異物が住み着いたのは。
叫び出しそうな、決して飲み込めないこの違和感は、大きくなることも小さくなることもなく僕の胸と喉の間に居座った。
「怖い」
「恐い」
「今はおとなしいが、怒らせたらきっと殺される」
「いなくなってしまえばいいのに」
「どうしてここに住むんだ」
周りの人間がそう言って僕達を遠ざける事を、僕はちゃんと受け入れていた。
だって、そうしない保証なんてなかったから。
侮辱されたり、殴られたり、あまつさえ殺されかけた時に、相手を殺したいと思ったことは幾度となくあるのだ。
ただ、それをする事に意味を感じず、実行しなかっただけで。
目の前の人間は、自分という害を退けようとしているだけなのだ。
彼らには彼らなりに正義や理由があって、僕を殴っている。
僕はこの世界にとって害でしかない。
けれど、僕はできる限り無害でありたい。
ガラリ、と引き開けられる扉の音。
それまで僕に注がれていた視線が遠のいたと同時に、僕の思考もまた引き戻される。
「一義君!おはよう!!」
その場に人間の視線を一身に受けた人物が、大きな声で僕の名前を呼んだ。その挨拶を僕は当然のように無視する。
ぐんぐんと近づいてくる気配はすぐ真横までやってきた。そして、視界の端でニカリと笑いながら声をあげる。
「お!は!よ!う!」
「……おはようございます」
「なぁ~一義君。いい加減、敬語は取ってくれよ」
「……」
ぐ、と喉を絞る。薄暗い異物が口の中を満たしかけるが、辛うじて飲み込んだ。
彼は僕から反応を得られないと分かると、やれやれと言った様子で前の席の椅子を引く。
僕は鞄から一冊の本を引っ張り出し、挟んであったしおりを頼りにページを繰った。
前方から性懲りもなくかけられる声を延々と無視し続け、朝のホームルームが始まるチャイムが鳴った瞬間に本を閉じる。
眼前に映る少年は、茶色い短髪の生えた頭をポリポリと指でかくと
「なんでそう頑なかな……」
そう呟いた。
と同時に、教室の前方のドアが開く。担任が「おはよー。朝のホームルームはじめるぞー」と間延びした言い方で声をかければ、それまで立ち上がって雑談していた生徒は誰もがおとなしく席に着いた。
担任は前方の席から出席番号をとってゆく。
美月一義と名を呼ばれ、僕は淡々と返事を返す。
名前のような変わった苗字。父親の姓だ。
父親の無実を頑なに信じる母親は、離婚という選択肢を取る事も、姓を変えるという事もしなかった。
このおかげで僕達の素性が周囲にバレる事は数多く、最初は僕も母親の愚行だと思っていた。
けれど、きっと彼女は彼女なりの考えを持ってそれを貫いていたのだろう。
そもそも、僕を放り出すこともせず、義務教育を終えてもなお高等教育機関に通わせてくれている母親には感謝こそすれ、恨みなどあろうはずがない。
この姓が嫌であれば、僕はさっさと母親の元から離れ、就職なりなんなりすればよかったのだ。それを選ばなかったのは僕なのだから、文句を言う筋合いもない。
「ねぇレイジ……いい加減かかわるのやめなよ」
「なんで?」
「いや、なんでッて……」
担任がクラス名簿を読み上げている最中、前方の男子生徒と右斜め前の女子生徒の声が僕の耳に届く。
「一義君は何一つとして悪い事はしていないじゃないか。何もしていない人間を避ける方がおかしくないか?」
「いや……それはそうかもだけどさ」
「おーい、石井。石井零士。遅刻かー?」
「うわっひでえな先生!どう見てもクラス全員そろってんじゃん!!」
名を呼ばれおどける彼に向けて、クラスの数人がくすくすと笑う。
好意に満ちた笑みばかりだ。――そう。分かっている。彼は、石井零士という人物は、確かに善人なのだ。
僕は静かに目を閉じ、喉の奥までせり上がった感情を何とか飲み下す。異物、としか言いようないそれが何の感情を孕んでいるのか、僕には分からなかった。
だが、それが多くの感情を綯交ぜにした黒々としたものであることは確かだ。
そして、彼が近くに寄るたびにその異物は存在を主張し始める。あぁ、なんて煩わしい。近寄らないでほしい。放っておいてほしい。ただ、ただそれだけで良かったのに。
「あー。まぁ、皆も多分知ってると思うんだがな」
律儀に出席を取り終えた担任が、徐に咳ばらいをして切り出した。
その瞬間、それまで教室のいたるところで勃発していた小さな話声が一気に止む。
僕はといえば、一番後ろの席を良い事に先ほどまで開いていた本を再び開き、文字列を目で追う事に忙しい。
文庫カバーがいちいち取れかかるのが煩わしかった。エラリー・クイーンをはじめとした海外の推理小説を読むことは好きだが、あらぬ噂を立てられないためにはブックカバーは必須である。
「今日からクラスに仲間が増えるからな。転校生だ。仲良くするんだぞ」
「うちのクラス、他のクラスより人数1人少ないからクラス対抗戦不利だったもんなー」と続けながら、担任が黒板にチョークを打ち付ける音。
だが、担任が続きの言葉を紡ぐより先に、教室の扉が開く音がした。
「あ、やっべ。タイミングミスった」
そう声が聞こえるや否や、バン!と教室の扉が乱暴に閉められる。
思わず顔をあげるが、そこに『転校生』らしき影はなかった。どうやら先走って扉を開けた癖に入らずに閉めたようだ。
一瞬唖然とした雰囲気に包まれた教室が、誰かが吹き出した事を皮切りに笑い声で包まれる。
「あー……。佐々木。入ってきて良いぞ」
苦笑ともつかない表情の担任が扉に向かって手招きすると、彼はそろりと扉を開け、愛想笑いを浮かべて入ってくる。
短い茶髪に快活とした表情が似合う少年。のように見える。
僕はそれだけを確認して再び本に目を落とした。
「うわー……初手からミスっちまったんでクソはずいんすけど、えっと、佐々木です」
「いや、下の名前」
「あッ、コーヘーです!幸せな平面で幸平!」
「幸せな平面ってなんだよ!!」
前方の人間からヤジが飛ぶ。笑いに包まれる教室。まるでその場の全員が陽だまりに浸かったようだった。
恥ずかしそうに頭をかきながら苦く笑う少年は、そんな笑顔を一身に受けている。
あぁ、きっと彼も『良い人』なんだろう。
少なくとも、他者を笑顔にできる人間だ。僕とは違う。
本に目を落としながらそう思う。そこに感情は特にない。
「んじゃ、佐々木は一番後ろの席な」
「マジすか!?俺目ェめっちゃいいんですよ!」
「だから何なんだよ」
呆れ気味の担任が言葉を返す。脈絡のないそのやり取りがツボに入った人間も多いようだ。
先程まで俺に視線を送っていた人間が変化したわけではない。人間の変わりようは不思議なものだと感嘆さえ漏れる。
転校生の少年は、担任に指定された席に着く。教室の一番後ろ。窓際から数えて二番目。つまりは僕の隣だ。
「あ、よ、よろしくな?」
席に着くと同時に、何故か疑問符の付いた挨拶。
僕が本から顔を上げれば目がしっかと合ってしまった。逸らすタイミングを見失い思わず硬直した途端、目の前に手を差し伸べられる。
「俺、コーヘー。おま、き、あー、なた様は?」
おまえ、きみ、あなた、と探して着地したのが『あなた様』とは、随分言葉選びが下手らしい。
眼前の少し抜けた様子の少年にかけられた問い。僕がそれに答えたのは、ほとんど反射のようなものだった。
「……美月」
瞬間、教室内の空気が凍り付いた。
奇異の視線。だけではない。不信感、驚き、それから、不安だろうか。
あぁ、失敗したのか、僕は。いや、挨拶をされて返す事の何が悪い。僕は何も悪い事をしていない、はずだ。
けれど、自信はなかった。周囲が何を考えてこの空気を作り出しているのか僕には分からない。
胸と喉にあの不安な塊が押し寄せるばかりで息が詰まる。
「へー。ミツキ。良い名前だな!」
差し伸べられた手を引っ込めることなく、彼は僕にそう言って笑いかける。
が、僕にその笑顔を見る余裕などなかった。
――僕は、この手を取るべきなのだろうか。
分からない。分からない。
視線は何を考えているのか。名前を名乗っただけでこの空気になる程だ。手を取ったら、どうなる。
僕は
僕は無害でありたい。それだけだ。どうすればそういられる。
掻き混ぜられる思考がショートするその寸前、不意に横から彼の手を掴むものがあった。
「コーヘーっていうんだね!よろしく!オレは石井零士!」
「え?」
僕の前に座る石井零士が、転校生の手を取って握手をしたのだ。
――助かった。のだろうか。少なくとも僕が彼から視線を逸らす理由はできた。
転校生は突然割って入った石井零士に気を取られたようで、困惑しつつも愛想笑いを浮かべ直している。
「仲良くしろよぉ。じゃ、一時間目の準備をしてください」
そう担任が締めくくると同時に、僕は英語の教材を机から引っ張り出し席を立った。
「あ、ちょい」
転校生は何かを言いたげだったが、聞こえないふりをする。
僕が彼の背後を何も言わず通り過ぎると共に、転校生の周囲にはあっという間に人だかりが出来上がった。
「ねぇねえ!どっから来たの?」
「部活何入るとかあんの?」
「え?あ、えっと、……どっから?トーキョー?」
「東京!都会っ子じゃん!」
「てかウチの学校、3年の修学旅行先東京だよ?里帰りじゃん」
「えっ、マジ!?うわー、沖縄とか行きたかったわ」
――あぁ、良かった。
背後から聞こえてくるそんな言葉を、声を聞いて、僕は安堵する。
転校生に対する対応を僕は少し間違えたかもしれない。けれど、変わらなかった。
ちゃんと、僕は無害でいられた。
僕とさえ関わらなければ、転校生の彼は、これから先きっと明るい高校生活を送る事ができるだろう。
決してこの学校は陰湿な訳ではない。
誰しも他人の机の上に花を置くなんて遠巻きな嫌がらせを好んでやりたい訳がないのだ。
彼らは僕が怖いだけ。僕さえいなければ平穏な生活を送れると信じているだけで。
ごめん。僕は無害でいるから。何も、何もないから。だから、せめて存在する事は許してほしい。
教室を出る僕の背後からは転校生を歓迎する声が絶えず湧く。
明るい光を遮るように、僕はゆっくりと後ろ手に扉を閉めた。
*
朝。
僕はいつも、ホームルーム開始のチャイムが鳴る数分前に教室に入るようにしている。
他の人間に紛れ、できるだけ教室に居座らないようにするためだ。
教室に入ればいつも通り机の上には花瓶があって、数人が怯えた目で僕を見る。
怯えた目をしている人間が恐らくその日の«当番»なのだろう事は、このクラスになって数日で分かった。
そんな顔をするくらいだったら、やらなければいいのに。
僕にこんな安い精神攻撃が効かない事くらい、2ヶ月も経っているのだから分かってほしいものだ。
いちいち避けるのも面倒くさいが、直接暴力を振るわれる“いじめ”よりなら数百倍マシというものである。
僕の直後に、石井零士はやってくる。いつも僕に何かと話しかけてくる、席が近いだけの男。
彼は明るく語り掛けてくるが、僕は無視をする。
それがいつもの日常。
何も変わらない。けれどある意味では【平穏】な日々。
「すいません!!!遅刻しました!!!」
ホームルームが始まった30秒後に飛び込んでくるのは、転校生だ。
担任が軽い口頭注意で済ませ、周囲からは小さな笑いや「またかよ!」という野次が飛ぶ。
恥ずかしそうに頭をかきながら座る転校生。
ここ最近ではお決まりの光景だ。
隣人となった転校生は度々僕に話しかけてこようとしてきたが、無視にならない程度に避け続けた。
クラスの人間とほぼ数日で打ち解けた様で、彼は自然とクラスの輪に入っている。ように思える。
実際の所どうであるかは分からない。知る由がないのだ。
僕はホームルームと授業、それから掃除以外の時間は、ほとんど人目の付かない屋上で過ごしている。
だから彼がクラスメイトとどう過ごしているか、僕は知らない。
けれどそれでいい。
陽だまりの中にいる人間を、僕のせいで日陰に追いやることになったらと思うとぞっとする。
ただ、今は僕に与えられた【平穏】を享受するべきだ。いない者として扱ってくれるならそれで。
僕のその願いが通じたのかは分からない。
だが、確かに僕は【平穏】を享受し続ける事ができたのだ。
*
それは唐突にやってきた。
いつも通り屋上で、家で握ってきたご飯をほおばる。すっかり固くなった米を咀嚼しながら、その日はアガサ・クリスティを読んでいた。
アガサ・クリスティと言えば灰色の脳細胞を持つ名探偵が代名詞かもしれないが、僕は彼女の書く安楽椅子探偵が好きだった。
推理小説ではほとんど必ずと言っていいほど人が亡くなる。そして登場人物は誰しもがその死と向き合うのだ。そこにはどうしても、死に対する『やりきれなさ』が存在する。
その『やりきれなさ』。あるいは『痛ましさ』は、僕の喉の奥にある異物とたまに混ざり合う。そしてその異物が『推理小説による痛ましさ』なのだと考えると、幾分か心が楽になった。
屋上に僅かに存在する日陰に身を寄せ、静かに食事を摂る。
「あ、やっと見つけた」
そんな【平穏】を壊す声に、僕は思わず身を固くした。
本から顔を上げず、平静を装って文字列を追い続ける。さっぱり頭に入ってこないままページを繰る。
そんな動作を続ける僕の元に、声の主はやってきた。
「えっと……。美月……」
「……」
「あれ?美月は覚えてんだけどな?」
壁に背中を預けて座る僕の前に、彼がしゃがみ込んでくる。
少しでも視線を上げれば彼の顔は目に入るだろうが、極力それは避けたかった。
「……関わらない方が良いよ」
「え」
僕が本に目を落としたまま口を開けば、相手は素っ頓狂な声を上げる。
1カ月前にやってきた転校生の声は、もはや聞き慣れたものだ。
「僕の事、聞いてない訳ないだろ。……関わると、貴方まで避けられる」
「避けられる?なんで」
そこで僕は顔を上げた。正面にしゃがむ彼は陽だまりの中でじっと僕を見つめている。
思わず息を飲みこむが、彼の瞳に捉えられた僕の視線はもう外せない。
「何でって……。僕は……」
「俺さ、美月君を探してたんだ」
「……?」
誰かの目を見て話すなどいつぶりの事なのだろう。いや、目を見て話すどころか会話すらままならないのが僕の常だ。近頃は母親とすら話をしていない。
久しぶりの会話に戸惑うばかりで、僕は「探してた……?」と彼の言葉を繰り返す事しかできなかった。
「前から話してみたかったんだよな。隣の席なのに全然話した事ねえじゃん?な、推理小説好きなんだろ?」
「えっ」
何故それを。と続けそうになって、必死に飲み込んだ。
本には常にブックカバーをつけているはずだ。僕が読んでいる本が推理小説だとバレないように。
今ここで声を出せば、僕が推理小説を、『殺人』に関わる本を読んでいる事がバレる。
そうすれば、どうなるのだろうか。怯えるのだろうか。他の皆と同じように。
それは、僕の本意ではない。
ぐ、と自分が本を持つ手に力がこもった。彼はそれを見止めたのか、苦笑を浮かべて僕に笑いかけてくる。
「あー、いや、その。……盗み見たのは悪かったよ。俺、昔っから目が良くて。けどこの前美月君がエラリー・クイーン読んでたの見えて、うわ、読んでる人いるんだと思ってうれしくなってさ」
まるで言い訳のように捲し立てられたその内容を、一拍置きで把握する。
そして、納得した。
あぁ、彼はきっと僕の事を知らないのだ、と。
知らなければ、恐怖もすまい。
僕は彼の言葉には何も返さず、日陰の中立ち上がる。
「佐々木君。僕の事、本当に何も聞いてない?」
「? どうしたんだよ、さっきから」
「なら、知っておいた方が良い。……僕の父親は殺人犯だ」
日向の彼は首を傾げる。
「だから?」
「……だからって」
「いや、何かクラスの奴らも言ってたんだけどさ。え?だから何?」
視線を落とした。しゃがんだまま僕を見上げる彼は、眉をひそめている。
まるで心底意味が分からないとでもいう様に。
咄嗟に歩き出そうとした僕の腕を、彼の手が掴んだ。
「ちょ、おい!そんな逃げなくたっていいだろ!?」
「でも」
「いやいや、俺、別に美月君の親父の話しに来たんじゃなくて、趣味の話しに来たんだって」
「趣味って……」
「え?推理小説好きって訳じゃねえの?」
「いや……好き、ではあるけど」
「やっぱり!そうか!よかった!なぁ、エラリー・クイーン好きなのか!?俺『悲劇4部作』好きでさ!」
呆気にとられた僕の腕をあっさりと離し、彼はエラリー・クイーンだけではなく、コナン・ドイルが、東野圭吾の名作がと目を輝かせて話を始めてしまった。
完全にその場を去るタイミングを計り損ねた僕は、あぁ、とか、うん、とか、へどもどな返事しか返す事ができず、視線を宙に彷徨わせる。
「……って、悪い。……迷惑だったか?」
だが、熱を持って僕に語り掛けていた転校生は、僕の反応を見てすぐに口を閉ざした。
1人で長々と語る趣味は流石にないらしい。彼は恐らく本当に推理小説を語れる人間を探していただけなのだろう。
それがたまたま運悪く僕しか見つける事ができなかった。それだけの話なのだ。
「僕は迷惑じゃないけど。……でも、僕の方が佐々木君に迷惑かけかねないから」
「いやいや、俺がそっちと話したくて探してたんだから、迷惑な訳ないだろ」
「でも、僕と話してたら、クラスの皆に冷たくされるかもしれない」
「はぁ……?マジで意味わかんねーな。じゃぁ、そん時は美月君が俺の相手してくれよ」
そう言って転校生は膝を伸ばし立ち上がる。昼間の日光を浴びた彼は、口元を吊り上げて僕に笑顔を見せた。
「な、美月君が好きな推理小説とかないのかよ」
「え、……」
「あぁ。ほら、何か俺よりずっと小説読んでそうだったし、おすすめとかあればさ!」
屈託のない笑顔だった。
先の反応を見る限り、僕の事をクラスの人間から聞いていない訳ではないのだ。
ただ彼は、僕の父親という存在をを完全に僕から切り離していた。それだけの話で。
今まで、僕に好奇心で近づいてきた人間は少なからずいた。
僕に優しくすることで、自身の優しさを誇示しようとする者もいた。
けれど、それらが見ていたのはあくまでも『殺人犯の父親を持つ美月一義』だ。
「……僕は、『容疑者Xの献身』が好き……かな」
「うっわ、分かる!!やっぱお前分かる奴だった!!」
興奮気味に人差し指で僕を指し、直後「やべ、うっかりお前とか言っちまった」と慌てふためく。
やはり彼は言葉を選ぶことが苦手なのだろう。けれど、それを悪し様に思う事はない。
口から言葉が滑り出した今でも、まだ半信半疑だった。本当に、僕個人に対して好奇心を向ける人間が存在する事があり得るのか。
だがこの場で、この瞬間に答えが出る事はないだろう。
例え裏切られたとしても。目の前で笑う彼がやはり『殺人犯の父親を持つ人間』に興味があっただけだとしても。
それでもかまわないと思えた。
あの不気味な異物が、少しだけ薄まる。この感覚を、もう少し留めていたかった。
そうして僕と彼が共に行動するようになって1ヶ月後。
珍しく彼が僕より先に席について、その日は確か『アヒルと鴨のコインロッカー』を読んでいた。珍しいな、と思ったのを覚えている。
僕の机の上に、花瓶はなかった。
遠巻きに僕を見る視線の中、先に座っていた佐々木幸平が、僕を見て笑ったのだ。
「よ、おはよ」
小さく挨拶を返し、席に座る。
足元が少しだけ砂利ついた。
その日以降、僕の机の上に花瓶が置かれる事は無くなった。
*
転校生――佐々木幸平と趣味を語り合う仲になった。
お互いを苗字に君付けで呼び合うのは流石によそよそしすぎる、ということで、僕は彼を『幸平』と呼び、幸平は僕の事を『カズ』と呼ぶようになっている。
何故僕だけ略されるのかと言えば、「僕の下の名前を呼び間違えたら流石に申し訳ないから」だとか何とか。
致命的に人の名前を覚えることが苦手な幸平は、僕の名前を最初『美月』だと思って珍しい名前として憶えていたらしい。その後ちゃんと自己紹介をしたところ、下の名前がなかなか覚えられず、結果『カズ』呼びが定着した。
今となっては流石にフルネームを覚えてもらっているが、当初は『カズヨシ』『カズヒコ』『カズオ』と呼びたい放題だったのだ。本人には一切の悪気がない点が、僕としては面白かった。
ここ最近でわかったのは、佐々木幸平という男はよく喋り、よく動くという事。
感情表現の豊かな彼の言動や行動は、今まで対話をした人間の中でもずば抜けて分かりやすかった。
僕は自分が他人の機微に疎い事を自覚しているが、それを加味してもなおこの男の考えている事は面白いほどに筒抜けだ。楽しければよく笑うし、気に入らないことがあればすぐに言葉にする。
「自分といて本当に楽しいのか」「気を使っているのではないか」と罪悪感じみたものを僕が抱えた事もあったが、幸平は僕との時間が嫌になったらきっと勝手に離れていくだろう。彼がこうして僕といるのは、あくまでも彼の意志なのだ。
幸平といて楽なのは、そう僕自身が思える事でもあった。
決定的だったのは、僕の机に花瓶が置かれなくなって半年が経った頃。
帰りのホームルーム前に行われる清掃時の事だ。
その週、僕達は男子トイレが担当だった。
掃除場所の担当は、席の近い者を6人で括って割り振られる。席の近い者ということはつまり、幸平と、そして石井零士もいるという事だ。
毎日毎日話しかけてくる石井零士があまりにも煩わしく、僕が学校裏までのゴミ捨てを買って出るのが常だった。
「なあ、どうして君は彼とそんなに仲良くなれたんだ?」
「あ?」
それもあと2日の我慢、と考えながら戻ってきた水曜日。トイレの中から聞こえてきた声に僕ははたと足を止めた。
「彼?」
「一義君だよ。オレはキミが来る前から、よく彼に話しかけてあげてるんだが……。何故か全く相手にしてくれなくて」
その問いに答えとなる声は無かった。
女子トイレの方聞こえてくる楽しげな話声にまぎれて聞き逃してしまったのだろうかと、僕は少し足を踏み出す。が、
「……石井ってさ、カズの事どう思ってんの?」
ああ、機嫌を損ねたな。
耳に届いた低い声に覚えがあるわけではない。普段自分の機嫌を取るのが上手い幸平が僕に怒った事は1度もなかった。
だが、彼ほど感情をストレートに投げる人間もそういない。聴覚でしか状況は探れないが、それはあまりにも分かりやすい空気の変化だった。
「どう、とは?」
「お前、よくカズに話しかけてるじゃん。そんとき、アイツはどんな奴だと思って話しかけてんだ?」
「どんな奴……。彼は大変な思いをしてる人だと思ってる。だから少しでも力になれたらと。彼が悪い事をした訳じゃないから……」
「へぇ。そういうくせに、あの花瓶は放置してたんだな」
幸平の声が鋭さを増した。その剣呑さにあてられてか、石井零士の声が上ずる。
「それは……和義君がクラスに打ち解けてくれたら、自然となくなると思ったんだ。彼がみんなに理解されればきっと」
「……そうかよ」
カラン、と木が固いものに打ちつけられる音。
続けて聞こえてきたのは、静かな怒号だ。
「俺さ、お前のこと嫌いだわ」
「え……」
「お前が最初にクラスの奴らにカズの家の事情バラしたんだろ?『話しかけて“あげてる”』だ?アイツがハブられる理由作ったくせに、どの面下げてそんな偉そうなこと言えんだよ」
「バラした、って……。だって、彼が悪いことをした訳じゃ無いじゃないか!父親がどうとかは、彼が虐げられる理由にならない!それをみんなにも分かってほしくて……」
不意に、喉の奥に違和感が溜まった。
ああ、まただ。最近はあまり出会わなかったのに。
薄暗い異物。胸と喉の奥から音になって出てきそうになるのを押し止め、僕は学生服の裾を握る。
『一義君が悪い事をした訳じゃないんだ!皆にもそれを分かって欲しい!』
高校1年生のクラス委員長決めの日。クラス委員長に就任した石井零士が言い放った言葉。
一体どこでその話を知ったのかとか、そんな事は最早どうでも良かった。少しでも先延ばししたかったのは確かだが、どうせいつかはバレる話だ。忌避される事に慣れきってしまった僕にとっては些細な問題で。
ただ、それでも石井零士は確かに僕の心を蝕んだ。
彼は善意から、良かれと思って僕の事をクラスにバラしたのだ。彼にとっての正義感。呆れるほどに性善説を信じ、彼はクラスの人間へ訴えた。
石井零士という人間は恐らく善人だ。誰がどう見ても。そんな彼を僕は嫌いになりたくない。なってはいけない。
だから、無視をしていた。じっと、喉の奥の違和感に耐えながら。
「それをアイツが望んだのかよ」
「それは……でも、彼を虐げるのは間違ってるだろ?それを理解してもらわないと、いつまでも彼は変われないじゃないか!」
「るっせえな!!」
響き渡った大声に、周囲が水を打ったように静まり返った。。
女子トイレから恐る恐る顔を覗かせた女子が、立ち尽くす僕の姿を見て慌てて引っ込んでいく。興味本位で近付いてくる人間に僕が視線を送れば、彼らもまたそそくさとその場を離れていった。
幸平の低い声は続く。
「お前が言う事も一理はあるぜ。カズが悪い事をした訳じゃねえ。親父のせいでアイツが縮こまって生きるのは違うと俺も思う。けど、その話が先行したらアイツに対する偏見悪化するってなんで考えねえんだよ?俺でも分かるわ。お前がクラスにそれを訴えた結果何が残ったんだ?」
「だから……オレが話しかけて……」
石井零士はぼそぼそと歯切れ悪く反論する。
「『あげてる』か?気色悪ィ。誰がンな事頼んだんだよ。カズの態度見てりゃ分かんだろ?
自己満足のヒーローごっこにアイツを付き合わせんな!!」
吐き捨てた声が、こちらへと向かってくる。
今顔を合わせる事に気まずさもあるが、僕の足は動かない。
とうとうバチリと視線がぶつかって、僕たちの間に沈黙が訪れた。
「……掃除、終わった」
ただしそれはほんの一瞬で、幸平はそんな片言を残し足早に僕の隣を通り過ぎていく。
徐々に喧騒を取り戻し始めたこの場にとどまる意味などない。僕もまた踵を返してそれを追う。
大股でずかずかと進む幸平に、事情を知らない学校の人間は何事かと首を傾げて道を開けていた。
やがてたどり着いたのは、立ち入り禁止の貼り紙がされた屋上だ。
扉を開け放った幸平は、そこから数歩立ち入ってから頭を掻きむしってしゃがみ込んだ。
「あーーーー、ムカつく!!!」
頭上の空は透き通った水色をしていたが、フェンスの奥は赤く染まり上がっている夕方。西日に当てられて長く伸びた幸平の影が、僕の足元に落ちる。
僕が後ろ手に扉を閉めてもなお、幸平はしばらく不満げに喉から絞り出すような息を吐いていた。
「なんで、我慢できんだよお前」
「……」
その声はつっかえ、揺れている。叫び出しそうな声を必死に取り繕う様に、低い声で彼は呻いた。
「全部聞いてたんだろ」
呆然と立ち尽くす僕を振り返る。だが、幸平の背後から当てられた西日のおかげで、彼の顔が上手く見えない。
「まぁ……」
「……嫌じゃねえのかよ。周りの奴らにあんな態度取られてさ。花瓶の件とか、石井の野郎のやり方とか……色々!」
吐き出した言葉に脈絡はなかった。選ぶ余裕が無いほどに感情を高ぶらせて、幸平は声を揺らがせる。
彼が僕のために怒ってくれていると分からない程鈍くはない。
そして、幸平の問いかけに「嫌じゃない」と心から答えられるほど僕は善人ではなかった。
けれど
「駄目なんだ」
「……何がだよ」
喉の奥に声が堰溜まる。もういつから感じていたのか分からない、薄暗い違和感だ。
「僕は……皆にとって無害でありたい。だから、ダメなんだ。嫌だって思ったら」
「……」
「皆は僕を怖がるけど、それは当たり前だ。僕自身ですら今後一生父さんと同じことをしないとは言い切れない。だから、距離を置くのは当然だと思う」
無害でありたい。無害でなければいけない。
叫び出しそうな苦みをかみつぶして、僕はずっとそう思うようにしてきた。
仕方がないんだと。何もかもが僕にはどうしようもないのだと。
クラスの人間の事も理解して、石井零士の行動も理解して、そしてそれを飲み込まなければならないと、ずっと思っていた。
「僕が周りに生きることを許してもらうためには、無害でなければいけないんだ。だから、僕はそうする。それが許されるように」
掌が焼き付くほどに握り込む。
嫌だと、ムカつくと、声をあげられる幸平がうらやましかった。
僕が一度でもそんな姿を誰かに見せたらどうなるか。そんな事は想像に難くない。
「……クソみたいだな」
「……」
ゆっくりと幸平は立ち上がった。膝に手をついて、そして大きく息を吐く。
「カズが生きる事に許すも許さねえもねえだろ」
膝から手を離し、日差しを背に僕をじっと見つめた。
冷たく澄んだ風が僕の頬を撫ぜる。
影になって顔なんて見えない。だが顔を背ける事はできなかった。幸平は確かに僕の目を覗いている。
「なぁ。お前が何をしたってんだよ?」
「何もしてない。けど」
「俺は!」
自分の想像以上に声を張ったのか、幸平は驚いたように肩を震わせトーンを落とした。
「……少なくとも俺は、お前に幸せになってほしいと思うし、お前に笑って生きてくれって思う」
「それも駄目なんだ」
「ダメじゃねえ!!」
影のようだった幸平が、徐々に僕に近づく。
その黒い瞳が、僕を捉えた。
「お前が諦めてんじゃねえよ!嫌だって思う事は悪い事じゃねえんだ。嫌なことがあったら、拒否っても怒ってもいいんだ!」
駄目なんだと、口から出かかった。胸の異物がその言葉をわざと押し出そうとする。
しかし、それを幸平は許さない。
「いいか!これからお前は俺と一緒に色んな楽しい事沢山やって、嫌いなモン忘れるくらい好きなモンつくんだよ!!ダメじゃねえって、今俺が決めたんだ!分かったか!!」
まくしたてるように。矢継ぎ早に。幸平は僕をにらみつけて叫んでいる。顔も目線も逸らす事はできない。
返す言葉は思いつかなかった。本来であれば否定しなければならない言葉も、何故か今はすんなりと自分の中に落ちてくる。
ここで上っ面の返事を返す事だって簡単だ。
「……うん」
――けれど、それをする必要なんてない。
「よし!」
掴みかからんばかりの勢いが、僕の返事で少しだけ収まった。
が、それでもまだ落ち着かないのか頭をガシガシとかいて唸る。
「あーッ、むしゃくしゃする!!とりあえず!今日はめちゃくちゃ美味いモン食って帰るぞ!!」
「……」
拒否する事も、怒る事も、嫌う事も。楽しい事も、好きなものを作る事も、親友がいる今も。
全て『自分がやってはいけない事』だと思っていた。
けれど、目の前で自分の代わりに怒り、全てを許してくれる人間がいる。
怖かった。
あり得ない事だと疑うべきだ。いずれ裏切られるんじゃないかと警戒するべきだ。
けれど、僕のそんな警戒や疑いは飛び越えられてしまった。
「僕、から揚げ食べたい」
「っしゃぁ!!じゃあ岩谷商店いこーぜ!」
これから先、僕はコイツに裏切られたらきっと二度と立ち直れない。自覚ができるその域までコイツは踏み込んだのだ。
それでもいいと思うなんて、どうかしている。
心を許す事はこんなに怖いのか。
怖いけれど、――コイツならいいや。
あの薄暗い違和感は、胸の奥へと解けていた。
*
「石井が帰ってこない?」
ほっとけンなモン、と幸平はそっぽを向きゲーム画面に目を落とす。
が、同室の男子生徒は焦ったように僕らに訴えた。
「そういう訳にもいかねえよ!先生にバレたら俺らだけ明日の自由行動無しだぞ!?」
「あー、それはだりぃ」
「だろ?頼むよ、2人も探すの手伝ってくれ!」
高校3年生にあがってから、僕は幸平の人望に助けられてある程度クラスに受け入れられるようになっていた。
僕に怯える人間がいない訳ではなかったが、あからさまな嫌がらせも格段に減ったのだ。
そのおかげと言えばいいのか、3年の修学旅行も特に仲間外れにされることなく、クラスメイトの班の中に入ることができている。
1つだけ懸念点があるとすれば石井零士も同班だったことだが、彼はあの一件以来僕に対して必要以上に話しかけてくることが無くなった。
「くっそめんどくせえなー、あの野郎迷惑しかかけてきやがらねえ……」
「まぁ、明日遊ぶ下調べがてらって事でいいんじゃないかな」
「お前があっけらかんとしてんの、俺マジで腑に落ちねえんだけど」
都内で闇雲に探すわけにもいかないが、幸い旅行前に班メンバー共通で入れた携帯端末アプリによって、僕たちは過去30分以内に立ち寄った場所がお互いに把握できる。
石井零士はどうやら僕達が泊るホテルの近くをうろついているという事は分かっていたので、2人と3人に別れて捜索する形となった。
「ったく……何してんだ?」
「何だろうね。1時間くらい前から、ずっとここを円状に回ってる」
「とうとう頭でもバグったかアイツ……」
呆れた表情を浮かべながらも、幸平は迷うことなく道を進んでゆく。
その後ろをついて歩くが、都会らしい都会に出てきた事がほぼない僕の目には全てが珍しく映るのだ。きょろきょろと辺りを見渡しては、幸平に「気になんのか?」と問われ立ち止まる。
いつの間にか夜の都内見物と化した僕らの捜索は、別に回っていた3人と合流を果たして強制終了を余儀なくされた。
「あ、コーヘーにカズヨシ!あいつ、いたか?」
「いや、こっちは会ってないぜ。アプリだとこの道順通ってるはずだから、どっかですれ違ってんのかねー……って、うぉ!?」
端末をいじる幸平が、突然声をあげて顎を引いた。
「どうしたんだ?」
幸平はそう問いかける僕に一度目配せをして、自身の端末を耳に当てる。
着信か。そう合点がいくと同時に、胸にチクリと針が刺さるような感覚があった。
「よぉ、石井か?お前何してんだよ?今班の皆でお前の事……」
そこまで口にして、ふと幸平の顔が曇る。幸平は僕たちの顔を一瞥すると、すぐに耳から端末を離した。
全員の前に突き出した彼の端末から聞こえてくるのは、恐らく石井零士の声だ。
「正義を執行しなければならない。正義を執行しなければならない。苦しい思いをしている人間は、オレが救う。オレが救う。救うために、必要なんだ。必要な事なんだ」
スピーカー設定のなされた電話口から流れてくるのは、そんな言葉。
異常。いや、どちらかといえば狂気の方が近い。
端末からは石井零士の声がまるで巻き返した動画のように垂れ流されている。
「先生たちに知らせよう。コイツ、何か変なことに巻き込まれ――」
幸平が顔をあげ僕を見やる。だが、彼がその言葉を最後まで言い切る事はなかった。
徐々に大きく見開かれる目。僕が疑問に思う間もなく、幸平が僕の方へと手を伸ばし
「――カズ!!」
突き飛ばした。
瞬間、轟音が劈く。
吹き飛ばされ、肩から地面に激突した感覚。
僕の視界は何を映す事も無くただ暗転した。
激痛が身を襲い、口から意図せず嗚咽が漏れる。
どれほどの時間気を失っていたのだろう。一瞬だったのかもしれないし、長い時間が過ぎたのかもしれない。
が、辛うじて死んではいない。こうして思考できている事がその証拠だ。
耳に届くのは、悲鳴。それから火が弾ける音に、遠くからのサイレン。
何が、起こったのだろうか。
痛みに耐えながらゆっくりと身を起こせば、焼き切るような頭痛が襲った。右手をあてようと動かして、そこで初めて自らの身体の異常を知る。
破れた服の下からは皮膚が擦り切れて赤黒い肉がのぞいていた。ぼたりと垂れた血液を呆然と見つめ続ければ、徐々に痛みが身を裂いてゆく。どろりと赤い液体が右目に被る。目の上を切ったのかと左腕で拭った。
判然としない僕の視界に映るのは、瓦礫と炎。覚束ない炎から黒い煙が立ち込める。
辺りに落ちている布を纏った肉片が何なのか、それを理解するための処理を僕の脳は拒否していた。
先の一瞬でこの光景が生まれたのか、それとも僕が気を失っている間に作り出されたのか。どちらにせよ、これが現実なのだと激しい頭痛が僕に突き付ける。
霞む意識を奮い立たせ、僕は何とか両膝に力を入れて立ち上がった。
「コウ……」
名前を呼ぼうとして、声がかすれた。火の粉交じりの煙を吸って思わずむせ返る。
どこに向かえばいい。どこに向かえば、アイツはいる。
さっき幸平が僕を突き飛ばしたのは何故なのか、何がこの光景を作り出したのか。何も分からない。分からないが、動かなければならない。
「――ミツキ、カズヨシ」
「!」
不意の声。反射的に振り返って体が軋む。思わず悲鳴が漏れ出そうになりながらも、歯を食いしばって押しとどめた。
「……石井?」
背後から僕の名を呼んだのは、確かに見慣れた顔だった。
つい先ほどまで僕らが探していた人物。石井零士が煙の中から顔を出す。
僕は胸をなでおろした。こんな状況、生きている人間の顔を見て安堵しない人間などいないはずだ。
今まで何をしていたんだ。一体何が起こったんだ。お前は大丈夫なのか。
そう混乱した頭の中で作り上げた疑問は、終ぞ僕の口から問われる事はない。
「……おい」
全身の痛みが止んだ。
煙の中から現れたのは確かに石井零士の顔だ。ただし、その身体は最早人間の姿を保っていない。
狼のような爪が生えた腕に、羆を思わせる体躯。その異常な体は燃え盛る炎をものともせず、そこに立ち尽くしている。
そしてその怪物は、確かに右手に人間を携えていた。
「カズヨシ、くん。オレは、救いたい。オレが、オレが皆を」
一歩後ずさり、瓦礫に足を取られてしりもちをつく。
ざり、と石井零士の顔をした怪物が僕へと歩みを進めた。ゆっくりと、ただし確実に近づいてくるそれを、僕は凝視する事しかできない。
死ぬ、のだろうか。
受け入れがたいはずのその事実は、ただ僕の身体を強張らせるだけだ。恐怖なのかももう自分では判断が付かない。
ただ心臓が何度も跳ね上がり鼓動を繰り返している。
「……石井」
口から転がり落ちたのは、震える自分自身の声だった。
あぁ、なんて情けない声なんだろうと、その場にそぐわない感想が脳裏を過る。その拍子に、僕の意識は怪物の持つ人間へと逸れた。
大きく心臓が脈打つ音が、自分の耳と、そして痛みが続く頭を殴る。
「――幸平」
大きな爪の生えた手に捕まれて引きずられた人間を、見間違えるはずがない。
力が完全に抜けた身体は、――その半身が、引きちぎられて
光景が焼き付いた瞬間、身体が弾けるように前に出た。
助けようとしたのか、それとも怪物に殴りかかろうとしたのか、最早分からない。ただ痛みも何もかもを忘れて、石井零士へととびかかる。
ガツ、と言う音と共に、視界が明滅した。
「がッ……!」
どう吹き飛ばされたのかも分からないまま、背中が叩きつけられる。
衝撃に脳が揺さぶられ、喉の奥から熱いものが湧き上がった。ぬるりとした熱い血液を口から吐き出す。腕をついて身を起こした。内臓が掻き混ぜられる。脳が焼き切れそうなほどの痛みに、意識を手放しそうだ。
明確に横たわる死の怖気。それが僕の身体から発される最後の警告なのだろう。逃げなければ、きっと死ぬ。
しかし、僕の足は地面を蹴った。
殴りかかっても、何も意味はない。助け出そうとしても、僕が死ぬだけ。そんな分かり切った事を前に、ただ僕は右手を振り上げる。
胸がざわついた。こんな感情が自分にあるなどとは知らなかった。
これは、ただ一方的に奪われたことに対する明確な怒りだ。
今まで感じた事が無い訳じゃない。けれど、表にしてはいけないと塞いでいた感情。
何故なのだろうか。何故、突然奪われなければならないのだろうか。
これ以上声をあげれば喉は張り裂ける。それを止める事はできなかった。焼き付くような絶叫をあげ、僕は怪物へと殴りかかる。
その右手が、不意に赤く染まった。全身の血が、いや、場にある僕の血が、形を変えて怪物へと向けられる。
それは、僕が拳を振り下ろすと同時に爆散した。幾重にも折り重なる血液の刃のように、血が怪物に襲い掛かる。
腕が引き裂かれる痛み。耳鳴りがする。心臓の鼓動がうるさい。
いつの間にか瞑っていた目をゆっくりと開けば、目の前には石井零士の顔があった。
「オレはッ、全てを……」
口から大量の血を吐きながら、彼はゆっくりと僕にのしかかる。全体重を預けてくる石井零士を、僕は足に力を入れて抱きかかえた。
再び右腕に激痛が走る。
「……え」
自らの右腕が石井零士の胸を貫通している事に気が付いたのは、僕の膝が折れて地面につくのと同時だった。
肉が引きちぎれる音と共に、ずるりと腕が抜ける。僕の右腕は、石井零士の折れた骨に引っかかり縦に大きく引き裂かれていた。
裂かれた箇所から血が流れているのか、それとも石井零士の血なのか。赤く染まりすぎていて最早分からない。
ただ熱い。まるで腕が鼓動を繰り返すかのようで、焼け爛れる程の温度が襲う。
痛みとも違う熱に耐えながら、抱えていた石井零士の体躯を横たえた。つい先ほどまで怪物然としていたその身体は、いつの間にか僕の知る人間の物へと変化している。
幻覚を見ていたのか。いや、だとしても。
石井零士の手から落とされうつ伏せに倒れた親友まで幻覚だとは到底思えなかった。重い身体を引きずり、幸平の近くへと這いずる。
「……幸平」
名前を呼ぶことに、意味がないと分かっていた。
幸平は、その身体は、下腹部から下が消失している。
確かに横たわるその死に、それでも僕は声をかけることをやめられなかった。どうしてもできなかった。
「――カズ」
やめておけばよかったと後悔したのは、その掠れた声が耳に届いたからだ。
聞きたかった。聞きたかったが、そんな奇跡は望んでない。
「幸、平」
「あぁ……良かった……」
下半身が引き裂かれても、人は生きられてしまうのだろうか。いや、この燃え盛る炎にあぶられて出血が抑えられでもしたのだろうか。
良かったってなんだ。苦しそうな顔で、何を言ってるんだ。
今すぐ人を呼べば間に合うのだろうか。そんな――
「カズ……」
絞り出される声。散らばった思考が停止する。
僕の方に伸ばされていた手はもう動かない。
「――――」
幸平の口は、数文字の言葉をこぼれ落とした。そして、少しずつ僕を映しているのかも分からない瞳が、瞼が落ちる。
必死に這いよった。そして触れる。赤く染まった右手の温度のせいで、幸平を触る感覚が届かない。
この耳を劈く慟哭は、どこから聞こえるのだろうか。
鼓膜が破れる。喉が張り裂ける。胸を焼き切る。
身体の痛みはないはずだった。自分の身体を失ったように、
目の前にかざされたものがただの現実であることを。
どうして受け止められるのだろうか。
挽き潰れたその半身は、もう二度と言の葉を紡がない。
僕はその日、親友を喪った。
*
「前から訊いてみたかったことがあるんだ」
大きな事務机の上には大量の資料。その奥にある座り心地のよさそうな椅子に座り、霧谷雄吾は穏やかに問いかけた。
「……何でしょうか」
「君は何故UGNに協力してくれるのかな」
スケジュールが毎秒刻みの多忙な人物だという事に疑いはない。UGNの日本支部支部長ともなれば致し方のない事だろう。
だが、突拍子の無いその質問をする程度には余裕があるのか、と思ってしまう事に罪はないはずだ。
怪訝な表情を向けてやれば、彼は「はは」と人のよさそうな笑みを零す。
「私も決して興味本位で訊いている訳ではないんだ。君は今、私の依頼を受ける事で各地のFHセルに敵対視されている。こちらとしては君をエージェントとして日本支部に迎え入れ、保護したいところだが……」
「お断りします」
「だろうね」
穏やかな笑みは崩れない。
UGNエージェントへの加入は10年前から何度も断り続けている事柄だ。もう長年の付き合いとなる霧谷が今更確認するものでもないだろう。
霧谷は一度目を伏せるとその続きを口にした。
「君の過去からすれば、UGNを恨んでいてもおかしくはないはずだ。UGNチルドレン『石井零士』がジャーム化し暴走したことによって、君は親友を喪った。」
「……」
何も言わず、彼の言葉を待つ。
「組織内でそんな君を疑う声や、FHセルへの引き抜きを懸念する声が無いわけでもない。だから、君の真意を聞いておきたいと前から思っていた」
「随分明け透けに話をしますね」
「隠し事や陰口は、君にとって有効ではないだろう?」
そう言って彼は軽く肩を竦めた。
霧谷雄吾という男の周到さや理想主義ぶりには度々呆れる面もあるが、一番質が悪いのはそれが彼の美点であるという所だ。憎めないその立ち振る舞いは、残念ながら俺にとっては好ましい。
数枚の報告書を手の中で弄びながら、俺は言葉を返す。
「FHの活動に興味がないんですよ。俺は別にUGNが嫌いなんじゃない。オーヴァードが嫌いなんです」
「なら、オーヴァードを滅ぼそうとするFHセルがあったら加担するかもしれない訳だ」
「そんな自分たちを棚上げにしたセルに入りたいとも思いません。……俺はあくまで中立に立って、正しいと思った方についてるだけです。まぁ、今後貴方からの依頼が図抜けて気に入らなかったら裏切りますけど」
「君も言うね」
ジャームを肯定する立場の多いFHの連中がそんなコミュニティを作るとも思えない。
そもそも本当に霧谷雄吾自身が俺を疑っているのなら、常から2人きりで依頼受諾や報告を行う環境下になるわけがないのだ。
冗談としか思えない発言にこちらも冗談で返してやると、彼はくつくつと笑っていた。
「ああ、おかしなことを聞いてすまなかった。気を悪くしていなければ、今後ともよろしく」
「貴方のスケジュールに組み込んでもらえるだけの仕事はするつもりです。……今後とも御贔屓に」
報告書を彼の机の上に置き、一礼して部屋を出る。
俺が外に出ると、外に立っていた霧谷の護衛と思しき人間がこちらを一瞥してすぐさま視線を外した。
室内の話は聞こえていただろう。
霧谷雄吾という男の細やかさには頭が下がる。日本支部長ともあろう御方が一介のイリーガルに直接依頼を行う事に疑いを持った事もあったが、――このようなことが積み上がった結果、最近では霧谷本人に対する抵抗感は払拭しつつあった。
支部の廊下を歩き、ふと立ち止まる。
窓を雨粒が打っていた。
俺がFHに加担しうると判断されるのは当然だ。
FH側からすればUGNの情報を持っているイリーガルの引き抜きを狙わない手はない。実際に声をかけられる事は度々あるのだから、ある程度疑いは持たれてしかるべき。
だが、例え疑われても、誰にも理解されずとも関係ない。
許せないのは、UGNでも、ジャームでも、オーヴァードでもない。
生かされてしまった。
それは救いだった。いや、救いだと、思わなければならなかった。
喉の奥に堰溜まった薄暗い異物。
叫び出しそうな、絞り出すしかないそれを。取り除く術を俺は知っている。
けれど、もう二度と取り去る事は許されない。
俺が許さない。
『カズ』
どうして人を救えるアイツが死んで、何もできなかった俺が生きているのか。
『――助けて、くれ』
永遠に答えの出ない問いを、投げかけ続けている。
ふせったーは日本語のほかに、韓国語、英語、中国語(繁体)、フランス語に対応。画面右上のテンテンテン「︙」をポチッとしてね
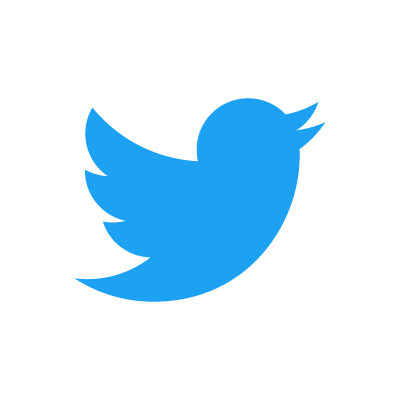 元ツイート
元ツイート