ノクチルシナリオイベント「天塵」の内容についての感想
初出:2020年7月9日Privatterに投稿
1.雛菜の「好き」について
ネット配信番組の側の口パクをしてくれという要求に答えなかった浅倉透のことを雛菜は「雛菜、透先輩好きだな」と言う。雛菜は以前から透のことを「好き」と言っていたた。雛菜のふわふわした印象から軽い感じがしてしまうと思うのだが、この場面からこの言葉の軽くなさがここから感じられる。誰にでも「好き」と言うわけではないのだと思う。
口パクをしてくれという要求に答えなければ、番組は大変なことになる。番組だけでなく、透自身、ユニット自身にも影響が出るし、事務所だって他のアイドルだって影響がないとは言えない。それだけのことをしているのだが、その上で「透先輩好きだな」と言っていて、この言葉は軽いものではない。
雛菜は透以外にもプロデューサーに対しても「好き」と言っていて、雛菜が言う「好き」が軽い言葉でないならば、プロデューサーに対する「好き」も軽いものではないのだということがうかがえる。WINGのシナリオの中でも「好きかも」で始まり、優勝後に初めて「好きだよ」と言ってくれるわけで、この違いが重要だと思う。「好きかも」は色んなひとに言うかもしれないけれども、「好き(だ)」と断定的に言う相手はよく選んでいるのではないか。
2.テレビの論理(あるいは業界の論理)について
ノクチル4人の歌が番組配信に使えないと判断したディレクターは、口パクを要求する。それはプロデューサー側との事前の申し合わせと異なるものだった。
テレビってこうだよねという話で、それはテレビの裏側だけのものではなく普通に放映されているバラエティ番組からも感じる。特に日テレ(私の主観です)。番組の企画などで、お笑い芸人やバラエティ慣れしたタレント以外の、ドラマ専門の俳優とかスポーツ選手とか素人がゲストが来たとき、司会者がスタジオの中にいる芸人を無理やりに絡ませて芸人にやけど(あるいは痛い思い)を負わせて笑いを取るみたいな場面がよくある。
私はこれをすごく変だなと感じていて、それはゲストの俳優とかスポーツ選手とか素人単体ではテレビ的に面白くならないと暗に宣言しているようなもので、それはゲストに対して礼を欠くことなのではないかという気がするからだ。ここにはテレビの「面白くさせなければいけない」「テレビ慣れしていないゲストだけでは番組を面白くできるはずがない」というテレビを作る側の不安が現れているように感じる。
それで思い出したのだが、何年か前に有吉がやっている番組(「有吉反省会」)にアクション俳優のドニー・イェンのファンである飯星景子が出たとき、有吉を始めとしてスタジオの中の芸人やタレントがドニー・イェンの名前をわざと間違えて笑いを取るということがあった。
これはドニー・イェンなんて誰も知らないし、誰も興味ない、という前提の下でしか起こらないことだと思う。ドニー・イェンのことなんて視聴者は知らないし、興味もない、だから真面目にドニー・イェンの話をして面白くなるはずがない。それで変に名前をいじって面白くしよう、というわけである。明らかにゲストとドニー・イェンのファンに対して礼を欠く行為であるし、何よりドニー・イェン本人に対してあまりにもひどい。
何がテレビ番組的に面白いのか、何を視聴者は面白いと思うのか、このポイントが完全にテレビ番組側の論理で決まっているような気がしてくる。われわれ視聴者は長いことテレビを見ることに慣らされてしまっているため、こうしたテレビの論理を当たり前のように受け止めてきてしまったのではないか。
「ストーリー・ストーリー」では、テレビ番組側と視聴者との間で、いわば共犯関係のようなものが出来上がっていた。テレビ番組側が面白くするために手を加えたものについて、まさに視聴者はそれを面白がって受け取っていた。「天塵」では、ノクチルの4人がテレビ番組側の要求をのまなかったことで、テレビ番組側の論理が視聴者に対してあからさまな形で明らかになるのだが、それでも視聴者はテレビ番組の側に付く点は興味深い。
樋口円香が見ていたSNSの書き込みにはこうある、「干されてるらしい」「自業自得でしょ、アイドルなめんな」と。これらは業界内の話を第三者である視聴者たちが推察して書いていることだ。これはファンの人たち自身の目線による感想ではない。彼らが放送された番組をどう感じたかという感想ではない。彼らが話しているのは、業界内部の話である。これらが意味するのは、アイドルならばテレビの論理に従わなければならないし、それに反旗を翻せば仕事がなくなって当然である、という業界の論理を視聴者もまた当然視しているということだ。
テレビの論理は、おそらくは視聴者が何に興味を持っていて何を面白いと思うのかということを先取り的に想定して番組を作っていくものだが、しかしその当の視聴者自身がその「テレビの論理」はテレビの業界内の論理だということをよく知っているのである。ならば「視聴者」とはいったい何なのか、「視聴者」はどこにいるのか。
3.「売り物」について
ここで置き去りになっているものがもう一つ(もう一人)ある。それはアイドル自身だ。
あのネット配信番組への出演が決まった後で、樋口円香はプロデューサーの意図を問いただす。そもそも円香は、透たちがプロデューサーに騙されているのではないか、と疑ってアイドルを始めた人間であり、その疑いはまだ晴れていない。プロデューサーは、番組に出ることについて「大事な経験になる」と言い、視聴者の反応を「謙虚に受け止めてほしい」と言う。だが円香は、「好きに言ってくれますね。矢面に立つ、売り物はこっちなのに」と釘を刺すのである。「何かあったら許しませんので」。
そして起こった事態が、口パクの要求であった(さらに言えば透のみの優遇対応であった)。口パクの要求(テレビの論理)に従わなかったのは彼女たち自身(主に透の意志)であるが、そもそもは番組側が事前の打ち合わせにない要求を直前になって突然ふっかけてきた、という問題がある。ここにはアイドル自身の意志は顧みられていない。
このことについて、別の番組のディレクターはこう言っている、「最近の子は、いっぱしに業界のことも知っている」「『見せる』技術も『見られる』覚悟も持ってたりする」「売り物としての安全性をお約束いただかないと」と。業界の中では、テレビの論理や業界の論理は前提となっている。そしてアイドルはそれらの論理に合意して、業界の中に、テレビの中に入ってくる、ということになっている(されている)。アイドルは「見せる」技術と「見られる」覚悟が要求されるのである。
これは「ストーリー・ストーリー」におけるように、テレビの論理によって手が加えられたとしても、視聴者に「見られる」ことを覚悟しておかなければならない、ということだろう。「自分のこと人に見てもらいたいんでしょう? われわれは君のことを人に見せてあげるよ。でもそのためにはわれわれの側の論理に従ってもらわないと。業界はそういうところだって知ってて入って来たんでしょう? 覚悟は当然あるよね?」
そして円香が言ったのと同じ「売り物」という言い方をこのディレクターはする。「売り物としての安全性」はテレビ番組を破壊しない、迷惑をかけないということ(さらに言えばテレビの視聴率や売り上げに貢献するということ)を保証しろ
と言うことだ。重要なのは、このディレクターはプロデューサーに向かって言っているのである。だからプロデューサーは、「『売り物』だとすれば、俺のディレクション能力の問題だ」とつぶやく。これは野菜を出荷する農家が、消費者に対して安全に食べられるということを保証する責任がある、ということだ。
樋口円香は自身のことを「売り物」と言っており、このディレクターと同じ観点に立っていると言える。けれど、アイドルは野菜ではない。売買されるような「売り物」ではなく、人間である。プロデューサーはこのことを分かっている。「彼女たちは彼女たちなんだけどな」と「売り物」という見方に反対する考えを持っているのだ。
「ストーリー・ストーリー」では、テレビの論理によって物語が作られてしまうということを前提として認め、テレビ制作者の側に勝手に作られるのではなく、自分たちで物語を作ることを選ぶことで問題を打開した。すでに多くの人に指摘されているように、「物語を作る」というテレビの論理そのものを打開できてはいないのである(これに対する答えが霧子の「私たちが私たちなら」だった)。
ノクチルの「天塵」は言ってみれば、その先を行っている。テレビの論理そのものを拒否するのである。テレビの論理は、プロデューサーとディレクター、そして視聴者たちの間の共犯関係で作られている。アイドルはプロデューサーのプロデュースと、テレビの論理(あるいは業界の論理)に従って、仕事をする。これがアイドルをするということだと業界の人も、視聴者さえも、そう思っている。けれど、そこにアイドルの意志はほとんどない。
テレビや業界の論理が先立っていて、視聴者はそれと共犯関係を結んでいる。そこにアイドルの意志は介在しない。テレビや業界の論理が先立っているかぎり、そこには「売り物」ではない人間としてのアイドルそのものと、そうした人間そのものを見ようとする視聴者は存在しないのである。
これが、「天塵」のラストシーンに繋がってくる。花火会場のステージでライブをするという仕事なのだが、ほとんどの人は花火の方を見ていてノクチルのライブには興味がない。視聴者もアイドルも存在していないという構造がここに端的に表れている。そしてノクチルの4人は海に飛び込み、花火を見に来た客に向かってこう言うのだ、「こっち見ろ」と。プロデューサーは、あのネット配信番組で口パクの要求に答えなかった4人に輝きを見た。それは「売り物」なんかではない輝きであって、それと同じ輝きを海の中に飛び込んで「こっち見ろ」という4人に感じている。それは「彼女たちは彼女たち」という輝きであって、霧子が言った「私たちが私たちなら」ということと通底しているように思う。それは物語によって脚色されたキャラクターのような存在ではなく、ただ生きている存在、ただ存在している存在の輝きだ。それはわざと面白おかしくしたり、物語を作ったりすることで簡単に見えなくなってしまう。
透はアイドルをするにあたっての目標などについて「楽しいんだ、最近、こうしてるの」「それしかないや、私、理由とか」と言っている。ここには誰もが感動する目標とか、誰もが納得する理由みたいなものはない。物語も理由も欠如している。ただ今が楽しい。それだけである。ただ、それだけだ。(テレビ制作者側が想定する)視聴者にとっての分かりやすさや面白おかしさが重要なテレビの論理とはかなり相性が悪い。けれど、宇宙が存在しているということに目的や意味や理由を見いだすのが困難であるように、ただ存在しているということには、物語もなければ特に理由もないのである。そしてそれで良いのである。
*Privatterの投稿は削除済み
1.雛菜の「好き」について
ネット配信番組の側の口パクをしてくれという要求に答えなかった浅倉透のことを雛菜は「雛菜、透先輩好きだな」と言う。雛菜は以前から透のことを「好き」と言っていたた。雛菜のふわふわした印象から軽い感じがしてしまうと思うのだが、この場面からこの言葉の軽くなさがここから感じられる。誰にでも「好き」と言うわけではないのだと思う。
口パクをしてくれという要求に答えなければ、番組は大変なことになる。番組だけでなく、透自身、ユニット自身にも影響が出るし、事務所だって他のアイドルだって影響がないとは言えない。それだけのことをしているのだが、その上で「透先輩好きだな」と言っていて、この言葉は軽いものではない。
雛菜は透以外にもプロデューサーに対しても「好き」と言っていて、雛菜が言う「好き」が軽い言葉でないならば、プロデューサーに対する「好き」も軽いものではないのだということがうかがえる。WINGのシナリオの中でも「好きかも」で始まり、優勝後に初めて「好きだよ」と言ってくれるわけで、この違いが重要だと思う。「好きかも」は色んなひとに言うかもしれないけれども、「好き(だ)」と断定的に言う相手はよく選んでいるのではないか。
2.テレビの論理(あるいは業界の論理)について
ノクチル4人の歌が番組配信に使えないと判断したディレクターは、口パクを要求する。それはプロデューサー側との事前の申し合わせと異なるものだった。
テレビってこうだよねという話で、それはテレビの裏側だけのものではなく普通に放映されているバラエティ番組からも感じる。特に日テレ(私の主観です)。番組の企画などで、お笑い芸人やバラエティ慣れしたタレント以外の、ドラマ専門の俳優とかスポーツ選手とか素人がゲストが来たとき、司会者がスタジオの中にいる芸人を無理やりに絡ませて芸人にやけど(あるいは痛い思い)を負わせて笑いを取るみたいな場面がよくある。
私はこれをすごく変だなと感じていて、それはゲストの俳優とかスポーツ選手とか素人単体ではテレビ的に面白くならないと暗に宣言しているようなもので、それはゲストに対して礼を欠くことなのではないかという気がするからだ。ここにはテレビの「面白くさせなければいけない」「テレビ慣れしていないゲストだけでは番組を面白くできるはずがない」というテレビを作る側の不安が現れているように感じる。
それで思い出したのだが、何年か前に有吉がやっている番組(「有吉反省会」)にアクション俳優のドニー・イェンのファンである飯星景子が出たとき、有吉を始めとしてスタジオの中の芸人やタレントがドニー・イェンの名前をわざと間違えて笑いを取るということがあった。
これはドニー・イェンなんて誰も知らないし、誰も興味ない、という前提の下でしか起こらないことだと思う。ドニー・イェンのことなんて視聴者は知らないし、興味もない、だから真面目にドニー・イェンの話をして面白くなるはずがない。それで変に名前をいじって面白くしよう、というわけである。明らかにゲストとドニー・イェンのファンに対して礼を欠く行為であるし、何よりドニー・イェン本人に対してあまりにもひどい。
何がテレビ番組的に面白いのか、何を視聴者は面白いと思うのか、このポイントが完全にテレビ番組側の論理で決まっているような気がしてくる。われわれ視聴者は長いことテレビを見ることに慣らされてしまっているため、こうしたテレビの論理を当たり前のように受け止めてきてしまったのではないか。
「ストーリー・ストーリー」では、テレビ番組側と視聴者との間で、いわば共犯関係のようなものが出来上がっていた。テレビ番組側が面白くするために手を加えたものについて、まさに視聴者はそれを面白がって受け取っていた。「天塵」では、ノクチルの4人がテレビ番組側の要求をのまなかったことで、テレビ番組側の論理が視聴者に対してあからさまな形で明らかになるのだが、それでも視聴者はテレビ番組の側に付く点は興味深い。
樋口円香が見ていたSNSの書き込みにはこうある、「干されてるらしい」「自業自得でしょ、アイドルなめんな」と。これらは業界内の話を第三者である視聴者たちが推察して書いていることだ。これはファンの人たち自身の目線による感想ではない。彼らが放送された番組をどう感じたかという感想ではない。彼らが話しているのは、業界内部の話である。これらが意味するのは、アイドルならばテレビの論理に従わなければならないし、それに反旗を翻せば仕事がなくなって当然である、という業界の論理を視聴者もまた当然視しているということだ。
テレビの論理は、おそらくは視聴者が何に興味を持っていて何を面白いと思うのかということを先取り的に想定して番組を作っていくものだが、しかしその当の視聴者自身がその「テレビの論理」はテレビの業界内の論理だということをよく知っているのである。ならば「視聴者」とはいったい何なのか、「視聴者」はどこにいるのか。
3.「売り物」について
ここで置き去りになっているものがもう一つ(もう一人)ある。それはアイドル自身だ。
あのネット配信番組への出演が決まった後で、樋口円香はプロデューサーの意図を問いただす。そもそも円香は、透たちがプロデューサーに騙されているのではないか、と疑ってアイドルを始めた人間であり、その疑いはまだ晴れていない。プロデューサーは、番組に出ることについて「大事な経験になる」と言い、視聴者の反応を「謙虚に受け止めてほしい」と言う。だが円香は、「好きに言ってくれますね。矢面に立つ、売り物はこっちなのに」と釘を刺すのである。「何かあったら許しませんので」。
そして起こった事態が、口パクの要求であった(さらに言えば透のみの優遇対応であった)。口パクの要求(テレビの論理)に従わなかったのは彼女たち自身(主に透の意志)であるが、そもそもは番組側が事前の打ち合わせにない要求を直前になって突然ふっかけてきた、という問題がある。ここにはアイドル自身の意志は顧みられていない。
このことについて、別の番組のディレクターはこう言っている、「最近の子は、いっぱしに業界のことも知っている」「『見せる』技術も『見られる』覚悟も持ってたりする」「売り物としての安全性をお約束いただかないと」と。業界の中では、テレビの論理や業界の論理は前提となっている。そしてアイドルはそれらの論理に合意して、業界の中に、テレビの中に入ってくる、ということになっている(されている)。アイドルは「見せる」技術と「見られる」覚悟が要求されるのである。
これは「ストーリー・ストーリー」におけるように、テレビの論理によって手が加えられたとしても、視聴者に「見られる」ことを覚悟しておかなければならない、ということだろう。「自分のこと人に見てもらいたいんでしょう? われわれは君のことを人に見せてあげるよ。でもそのためにはわれわれの側の論理に従ってもらわないと。業界はそういうところだって知ってて入って来たんでしょう? 覚悟は当然あるよね?」
そして円香が言ったのと同じ「売り物」という言い方をこのディレクターはする。「売り物としての安全性」はテレビ番組を破壊しない、迷惑をかけないということ(さらに言えばテレビの視聴率や売り上げに貢献するということ)を保証しろ
と言うことだ。重要なのは、このディレクターはプロデューサーに向かって言っているのである。だからプロデューサーは、「『売り物』だとすれば、俺のディレクション能力の問題だ」とつぶやく。これは野菜を出荷する農家が、消費者に対して安全に食べられるということを保証する責任がある、ということだ。
樋口円香は自身のことを「売り物」と言っており、このディレクターと同じ観点に立っていると言える。けれど、アイドルは野菜ではない。売買されるような「売り物」ではなく、人間である。プロデューサーはこのことを分かっている。「彼女たちは彼女たちなんだけどな」と「売り物」という見方に反対する考えを持っているのだ。
「ストーリー・ストーリー」では、テレビの論理によって物語が作られてしまうということを前提として認め、テレビ制作者の側に勝手に作られるのではなく、自分たちで物語を作ることを選ぶことで問題を打開した。すでに多くの人に指摘されているように、「物語を作る」というテレビの論理そのものを打開できてはいないのである(これに対する答えが霧子の「私たちが私たちなら」だった)。
ノクチルの「天塵」は言ってみれば、その先を行っている。テレビの論理そのものを拒否するのである。テレビの論理は、プロデューサーとディレクター、そして視聴者たちの間の共犯関係で作られている。アイドルはプロデューサーのプロデュースと、テレビの論理(あるいは業界の論理)に従って、仕事をする。これがアイドルをするということだと業界の人も、視聴者さえも、そう思っている。けれど、そこにアイドルの意志はほとんどない。
テレビや業界の論理が先立っていて、視聴者はそれと共犯関係を結んでいる。そこにアイドルの意志は介在しない。テレビや業界の論理が先立っているかぎり、そこには「売り物」ではない人間としてのアイドルそのものと、そうした人間そのものを見ようとする視聴者は存在しないのである。
これが、「天塵」のラストシーンに繋がってくる。花火会場のステージでライブをするという仕事なのだが、ほとんどの人は花火の方を見ていてノクチルのライブには興味がない。視聴者もアイドルも存在していないという構造がここに端的に表れている。そしてノクチルの4人は海に飛び込み、花火を見に来た客に向かってこう言うのだ、「こっち見ろ」と。プロデューサーは、あのネット配信番組で口パクの要求に答えなかった4人に輝きを見た。それは「売り物」なんかではない輝きであって、それと同じ輝きを海の中に飛び込んで「こっち見ろ」という4人に感じている。それは「彼女たちは彼女たち」という輝きであって、霧子が言った「私たちが私たちなら」ということと通底しているように思う。それは物語によって脚色されたキャラクターのような存在ではなく、ただ生きている存在、ただ存在している存在の輝きだ。それはわざと面白おかしくしたり、物語を作ったりすることで簡単に見えなくなってしまう。
透はアイドルをするにあたっての目標などについて「楽しいんだ、最近、こうしてるの」「それしかないや、私、理由とか」と言っている。ここには誰もが感動する目標とか、誰もが納得する理由みたいなものはない。物語も理由も欠如している。ただ今が楽しい。それだけである。ただ、それだけだ。(テレビ制作者側が想定する)視聴者にとっての分かりやすさや面白おかしさが重要なテレビの論理とはかなり相性が悪い。けれど、宇宙が存在しているということに目的や意味や理由を見いだすのが困難であるように、ただ存在しているということには、物語もなければ特に理由もないのである。そしてそれで良いのである。
*Privatterの投稿は削除済み
追記を使えば最大100000文字まで書けちゃう!
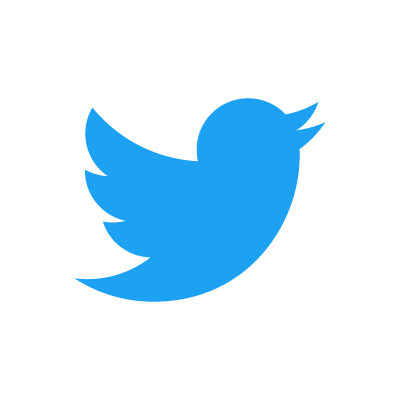 元ツイート
元ツイート