閃光星 flare star ※つるみか ★R18シーンがあります★
第六話 龍神湖 -手入れ-
★設定は捏造。
★適当な審神者名が出ます。
同人誌にする予定のつるみか話 バックアップ兼サンプル べったーではとりあえずここまで
第六話 龍神湖 -手入れ-
★設定は捏造。
★適当な審神者名が出ます。
同人誌にする予定のつるみか話 バックアップ兼サンプル べったーではとりあえずここまで
一
その本丸は、京都、巨椋(おぐら)池とその周辺を模していた。
巨椋池は干拓により埋め立てられ、現在では影も形も無い。
ここは秋津の本丸より数倍広い。池の真ん中、浮島に社があってそこが本丸だ。
湖畔に浮かぶのは蓮の花。池の名前は『龍神(りゅうじん)湖』。
「見事な……」
三日月は感嘆した。
「凄いな、これは」
三日月の隣で鶴丸も喜んでいる。
三日月と鶴丸はある刀剣に誘われ、ここを訪れた。
転送され、まず見たのは蓮の花。湖面。その後、広い橋と開いた門があって、門の前に人影がある。近づくまでもなく、二振を呼んだ刀剣だと分かる。特徴的な白い姿、容姿は鶴丸と酷似しているが、鎧が違う。鶴丸国永の極めた姿だった。
「良く来たな。案内する」
三日月も鶴丸の極は初めて見る。彼が三日月達をここに呼んだ。
三日月は頷いた。鶴丸が疑問を投げかける。
「――その格好は?」
「これか。こっちが俺の本当の姿なんだ。訳あってな。呼びつけて済まない。立ち話も何だから、歩こう。しばらくかかるが景色を楽しんでくれ」
鶴丸極はさっさと歩き出す。三日月と鶴丸は後に続いた。
時の政府から戻った後、三日月は本丸への通行手形を持ち、鶴丸、山姥切と相談した。
過去の出来事は通常、一方通行。三日月の本丸が無くなった事実は、いくら調査しても、改変を試みない限り変わらない。歯車の歯が少し欠けただけで、全く意図しない結果になったり、歯車がはずれ転がっていく事もある。三日月の本丸は、今は歴史に収まった歯車だが、万が一、干渉してしまったら、取り返しの付かない事になる。
具体的には仲間の魂の行き場がなくなったり、三日月自身に何かが起こり、本丸に閉じ込められたり、存在が歪んだりする可能性がある。
そうならない為に慎重を期すべきだが、その一方、過去は既に終わった事だから、画像を再生する、あるいは本を読むように、いつ出かけても、何度見ても変わらない。
理論上、過去がすり切れる事もあるらしいが、あるとしても何億、那由多と跳んだ後の事で――先に跳ぶ方の心が枯れる。
山姥切は、A三十七の事を気にしていた。山姥切は彼と顔見知りで、さほど親しくは無いが、山姥切が年長、つまり先輩にあたるという。
この話になったのは、三日月が『長義は疲れていたようだ』と語ったからだが、それまで三日月は二振が知り合いだとは知らなかった。
山姥切は長義が顕現して間もない頃、数回、技術指南をした、と語った上で、『先日、主の引退と俺が刀解される事を話したから、事後処理で忙しいのかも知れない』と呟いた。
鶴丸が『そいつは、きみが刀解された事を気に病んでるんじゃ無いか?』と言ったが、三日月も同感だった。長義は非常に優しい刀剣だ。いずれ山姥切の生存に気付くかもしれな
い。長義は三日月の担当だから『三日月の都合を優先するように』と命令を受けているはずだ。
そんな会話をしていたら、加州が離れにやってきた。山姥切がさっと顔を隠した。
『主が話があるって』
そこで聞いたのが、この龍神湖本丸からの依頼だった。
送り主は審神者『霞(かすみ)』と連名で鶴丸国永。
鶴丸は自分が、以前街の鯛焼き屋で鶴丸の前に並んでいた刀剣だと明かして、是非、三日月と鶴丸の力を借りたいと言ってきた。火急の用件だと言うので、こうして先に訪れた。
……自分の問題から逃げている自覚はある。が、本丸が無くなり五ヶ月になる。今更一つ遅くなったところで変わらないし、未だ手がかりも少ない。今行ったところで悲劇が再生されるだけ。それを受け止める覚悟は今の自分にはない――ならばこちらを済まそうと、三日月はのんびり構えていた。
百メートルほどの橋を渡り終えて、敷地に足を踏み入れる。踏み入れた時、三日月は、おや、と思った。
「分かるか?」
「ああ」
三日月は頷いた。
鶴丸が分からない、という顔をしていたので、三日月は説明した。
「少し、空気が薄い。これはやはり……審神者の問題だな」
鶴丸極が頷いた。
「ああ。主は奥で待ってるから入ろう。広くて悪いな」
玄関も広かった。中で待っていたのは宗三左文字だった。彼が丁寧に履き物を預かる。
「宗三か? 他は?」
鶴丸極は少し驚いたようだ。
「皆、稽古場に居ますよ。他は庭で休んでいます」
「ああ」
鶴丸極が苦笑した。
「お茶は要りますか」
「いや、乱に頼んである」
「そうですか」
鶴丸極に続いて本丸の廊下を歩く。主の居室へ向かっているのだろうが、何部屋も通過した。ある場所を越えたところで、構造が変わった。今までは廊下、居室、という日本家屋に良くある造りだったが、この辺りは丸い柱が並んで、その間に龍の刺繍が入った蒼い布が垂れて居る。――神社にはこのような造りが見られる。
一つ回廊を通って、しばらくして、中央に着いた。
鶴丸が呼びかける。
「主、御仁方をつれて来た。入るぞ」
呼びかけは適当だった。三十畳ほどの板敷きの間の、一番奥に、部屋の端から端まで届く大御簾が巻いてあって、上下とも白い袿を纏った一人の女性が座っている。束髪に面布という審神者に良くある格好だ。
鶴丸極が進み出て、少し逸れて、床に膝をつく。座布団が二枚用意されていて、三日月は正面、鶴丸が横に腰を降ろした。
審神者が頭を下げた。
「三日月宗近様。鶴丸国永様。ようこそ、龍神湖の本丸へ。わたくしは審神者、霞と申します。此度はわたくしの我が儘を聞いて下さり、誠に感謝いたします。本来なら上座をお譲りするべきでしょうが、この御簾より出られないため、失礼いたします」
御簾には結界が張られていて、完全に分かれている。
「まあ気にするな。三日月宗近だ。こちらは近侍の鶴丸国永。早速だが、用件を伺おう」
「はい。鶴丸。説明を」
審神者が言って、鶴丸極が頷いた。
「分かった。鶴丸国永だ。ややこしいから『国永』とでも呼んでくれ。まずこの本丸についてだが。ここは少々特殊でな。時の政府が刀剣男士の開発中に見つけた、ある神『龍神』を奉る為の本丸だ。政府は付喪神以外の神々の力を借りようとして、ひとつ失敗した。それを帰そうと願ったところ、また失敗した上、ある条件を付けられた。案外普通、と言っては何だが、信仰――自らを奉り、神楽を捧げる事。だからこの本丸では皆が舞を嗜んでいる。俺も一応できる」
「ほう、舞か」
「ああ。年に数回なんだが――」
そこで「失礼致します」と声がして、部屋の左手、間口から極ではない乱藤四郎が入ってきた。手には盆を持っている。しずしずと、美しい所作で茶を並べる。
「おぬしは、あの時の乱か?」
三日月は尋ねた。極であったと思うが――今は特の姿だ。
乱は少し戸惑ったが、鶴丸が街へ行った時の事を話すと、乱が頷いた。
「あ……はい。そうです。僕も不具合で。街へ行ったときは大丈夫だったんですけど、今はこの姿しかとれないんです」
乱は敬語を使った。
「不具合か。審神者殿の、霊力の減少と言ったな」
これはあらかじめ聞いていた。
三日月が言うと、国永が頷いた。
「そうだ。三日月殿の主殿の本丸と近い現象が、俺の本丸で起きている」
国永の表情は明るくない。
国永は政府に調査を依頼して、そこで同様の事件として三日月宗近の本丸で起きた事を聞いたのだ、と語った。
「ただし、ここでは、今の所、手入れはできる。異常を感じたのは、一年ほど前からだ。極めた者の顕現が不安定になった。俺もそうだが、外に出ると極でなくなる。そこで政府に調査を依頼し、三日月殿の本丸の存在を知った。原因の究明を待ったが、四ヶ月前、調査の甲斐なく、該当の本丸が無くなったことを知らされた。ただ一つの手がかりだったから、俺達は必死になって他に同じ症状の場所は無いか、原因は何だと探した。まあ俺はその一環で連絡先を配って、そこで三日月殿達に出会ったんだ。近頃は外に出ていなかったら少し時間がずれていたらと思うと、ぞっとする」
そこで国永は乱を見た。乱は国永の側に控えていた。
「乱、三日月の様子はどうだ?」
国永が言った。
「うん、何とか、起きてるよ」
「詳しい話はまた、とりあえず三日月を見て頂きたい。奥で寝ている」
◇◆◇
その三日月は大怪我を負って、布団に横たわっていた。側には骨喰藤四郎と薬研藤四郎が控えている。
右目ごと、頭を包帯で巻いている。そこが少し凹んでいるのが見て取れる。首から下は見えないが首筋にも包帯が巻いてある。
「三日月、連れて来た」
国永がしゃがんで声をかけた。
三日月は思わず膝を付いて見舞った。
「なんと……」
かける言葉が見つからない。生きているのもやっと、生きていてはおかしいと言う状態だろう。
目を閉じていたが、三日月達が膝をつくと、うっすら目を開けた。
「こんな格好で、すまんな……御仁よ」
かすれた声でそれだけ言って、また目を閉じた。
三日月と鶴丸は国永に連れられ部屋を出た。
そして、少し離れた八畳の小部屋に移動する。中央に卓が置かれていて、中庭に面している。
それぞれ腰を下ろして、国永が溜息を吐いた。
「手入れはできると言ったが、三日月だけは例外だ。他の刀剣にも同じ症状が出るかと思ったが、幸い、まだ出ていない。運が良いと言えるのか、それさえ分からん。三日月は、麻酔で痛みは無くしているが……全く動けないんだ」
部屋の外から、静やかな声が聞こえる。この本丸では、刀剣達の遊びも静かだ。
「三日月は龍神のお気に入りで、三日月がいないと龍神が不機嫌になる。そっちは二ヶ月後だからまだいいが、他にも問題があってな。今は出陣を控えているが、一カ所どうしても俺達が行くべき時代がある。その時代に関して、主はこの本丸より、三日月殿の方がふさわしいのでは無いかと、そんな託宣を得ている」
国永は三日月に頭を下げた。
「三日月殿。どうか、手伝ってくれないか? 御仁の本丸についても、詳しい話を聞かせて欲しい。三日月の傷では、もはや自然治癒も見込めない。あれで保っているのは三日月が龍神のお気に入りだから、龍神の力で折れずにいるだけだ。三日月を放置している俺達に、龍神は怒っている。政府の審神者も呼んだ。だが、無理だった。外に出せば三日月は折れる……! どうか、頼む!」
必死の懇願に、三日月は直ぐ頷いた。
「あいわかった。何とかしよう。まずは、手入れ出来ぬか試してみるが……よいか?」
◇◆◇
三日月はまず、三日月宗近――『宗近』と呼ぶことにする――の容態を診た。
部屋には鶴丸と、国永、薬研と骨喰がいる。
薬研が状態を説明する。
「三日月は半年前、出陣先で大怪我を負って、一度破壊され、御守りで蘇生した。本丸に運び込まれた状態のまま、今に至る。落とすところは落として、縫える傷は縫ったが、内臓の欠損と、頭の傷が致命傷だ。そもそも三日月は龍神の加護……ぼやかすのは良くないな。寵愛を受けていて……まあ寵愛と言っても形だけの物で、神楽を奉納した後、社で一晩過ごすだけだが……おかげで滅多な傷では……というか折れるはずの傷を受けても折れないんだ。重傷でも帰還すれば手入れで治る――だからこの本丸には危ない任務が回ってくる。龍神の加護を受けているのは三日月と、三日月の伴侶である鶴丸の旦那もそうだ。二人は龍神の前で結婚した。神楽は交代で、半年前の宴では鶴丸の旦那が舞ったから、次はどうしても三日月の番だ。極の御守にしておけばと、主が泣いて大変だったな……」
薬研が溜息を吐いた。疲れているようだ。
国永が布団に触れる。
「三日月、少しめくるぞ」
国永が半分ほどめくると、体の状態が見て取れた。
三日月ははっとした。
「これはどんな戦いだったのだ」
「――馬上での戦いだが、検非違使に囲まれ、滅多刺しだったらしい。俺も出ていればと何度も思った。その戦いで三振りが折れた。残った二振、一期と御手杵が三日月を連れ帰った。他の三振は回収できていない」
国永が言った。
「検非違使か……多かったのか」
三日月は呟いた。
国永は頷いて、続けた。
「あの時代は、放棄寸前なんだ。だから毎回、検非違使が出る。だが、あの時は尋常じゃ無かったと聞いている。一期の報告では数はおよそ百二十騎。三日月は隊長だったが……政府は三日月の敗退を聞き放棄を決定しかけた。それを主が止めた。託宣があったからな。主は優秀な巫女で、今、龍神と交信できる唯一の人間だ。三日月は社に籠もれば直接会話ができるらしいが、俺にはだんまりだ。嫌な感じはしないんだがな……それこそ気に入りの刀剣の旦那をもてなしている、とかそんな感じで色々世話になってる」
「半年前か……」
三日月は『もっと早く来ていれば』と思ったが、丁度自分が追放された時期と重なる。
「……わかった。まずは手入れだ。長丁場になるが、どこまで手入れができるかは分からん。期待はするな。先だって審神者殿に確認したい事がある。ついでに許可を得て来よう。皆、ここで待て」
◇◆◇
――三日月が部屋を出た後、鶴丸は詰めていた息を吐いた。
先程、宗近の傷を見たが、これは折れていなければおかしい。
右腕は肩からなかった。左腕だってあるか怪しい。頭蓋はかなり陥没していて脳も欠けている。包帯の下に右目は無いのだろう。痛み止めがあっても話せる訳が無いのだが、これが『龍神の加護』なのだろうか? こんな状態でも折れる事ができないのは……逆に呪いだと言いたくなる。
「検非違使か……見たことは無いな、どんな相手なんだ――?」
鶴丸は声をひそめて尋ねた。
検非違使の事は聞いていたが、実際に見た事は無い。国永に『そんな場合では無い』と言われたら謝るつもりだった。
国永が鶴丸の呟きを拾って、口を開いた。
「検非違使は練度の高い者に合わせて強さを変える。あの時の部隊は、極が混じっていて、三日月、一期、御手杵が最高練度。折れたのは鯰尾極、堀川極、長谷部。主は偵察の為に脇差を入れたのが失敗だったと言うが、そんな事は無い。脇差の働きが必要な任務なんだ」
国永は、意外にしっかりした声で答えた。
『鯰尾』と聞いて鶴丸は側の刀剣を見た。
骨喰と薬研、一期一振も粟田口だ。加州の本丸に鯰尾がいるが、明るく素直で気持ちの良い刀剣だ。骨喰も薬研も兄弟を失ってさぞ悲しんだだろう。
「そうか……だが、なぜ三日月に任務まで頼むんだ? 相手が百二十騎の軍勢でも、こちらは二振だ」
鶴丸が言うと、国永が同意した。
「そうだな。主が事態の打開を願って、龍神に伺いを立てた。知恵を借りるという感じか。それで出て来たのが、審神者なる三日月と、政府の刀剣、山姥切長義の名前だ。長義が彼の目付役って事を調べて、彼に頼んで審神者の三日月を探して貰っていた。あの三日月、いや、御仁にはある噂があって……」
そこで三日月が戻って来た。
◇◆◇
――審神者に手入れの許可を取った後、三日月は部屋に戻った。
『それで彼が助かるなら。どうか、お願いいたします……!』
審神者『霞』は三日月に頭を下げた。三日月は「最善を尽くそう」と答えた。
審神者の許可を取ったのは瀕死の宗近と性交する可能性があったからだ。
――それは本当に最後の手段、あくまで可能性だと伝えた。
部屋に戻った三日月は骨喰と薬研に一時席を外すように頼んで、鶴丸と国永には残るように言った。
国永が薬研に確認する。
「麻酔は?」
「あと二時間は保つ。切れるようなら呼んでくれ」
薬研が答えて、国永が頷いた。国永の手元にはボタンだけの機械がある。
「まず本体をよく見せて貰いたい」
三日月は言った。
本体は床の間の近くに、白布を敷いて置いてあった。
敷かれた白布には赤黒い染みがあって、固い鎧を叩き斬ったのだろう。刃はぼろぼろに欠けている。柄には血がにじんでいて鞘は無い。
国永が見下ろして歯を食いしばった。
「あの時置いたきり、恐くて持ち上げられない」
「……なるほど。触らんが、視るぞ」
三日月は手をかざして、様子を確かめた。目を閉じると、消えそうな弱い光が見えた。それを守る大きな光――大きな、龍の形が確かに見える。これが龍神の加護だろう。
弱り切っていて、下手に霊力を注げない。
「なるほど。確かに龍神の加護が見える。三日月の輝きは酷く弱い。この刀の手入れは俺では無理だ。龍神の力にはじかれる。だが……」
三日月は鶴丸の隣に戻った。向かいに座る国永に目をやる。
「国永よ。俺は今から三日月――いや、宗近と呼ぶか。宗近を手入れする。できるかは試さなければ分からん。だがかつて同じ状況にあった俺の本丸では、俺が顕現した刀剣には手入れが効いた。宗近に効くかは分からぬが、試してみよう。国永は浮気に寛容か?」
「浮気?」
三日月の言葉に国永が首を傾げた。三日月は頷いて、今は三日月の左隣、障子の前に座る鶴丸を見た。
「鶴丸にも迷惑をかける。霊力が切れたら協力してくれ」
「分かった」
鶴丸は心得た様子で頷いた。
三日月は鶴丸を見て微笑み、再び一度国永を見た。
国永がきょとんとしているので説明をする事にした。
「俺の手入れは、刀本体にもできるがそちらは下手でな。宗近は折れかけだ。体に霊力を注いでやらねば……まずは接吻と、場合によっては、それ以上の事もせねばならん……が、意識があるなら、接吻で様子を見る。いきなり精を注いではそれこそ毒だ。少しずつ、ゆっくり馴染ませ、治していこう。良いか?」
「――接吻?」
国永は話が見えないようだ。いきなり言われて目を丸くしている。少々幼げな表情は、これが国永の素なのかもしれない。
隣で鶴丸が立ち上がった。
「まあ、君は見ない方がいいぜ。三日月、まずは試すんだろう。俺達は外にいる。どこか部屋を借りておく。近い方がいいか?」
鶴丸が言った。話が早くて助かった。
「ああ、そうしてくれ――いや、少し離れた、静かな部屋がいい」
三日月は言い直した。
「分かった。じゃあ……そこの縁側で待っている。初めの一回で駄目ならどうしようも無い。終わったら教えてくれ。行こう」
鶴丸が戸惑う国永の手を引いた。
「頼んだぞ」
三日月は微笑んだ。
◇◆◇
部屋から出た鶴丸は縁側にあぐらを掻いて座った。
暦の上では冬のはずだが、この本丸も桜が狂い咲いている。
これが普通なのか鶴丸にはまだ分からない。
「……治るといいな」
鶴丸は宗近の怪我を思い出して呟いた。
――鶴丸の左隣に国永が腰を下ろした。こちらは正座している。
「……事情はよく分からないが、感謝する」
「それこそまだ分からない。俺は何もしないからなぁ……はぁ」
鶴丸は溜息を吐いた。
鶴丸は、軽く説明するか、と思って口を開いた。
「三日月は、手入れが下手、って言ってるがそこまでではない筈だ。俺の刀は普通に手入れが出来る。ただ他の審神者の刀は苦手だって言ってるな。普通の手入れの他に、接吻、口婬、性交、まあつまり、体に触れて霊力を渡す事が、得意なんだと」
鶴丸は膝に右肘をついて、頰を支えた。
そのまま、国永の返事を待たずに続ける。
「……三日月自身の霊力は、審神者としては大した事が無いらしい。しょっちゅう霊力切れでふらつくし、熱も出してたな。あと霊力が減るとよく寝るし、大食いになる。三人前は平らげるから用意してくれ。俺の役目は三日月の霊力補給だ。今まで手入れの度にまぐあうのはどうなんだって、接吻以外は避けて来たが、そろそろ喰われそうだな。まあ、覚悟を決めるか……」
鶴丸は一人ごちた。
「――避けて来たのか?」
国永が言った。
「ああ、三日月が嫌なわけじゃない。が癖になるのは不味い。接吻で済む時は、それで済ませた方がいい。俺が勝手に思ってるだけだが」
「なるほど。確かに、癖になるのは不味いな」
国永が言った。
鶴丸は苦笑した。
「瀕死の重傷で抱かれたら死ぬぜ。やさしくして貰えるとしても、さすがに無理だ、逆もできる気がしない」
「逆ってのは……?」
国永が呟いた。
鶴丸は三日月自身の手入れにも、接吻や性交が効果的だと伝えた。
「三日月の場合は、それ以外に方法が無いらしい」
「なるほど……それはきついな。重傷の恋刀を折らずに抱くって、相当だぞ」
国永は宗近の状態を思い出したのだろう。「俺には……無理だ。できるかもしれないが、折れそうだ」と呟いた。
「しかし、薄情に聞こえるが……お前さんの本音は違うんだろう?」
国永が言った。
「本音?」
鶴丸は首を傾げた。国永が口の端を上げた。
「君はあの御仁が好きだから、いくらでも抱ける。だが、手入れを理由にするのが恐い。違うか?」
「――」
鶴丸は頭を抱えた。さすが自分と言う他ない。見事に図星を突いてきた。
……鶴丸は今では、三日月の事が好きでたまらない。
凛としているようでどこか抜けているところ。優しいところ。変わりやすい感情や表情。抱きしめたくなる体。匂い立つ肌、月の浮いた瞳……。
三日月は誘って来るが――義理で抱いたと思われたくない。
鶴丸の様子を見て、国永が控え目に声を上げて笑った。
「ははは。ご愁傷様。おめでとう、と言ってやろうか? 俺は惚れた方だからなぁ。全く羨ましい限りだ。しかし意外だな。あの大層な御仁が顕現したての君に惚れたのか?」
……意外そうに言われても、良い仲ではないし好き合ってもいない。
鶴丸は溜息をついた。
「いいや、三日月は初めから俺を好きになろうとしていた。俺達は二振きりだから、俺を伴侶にするんだという――固定概念? みたいな――俺と三日月は人で言う所の、許嫁、みたいなもんだ。俺達はまだ仲間がいない。だから三日月は俺を好きになりたいのさ」
鶴丸は襟足を撫でた。気恥ずかしいのは仕方ない。鶴丸は国永とどうしてこんな話をしているのだろう、と思った。国永が同じく『三日月宗近』を愛しているからだろうか。
すると国永が思いっきり眉をひそめた。
「はぁ? いや馬鹿言うなよ! 俺は三日月の表情なら良く知ってるが、あれはそんな生優しい目じゃない。君に心底惚れきった目だ」
「まさか」
鶴丸は虚しく笑った。
……鶴丸には三日月の気持ちがまだよく分からない。
三日月は、簡単に本音を打ち明ける刀では無いのだ。ただ抱く事を求められるが、それは不味い。
――鶴丸は一つ、自分の感情で困っていることがある。良い機会だから、今夜にでも打ち明けるつもりだ。
乾いた笑いを収めて、鶴丸は続けた。
「そう言う訳だから、なるべく静かな部屋を用意してくれ。というか離れた部屋だな。近くに風呂があれば言う事はない。三日月は照れ屋でな、絶対に口外するなよ。もし三日月がいたたまれない思いをするようなら……分かるな?」
国永は即座に頷いた。
「――分かった。治療の際は誰も近づけない。ちょうどいい部屋がある。風呂付きだ。飯も最高の物を提供しよう。部屋の前に箱膳を置けばいいか? なるべく関わらないから、二人きりで過ごしてくれ。掃除や世話は骨喰か、俺か、薬研にさせよう。いや、薬研は三日月についてなきゃいけないから、俺か骨喰、それか乱だな。どうだ」
「話が分かるな、さすが俺の先輩だ。極だとは思わなかったが……」
「外に出ると戻っちまうんだ」
国永が苦笑した。
「まあ、鯛焼き奢って貰ったし。その節はありがとう。初めて食べたんだが、美味かった」
「ああ気にするな――ずっと思ってたが、君はやっぱり初々しいな。その良さをぜひ大事にしてくれ! あの時は三日月が食いたいと言ってな。急いで買いに出た。結局匂いを嗅いで満足したが……本当に、少し入れ違っていたらと思うと……ぞっとする――じゃあ、部屋を用意して来る」
国永が立ち上がりかけたが、鶴丸は袖を引いた。
「あ、いや。結果が分かってからでいいぜ。そうださっきの話だが、三日月の噂って何だ?」
鶴丸は気になっていたことを尋ねた。
立ち上がりかけた国永が、動きを止めた。
「ああ、あれか。本人に聞いた方がいいんじゃないか」
「分からなければ聞きようが無い。三日月ははぐらかすのが上手すぎる。同じ刀のよしみで少し教えてくれ」
鶴丸は言った。三日月は自分から何かを話す事が少ない。必要な事は教えてくれるが、まだ知らない事が沢山ある。主の本丸を出て自分の本丸を持ったと言うが、その話は全くしない。噂になるような事があるなら、尚更言わないだろう。
国永が渋々口を開いた。
「そうだな……ある時、政府の部隊が検非違使の大群と遭遇した。その作戦では多くの刀剣が出陣していたが、生き残りはただ一振。それがあの三日月宗近だって話だ。これ以上は彼に聞いてくれ」
◇◆◇
――淡い光が収まった後、三日月は同じ顔から舌を抜いた。
三日月はほっと息を吐いて、意識の無い宗近を見下ろした。
初めの手入れは上手く行った。これなら、時間をかければ回復できる。開いた口をつぐませて、手ぬぐいで拭ってやった。接吻だけでは全快は難しいが、良い所までは行けるだろう。頭の傷が気に掛かる。まずは宗近の体力を戻さなければ、傷を治すことも叶わない。
三日月は過去の戦を思い出した。
怪我をした仲間――同じ三日月だった――の太刀に、急激に霊力を注いで怪我を治した結果、窮地を脱したが、戻る直前に彼だけ折れた。あんな思いはもうしたくない。
……三日月の体は霊力の塊で、言うなれば劇薬だ。
まともに手入れしたら折ってしまう為、なるべく力を抜いている。
三日月は加減が下手すぎて、いくらやっても調整出来ないから、遠回しな接吻や性交くらいが丁度いい。
性交抜きで三日月の霊力に耐えられるのは鶴丸だけだ。
あれほど霊力を注いでも、まるで痛がらず、うんともすんとも言わない刀は珍しい。
三日月は言うのを控えていたが、鶴丸を主が顕現できなかったのは、おそらく単純に霊力が足りなかったからだ。
そもそも、なぜ三日月が審神者の力を持ったのか?
三日月は全く普通の主に呼び出されて全く普通の三日月宗近として顕現したはずなのに。
政府のとある審神者は『分量間違え』『あるいは混入』ではないか、と語った。
審神者は三日月を隅々まで調べ、こう述べた。
『固く結ばれた、幾振りかの三日月宗近の魂が……、どこかの審神者を巻き込み、消えたと仮定して。それが離れる事なく、運良く安定した状態で、依り代に降ろされた……? それくらいしか、思いつかない』と。
恐ろしい奇跡だ、人為なら尚恐い、これは刀剣男士ではないと言われた。
――それが事実なら、全く迷惑な話だ。
刀解が決まった時、まあ良いかと思った物だ。一度戻って、道具として生きる方が楽に思えた。翌朝を心待ちにした。
しかし政府の審神者は誰も三日月を刀解できなかった。
三日月には鎖が絡みついていて、どうやっても依り代と魂が離れないのだという。
政府は躍起になってありとあらゆる方法を試した。
三日月は不死身では無い。衝撃を受ければ折れるし怪我もする。主以外の手入れは受け付けない。政府は破壊しようと試みたが、なぜか失敗された。
……三日月自身は、その時、何があったか覚えていない。
それはいい。もう怒っていない。三日月は何にも怒っていないし、政府に何も期待しない。
唯一欲しがって期待しているのは鶴丸なのだが……どうも煮え切らない。
三日月はあの刀剣が何を考えているのか全く分からない。
手入れの度に接吻して、鶴丸にも『淫乱な刀だ』と嫌われているのかもしれない。
急いている自覚はある。鶴丸にしてみれば顕現して二月そこそこで、性交云々言われても困るだろう。
三日月は苦しくなった。
溜息を吐いたが、鶴丸との事と、宗近の治療は別問題だ。
……『鶴丸国永』と幸せに生きている『三日月宗近』なら、是が非でも救いたい。
三日月は『三日月宗近』に対して特別な感情を抱いていた。自分だから当然なのだが、いつだって彼等の優しさに救われてきた。彼等の事を思うと胸の内が温かくなる。
三日月は微笑んだ。
「三日月宗近よ。必ず助ける故、もう少しの辛抱だ」
部屋を頼んだが、そこへ行けるのは少し後かもしれない。
三日月は立ち上がって、障子を開けた。
――それから五日が過ぎた。
三日月はずっと宗近の側にいて、寝泊まりは隣の部屋でしていた。手入れはできたが回復が遅く、宗近の側を離れられなかったのだ。
おかげで宗近の状態は大分良くなった。顔色も良くなり、細かな傷は消えていた。会話も少し流暢になったが、ここ数日は眠らせてある。薬研が『薬の効きが良くなったし、血も止まった』と喜んでいた。国永はずっと離れない。
途中から鶴丸も部屋に入り、霊力の補給を手伝ってくれたが、体の疲労はどうしようもない。鶴丸はまだ元気そうだが、三日月が明らかに疲れていたので、国永が休息を勧めてくれた。
宗近の容態は安定しているから、一日、二日程度ならこのままでも問題ないと伝えた。
上手く立ち上がる事ができなかったので、鶴丸の手を借りた。
◇◆◇
三
国永が用意した部屋は、宗近の部屋から大分離れた場所にあった。
鶴丸は三日月を支えて、廊下を歩いていた。
「疲れた……」
三日月は部屋に着くなり布団に倒れ込んだ。
「大丈夫か?」
鶴丸はうつぶせの三日月を気遣った。
三日月は枕に顔を埋めて、何かもごもごと呟いた。
「年寄りには堪える」とかそんな事を言っている。
鶴丸は微笑んだ。
「良く頑張ったな」
鶴丸は三日月の頭をそっと撫で、しばらく背中をさすってから、掛け布団を引っ張った。
この部屋には布団が一つしかない。綿の布団は大きく軽く、いかにも温かそうだ。
敷き布団に腰を下ろしてみる――綿の良さがよく分かる。三日月の呼吸は穏やかで、直ぐ眠りそうだ。
三日月は藍色の着物を着ている。これは宗近の着物だ。三日月は今でこそ食事も睡眠も取っていたが、二日目までは徹夜していた。
三日月は一昨日から、一時間に一度くらいの頻度で接吻を繰り返していた。流石に夜中は休んだが、禄に寝ていない。鶴丸も霊力が減っている実感は無いが疲れてきた。
……三日月と宗近が接吻すると、互いの体が淡く光る。黄色みを帯びた温かい光だ。
鶴丸と三日月が接吻すると、こちらは互いに白く光る。
霊力は刀剣によって性質が違って、それが色の変化に現れているらしいが、ここまでしっかり見えたのは初めてだ。宿で軽傷の手入れした時は、もっと光が薄かった。
おかげで宗近は快方に向かっている。
様子を見て手入れ部屋に入れる案もあったが、審神者の力は戻っていない。
三日月も『俺の霊力に満たされているから、今、審神者の霊力を混ぜるのは良くない』と言った。三日月は疲労が回復したら、傷を治していくという。その後なら試す価値はあるが、頭の傷も、腕も、全快できるだろうと語った。
『御仁は本当に凄いな……! 感謝する!』
『ははは』
国永はすっかり三日月に懐いたが、その鎧はずいぶんすっきりして、鶴丸と同じだ。
――昨日、国永は極の姿を維持することができなくなったのだ。最後に残った極は骨喰だったが、同日夜、彼の姿も特に戻った。
……全員が極を維持出来なくなったことで、霞の本丸は方針を変えた。
手入れが出来ない事、極が維持出来ないこと。重大すぎる理由で『可能なら、任務の引き継ぎが可能な本丸を探して欲しい。見つからなければ、時代の放棄もやむなし』と政府に連絡を入れた。
今は返事待ちの状態らしいが、国永は『やりたいって本丸は何処かにあるだろう』と語っていた。表情はあまり明るくなかった。政府は検非違使を恐れている、らしい。
「ゆっくり休め」
三日月だけ寝かせて鶴丸は新しい布団でも出すかと思ったが、無言で袖を引かれた。
「……仕方無いな」
鶴丸は溜息を吐いて、三日月の右側に潜り込んだ。ご丁寧に枕は二つある。
三日月が、はぁ……、と長い息を吐いた。疲れた溜息だ。
三日月が枕を外れて、鶴丸の側に寄ってきた。三日月は鶴丸の腰に腕を回し、鶴丸の胸に頭を寄せた。
――鶴丸も三日月の背中に手を回した。
三日月は背中を曲げて布団に潜り込んでいるので、鶴丸に見えるのはつむじだけだ。
抱き合ったまま、鶴丸は笑った。
「全く、この五日で、飽きるほど接吻したなぁ。口が疲れただろう?」
「ああ……唇が乾いた」
三日月が答えた。
三日月は宗近とも接吻しているから、鶴丸の倍だ。減る物では無い……と思えば良いが、大盤振る舞いだ。
「薬研の薬を塗ったか?」
三日月も鶴丸も唇を腫らしていたので見かねた薬研が軟膏をくれた。唇に塗っても良い物で、少し草の香りがする。
「あれは味が悪い。蜂蜜がいい」
三日月は蜂蜜も試していて、そちらがお気に入りらしい。蜂蜜を見て『鶴の目のようだ』と言って笑っていた。
「蜂蜜は甘いが、あまり好きじゃないな。手に付くとベタつく。なあ、三日月。このまま接吻だけで治りそうなのか?」
鶴丸は尋ねた。すると三日月が顔を上げて、枕に頭を乗せた。
「実は、厳しい」
「……そうか」
鶴丸は言った。そんな気はしていた。だが疑ってもいる。三日月は何かと理由を付けて鶴丸に触れてくる。嘘だと分かる時もある。
「だが、きみ、それは本当か? きみは何かと触れたがる」
「実を言うと、分からぬが、あまり悠長な事はできん。滞在が長引けば政府に知られる。出陣に手を貸せと言われたが……さて、どうするか……」
「そっちは取りやめじゃないか?」
「どうだろう。俺が居ると分かったら、無理に押しつけるかも知れん」
「きみ、そんなに仲が悪いのか……?」
鶴丸は言いながら首を傾げていた。
三日月の顔が、今日はやけにはっきり見える。部屋が明るいから、と思ったが灯りは全く点いていない。三日月が光っているわけでも無い。
目を擦って、体を起こしてみた。周囲を見ると、暗い部屋の様子もよく見えた。
「つる?」
三日月が少し眠そうにする。
「なあ、今日はきみの姿が実によく見える。畳の目や縁の模様も、まるで昼みたいに見えるんだが……暗いよな?」
辺りを見回すと、掛け軸の絵が見えた。鶴丸は目を擦った。自分の手も良く見える。
「手入れの後、こういうことはあったんだが、これは何だ?」
「そうか、鶴はやはり夜目が利くのか。目が光っておるぞ」
三日月が微笑んだ。
「えっ、光ってるのか!?」
「ははは、まるで猫だなぁ」
三日月がおっとりと言って、手を伸ばして来た。
「なあ鶴、鶴は俺の事が嫌いか? いつになったら抱いてくれる?」
三日月は眉を下げて不安そうにしている。
鶴丸は溜息を吐いた。
「別に嫌いじゃ無いぜ。そのつもりもある。でも、今はまだ、もう少し考えたい。ずっと気になってたんだが……何て言えば良いのか、実は――」
鶴丸は、自分の悩みを伝える事にした。
「きみを抱けないって言うのは、俺がきみをどう思っているか分からないからだ。いや、分かって来たんだが、それだけじゃなくてな……俺はきみを主だから好いているのか、そうじゃないのか、いまいち区別が付かないんだ。正直、きみのことはかなり、大好きなんだが、恋愛かと言われると……ああ、違う、確かにきみの事は好きなんだ」
鶴丸は赤面した。自分は何を言っているのだろうと思った。結局『三日月が好きだ』と言えば済むことだ。
それを認めてしまったら、取り返しが付かない気がして、ためらっていた。
すると三日月が体を起こした。
「鶴丸。おぬしには言っていなかったが、刀剣男士には『領分(りょうぶん)』という物がある」
「りょうぶん?」
初めて聞く単語に鶴丸は戸惑った。
「刀剣男士が持つ、本能のようなものだ。ふむ。例えば……」
三日月は語った。
一つ、刀剣男士は理由無く人を傷付ける事が出来ない。
一つ、刀剣男士は主の命に従う。
一つ、刀剣男士は、刀剣男士間では問題ないが、審神者に対して恋愛感情を持つ事ができない。これは主だけではなく、他の審神者に対しても同じである。その他一般人、政府職員に対しても同じである。
神と人は相容れない。寿命も違いすぎる。痴話喧嘩、刃傷沙汰、虐待、自殺などを防止する為の仕組みだ。三日月は鶴丸がためらっているのはそのせいではないかと語った。
「俺は刀剣男士だが審神者ゆえ、余計に戸惑っておるのでは?」
鶴丸はなるほど思った。確かに、審神者と恋愛ばかりでは戦が滞りそうだ。
「そんな物があるんだな。だが、それと、俺がきみを好きだって事はおそらく関係が無い」
鶴丸ははっきり言った。
もう既に『好きだ』と言ってしまっているのだが、鶴丸が言いたいことはまだ他にもある。
「手入れの度に熱をもてあますのは、俺は不味いと思ってる。きみだって昼間は普通に接吻しただろう。そういう風じゃだめなのか。宿でしたみたいに、抜き合いまでする必要があったのか。色々教えてくれた事には感謝しているが、もう少しわきまえてくれ」
鶴丸は溜息を吐いて、大人げない――と思いながらも思っていた事を吐き出した。鶴丸に大人げがあるかは置いておくとして。三日月に自慰を教えられて、鶴丸はなんとも言えない気持ちになったのだ。
接吻の後熱をもてあましても、抱く気がないとはっきり言えば、三日月は仕方無いといった風で、横になってくれたが……どれだけ恥ずかしかったか分からない。
よく我慢したと思う。少しくらいは怒ってもいいと思う。
……与えられる愛情は嬉しかったし、三日月を『愛しい』と思う気持ちもある。
だが、それが三日月が主だからか、鶴丸が三日月を好きだからか、本当に分からなかった。
「いいかい、物事には順序って物がある……全く、何が悲しくてきみに説かなきゃいけないんだ……」
鶴丸は布団に顔を埋めた。
「では鶴は……やはり」
三日月は座ったまま、項垂れた。
「困っていたな」
「ぁぁ……そうか。性急だったな」
三日月は悪い事をした自覚があるようだ。
それは鶴丸にも伝わっていた。
一々『すまん』『悪いな』『我慢してくれ』と言われ、申し訳無そうに触れられて、どういう反応を返せばいいのか分からなかったのだ。
「いいや、嫌だと、はっきり言わなかった俺も悪い。だいぶはっきり言った気もするが。ここは一つ仕切り直しだ。今までの事は忘れよう。きみは疲れてるだろう、一先ず横になって、寝るといい」
すると三日月が固まったまま、眉をひそめた。
「おぬし、そうやってまた逃げるのか?」
「いや、もう逃げないが、きみは今、ふらふらだ」
「それが逃げていると言うのだ――意気地無しめ」
恨みの籠もった口調だった。鶴丸は思わず反論した。
「はぁ? きみ、それはあんまりじゃ無いか、俺は今日、もうそういう気分じゃ無いんだ」
「……気分? 鶴は気分で抱くのか? 俺がどんな想いで鶴を待っていたか……そうか、知らぬからそんな口をきけるのだな。よかろう。朝まで延々話してやる」
三日月の言葉に鶴丸は焦った。
「なっ、馬鹿、寝ろ! ぶっ倒れるぞ」
「知ったことでは無い」
「――それはだめだ。宗近が助からなくて良いのか」
「宗近は助かる。俺は助からん。鶴に軽蔑されていた俺の気持ちが分かるか。年甲斐も無く舞い上がって、自分を止められなかった。ああ、皆、俺の事が嫌いなのだ! 俺は真面目にやっているのに、皆が俺を淫乱刀剣だと言う!!」
「それは酷いが、きみは意外にめんどくさいな」
「面倒? 面倒と言ったか? めんどう、これは我が儘だ。鶴は俺の言うことを聞け」
「……言う事? 何をしたいんだ?」
「何もしとう無い!」
ついに三日月はそっぽを向いた。
「えっあ、ちょ、落ち着け、なあ三日月……!」
鶴丸は溜息を吐いた。
これを収める方法はただ一つ。
「……俺はきみが好きだ。それだけはもう分かっているから、どうか許してくれないか」
顕現して約二ヶ月で、鶴丸は引く事を覚えた。
◇◆◇
「分かれば良い……俺も悪かった」
三日月はそう言って、溜息を吐いた。その後、急に機嫌が直り、穏やかに、嬉しそうに微笑んだ。
三日月はさっさと布団に横になって「鶴も寝ろ。なあ……俺の事を好きと言ったか? 聞いたぞ。なあ好きと言ったのか? 聞こえたぞ」と三回は繰り返した。
「間違いは無いな?」
「あー、間違い無い。確実だ。明日辺り抱いてやるから、安心して、早く寝てくれ」
鶴丸は三日月の肩を撫でながら言った。三日月は目を輝かせている。
「言うたな? 俺は聞いたぞ」
「言ったし、聞かれたな……」
鶴丸は苦笑した。三日月を抱けるのだろうか、と考えて、腕の中を眺める。
三日月は嬉しそうで――無邪気で、しかしどこか捉えどころの無い表情をしている。
鶴丸は抱きしめる腕にほんの少し力を込めた。
「あ。そう言えば――かだいって何だ?」
「かだい?」
鶴丸は山姥切に聞いた話をした。すると三日月が笑った。
「ははは、うん、課題か。そう言えば、そんな夢を見たな。うん、よく見る。審神者の勉強をしていた時のことだなぁ。もう終わったのに、未だに見る……枚数が足りているのに、足りない夢とか、遅刻する夢も見るぞ」
……国永に聞いた噂について尋ねると、三日月は眉を下げた。
「そうか、聞いたのか。悪いが、その話は、あまりしたくない。俺の失敗で、俺以外、全滅した」
静かな声だった。
「……全滅か」
鶴丸は天井を見ながら相づちを打った。
「ああ。全滅だ。手入れは主がしてくれたのだが、主に会ったら何もしたく無くなった。心を病んでしまい具合も悪かった。だから我が儘を言って本丸に戻った」
三日月も仰向けになって天井を見ている。近代的な電灯が吊されていた。
「きみは大変だな」
「うん。大変だ。おかしいと思ったのは――初めからだな」
三日月がぽつぽつと語る。
「演習で、三日月宗近に出会うとな。皆が俺を『御仁』と呼ぶのだ。初めは単なる呼びかけだと思っていたが、どうも違うらしい。恐ろしい事に、三日月は皆、俺をそう呼ぶ――あらかじめ刷り込まれているように。何が違うのか、どう違うのか。俺は恐かった。三日月達にも理由は分からぬという。ただ、俺が俺だと分かるのだと。本霊の号令では無いかとか、色々言われたが、結局分からぬままだ。政府の連中は俺を嫌っているからな。本霊には近づけない。俺が何かすると思っているのだろう」
「きみは色々、悪い事をしそうだからな。本霊をたたき割ったりとかしないよな」
鶴丸は苦笑した。
「ははは――そうだなぁ。沢山悪い事をした。懐かしい」
「そこは返事をしてくれ」
「殴りたいとは思っている」
真面目に言うので鶴丸は笑った。
三日月の方を向くと、ちょうど目を閉じていた。眠るのかと思って三日月の方を向いて、彼の頰にかかった髪を払う。寝姿をずっと眺めていたいと思ったら、三日月が目を開けて、こちらを向いた。
「つる。ひとつ話す事がある」
「……何だ?」
「俺はな、本丸を追い出された時、主と通じた。主は自分の行いを後悔して死んだのだと思う。今まで嫌だ嫌だと言っておぬしを待っていたのだが、結局、主に食われてしまった。初物でないから、好きな時に抱いてくれ」
三日月はやっと言えた、と溜息を吐いた。
途端に、鶴丸はかっと赤くなった。
「――なんだって、きみ……」
鶴丸は動揺した。心臓が凄い音を立てた。止まるかと思った。
三日月は今なんと言った?
主と通じた?
「待て、さっき、領分って」
「審神者に制限は無い。罰はいくらでもあるが、効かん時もある」
その言葉で、今までの色々な事が一気に腑に落ちてしまった。
三日月があんなに泣きじゃくったこと、山姥切が協力した事。
性交が必要、と明け透けに言うから経験を積んでいると思っていた。
思わず三日月の着物を引っ張った。
「待て、寝るな、三日月」
「何だ、俺は眠い」
「きみはいつから、俺を待っていた?」
「ん、言うたと思うが――おらんかったか。まあよい。演習で余所の鶴丸を見てな、真っ白でなんと美しいのかと、一目で気に入った。運良く拾えて、それからだ。毎日話掛けておったが、中々起きなくてなぁ。こんな事になってしまった。すまんな」
鶴丸はひゅっと息を呑んだ。
……そう言えば、鶴丸を拾った経緯は、顕現初日に聞いていた。
だがその時とは全く意味が違う。鶴丸は肘を付いて体を起こしたが、三日月はこちらを向いて横になったままだ。
「審神者とは、どうやって通じた? ちゃんと想い合っていたのか」
これだけ一途な三日月が、浮気をするとは思えない。三日月は政府へ行く時、鶴丸に聞かれたく無いと言った。その時は何か余程の事情があるのだろうと――正直言って、あまり気にしていなかった。
何があっても三日月なら大丈夫だと。実際に三日月は無事戻って来た。
鶴丸は三日月の肩を掴んだ。
「追い出された日の事を教えてくれ、言いたくないって、何があったんだ!」
三日月は苦笑した。
眉を下げて、仕方無いな、と言うような。少し笑っている。
「――俺がうかつだった。それだけだ。どうせ、本丸へ行けば見る事になる。その時見れば良い。今は審神者の執念に免じて、許してやろうと言う気分だ」
「……っ」
「俺を犯して死ぬとは天晴れだ。さすがは俺の主、とさえ思うな。今こうしておぬしと、温かい布団で眠っている。もうそれで十分だ」
三日月は幸せそうに微笑んだが――鶴丸はそれどころでは無かった。
「ッ……そういう事は、早く言え! ……くそッ……何でもっと早く顕現できなかったんだ!!」
鶴丸は自分の頭を引っ掻いた。一年早く顕現できていれば、間に合った。三日月の隣で、三日月と恋仲になって、守る事もできた。山姥切の『歴史を変えたいと思ったのは初めてだ』という言葉が思い出される。重くのしかかる。鶴丸も今そう思っている。
鶴丸は叫んだ。
「歴史を……変える事は出来ないのか、起きた出来事を! 過去へ飛べるんだろう! 審神者を殺すか、俺が会いに行けば」
すると三日月が鶴丸を叩いた。叩かれた、と思う間もなく頰に衝撃があった。
「目を覚ませ。それはできぬ。だから俺も受け入れた。あれは単なる事故だとな。こうしてお前がいればそれで良い」
「……それでいいのか!? 三日月……ッ」
「初物でないのが嫌か」
「そうじゃない!! ただ、許せない!」
「何が?」
「……わからない、わかるもんか! 全部許せない! きみは……俺の気持ちを知らない」
ぼろ、と涙がこぼれた。それを無理矢理、拭った。
「……きみを思うといつだって悲しくなる。顕現した日から、おれが何を思ってるか、きみはしらない」
鶴丸を襲う得体の知れない不安、焦燥。三日月の現状に対する怒り。主にみすぼらしい格好をさせているという屈辱。触れる度に苦しくなって、ああ、恋だなと自覚して。自覚されられて。嬉しいより悲しい。三日月の覚悟が辛い。その顔が、本当の意味で晴れることは無い。いっそ引き倒して。閉じ込めて――。
鶴丸は三日月の右手を掴んだ。
「鶴?」
「分かった、抱けば良いんだろ。きみの主も、きみが好きで好きで仕方無かったんだろう。きみは人を狂わせる。刀も、このままじゃ俺も狂う。とっくに狂ってる。きみの血が見たくて仕方無い。引きずり込んで、肉を喰らって、骨だけを愛でたい。そうすればきみは何処へも行かないし、俺達は一つだ」
三日月がはっとして、敷布に押さえ付けられた右手首を見る。三日月はまだ横になっていて、鶴丸は体を起こしているから、押し倒している訳でも無いのに、しっかりと縫い止めた右手首は、それだけで三日月の自由を奪っていた。
――三日月は抵抗しない。驚いた様子で鶴丸を見つめている。
時折痛みに顔をしかめる。
三日月の手首に爪が食い込む。皮膚が破れて血が滲んだ。骨を折りそうになって、鶴丸は目を閉じた。
「……ちがう……三日月。俺はそんな事がしたいんじゃない……畜生にも鬼にもなりたくない。きみに触れたいだけなんだ」
◇◆◇
暗闇で、鶴丸の瞳が光っている。そこから涙がこぼれ落ちていく。
鶴丸が三日月の真上にいる。
――視線が合わさった。
「鶴丸は、俺の事を、ずっとどう思っていた?」
三日月は問うた。
「好きだと思っていた。主だと思っていた。苦しかった」
鶴丸の指が頰を撫でる。三日月は目を細めた。
「……俺も」
俺も好きだと思っていた、と言いたかったが上手く言葉が出なかった。
「口を吸って欲しい。好きなだけ触れてくれ」
出て来たのは情緒の無い言葉で、どうして俺はこうなのだ、と自分が恨めしくなった。
他の三日月はもっと可愛げあるのに、俺はこうだ。
すぐに口が塞がれて、すっかり慣れた接吻が、と思ったが、何かが違った。
「んッ?」
熱に任せて舌を絡め合ったこともあったが――この接吻はそれより遙かに強引で乱暴だった。歯列を舐めて、歯の裏、口蓋へと進み、できる限り奥まで入ろうとしてくる。顎を掴まれて目一杯口を開いたまま、舌の動きを感じた。舌をすくわれ、唾液があふれてむせかけた。髪に触れられ、体がうずいた。襟に手がかかる。今まで鶴丸は、決して三日月の着物を乱さなかったから驚いた。こんな事で、と思ったら息が詰まって、舌の動きに翻弄された。押さえ付けられて、声を上げる事が出来ない。ふと、あの夜の事を思い出した。
自分の上にいるのは審神者だろうか。目を開いても見えるのはおかしな光ばかりで、三日月は目を瞑った。一瞬離れたと思ったら、また捕まった。手首を掴んで布団に縫い付けられる。
嫌だと首を振っても止められない。これは鶴丸だ、と思って耐える。冷静になれと自分に言い聞かせて呼吸を整えようとしたが、絶えず舌と舌が擦れあっている。吸われて、喉の奥で唾液が混ざり合う。
思った以上に覚えている。それでも気持ちは良い。腰が跳ねた。首に触れられ、肌が粟立つ。首を振ると、鶴丸が離れた。
「っ……」
三日月はごほごほとむせ込んだ。
息を整えて見上げると、真っ暗闇に金色の双眸が浮いている。
この部屋はおかしい。部屋に一片の灯りも無く暗すぎて、何も見えない。
口元に近づく気配がある。
「待っ、少し恐い、灯りを」
鶴丸が優しく笑った気がする。
「――俺のどこが恐いんだ? 心配しなくても、ちゃんと優しく抱いてやる。まあ、やったことはないから、きみの力を借りる事になるが、覚えは良い方だ」
つい、と鎖骨の下に触れられる。胸に触られる。鎖骨に濡れた感触があって、息がかかる。髪が乱れる。
「恐い、駄目だ鶴丸、恐い」
三日月は震えた。
「鶴丸が主に見える……恐い」
三日月が訴えると、鶴丸の手が止まった。
「暗いのが駄目か」
「違う、見えんのが恐い。乱暴もやめてくれ、ほんに、やつを思い出す。思い出したくないのに、思い出す……」
三日月は首を振った。鶴丸が三日月の上から退いた。
立ち上がる気配があって、しばらくしたら枕元が明るくなった。
行燈を模した灯りの温かい光に照らされて、鶴丸の姿が浮かんだ。白い肌に蜂蜜色の瞳、銀色の髪に、真白い浴衣。
「……悪かったな。怖がらせたい訳じゃ無い、手、痛くなかったか」
三日月は自分の姿も見ることができた。
呼吸を整えてから声を発した。
「……すまん……落ち着いた。この部屋は暗すぎる」
「窓が無いからな」
三方は壁で、頭に床の間、足元に障子。それだけの六畳間だ。床の間、押し入れがあるが、秋津の本丸の部屋より狭く感じる。
明るくなって、ようやく、三日月は自分の様子も見ることができた。はだけた胸元、解けかけた帯に、裾もわずかに乱れている。この程度で余裕を失ってしまって、少し情けなく思った。
鶴丸が灯りを絞って、辺りが暗くなる。このくらい暗ければ恥ずかしくも無く、目が慣れれば鶴丸の姿もよく見えるだろう。暗い中でも鶴丸はよく見えた。白い肌がよく目立つ――先程はどうして見えなかったのだろう、とさえ思った。真っ暗だったから、それは間違い無い。改めて鶴丸を見て、彼の独特の美貌に驚いた。儚いという言葉がぴったりで、この世の物とは思えない。彼は黄泉に属する物だろう。白い着物は死装束だ。鶴丸は誰彼構わず愛想を振りまくので、少し心配だ。攫われやしないかと――これは『三日月宗近』が持つ兄心かもしれない。三日月は記憶が薄い方だが、三条と五条は師弟だったと言われている。そこに拘る刀剣を数多く見て来た。
鶴丸は背を向けて、湯飲みに白湯を注いでいる。
「落ち着いたか? 飲むか」
「もう大丈夫だ。熱そうだから、後で良い。少々、みっともない所を見せた」
三日月は寝転がったまま、頑張って微笑んだ。鶴丸も微笑んで、戻って来た。
「いいや俺も脅しすぎた。冷静じゃなかった。ほら、これ、国永がくれた油だ。すっかり忘れていた。せっかくだから使おう」
鶴丸が苦笑して、小瓶を見せた。目が慣れてよく見える。
「三日月、一つ提案があるんだが、いいか?」
「何だ? 申してみよ」
鶴丸が自然と、三日月の上に跨がる。
「きみを抱く度に、辛い情事を思い出されたんじゃあ嫌だ。だから、できる限り、その時の事を、なぞって、一つずつ忘れていこう。それでも駄目なら、その時と違う趣向ですればいい。どうせちっとも良くなかったんだろう? 時間はたっぷりあるんだ。辛いのは今日限りにして、後は楽しもうぜ」
鶴丸の言葉に、三日月は、ああなるほど、と思った。
「確かに、その通りだな。それは良い考えだ。良い事を言う」
鶴丸は穏やかに微笑んでいる。
「そうだろう? 快楽で上塗りすれば、思い出すのはそちらになるかもしれない。思い出すだけで体が疼くようにすれば良い。俺は協力を惜しまないぜ? どうだ、辛いかもしれないが、やるか?」
「ああ、やる」
三日月は頷いた。情事の度に思い出すくらいなら、鶴丸との情事を思い出すようになればいい。目から鱗で、やる気が出た。
「接吻はもう十分だから、体に触れてくれ。実は少しきついのだ」
三日月の物は先程の接吻で兆していた。鶴丸もそうだというのが、分かる。
「よし、まず、どこに触る?」
「あの時は出陣服を着ていて……首の下、この辺りに吸い付かれた。あと耳も囓られたな。その後は胸を弄られた。こちら側を舐められて、跡が付くほど噛まれて、こちら側は痛いくらい押しつぶされた」
鶴丸が「分かった」と言って順番になぞっていく。普段黒襟で隠れる場所の少し下を鶴丸が舌でなぞる。濡れた舌の感覚は似ているが、舐め方が違って驚いた。場所はほぼ同じだ。鶴丸は慣らすように何度も舐めた。その後、三日月の髪を払って、左の耳を酷く優しく、甘く控え目に囓った。そのまま耳元を舐めて、耳の中に舌を差し込む。くすぐったさに身をすくめたが、抵抗はしなかった。吐息がかすめる。その後、外耳を執拗に舐められて、少し顔を背けた。鶴丸は、両手を三日月の頰に添えて接吻してきた。三日月は目を閉じて受けた。口元で舌が触れ合った。舌を絡めたが浅く、少し物足りない。膝を少し曲げて、物足りなさを我慢した。
接吻が終わった後、鶴丸は三日月の口の端を指で拭った。その後に自分の口を手の甲で拭う。目に焼き付ける為、三日月は見つめた。
未来永劫、自分が抱かれるのはこの男だけだと――信じている。指が伸びて来て、胸の尖りを刺激する。指先でつままれ、思わず声を上げた。
「んっ……?」
刺激と言うほどの物では無いのに、じれったくてもどかしい。左片方に舌が這って、今度はもう少し大きな声が漏れた。こんな事で、と思った。鶴丸は舌では上下に舐めて、吸って、左手では円を描くように、弾いて押しつぶした。濡れたと乾いたに混乱して利き腕を動かしたが、緩く布団に押さえ付けられた。
「悪いな、噛む」
「えっ――あッ!?」
舐めていた場所を、がり、と噛まれた。一瞬、鋭い痛みが走る。噛んだ跡を大きく舐められて呼吸が乱れた。甘い疼きが、足の先から上がってくる。
(――鶴丸が舐めている。俺の体を? 鶴丸が?)
ふっと、心が温かくなった。そこで胸の痛みに引き戻された。
「うっ、あ。痛っ」
三日月が『痛いくらい押しつぶされた』と言ったからだろうか。押しつぶす力が強い。思わず声が出た。
「う……っ、っ……ッ」
「次はどうする? 三日月」
耐えていると、鶴丸が微笑んだ。
三日月は「接吻されながら、下に触れられた、いかされるまで」と恥を忍んで伝えた。「腕は? 抑えられてたか」と言われたので「頭の上で、縛られていた、術で……」と言った。言っただけで股間が疼いたし、鶴丸が目の色を変えた。
三日月は恥ずかしさに顔を背けた。
鶴丸が三日月の帯を解いて、それを使って三日月の両腕を縛った。鶴丸が三日月の陰茎を容赦なく握り込み、高めていく。三日月は喘ぎそうになるのを我慢した。
「っ……、っ」
「そうだ声は? きみはどんな調子で喘いだ? 黙っていたか?」
ともすれば楽しんでいるような、彼らしい声だった。その間も手が動いていて、三日月は上ずった声を上げた。
「あっ、喘いだ、嫌だと言った、何度も、泣きながら」
「じゃあそうしてくれ。嫌だと言って泣き叫べ」
「あっ、嫌、嫌……鶴……! どうして、主」
「主じゃない」
鶴丸が一際強く握り込んで、三日月は声を上げた。つる、つる、と何度も呼んで、刺激にぽろりと涙をこぼした。その後も涙が出て来る。
「あっ」
「こいつは驚いた。きみは泣くのが上手いなぁ。辛いのか?」
三日月は首を振った。
「あっ、違、気持ち良くて――」
「この後は?」
絶妙な加減で、ゆっくりになる。三日月は体を震わせた。
「ひ……っ」
「次は何だ?」
鶴丸の手がまた動き出して、三日月は悶えた。しばらく声が出せなかったが、何をされた、と何度も聞かれて、ついに口を突いて出た。
「っ、ああ、もっと、何度もやられた、俺が喋れなくなるまで、しゃべろうとしたら、殴られ――あっうううッ!」
押し寄せる波に呑まれて、三日月は精を吐き出した。鶴丸は手を止めなかった。
「あっ、あっつ、あつい、あう、あ、つる!」
起き上がろうとしても起き上がれない。足を大きく広げられて、ただ泣く事しかできない。あの時は部屋にも術が巡らされていて、体はほとんど動かなかった。
今は腕はともかく、足は動くはずなのに。足もどこも動かない。体の痺れでろれつが回らない。
「はぁ、ぁあ、ぁああ、つる……っ」
急に口を塞がれた。舌が入って来て三日月を温めていく。鶴丸は色々な所に触れた。首筋かじりついて、胸に触れ、脇の下や二の腕、背中に手を回してされて、うなじにも触れられた。誰も触れたことのない場所を、鶴丸が探っていく。
三日月の物は鶴丸の手の中で、すっかり濡れて、固く形を変えている。
「ぁ、あぁ……ふ、ぁ……っ、ぁっう、あ゛ぁ」
体が震えて声が抑えられない。
「ぁあ! ぁ――」
目の前が明るくなって、快楽に堕ちた。藻掻いても腕が動かない。
三日月は足を広げたまま達した。
◇◆◇
一つどころか二つも三つも、全てが苛つく。
具体的な言葉は鶴丸を怒らせるのに十分過ぎた。
「ふぁ、ひゃぁ、ぁあッ、つる、ぁッ、だ、あぁ、ぁ……っ! あッぁああ! ぁあッ!」
鶴丸の下で、三日月が乱れ喘いでいる。
何度もというから、何度もいかせて、三日月の体中を気が済むまで舐めて、ようやく息を付いた。
三日月の反応が無いのではっとして見下ろすと、三日月は息も絶え絶えで、ぐったりして、とろけた表情をしていた。口からは涎が垂れて、目は潤み、涙がこぼれて、髪は乱れて、両腕は縛られたままで、拘束は少し緩み、足も立てて開いたたままだ。萎えてしまった逸物から白い液体が垂れて敷布を濡らしている。胸には付けた覚えの無い跡が散って、首にも二の腕の内側にも噛み跡がある。
下半身に熱が集まって、今すぐにでも突き入れたいと思ったが、このまま抱くのは可愛そうに思えた。腕を解いてやると、何故? という顔をされて驚いた。
鶴丸は少しむっとして、三日月を転がした。四つん這いにして足を曲げさせる。三日月はあっさり従った。自分の手に油を垂らして、少し指を曲げて伸ばして、息を吐いて、尻の肉を広げて、真ん中の場所に指を突っ込んだ。三日月が小さく震えたのが分かった。
鶴丸は恐怖の震えと心地良さからの震えの違いが分かるようになっていた。今のは心地良さからの震えだ。油なんて使った事は無いだろう。
背中には跡も付いていないしまだ触れていない。三日月の肢体が、しなやかに揺れる様は、いくら見ていても飽きない。鶴丸はこの先、三日月を何度だって抱いて、良いように扱うのだから、初めの一度くらい三日月の為に使いたい。後ろからもヤられたかも知れないが、後で前もすればいい。
指を二本に増やして、しっかり深く入れていく。意外にすんなりと入っていくのでこの姿勢で良かったかもしれない。程なく三本に増やしても、さほど苦労はしなかった。くちょくちょと言う音がいやらしい。三日月は浅い呼吸を繰り返していて、頭を下げて、つかみ所のない敷布を掴んでいる。なるべく奥まで入れて、今度はまとめて動かすと「う゛っう゛」と鈍い声を上げた。
「三日月、起きてるか?」
「起きている……後ろからするつもりか」
「後で前もやるぞ。きみのとけた顔が見たい」
「……好きにしろ。ん、もう少し、浅い所、腹の方を押してくれ」
「ん?」
命令されたので首を傾げながらその辺りを探る。「そう、そこだ」と言われた後三日月が細い声を上げて、内側が震えた。勝手に達したというのが分かり、鶴丸は少し虚しくなった。
「丁度良い塩梅だな……三日月の中に、これを入れる場所があるって言うのは驚きだ……」
鶴丸は小さく呟いて、自分の物を更に起たせて、用意された場所へあてがった。
三日月は腰を上げてぐったりとしている。髪が逆立って、うなじがよく見える。呼吸は浅かったり、深かったり。腕は敷布に伸ばされていた。かるく拳を握っている。鶴丸が手を伸ばして触れようと思えば、その手に触れられる。手首を掴もうと思ったがやめた。
押し当てると、三日月が急に腕を動かして曲げた。
その仕草に鳥肌が立った。
腰を掴んで一気に入るところまで押し込んだ。鼠がつぶれたような、濁音の悲鳴が聞こえた。
未知の感覚に全身が震える。おかしな肉に締め付けられて、戸惑ったが、良く濡れている。この先に極楽があると分かった。はぁ、はぁ、と三日月の呼吸が聞こえる。震えながら、受け入れようと、耐えているように見えた。鶴丸は腰を掴んで、奥まで沈めようとした。
どこまで入るかよく分からない。良いと言われた場所も忘れた。体の仕組みもよく分からない。
「……三日月……! なんだこれは」
「……っ」
三日月の反応は微かだ。ただひたすらに黙って、声を出さないように耐えている。
……詰まったような呼吸音が聞こえて、彼が泣いている事に気が付いた。
少しずつ押していくと、次第に馴染んで、一番奥まで収まった。
三日月の腿に、鶴丸の浴衣が当たる。脱ぐのを忘れた。浴衣が邪魔で角度を変えると、三日月が呻いた。
「っ……つるや、良い子だ、良く出来たなぁ」
三日月が言った。明らかな強がりだ。
「ははっ、本当にな、もう動いて良いか、出しそうだ」
「ああ、いつでも――、っ!?」
中で突き上げると三日月が震えた。
「ぁあああぁッ」
引き下がると、また声を上げた。
「んっ、ん゛っ? あ、やめ、ああ゛っ――あ゛! ひ、あっあっ、あっ」
――三日月の中身がこんな風になっているなんて、信じられなかった。
「っ゛あ゛――ぁ!」
三日月が悲鳴を抑える。
鶴丸にも絶頂が訪れて、震えるままに三日月の奥に向けて注いだ。
一度で収まらず二度、しっかり注いで、ずるりと引き出した。
布団に手を突いて、視界が戻るまで何回も呼吸をして、息を整えて、三日月に声をかけるが反応は鈍い。
三日月の体を抱えて、仰向けにするとかくんと細い首がのけぞった。三日月は気を飛ばしかけていた。
「三日月」
寝かせて、声をかけるとわずかに反応がある。髪を整えてからまた声をかけた。
「まだいけるか?」
三日月は眩しそうに目を細め、瞬きを数度繰り返して、目を開いて、わずかに頷いた。すがる物が必要かと思って、自分の背中を掴ませた。その時、三日月が笑った気がする。
足を開かせ、持ち上げ、再びあてがう。
あてがう側から、残滓が垂れて来た。入りながら、鶴丸は耐える三日月を見下ろした。
夜色の髪は汗で濡れて額に張り付いている。さらさらしているのは少し長い左側の髪だ。
長い睫毛の端から、涙がこぼれて敷布に落ちる。整いすぎていて、ぞっとした。
いくら高慢でも、いびつでも。これも『三日月宗近』なのだと悟った。
鶴丸は三日月の手を取って、軽く噛んだ。
その後も鶴丸は精一杯抱きしめて、甲高い声を聞いた。
◇◆◇
「……」
三日月が目を開けると、蜂蜜色の双眸と目が合った。
鶴丸は浴衣を着ていたが、三日月は全裸だった。
鶴丸は数度瞬きして、目を擦った。
「あ……おは、よう……三日月」
気まずそうにされると困るので、もう少しはっきり言って欲しかった。
三日月は体を起こして自分の体がどうなっているか確かめたが……何も片付いていなかった。どこもかしこも濡れて、乾いている。
鶴丸の着物も乱れている。かろうじて布団を着てそのまま寝た、と言った様子だ。
「すまん、俺も今起きた所だ」
鶴丸が言った。
「いや、それは構わんが……着物は……ん、あったな」
布団の外にあった浴衣を引っ張り、肩に引っかけた。
立てるかと思ったが、足に力が入らない。尻が痺れて感覚がない。これには少し驚いた。
「さっき、骨喰が昼飯を置いて行った。それで目が覚めた」
「……昼? 朝の間違いではないか?」
「昼だって」
鶴丸は隣で伸びをして、布団から出ていく。
――終わった後、鶴丸の膝に頭を乗せて休んだ事は覚えている。
その後、再び寝転んで抱き合ったが、その時はまだ暗かったはずだ。終わりは覚えていないから、揃って寝過ごしたのだろう。
鶴丸が障子を開けると、眩ゆい光が差し込んだ。
その本丸は、京都、巨椋(おぐら)池とその周辺を模していた。
巨椋池は干拓により埋め立てられ、現在では影も形も無い。
ここは秋津の本丸より数倍広い。池の真ん中、浮島に社があってそこが本丸だ。
湖畔に浮かぶのは蓮の花。池の名前は『龍神(りゅうじん)湖』。
「見事な……」
三日月は感嘆した。
「凄いな、これは」
三日月の隣で鶴丸も喜んでいる。
三日月と鶴丸はある刀剣に誘われ、ここを訪れた。
転送され、まず見たのは蓮の花。湖面。その後、広い橋と開いた門があって、門の前に人影がある。近づくまでもなく、二振を呼んだ刀剣だと分かる。特徴的な白い姿、容姿は鶴丸と酷似しているが、鎧が違う。鶴丸国永の極めた姿だった。
「良く来たな。案内する」
三日月も鶴丸の極は初めて見る。彼が三日月達をここに呼んだ。
三日月は頷いた。鶴丸が疑問を投げかける。
「――その格好は?」
「これか。こっちが俺の本当の姿なんだ。訳あってな。呼びつけて済まない。立ち話も何だから、歩こう。しばらくかかるが景色を楽しんでくれ」
鶴丸極はさっさと歩き出す。三日月と鶴丸は後に続いた。
時の政府から戻った後、三日月は本丸への通行手形を持ち、鶴丸、山姥切と相談した。
過去の出来事は通常、一方通行。三日月の本丸が無くなった事実は、いくら調査しても、改変を試みない限り変わらない。歯車の歯が少し欠けただけで、全く意図しない結果になったり、歯車がはずれ転がっていく事もある。三日月の本丸は、今は歴史に収まった歯車だが、万が一、干渉してしまったら、取り返しの付かない事になる。
具体的には仲間の魂の行き場がなくなったり、三日月自身に何かが起こり、本丸に閉じ込められたり、存在が歪んだりする可能性がある。
そうならない為に慎重を期すべきだが、その一方、過去は既に終わった事だから、画像を再生する、あるいは本を読むように、いつ出かけても、何度見ても変わらない。
理論上、過去がすり切れる事もあるらしいが、あるとしても何億、那由多と跳んだ後の事で――先に跳ぶ方の心が枯れる。
山姥切は、A三十七の事を気にしていた。山姥切は彼と顔見知りで、さほど親しくは無いが、山姥切が年長、つまり先輩にあたるという。
この話になったのは、三日月が『長義は疲れていたようだ』と語ったからだが、それまで三日月は二振が知り合いだとは知らなかった。
山姥切は長義が顕現して間もない頃、数回、技術指南をした、と語った上で、『先日、主の引退と俺が刀解される事を話したから、事後処理で忙しいのかも知れない』と呟いた。
鶴丸が『そいつは、きみが刀解された事を気に病んでるんじゃ無いか?』と言ったが、三日月も同感だった。長義は非常に優しい刀剣だ。いずれ山姥切の生存に気付くかもしれな
い。長義は三日月の担当だから『三日月の都合を優先するように』と命令を受けているはずだ。
そんな会話をしていたら、加州が離れにやってきた。山姥切がさっと顔を隠した。
『主が話があるって』
そこで聞いたのが、この龍神湖本丸からの依頼だった。
送り主は審神者『霞(かすみ)』と連名で鶴丸国永。
鶴丸は自分が、以前街の鯛焼き屋で鶴丸の前に並んでいた刀剣だと明かして、是非、三日月と鶴丸の力を借りたいと言ってきた。火急の用件だと言うので、こうして先に訪れた。
……自分の問題から逃げている自覚はある。が、本丸が無くなり五ヶ月になる。今更一つ遅くなったところで変わらないし、未だ手がかりも少ない。今行ったところで悲劇が再生されるだけ。それを受け止める覚悟は今の自分にはない――ならばこちらを済まそうと、三日月はのんびり構えていた。
百メートルほどの橋を渡り終えて、敷地に足を踏み入れる。踏み入れた時、三日月は、おや、と思った。
「分かるか?」
「ああ」
三日月は頷いた。
鶴丸が分からない、という顔をしていたので、三日月は説明した。
「少し、空気が薄い。これはやはり……審神者の問題だな」
鶴丸極が頷いた。
「ああ。主は奥で待ってるから入ろう。広くて悪いな」
玄関も広かった。中で待っていたのは宗三左文字だった。彼が丁寧に履き物を預かる。
「宗三か? 他は?」
鶴丸極は少し驚いたようだ。
「皆、稽古場に居ますよ。他は庭で休んでいます」
「ああ」
鶴丸極が苦笑した。
「お茶は要りますか」
「いや、乱に頼んである」
「そうですか」
鶴丸極に続いて本丸の廊下を歩く。主の居室へ向かっているのだろうが、何部屋も通過した。ある場所を越えたところで、構造が変わった。今までは廊下、居室、という日本家屋に良くある造りだったが、この辺りは丸い柱が並んで、その間に龍の刺繍が入った蒼い布が垂れて居る。――神社にはこのような造りが見られる。
一つ回廊を通って、しばらくして、中央に着いた。
鶴丸が呼びかける。
「主、御仁方をつれて来た。入るぞ」
呼びかけは適当だった。三十畳ほどの板敷きの間の、一番奥に、部屋の端から端まで届く大御簾が巻いてあって、上下とも白い袿を纏った一人の女性が座っている。束髪に面布という審神者に良くある格好だ。
鶴丸極が進み出て、少し逸れて、床に膝をつく。座布団が二枚用意されていて、三日月は正面、鶴丸が横に腰を降ろした。
審神者が頭を下げた。
「三日月宗近様。鶴丸国永様。ようこそ、龍神湖の本丸へ。わたくしは審神者、霞と申します。此度はわたくしの我が儘を聞いて下さり、誠に感謝いたします。本来なら上座をお譲りするべきでしょうが、この御簾より出られないため、失礼いたします」
御簾には結界が張られていて、完全に分かれている。
「まあ気にするな。三日月宗近だ。こちらは近侍の鶴丸国永。早速だが、用件を伺おう」
「はい。鶴丸。説明を」
審神者が言って、鶴丸極が頷いた。
「分かった。鶴丸国永だ。ややこしいから『国永』とでも呼んでくれ。まずこの本丸についてだが。ここは少々特殊でな。時の政府が刀剣男士の開発中に見つけた、ある神『龍神』を奉る為の本丸だ。政府は付喪神以外の神々の力を借りようとして、ひとつ失敗した。それを帰そうと願ったところ、また失敗した上、ある条件を付けられた。案外普通、と言っては何だが、信仰――自らを奉り、神楽を捧げる事。だからこの本丸では皆が舞を嗜んでいる。俺も一応できる」
「ほう、舞か」
「ああ。年に数回なんだが――」
そこで「失礼致します」と声がして、部屋の左手、間口から極ではない乱藤四郎が入ってきた。手には盆を持っている。しずしずと、美しい所作で茶を並べる。
「おぬしは、あの時の乱か?」
三日月は尋ねた。極であったと思うが――今は特の姿だ。
乱は少し戸惑ったが、鶴丸が街へ行った時の事を話すと、乱が頷いた。
「あ……はい。そうです。僕も不具合で。街へ行ったときは大丈夫だったんですけど、今はこの姿しかとれないんです」
乱は敬語を使った。
「不具合か。審神者殿の、霊力の減少と言ったな」
これはあらかじめ聞いていた。
三日月が言うと、国永が頷いた。
「そうだ。三日月殿の主殿の本丸と近い現象が、俺の本丸で起きている」
国永の表情は明るくない。
国永は政府に調査を依頼して、そこで同様の事件として三日月宗近の本丸で起きた事を聞いたのだ、と語った。
「ただし、ここでは、今の所、手入れはできる。異常を感じたのは、一年ほど前からだ。極めた者の顕現が不安定になった。俺もそうだが、外に出ると極でなくなる。そこで政府に調査を依頼し、三日月殿の本丸の存在を知った。原因の究明を待ったが、四ヶ月前、調査の甲斐なく、該当の本丸が無くなったことを知らされた。ただ一つの手がかりだったから、俺達は必死になって他に同じ症状の場所は無いか、原因は何だと探した。まあ俺はその一環で連絡先を配って、そこで三日月殿達に出会ったんだ。近頃は外に出ていなかったら少し時間がずれていたらと思うと、ぞっとする」
そこで国永は乱を見た。乱は国永の側に控えていた。
「乱、三日月の様子はどうだ?」
国永が言った。
「うん、何とか、起きてるよ」
「詳しい話はまた、とりあえず三日月を見て頂きたい。奥で寝ている」
◇◆◇
その三日月は大怪我を負って、布団に横たわっていた。側には骨喰藤四郎と薬研藤四郎が控えている。
右目ごと、頭を包帯で巻いている。そこが少し凹んでいるのが見て取れる。首から下は見えないが首筋にも包帯が巻いてある。
「三日月、連れて来た」
国永がしゃがんで声をかけた。
三日月は思わず膝を付いて見舞った。
「なんと……」
かける言葉が見つからない。生きているのもやっと、生きていてはおかしいと言う状態だろう。
目を閉じていたが、三日月達が膝をつくと、うっすら目を開けた。
「こんな格好で、すまんな……御仁よ」
かすれた声でそれだけ言って、また目を閉じた。
三日月と鶴丸は国永に連れられ部屋を出た。
そして、少し離れた八畳の小部屋に移動する。中央に卓が置かれていて、中庭に面している。
それぞれ腰を下ろして、国永が溜息を吐いた。
「手入れはできると言ったが、三日月だけは例外だ。他の刀剣にも同じ症状が出るかと思ったが、幸い、まだ出ていない。運が良いと言えるのか、それさえ分からん。三日月は、麻酔で痛みは無くしているが……全く動けないんだ」
部屋の外から、静やかな声が聞こえる。この本丸では、刀剣達の遊びも静かだ。
「三日月は龍神のお気に入りで、三日月がいないと龍神が不機嫌になる。そっちは二ヶ月後だからまだいいが、他にも問題があってな。今は出陣を控えているが、一カ所どうしても俺達が行くべき時代がある。その時代に関して、主はこの本丸より、三日月殿の方がふさわしいのでは無いかと、そんな託宣を得ている」
国永は三日月に頭を下げた。
「三日月殿。どうか、手伝ってくれないか? 御仁の本丸についても、詳しい話を聞かせて欲しい。三日月の傷では、もはや自然治癒も見込めない。あれで保っているのは三日月が龍神のお気に入りだから、龍神の力で折れずにいるだけだ。三日月を放置している俺達に、龍神は怒っている。政府の審神者も呼んだ。だが、無理だった。外に出せば三日月は折れる……! どうか、頼む!」
必死の懇願に、三日月は直ぐ頷いた。
「あいわかった。何とかしよう。まずは、手入れ出来ぬか試してみるが……よいか?」
◇◆◇
三日月はまず、三日月宗近――『宗近』と呼ぶことにする――の容態を診た。
部屋には鶴丸と、国永、薬研と骨喰がいる。
薬研が状態を説明する。
「三日月は半年前、出陣先で大怪我を負って、一度破壊され、御守りで蘇生した。本丸に運び込まれた状態のまま、今に至る。落とすところは落として、縫える傷は縫ったが、内臓の欠損と、頭の傷が致命傷だ。そもそも三日月は龍神の加護……ぼやかすのは良くないな。寵愛を受けていて……まあ寵愛と言っても形だけの物で、神楽を奉納した後、社で一晩過ごすだけだが……おかげで滅多な傷では……というか折れるはずの傷を受けても折れないんだ。重傷でも帰還すれば手入れで治る――だからこの本丸には危ない任務が回ってくる。龍神の加護を受けているのは三日月と、三日月の伴侶である鶴丸の旦那もそうだ。二人は龍神の前で結婚した。神楽は交代で、半年前の宴では鶴丸の旦那が舞ったから、次はどうしても三日月の番だ。極の御守にしておけばと、主が泣いて大変だったな……」
薬研が溜息を吐いた。疲れているようだ。
国永が布団に触れる。
「三日月、少しめくるぞ」
国永が半分ほどめくると、体の状態が見て取れた。
三日月ははっとした。
「これはどんな戦いだったのだ」
「――馬上での戦いだが、検非違使に囲まれ、滅多刺しだったらしい。俺も出ていればと何度も思った。その戦いで三振りが折れた。残った二振、一期と御手杵が三日月を連れ帰った。他の三振は回収できていない」
国永が言った。
「検非違使か……多かったのか」
三日月は呟いた。
国永は頷いて、続けた。
「あの時代は、放棄寸前なんだ。だから毎回、検非違使が出る。だが、あの時は尋常じゃ無かったと聞いている。一期の報告では数はおよそ百二十騎。三日月は隊長だったが……政府は三日月の敗退を聞き放棄を決定しかけた。それを主が止めた。託宣があったからな。主は優秀な巫女で、今、龍神と交信できる唯一の人間だ。三日月は社に籠もれば直接会話ができるらしいが、俺にはだんまりだ。嫌な感じはしないんだがな……それこそ気に入りの刀剣の旦那をもてなしている、とかそんな感じで色々世話になってる」
「半年前か……」
三日月は『もっと早く来ていれば』と思ったが、丁度自分が追放された時期と重なる。
「……わかった。まずは手入れだ。長丁場になるが、どこまで手入れができるかは分からん。期待はするな。先だって審神者殿に確認したい事がある。ついでに許可を得て来よう。皆、ここで待て」
◇◆◇
――三日月が部屋を出た後、鶴丸は詰めていた息を吐いた。
先程、宗近の傷を見たが、これは折れていなければおかしい。
右腕は肩からなかった。左腕だってあるか怪しい。頭蓋はかなり陥没していて脳も欠けている。包帯の下に右目は無いのだろう。痛み止めがあっても話せる訳が無いのだが、これが『龍神の加護』なのだろうか? こんな状態でも折れる事ができないのは……逆に呪いだと言いたくなる。
「検非違使か……見たことは無いな、どんな相手なんだ――?」
鶴丸は声をひそめて尋ねた。
検非違使の事は聞いていたが、実際に見た事は無い。国永に『そんな場合では無い』と言われたら謝るつもりだった。
国永が鶴丸の呟きを拾って、口を開いた。
「検非違使は練度の高い者に合わせて強さを変える。あの時の部隊は、極が混じっていて、三日月、一期、御手杵が最高練度。折れたのは鯰尾極、堀川極、長谷部。主は偵察の為に脇差を入れたのが失敗だったと言うが、そんな事は無い。脇差の働きが必要な任務なんだ」
国永は、意外にしっかりした声で答えた。
『鯰尾』と聞いて鶴丸は側の刀剣を見た。
骨喰と薬研、一期一振も粟田口だ。加州の本丸に鯰尾がいるが、明るく素直で気持ちの良い刀剣だ。骨喰も薬研も兄弟を失ってさぞ悲しんだだろう。
「そうか……だが、なぜ三日月に任務まで頼むんだ? 相手が百二十騎の軍勢でも、こちらは二振だ」
鶴丸が言うと、国永が同意した。
「そうだな。主が事態の打開を願って、龍神に伺いを立てた。知恵を借りるという感じか。それで出て来たのが、審神者なる三日月と、政府の刀剣、山姥切長義の名前だ。長義が彼の目付役って事を調べて、彼に頼んで審神者の三日月を探して貰っていた。あの三日月、いや、御仁にはある噂があって……」
そこで三日月が戻って来た。
◇◆◇
――審神者に手入れの許可を取った後、三日月は部屋に戻った。
『それで彼が助かるなら。どうか、お願いいたします……!』
審神者『霞』は三日月に頭を下げた。三日月は「最善を尽くそう」と答えた。
審神者の許可を取ったのは瀕死の宗近と性交する可能性があったからだ。
――それは本当に最後の手段、あくまで可能性だと伝えた。
部屋に戻った三日月は骨喰と薬研に一時席を外すように頼んで、鶴丸と国永には残るように言った。
国永が薬研に確認する。
「麻酔は?」
「あと二時間は保つ。切れるようなら呼んでくれ」
薬研が答えて、国永が頷いた。国永の手元にはボタンだけの機械がある。
「まず本体をよく見せて貰いたい」
三日月は言った。
本体は床の間の近くに、白布を敷いて置いてあった。
敷かれた白布には赤黒い染みがあって、固い鎧を叩き斬ったのだろう。刃はぼろぼろに欠けている。柄には血がにじんでいて鞘は無い。
国永が見下ろして歯を食いしばった。
「あの時置いたきり、恐くて持ち上げられない」
「……なるほど。触らんが、視るぞ」
三日月は手をかざして、様子を確かめた。目を閉じると、消えそうな弱い光が見えた。それを守る大きな光――大きな、龍の形が確かに見える。これが龍神の加護だろう。
弱り切っていて、下手に霊力を注げない。
「なるほど。確かに龍神の加護が見える。三日月の輝きは酷く弱い。この刀の手入れは俺では無理だ。龍神の力にはじかれる。だが……」
三日月は鶴丸の隣に戻った。向かいに座る国永に目をやる。
「国永よ。俺は今から三日月――いや、宗近と呼ぶか。宗近を手入れする。できるかは試さなければ分からん。だがかつて同じ状況にあった俺の本丸では、俺が顕現した刀剣には手入れが効いた。宗近に効くかは分からぬが、試してみよう。国永は浮気に寛容か?」
「浮気?」
三日月の言葉に国永が首を傾げた。三日月は頷いて、今は三日月の左隣、障子の前に座る鶴丸を見た。
「鶴丸にも迷惑をかける。霊力が切れたら協力してくれ」
「分かった」
鶴丸は心得た様子で頷いた。
三日月は鶴丸を見て微笑み、再び一度国永を見た。
国永がきょとんとしているので説明をする事にした。
「俺の手入れは、刀本体にもできるがそちらは下手でな。宗近は折れかけだ。体に霊力を注いでやらねば……まずは接吻と、場合によっては、それ以上の事もせねばならん……が、意識があるなら、接吻で様子を見る。いきなり精を注いではそれこそ毒だ。少しずつ、ゆっくり馴染ませ、治していこう。良いか?」
「――接吻?」
国永は話が見えないようだ。いきなり言われて目を丸くしている。少々幼げな表情は、これが国永の素なのかもしれない。
隣で鶴丸が立ち上がった。
「まあ、君は見ない方がいいぜ。三日月、まずは試すんだろう。俺達は外にいる。どこか部屋を借りておく。近い方がいいか?」
鶴丸が言った。話が早くて助かった。
「ああ、そうしてくれ――いや、少し離れた、静かな部屋がいい」
三日月は言い直した。
「分かった。じゃあ……そこの縁側で待っている。初めの一回で駄目ならどうしようも無い。終わったら教えてくれ。行こう」
鶴丸が戸惑う国永の手を引いた。
「頼んだぞ」
三日月は微笑んだ。
◇◆◇
部屋から出た鶴丸は縁側にあぐらを掻いて座った。
暦の上では冬のはずだが、この本丸も桜が狂い咲いている。
これが普通なのか鶴丸にはまだ分からない。
「……治るといいな」
鶴丸は宗近の怪我を思い出して呟いた。
――鶴丸の左隣に国永が腰を下ろした。こちらは正座している。
「……事情はよく分からないが、感謝する」
「それこそまだ分からない。俺は何もしないからなぁ……はぁ」
鶴丸は溜息を吐いた。
鶴丸は、軽く説明するか、と思って口を開いた。
「三日月は、手入れが下手、って言ってるがそこまでではない筈だ。俺の刀は普通に手入れが出来る。ただ他の審神者の刀は苦手だって言ってるな。普通の手入れの他に、接吻、口婬、性交、まあつまり、体に触れて霊力を渡す事が、得意なんだと」
鶴丸は膝に右肘をついて、頰を支えた。
そのまま、国永の返事を待たずに続ける。
「……三日月自身の霊力は、審神者としては大した事が無いらしい。しょっちゅう霊力切れでふらつくし、熱も出してたな。あと霊力が減るとよく寝るし、大食いになる。三人前は平らげるから用意してくれ。俺の役目は三日月の霊力補給だ。今まで手入れの度にまぐあうのはどうなんだって、接吻以外は避けて来たが、そろそろ喰われそうだな。まあ、覚悟を決めるか……」
鶴丸は一人ごちた。
「――避けて来たのか?」
国永が言った。
「ああ、三日月が嫌なわけじゃない。が癖になるのは不味い。接吻で済む時は、それで済ませた方がいい。俺が勝手に思ってるだけだが」
「なるほど。確かに、癖になるのは不味いな」
国永が言った。
鶴丸は苦笑した。
「瀕死の重傷で抱かれたら死ぬぜ。やさしくして貰えるとしても、さすがに無理だ、逆もできる気がしない」
「逆ってのは……?」
国永が呟いた。
鶴丸は三日月自身の手入れにも、接吻や性交が効果的だと伝えた。
「三日月の場合は、それ以外に方法が無いらしい」
「なるほど……それはきついな。重傷の恋刀を折らずに抱くって、相当だぞ」
国永は宗近の状態を思い出したのだろう。「俺には……無理だ。できるかもしれないが、折れそうだ」と呟いた。
「しかし、薄情に聞こえるが……お前さんの本音は違うんだろう?」
国永が言った。
「本音?」
鶴丸は首を傾げた。国永が口の端を上げた。
「君はあの御仁が好きだから、いくらでも抱ける。だが、手入れを理由にするのが恐い。違うか?」
「――」
鶴丸は頭を抱えた。さすが自分と言う他ない。見事に図星を突いてきた。
……鶴丸は今では、三日月の事が好きでたまらない。
凛としているようでどこか抜けているところ。優しいところ。変わりやすい感情や表情。抱きしめたくなる体。匂い立つ肌、月の浮いた瞳……。
三日月は誘って来るが――義理で抱いたと思われたくない。
鶴丸の様子を見て、国永が控え目に声を上げて笑った。
「ははは。ご愁傷様。おめでとう、と言ってやろうか? 俺は惚れた方だからなぁ。全く羨ましい限りだ。しかし意外だな。あの大層な御仁が顕現したての君に惚れたのか?」
……意外そうに言われても、良い仲ではないし好き合ってもいない。
鶴丸は溜息をついた。
「いいや、三日月は初めから俺を好きになろうとしていた。俺達は二振きりだから、俺を伴侶にするんだという――固定概念? みたいな――俺と三日月は人で言う所の、許嫁、みたいなもんだ。俺達はまだ仲間がいない。だから三日月は俺を好きになりたいのさ」
鶴丸は襟足を撫でた。気恥ずかしいのは仕方ない。鶴丸は国永とどうしてこんな話をしているのだろう、と思った。国永が同じく『三日月宗近』を愛しているからだろうか。
すると国永が思いっきり眉をひそめた。
「はぁ? いや馬鹿言うなよ! 俺は三日月の表情なら良く知ってるが、あれはそんな生優しい目じゃない。君に心底惚れきった目だ」
「まさか」
鶴丸は虚しく笑った。
……鶴丸には三日月の気持ちがまだよく分からない。
三日月は、簡単に本音を打ち明ける刀では無いのだ。ただ抱く事を求められるが、それは不味い。
――鶴丸は一つ、自分の感情で困っていることがある。良い機会だから、今夜にでも打ち明けるつもりだ。
乾いた笑いを収めて、鶴丸は続けた。
「そう言う訳だから、なるべく静かな部屋を用意してくれ。というか離れた部屋だな。近くに風呂があれば言う事はない。三日月は照れ屋でな、絶対に口外するなよ。もし三日月がいたたまれない思いをするようなら……分かるな?」
国永は即座に頷いた。
「――分かった。治療の際は誰も近づけない。ちょうどいい部屋がある。風呂付きだ。飯も最高の物を提供しよう。部屋の前に箱膳を置けばいいか? なるべく関わらないから、二人きりで過ごしてくれ。掃除や世話は骨喰か、俺か、薬研にさせよう。いや、薬研は三日月についてなきゃいけないから、俺か骨喰、それか乱だな。どうだ」
「話が分かるな、さすが俺の先輩だ。極だとは思わなかったが……」
「外に出ると戻っちまうんだ」
国永が苦笑した。
「まあ、鯛焼き奢って貰ったし。その節はありがとう。初めて食べたんだが、美味かった」
「ああ気にするな――ずっと思ってたが、君はやっぱり初々しいな。その良さをぜひ大事にしてくれ! あの時は三日月が食いたいと言ってな。急いで買いに出た。結局匂いを嗅いで満足したが……本当に、少し入れ違っていたらと思うと……ぞっとする――じゃあ、部屋を用意して来る」
国永が立ち上がりかけたが、鶴丸は袖を引いた。
「あ、いや。結果が分かってからでいいぜ。そうださっきの話だが、三日月の噂って何だ?」
鶴丸は気になっていたことを尋ねた。
立ち上がりかけた国永が、動きを止めた。
「ああ、あれか。本人に聞いた方がいいんじゃないか」
「分からなければ聞きようが無い。三日月ははぐらかすのが上手すぎる。同じ刀のよしみで少し教えてくれ」
鶴丸は言った。三日月は自分から何かを話す事が少ない。必要な事は教えてくれるが、まだ知らない事が沢山ある。主の本丸を出て自分の本丸を持ったと言うが、その話は全くしない。噂になるような事があるなら、尚更言わないだろう。
国永が渋々口を開いた。
「そうだな……ある時、政府の部隊が検非違使の大群と遭遇した。その作戦では多くの刀剣が出陣していたが、生き残りはただ一振。それがあの三日月宗近だって話だ。これ以上は彼に聞いてくれ」
◇◆◇
――淡い光が収まった後、三日月は同じ顔から舌を抜いた。
三日月はほっと息を吐いて、意識の無い宗近を見下ろした。
初めの手入れは上手く行った。これなら、時間をかければ回復できる。開いた口をつぐませて、手ぬぐいで拭ってやった。接吻だけでは全快は難しいが、良い所までは行けるだろう。頭の傷が気に掛かる。まずは宗近の体力を戻さなければ、傷を治すことも叶わない。
三日月は過去の戦を思い出した。
怪我をした仲間――同じ三日月だった――の太刀に、急激に霊力を注いで怪我を治した結果、窮地を脱したが、戻る直前に彼だけ折れた。あんな思いはもうしたくない。
……三日月の体は霊力の塊で、言うなれば劇薬だ。
まともに手入れしたら折ってしまう為、なるべく力を抜いている。
三日月は加減が下手すぎて、いくらやっても調整出来ないから、遠回しな接吻や性交くらいが丁度いい。
性交抜きで三日月の霊力に耐えられるのは鶴丸だけだ。
あれほど霊力を注いでも、まるで痛がらず、うんともすんとも言わない刀は珍しい。
三日月は言うのを控えていたが、鶴丸を主が顕現できなかったのは、おそらく単純に霊力が足りなかったからだ。
そもそも、なぜ三日月が審神者の力を持ったのか?
三日月は全く普通の主に呼び出されて全く普通の三日月宗近として顕現したはずなのに。
政府のとある審神者は『分量間違え』『あるいは混入』ではないか、と語った。
審神者は三日月を隅々まで調べ、こう述べた。
『固く結ばれた、幾振りかの三日月宗近の魂が……、どこかの審神者を巻き込み、消えたと仮定して。それが離れる事なく、運良く安定した状態で、依り代に降ろされた……? それくらいしか、思いつかない』と。
恐ろしい奇跡だ、人為なら尚恐い、これは刀剣男士ではないと言われた。
――それが事実なら、全く迷惑な話だ。
刀解が決まった時、まあ良いかと思った物だ。一度戻って、道具として生きる方が楽に思えた。翌朝を心待ちにした。
しかし政府の審神者は誰も三日月を刀解できなかった。
三日月には鎖が絡みついていて、どうやっても依り代と魂が離れないのだという。
政府は躍起になってありとあらゆる方法を試した。
三日月は不死身では無い。衝撃を受ければ折れるし怪我もする。主以外の手入れは受け付けない。政府は破壊しようと試みたが、なぜか失敗された。
……三日月自身は、その時、何があったか覚えていない。
それはいい。もう怒っていない。三日月は何にも怒っていないし、政府に何も期待しない。
唯一欲しがって期待しているのは鶴丸なのだが……どうも煮え切らない。
三日月はあの刀剣が何を考えているのか全く分からない。
手入れの度に接吻して、鶴丸にも『淫乱な刀だ』と嫌われているのかもしれない。
急いている自覚はある。鶴丸にしてみれば顕現して二月そこそこで、性交云々言われても困るだろう。
三日月は苦しくなった。
溜息を吐いたが、鶴丸との事と、宗近の治療は別問題だ。
……『鶴丸国永』と幸せに生きている『三日月宗近』なら、是が非でも救いたい。
三日月は『三日月宗近』に対して特別な感情を抱いていた。自分だから当然なのだが、いつだって彼等の優しさに救われてきた。彼等の事を思うと胸の内が温かくなる。
三日月は微笑んだ。
「三日月宗近よ。必ず助ける故、もう少しの辛抱だ」
部屋を頼んだが、そこへ行けるのは少し後かもしれない。
三日月は立ち上がって、障子を開けた。
――それから五日が過ぎた。
三日月はずっと宗近の側にいて、寝泊まりは隣の部屋でしていた。手入れはできたが回復が遅く、宗近の側を離れられなかったのだ。
おかげで宗近の状態は大分良くなった。顔色も良くなり、細かな傷は消えていた。会話も少し流暢になったが、ここ数日は眠らせてある。薬研が『薬の効きが良くなったし、血も止まった』と喜んでいた。国永はずっと離れない。
途中から鶴丸も部屋に入り、霊力の補給を手伝ってくれたが、体の疲労はどうしようもない。鶴丸はまだ元気そうだが、三日月が明らかに疲れていたので、国永が休息を勧めてくれた。
宗近の容態は安定しているから、一日、二日程度ならこのままでも問題ないと伝えた。
上手く立ち上がる事ができなかったので、鶴丸の手を借りた。
◇◆◇
三
国永が用意した部屋は、宗近の部屋から大分離れた場所にあった。
鶴丸は三日月を支えて、廊下を歩いていた。
「疲れた……」
三日月は部屋に着くなり布団に倒れ込んだ。
「大丈夫か?」
鶴丸はうつぶせの三日月を気遣った。
三日月は枕に顔を埋めて、何かもごもごと呟いた。
「年寄りには堪える」とかそんな事を言っている。
鶴丸は微笑んだ。
「良く頑張ったな」
鶴丸は三日月の頭をそっと撫で、しばらく背中をさすってから、掛け布団を引っ張った。
この部屋には布団が一つしかない。綿の布団は大きく軽く、いかにも温かそうだ。
敷き布団に腰を下ろしてみる――綿の良さがよく分かる。三日月の呼吸は穏やかで、直ぐ眠りそうだ。
三日月は藍色の着物を着ている。これは宗近の着物だ。三日月は今でこそ食事も睡眠も取っていたが、二日目までは徹夜していた。
三日月は一昨日から、一時間に一度くらいの頻度で接吻を繰り返していた。流石に夜中は休んだが、禄に寝ていない。鶴丸も霊力が減っている実感は無いが疲れてきた。
……三日月と宗近が接吻すると、互いの体が淡く光る。黄色みを帯びた温かい光だ。
鶴丸と三日月が接吻すると、こちらは互いに白く光る。
霊力は刀剣によって性質が違って、それが色の変化に現れているらしいが、ここまでしっかり見えたのは初めてだ。宿で軽傷の手入れした時は、もっと光が薄かった。
おかげで宗近は快方に向かっている。
様子を見て手入れ部屋に入れる案もあったが、審神者の力は戻っていない。
三日月も『俺の霊力に満たされているから、今、審神者の霊力を混ぜるのは良くない』と言った。三日月は疲労が回復したら、傷を治していくという。その後なら試す価値はあるが、頭の傷も、腕も、全快できるだろうと語った。
『御仁は本当に凄いな……! 感謝する!』
『ははは』
国永はすっかり三日月に懐いたが、その鎧はずいぶんすっきりして、鶴丸と同じだ。
――昨日、国永は極の姿を維持することができなくなったのだ。最後に残った極は骨喰だったが、同日夜、彼の姿も特に戻った。
……全員が極を維持出来なくなったことで、霞の本丸は方針を変えた。
手入れが出来ない事、極が維持出来ないこと。重大すぎる理由で『可能なら、任務の引き継ぎが可能な本丸を探して欲しい。見つからなければ、時代の放棄もやむなし』と政府に連絡を入れた。
今は返事待ちの状態らしいが、国永は『やりたいって本丸は何処かにあるだろう』と語っていた。表情はあまり明るくなかった。政府は検非違使を恐れている、らしい。
「ゆっくり休め」
三日月だけ寝かせて鶴丸は新しい布団でも出すかと思ったが、無言で袖を引かれた。
「……仕方無いな」
鶴丸は溜息を吐いて、三日月の右側に潜り込んだ。ご丁寧に枕は二つある。
三日月が、はぁ……、と長い息を吐いた。疲れた溜息だ。
三日月が枕を外れて、鶴丸の側に寄ってきた。三日月は鶴丸の腰に腕を回し、鶴丸の胸に頭を寄せた。
――鶴丸も三日月の背中に手を回した。
三日月は背中を曲げて布団に潜り込んでいるので、鶴丸に見えるのはつむじだけだ。
抱き合ったまま、鶴丸は笑った。
「全く、この五日で、飽きるほど接吻したなぁ。口が疲れただろう?」
「ああ……唇が乾いた」
三日月が答えた。
三日月は宗近とも接吻しているから、鶴丸の倍だ。減る物では無い……と思えば良いが、大盤振る舞いだ。
「薬研の薬を塗ったか?」
三日月も鶴丸も唇を腫らしていたので見かねた薬研が軟膏をくれた。唇に塗っても良い物で、少し草の香りがする。
「あれは味が悪い。蜂蜜がいい」
三日月は蜂蜜も試していて、そちらがお気に入りらしい。蜂蜜を見て『鶴の目のようだ』と言って笑っていた。
「蜂蜜は甘いが、あまり好きじゃないな。手に付くとベタつく。なあ、三日月。このまま接吻だけで治りそうなのか?」
鶴丸は尋ねた。すると三日月が顔を上げて、枕に頭を乗せた。
「実は、厳しい」
「……そうか」
鶴丸は言った。そんな気はしていた。だが疑ってもいる。三日月は何かと理由を付けて鶴丸に触れてくる。嘘だと分かる時もある。
「だが、きみ、それは本当か? きみは何かと触れたがる」
「実を言うと、分からぬが、あまり悠長な事はできん。滞在が長引けば政府に知られる。出陣に手を貸せと言われたが……さて、どうするか……」
「そっちは取りやめじゃないか?」
「どうだろう。俺が居ると分かったら、無理に押しつけるかも知れん」
「きみ、そんなに仲が悪いのか……?」
鶴丸は言いながら首を傾げていた。
三日月の顔が、今日はやけにはっきり見える。部屋が明るいから、と思ったが灯りは全く点いていない。三日月が光っているわけでも無い。
目を擦って、体を起こしてみた。周囲を見ると、暗い部屋の様子もよく見えた。
「つる?」
三日月が少し眠そうにする。
「なあ、今日はきみの姿が実によく見える。畳の目や縁の模様も、まるで昼みたいに見えるんだが……暗いよな?」
辺りを見回すと、掛け軸の絵が見えた。鶴丸は目を擦った。自分の手も良く見える。
「手入れの後、こういうことはあったんだが、これは何だ?」
「そうか、鶴はやはり夜目が利くのか。目が光っておるぞ」
三日月が微笑んだ。
「えっ、光ってるのか!?」
「ははは、まるで猫だなぁ」
三日月がおっとりと言って、手を伸ばして来た。
「なあ鶴、鶴は俺の事が嫌いか? いつになったら抱いてくれる?」
三日月は眉を下げて不安そうにしている。
鶴丸は溜息を吐いた。
「別に嫌いじゃ無いぜ。そのつもりもある。でも、今はまだ、もう少し考えたい。ずっと気になってたんだが……何て言えば良いのか、実は――」
鶴丸は、自分の悩みを伝える事にした。
「きみを抱けないって言うのは、俺がきみをどう思っているか分からないからだ。いや、分かって来たんだが、それだけじゃなくてな……俺はきみを主だから好いているのか、そうじゃないのか、いまいち区別が付かないんだ。正直、きみのことはかなり、大好きなんだが、恋愛かと言われると……ああ、違う、確かにきみの事は好きなんだ」
鶴丸は赤面した。自分は何を言っているのだろうと思った。結局『三日月が好きだ』と言えば済むことだ。
それを認めてしまったら、取り返しが付かない気がして、ためらっていた。
すると三日月が体を起こした。
「鶴丸。おぬしには言っていなかったが、刀剣男士には『領分(りょうぶん)』という物がある」
「りょうぶん?」
初めて聞く単語に鶴丸は戸惑った。
「刀剣男士が持つ、本能のようなものだ。ふむ。例えば……」
三日月は語った。
一つ、刀剣男士は理由無く人を傷付ける事が出来ない。
一つ、刀剣男士は主の命に従う。
一つ、刀剣男士は、刀剣男士間では問題ないが、審神者に対して恋愛感情を持つ事ができない。これは主だけではなく、他の審神者に対しても同じである。その他一般人、政府職員に対しても同じである。
神と人は相容れない。寿命も違いすぎる。痴話喧嘩、刃傷沙汰、虐待、自殺などを防止する為の仕組みだ。三日月は鶴丸がためらっているのはそのせいではないかと語った。
「俺は刀剣男士だが審神者ゆえ、余計に戸惑っておるのでは?」
鶴丸はなるほど思った。確かに、審神者と恋愛ばかりでは戦が滞りそうだ。
「そんな物があるんだな。だが、それと、俺がきみを好きだって事はおそらく関係が無い」
鶴丸ははっきり言った。
もう既に『好きだ』と言ってしまっているのだが、鶴丸が言いたいことはまだ他にもある。
「手入れの度に熱をもてあますのは、俺は不味いと思ってる。きみだって昼間は普通に接吻しただろう。そういう風じゃだめなのか。宿でしたみたいに、抜き合いまでする必要があったのか。色々教えてくれた事には感謝しているが、もう少しわきまえてくれ」
鶴丸は溜息を吐いて、大人げない――と思いながらも思っていた事を吐き出した。鶴丸に大人げがあるかは置いておくとして。三日月に自慰を教えられて、鶴丸はなんとも言えない気持ちになったのだ。
接吻の後熱をもてあましても、抱く気がないとはっきり言えば、三日月は仕方無いといった風で、横になってくれたが……どれだけ恥ずかしかったか分からない。
よく我慢したと思う。少しくらいは怒ってもいいと思う。
……与えられる愛情は嬉しかったし、三日月を『愛しい』と思う気持ちもある。
だが、それが三日月が主だからか、鶴丸が三日月を好きだからか、本当に分からなかった。
「いいかい、物事には順序って物がある……全く、何が悲しくてきみに説かなきゃいけないんだ……」
鶴丸は布団に顔を埋めた。
「では鶴は……やはり」
三日月は座ったまま、項垂れた。
「困っていたな」
「ぁぁ……そうか。性急だったな」
三日月は悪い事をした自覚があるようだ。
それは鶴丸にも伝わっていた。
一々『すまん』『悪いな』『我慢してくれ』と言われ、申し訳無そうに触れられて、どういう反応を返せばいいのか分からなかったのだ。
「いいや、嫌だと、はっきり言わなかった俺も悪い。だいぶはっきり言った気もするが。ここは一つ仕切り直しだ。今までの事は忘れよう。きみは疲れてるだろう、一先ず横になって、寝るといい」
すると三日月が固まったまま、眉をひそめた。
「おぬし、そうやってまた逃げるのか?」
「いや、もう逃げないが、きみは今、ふらふらだ」
「それが逃げていると言うのだ――意気地無しめ」
恨みの籠もった口調だった。鶴丸は思わず反論した。
「はぁ? きみ、それはあんまりじゃ無いか、俺は今日、もうそういう気分じゃ無いんだ」
「……気分? 鶴は気分で抱くのか? 俺がどんな想いで鶴を待っていたか……そうか、知らぬからそんな口をきけるのだな。よかろう。朝まで延々話してやる」
三日月の言葉に鶴丸は焦った。
「なっ、馬鹿、寝ろ! ぶっ倒れるぞ」
「知ったことでは無い」
「――それはだめだ。宗近が助からなくて良いのか」
「宗近は助かる。俺は助からん。鶴に軽蔑されていた俺の気持ちが分かるか。年甲斐も無く舞い上がって、自分を止められなかった。ああ、皆、俺の事が嫌いなのだ! 俺は真面目にやっているのに、皆が俺を淫乱刀剣だと言う!!」
「それは酷いが、きみは意外にめんどくさいな」
「面倒? 面倒と言ったか? めんどう、これは我が儘だ。鶴は俺の言うことを聞け」
「……言う事? 何をしたいんだ?」
「何もしとう無い!」
ついに三日月はそっぽを向いた。
「えっあ、ちょ、落ち着け、なあ三日月……!」
鶴丸は溜息を吐いた。
これを収める方法はただ一つ。
「……俺はきみが好きだ。それだけはもう分かっているから、どうか許してくれないか」
顕現して約二ヶ月で、鶴丸は引く事を覚えた。
◇◆◇
「分かれば良い……俺も悪かった」
三日月はそう言って、溜息を吐いた。その後、急に機嫌が直り、穏やかに、嬉しそうに微笑んだ。
三日月はさっさと布団に横になって「鶴も寝ろ。なあ……俺の事を好きと言ったか? 聞いたぞ。なあ好きと言ったのか? 聞こえたぞ」と三回は繰り返した。
「間違いは無いな?」
「あー、間違い無い。確実だ。明日辺り抱いてやるから、安心して、早く寝てくれ」
鶴丸は三日月の肩を撫でながら言った。三日月は目を輝かせている。
「言うたな? 俺は聞いたぞ」
「言ったし、聞かれたな……」
鶴丸は苦笑した。三日月を抱けるのだろうか、と考えて、腕の中を眺める。
三日月は嬉しそうで――無邪気で、しかしどこか捉えどころの無い表情をしている。
鶴丸は抱きしめる腕にほんの少し力を込めた。
「あ。そう言えば――かだいって何だ?」
「かだい?」
鶴丸は山姥切に聞いた話をした。すると三日月が笑った。
「ははは、うん、課題か。そう言えば、そんな夢を見たな。うん、よく見る。審神者の勉強をしていた時のことだなぁ。もう終わったのに、未だに見る……枚数が足りているのに、足りない夢とか、遅刻する夢も見るぞ」
……国永に聞いた噂について尋ねると、三日月は眉を下げた。
「そうか、聞いたのか。悪いが、その話は、あまりしたくない。俺の失敗で、俺以外、全滅した」
静かな声だった。
「……全滅か」
鶴丸は天井を見ながら相づちを打った。
「ああ。全滅だ。手入れは主がしてくれたのだが、主に会ったら何もしたく無くなった。心を病んでしまい具合も悪かった。だから我が儘を言って本丸に戻った」
三日月も仰向けになって天井を見ている。近代的な電灯が吊されていた。
「きみは大変だな」
「うん。大変だ。おかしいと思ったのは――初めからだな」
三日月がぽつぽつと語る。
「演習で、三日月宗近に出会うとな。皆が俺を『御仁』と呼ぶのだ。初めは単なる呼びかけだと思っていたが、どうも違うらしい。恐ろしい事に、三日月は皆、俺をそう呼ぶ――あらかじめ刷り込まれているように。何が違うのか、どう違うのか。俺は恐かった。三日月達にも理由は分からぬという。ただ、俺が俺だと分かるのだと。本霊の号令では無いかとか、色々言われたが、結局分からぬままだ。政府の連中は俺を嫌っているからな。本霊には近づけない。俺が何かすると思っているのだろう」
「きみは色々、悪い事をしそうだからな。本霊をたたき割ったりとかしないよな」
鶴丸は苦笑した。
「ははは――そうだなぁ。沢山悪い事をした。懐かしい」
「そこは返事をしてくれ」
「殴りたいとは思っている」
真面目に言うので鶴丸は笑った。
三日月の方を向くと、ちょうど目を閉じていた。眠るのかと思って三日月の方を向いて、彼の頰にかかった髪を払う。寝姿をずっと眺めていたいと思ったら、三日月が目を開けて、こちらを向いた。
「つる。ひとつ話す事がある」
「……何だ?」
「俺はな、本丸を追い出された時、主と通じた。主は自分の行いを後悔して死んだのだと思う。今まで嫌だ嫌だと言っておぬしを待っていたのだが、結局、主に食われてしまった。初物でないから、好きな時に抱いてくれ」
三日月はやっと言えた、と溜息を吐いた。
途端に、鶴丸はかっと赤くなった。
「――なんだって、きみ……」
鶴丸は動揺した。心臓が凄い音を立てた。止まるかと思った。
三日月は今なんと言った?
主と通じた?
「待て、さっき、領分って」
「審神者に制限は無い。罰はいくらでもあるが、効かん時もある」
その言葉で、今までの色々な事が一気に腑に落ちてしまった。
三日月があんなに泣きじゃくったこと、山姥切が協力した事。
性交が必要、と明け透けに言うから経験を積んでいると思っていた。
思わず三日月の着物を引っ張った。
「待て、寝るな、三日月」
「何だ、俺は眠い」
「きみはいつから、俺を待っていた?」
「ん、言うたと思うが――おらんかったか。まあよい。演習で余所の鶴丸を見てな、真っ白でなんと美しいのかと、一目で気に入った。運良く拾えて、それからだ。毎日話掛けておったが、中々起きなくてなぁ。こんな事になってしまった。すまんな」
鶴丸はひゅっと息を呑んだ。
……そう言えば、鶴丸を拾った経緯は、顕現初日に聞いていた。
だがその時とは全く意味が違う。鶴丸は肘を付いて体を起こしたが、三日月はこちらを向いて横になったままだ。
「審神者とは、どうやって通じた? ちゃんと想い合っていたのか」
これだけ一途な三日月が、浮気をするとは思えない。三日月は政府へ行く時、鶴丸に聞かれたく無いと言った。その時は何か余程の事情があるのだろうと――正直言って、あまり気にしていなかった。
何があっても三日月なら大丈夫だと。実際に三日月は無事戻って来た。
鶴丸は三日月の肩を掴んだ。
「追い出された日の事を教えてくれ、言いたくないって、何があったんだ!」
三日月は苦笑した。
眉を下げて、仕方無いな、と言うような。少し笑っている。
「――俺がうかつだった。それだけだ。どうせ、本丸へ行けば見る事になる。その時見れば良い。今は審神者の執念に免じて、許してやろうと言う気分だ」
「……っ」
「俺を犯して死ぬとは天晴れだ。さすがは俺の主、とさえ思うな。今こうしておぬしと、温かい布団で眠っている。もうそれで十分だ」
三日月は幸せそうに微笑んだが――鶴丸はそれどころでは無かった。
「ッ……そういう事は、早く言え! ……くそッ……何でもっと早く顕現できなかったんだ!!」
鶴丸は自分の頭を引っ掻いた。一年早く顕現できていれば、間に合った。三日月の隣で、三日月と恋仲になって、守る事もできた。山姥切の『歴史を変えたいと思ったのは初めてだ』という言葉が思い出される。重くのしかかる。鶴丸も今そう思っている。
鶴丸は叫んだ。
「歴史を……変える事は出来ないのか、起きた出来事を! 過去へ飛べるんだろう! 審神者を殺すか、俺が会いに行けば」
すると三日月が鶴丸を叩いた。叩かれた、と思う間もなく頰に衝撃があった。
「目を覚ませ。それはできぬ。だから俺も受け入れた。あれは単なる事故だとな。こうしてお前がいればそれで良い」
「……それでいいのか!? 三日月……ッ」
「初物でないのが嫌か」
「そうじゃない!! ただ、許せない!」
「何が?」
「……わからない、わかるもんか! 全部許せない! きみは……俺の気持ちを知らない」
ぼろ、と涙がこぼれた。それを無理矢理、拭った。
「……きみを思うといつだって悲しくなる。顕現した日から、おれが何を思ってるか、きみはしらない」
鶴丸を襲う得体の知れない不安、焦燥。三日月の現状に対する怒り。主にみすぼらしい格好をさせているという屈辱。触れる度に苦しくなって、ああ、恋だなと自覚して。自覚されられて。嬉しいより悲しい。三日月の覚悟が辛い。その顔が、本当の意味で晴れることは無い。いっそ引き倒して。閉じ込めて――。
鶴丸は三日月の右手を掴んだ。
「鶴?」
「分かった、抱けば良いんだろ。きみの主も、きみが好きで好きで仕方無かったんだろう。きみは人を狂わせる。刀も、このままじゃ俺も狂う。とっくに狂ってる。きみの血が見たくて仕方無い。引きずり込んで、肉を喰らって、骨だけを愛でたい。そうすればきみは何処へも行かないし、俺達は一つだ」
三日月がはっとして、敷布に押さえ付けられた右手首を見る。三日月はまだ横になっていて、鶴丸は体を起こしているから、押し倒している訳でも無いのに、しっかりと縫い止めた右手首は、それだけで三日月の自由を奪っていた。
――三日月は抵抗しない。驚いた様子で鶴丸を見つめている。
時折痛みに顔をしかめる。
三日月の手首に爪が食い込む。皮膚が破れて血が滲んだ。骨を折りそうになって、鶴丸は目を閉じた。
「……ちがう……三日月。俺はそんな事がしたいんじゃない……畜生にも鬼にもなりたくない。きみに触れたいだけなんだ」
◇◆◇
暗闇で、鶴丸の瞳が光っている。そこから涙がこぼれ落ちていく。
鶴丸が三日月の真上にいる。
――視線が合わさった。
「鶴丸は、俺の事を、ずっとどう思っていた?」
三日月は問うた。
「好きだと思っていた。主だと思っていた。苦しかった」
鶴丸の指が頰を撫でる。三日月は目を細めた。
「……俺も」
俺も好きだと思っていた、と言いたかったが上手く言葉が出なかった。
「口を吸って欲しい。好きなだけ触れてくれ」
出て来たのは情緒の無い言葉で、どうして俺はこうなのだ、と自分が恨めしくなった。
他の三日月はもっと可愛げあるのに、俺はこうだ。
すぐに口が塞がれて、すっかり慣れた接吻が、と思ったが、何かが違った。
「んッ?」
熱に任せて舌を絡め合ったこともあったが――この接吻はそれより遙かに強引で乱暴だった。歯列を舐めて、歯の裏、口蓋へと進み、できる限り奥まで入ろうとしてくる。顎を掴まれて目一杯口を開いたまま、舌の動きを感じた。舌をすくわれ、唾液があふれてむせかけた。髪に触れられ、体がうずいた。襟に手がかかる。今まで鶴丸は、決して三日月の着物を乱さなかったから驚いた。こんな事で、と思ったら息が詰まって、舌の動きに翻弄された。押さえ付けられて、声を上げる事が出来ない。ふと、あの夜の事を思い出した。
自分の上にいるのは審神者だろうか。目を開いても見えるのはおかしな光ばかりで、三日月は目を瞑った。一瞬離れたと思ったら、また捕まった。手首を掴んで布団に縫い付けられる。
嫌だと首を振っても止められない。これは鶴丸だ、と思って耐える。冷静になれと自分に言い聞かせて呼吸を整えようとしたが、絶えず舌と舌が擦れあっている。吸われて、喉の奥で唾液が混ざり合う。
思った以上に覚えている。それでも気持ちは良い。腰が跳ねた。首に触れられ、肌が粟立つ。首を振ると、鶴丸が離れた。
「っ……」
三日月はごほごほとむせ込んだ。
息を整えて見上げると、真っ暗闇に金色の双眸が浮いている。
この部屋はおかしい。部屋に一片の灯りも無く暗すぎて、何も見えない。
口元に近づく気配がある。
「待っ、少し恐い、灯りを」
鶴丸が優しく笑った気がする。
「――俺のどこが恐いんだ? 心配しなくても、ちゃんと優しく抱いてやる。まあ、やったことはないから、きみの力を借りる事になるが、覚えは良い方だ」
つい、と鎖骨の下に触れられる。胸に触られる。鎖骨に濡れた感触があって、息がかかる。髪が乱れる。
「恐い、駄目だ鶴丸、恐い」
三日月は震えた。
「鶴丸が主に見える……恐い」
三日月が訴えると、鶴丸の手が止まった。
「暗いのが駄目か」
「違う、見えんのが恐い。乱暴もやめてくれ、ほんに、やつを思い出す。思い出したくないのに、思い出す……」
三日月は首を振った。鶴丸が三日月の上から退いた。
立ち上がる気配があって、しばらくしたら枕元が明るくなった。
行燈を模した灯りの温かい光に照らされて、鶴丸の姿が浮かんだ。白い肌に蜂蜜色の瞳、銀色の髪に、真白い浴衣。
「……悪かったな。怖がらせたい訳じゃ無い、手、痛くなかったか」
三日月は自分の姿も見ることができた。
呼吸を整えてから声を発した。
「……すまん……落ち着いた。この部屋は暗すぎる」
「窓が無いからな」
三方は壁で、頭に床の間、足元に障子。それだけの六畳間だ。床の間、押し入れがあるが、秋津の本丸の部屋より狭く感じる。
明るくなって、ようやく、三日月は自分の様子も見ることができた。はだけた胸元、解けかけた帯に、裾もわずかに乱れている。この程度で余裕を失ってしまって、少し情けなく思った。
鶴丸が灯りを絞って、辺りが暗くなる。このくらい暗ければ恥ずかしくも無く、目が慣れれば鶴丸の姿もよく見えるだろう。暗い中でも鶴丸はよく見えた。白い肌がよく目立つ――先程はどうして見えなかったのだろう、とさえ思った。真っ暗だったから、それは間違い無い。改めて鶴丸を見て、彼の独特の美貌に驚いた。儚いという言葉がぴったりで、この世の物とは思えない。彼は黄泉に属する物だろう。白い着物は死装束だ。鶴丸は誰彼構わず愛想を振りまくので、少し心配だ。攫われやしないかと――これは『三日月宗近』が持つ兄心かもしれない。三日月は記憶が薄い方だが、三条と五条は師弟だったと言われている。そこに拘る刀剣を数多く見て来た。
鶴丸は背を向けて、湯飲みに白湯を注いでいる。
「落ち着いたか? 飲むか」
「もう大丈夫だ。熱そうだから、後で良い。少々、みっともない所を見せた」
三日月は寝転がったまま、頑張って微笑んだ。鶴丸も微笑んで、戻って来た。
「いいや俺も脅しすぎた。冷静じゃなかった。ほら、これ、国永がくれた油だ。すっかり忘れていた。せっかくだから使おう」
鶴丸が苦笑して、小瓶を見せた。目が慣れてよく見える。
「三日月、一つ提案があるんだが、いいか?」
「何だ? 申してみよ」
鶴丸が自然と、三日月の上に跨がる。
「きみを抱く度に、辛い情事を思い出されたんじゃあ嫌だ。だから、できる限り、その時の事を、なぞって、一つずつ忘れていこう。それでも駄目なら、その時と違う趣向ですればいい。どうせちっとも良くなかったんだろう? 時間はたっぷりあるんだ。辛いのは今日限りにして、後は楽しもうぜ」
鶴丸の言葉に、三日月は、ああなるほど、と思った。
「確かに、その通りだな。それは良い考えだ。良い事を言う」
鶴丸は穏やかに微笑んでいる。
「そうだろう? 快楽で上塗りすれば、思い出すのはそちらになるかもしれない。思い出すだけで体が疼くようにすれば良い。俺は協力を惜しまないぜ? どうだ、辛いかもしれないが、やるか?」
「ああ、やる」
三日月は頷いた。情事の度に思い出すくらいなら、鶴丸との情事を思い出すようになればいい。目から鱗で、やる気が出た。
「接吻はもう十分だから、体に触れてくれ。実は少しきついのだ」
三日月の物は先程の接吻で兆していた。鶴丸もそうだというのが、分かる。
「よし、まず、どこに触る?」
「あの時は出陣服を着ていて……首の下、この辺りに吸い付かれた。あと耳も囓られたな。その後は胸を弄られた。こちら側を舐められて、跡が付くほど噛まれて、こちら側は痛いくらい押しつぶされた」
鶴丸が「分かった」と言って順番になぞっていく。普段黒襟で隠れる場所の少し下を鶴丸が舌でなぞる。濡れた舌の感覚は似ているが、舐め方が違って驚いた。場所はほぼ同じだ。鶴丸は慣らすように何度も舐めた。その後、三日月の髪を払って、左の耳を酷く優しく、甘く控え目に囓った。そのまま耳元を舐めて、耳の中に舌を差し込む。くすぐったさに身をすくめたが、抵抗はしなかった。吐息がかすめる。その後、外耳を執拗に舐められて、少し顔を背けた。鶴丸は、両手を三日月の頰に添えて接吻してきた。三日月は目を閉じて受けた。口元で舌が触れ合った。舌を絡めたが浅く、少し物足りない。膝を少し曲げて、物足りなさを我慢した。
接吻が終わった後、鶴丸は三日月の口の端を指で拭った。その後に自分の口を手の甲で拭う。目に焼き付ける為、三日月は見つめた。
未来永劫、自分が抱かれるのはこの男だけだと――信じている。指が伸びて来て、胸の尖りを刺激する。指先でつままれ、思わず声を上げた。
「んっ……?」
刺激と言うほどの物では無いのに、じれったくてもどかしい。左片方に舌が這って、今度はもう少し大きな声が漏れた。こんな事で、と思った。鶴丸は舌では上下に舐めて、吸って、左手では円を描くように、弾いて押しつぶした。濡れたと乾いたに混乱して利き腕を動かしたが、緩く布団に押さえ付けられた。
「悪いな、噛む」
「えっ――あッ!?」
舐めていた場所を、がり、と噛まれた。一瞬、鋭い痛みが走る。噛んだ跡を大きく舐められて呼吸が乱れた。甘い疼きが、足の先から上がってくる。
(――鶴丸が舐めている。俺の体を? 鶴丸が?)
ふっと、心が温かくなった。そこで胸の痛みに引き戻された。
「うっ、あ。痛っ」
三日月が『痛いくらい押しつぶされた』と言ったからだろうか。押しつぶす力が強い。思わず声が出た。
「う……っ、っ……ッ」
「次はどうする? 三日月」
耐えていると、鶴丸が微笑んだ。
三日月は「接吻されながら、下に触れられた、いかされるまで」と恥を忍んで伝えた。「腕は? 抑えられてたか」と言われたので「頭の上で、縛られていた、術で……」と言った。言っただけで股間が疼いたし、鶴丸が目の色を変えた。
三日月は恥ずかしさに顔を背けた。
鶴丸が三日月の帯を解いて、それを使って三日月の両腕を縛った。鶴丸が三日月の陰茎を容赦なく握り込み、高めていく。三日月は喘ぎそうになるのを我慢した。
「っ……、っ」
「そうだ声は? きみはどんな調子で喘いだ? 黙っていたか?」
ともすれば楽しんでいるような、彼らしい声だった。その間も手が動いていて、三日月は上ずった声を上げた。
「あっ、喘いだ、嫌だと言った、何度も、泣きながら」
「じゃあそうしてくれ。嫌だと言って泣き叫べ」
「あっ、嫌、嫌……鶴……! どうして、主」
「主じゃない」
鶴丸が一際強く握り込んで、三日月は声を上げた。つる、つる、と何度も呼んで、刺激にぽろりと涙をこぼした。その後も涙が出て来る。
「あっ」
「こいつは驚いた。きみは泣くのが上手いなぁ。辛いのか?」
三日月は首を振った。
「あっ、違、気持ち良くて――」
「この後は?」
絶妙な加減で、ゆっくりになる。三日月は体を震わせた。
「ひ……っ」
「次は何だ?」
鶴丸の手がまた動き出して、三日月は悶えた。しばらく声が出せなかったが、何をされた、と何度も聞かれて、ついに口を突いて出た。
「っ、ああ、もっと、何度もやられた、俺が喋れなくなるまで、しゃべろうとしたら、殴られ――あっうううッ!」
押し寄せる波に呑まれて、三日月は精を吐き出した。鶴丸は手を止めなかった。
「あっ、あっつ、あつい、あう、あ、つる!」
起き上がろうとしても起き上がれない。足を大きく広げられて、ただ泣く事しかできない。あの時は部屋にも術が巡らされていて、体はほとんど動かなかった。
今は腕はともかく、足は動くはずなのに。足もどこも動かない。体の痺れでろれつが回らない。
「はぁ、ぁあ、ぁああ、つる……っ」
急に口を塞がれた。舌が入って来て三日月を温めていく。鶴丸は色々な所に触れた。首筋かじりついて、胸に触れ、脇の下や二の腕、背中に手を回してされて、うなじにも触れられた。誰も触れたことのない場所を、鶴丸が探っていく。
三日月の物は鶴丸の手の中で、すっかり濡れて、固く形を変えている。
「ぁ、あぁ……ふ、ぁ……っ、ぁっう、あ゛ぁ」
体が震えて声が抑えられない。
「ぁあ! ぁ――」
目の前が明るくなって、快楽に堕ちた。藻掻いても腕が動かない。
三日月は足を広げたまま達した。
◇◆◇
一つどころか二つも三つも、全てが苛つく。
具体的な言葉は鶴丸を怒らせるのに十分過ぎた。
「ふぁ、ひゃぁ、ぁあッ、つる、ぁッ、だ、あぁ、ぁ……っ! あッぁああ! ぁあッ!」
鶴丸の下で、三日月が乱れ喘いでいる。
何度もというから、何度もいかせて、三日月の体中を気が済むまで舐めて、ようやく息を付いた。
三日月の反応が無いのではっとして見下ろすと、三日月は息も絶え絶えで、ぐったりして、とろけた表情をしていた。口からは涎が垂れて、目は潤み、涙がこぼれて、髪は乱れて、両腕は縛られたままで、拘束は少し緩み、足も立てて開いたたままだ。萎えてしまった逸物から白い液体が垂れて敷布を濡らしている。胸には付けた覚えの無い跡が散って、首にも二の腕の内側にも噛み跡がある。
下半身に熱が集まって、今すぐにでも突き入れたいと思ったが、このまま抱くのは可愛そうに思えた。腕を解いてやると、何故? という顔をされて驚いた。
鶴丸は少しむっとして、三日月を転がした。四つん這いにして足を曲げさせる。三日月はあっさり従った。自分の手に油を垂らして、少し指を曲げて伸ばして、息を吐いて、尻の肉を広げて、真ん中の場所に指を突っ込んだ。三日月が小さく震えたのが分かった。
鶴丸は恐怖の震えと心地良さからの震えの違いが分かるようになっていた。今のは心地良さからの震えだ。油なんて使った事は無いだろう。
背中には跡も付いていないしまだ触れていない。三日月の肢体が、しなやかに揺れる様は、いくら見ていても飽きない。鶴丸はこの先、三日月を何度だって抱いて、良いように扱うのだから、初めの一度くらい三日月の為に使いたい。後ろからもヤられたかも知れないが、後で前もすればいい。
指を二本に増やして、しっかり深く入れていく。意外にすんなりと入っていくのでこの姿勢で良かったかもしれない。程なく三本に増やしても、さほど苦労はしなかった。くちょくちょと言う音がいやらしい。三日月は浅い呼吸を繰り返していて、頭を下げて、つかみ所のない敷布を掴んでいる。なるべく奥まで入れて、今度はまとめて動かすと「う゛っう゛」と鈍い声を上げた。
「三日月、起きてるか?」
「起きている……後ろからするつもりか」
「後で前もやるぞ。きみのとけた顔が見たい」
「……好きにしろ。ん、もう少し、浅い所、腹の方を押してくれ」
「ん?」
命令されたので首を傾げながらその辺りを探る。「そう、そこだ」と言われた後三日月が細い声を上げて、内側が震えた。勝手に達したというのが分かり、鶴丸は少し虚しくなった。
「丁度良い塩梅だな……三日月の中に、これを入れる場所があるって言うのは驚きだ……」
鶴丸は小さく呟いて、自分の物を更に起たせて、用意された場所へあてがった。
三日月は腰を上げてぐったりとしている。髪が逆立って、うなじがよく見える。呼吸は浅かったり、深かったり。腕は敷布に伸ばされていた。かるく拳を握っている。鶴丸が手を伸ばして触れようと思えば、その手に触れられる。手首を掴もうと思ったがやめた。
押し当てると、三日月が急に腕を動かして曲げた。
その仕草に鳥肌が立った。
腰を掴んで一気に入るところまで押し込んだ。鼠がつぶれたような、濁音の悲鳴が聞こえた。
未知の感覚に全身が震える。おかしな肉に締め付けられて、戸惑ったが、良く濡れている。この先に極楽があると分かった。はぁ、はぁ、と三日月の呼吸が聞こえる。震えながら、受け入れようと、耐えているように見えた。鶴丸は腰を掴んで、奥まで沈めようとした。
どこまで入るかよく分からない。良いと言われた場所も忘れた。体の仕組みもよく分からない。
「……三日月……! なんだこれは」
「……っ」
三日月の反応は微かだ。ただひたすらに黙って、声を出さないように耐えている。
……詰まったような呼吸音が聞こえて、彼が泣いている事に気が付いた。
少しずつ押していくと、次第に馴染んで、一番奥まで収まった。
三日月の腿に、鶴丸の浴衣が当たる。脱ぐのを忘れた。浴衣が邪魔で角度を変えると、三日月が呻いた。
「っ……つるや、良い子だ、良く出来たなぁ」
三日月が言った。明らかな強がりだ。
「ははっ、本当にな、もう動いて良いか、出しそうだ」
「ああ、いつでも――、っ!?」
中で突き上げると三日月が震えた。
「ぁあああぁッ」
引き下がると、また声を上げた。
「んっ、ん゛っ? あ、やめ、ああ゛っ――あ゛! ひ、あっあっ、あっ」
――三日月の中身がこんな風になっているなんて、信じられなかった。
「っ゛あ゛――ぁ!」
三日月が悲鳴を抑える。
鶴丸にも絶頂が訪れて、震えるままに三日月の奥に向けて注いだ。
一度で収まらず二度、しっかり注いで、ずるりと引き出した。
布団に手を突いて、視界が戻るまで何回も呼吸をして、息を整えて、三日月に声をかけるが反応は鈍い。
三日月の体を抱えて、仰向けにするとかくんと細い首がのけぞった。三日月は気を飛ばしかけていた。
「三日月」
寝かせて、声をかけるとわずかに反応がある。髪を整えてからまた声をかけた。
「まだいけるか?」
三日月は眩しそうに目を細め、瞬きを数度繰り返して、目を開いて、わずかに頷いた。すがる物が必要かと思って、自分の背中を掴ませた。その時、三日月が笑った気がする。
足を開かせ、持ち上げ、再びあてがう。
あてがう側から、残滓が垂れて来た。入りながら、鶴丸は耐える三日月を見下ろした。
夜色の髪は汗で濡れて額に張り付いている。さらさらしているのは少し長い左側の髪だ。
長い睫毛の端から、涙がこぼれて敷布に落ちる。整いすぎていて、ぞっとした。
いくら高慢でも、いびつでも。これも『三日月宗近』なのだと悟った。
鶴丸は三日月の手を取って、軽く噛んだ。
その後も鶴丸は精一杯抱きしめて、甲高い声を聞いた。
◇◆◇
「……」
三日月が目を開けると、蜂蜜色の双眸と目が合った。
鶴丸は浴衣を着ていたが、三日月は全裸だった。
鶴丸は数度瞬きして、目を擦った。
「あ……おは、よう……三日月」
気まずそうにされると困るので、もう少しはっきり言って欲しかった。
三日月は体を起こして自分の体がどうなっているか確かめたが……何も片付いていなかった。どこもかしこも濡れて、乾いている。
鶴丸の着物も乱れている。かろうじて布団を着てそのまま寝た、と言った様子だ。
「すまん、俺も今起きた所だ」
鶴丸が言った。
「いや、それは構わんが……着物は……ん、あったな」
布団の外にあった浴衣を引っ張り、肩に引っかけた。
立てるかと思ったが、足に力が入らない。尻が痺れて感覚がない。これには少し驚いた。
「さっき、骨喰が昼飯を置いて行った。それで目が覚めた」
「……昼? 朝の間違いではないか?」
「昼だって」
鶴丸は隣で伸びをして、布団から出ていく。
――終わった後、鶴丸の膝に頭を乗せて休んだ事は覚えている。
その後、再び寝転んで抱き合ったが、その時はまだ暗かったはずだ。終わりは覚えていないから、揃って寝過ごしたのだろう。
鶴丸が障子を開けると、眩ゆい光が差し込んだ。
投稿したあとで公開範囲を変更することができるよ。マイページから、投稿したやつの右下にある「編集」をポチッとしてね
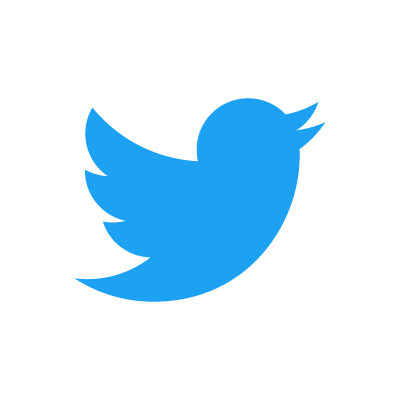 元ツイート
元ツイート