シャニマスが描くアイドルの存在論
初出:2021年2月14日Privatterに投稿
◆はじめに
この文章はシャニマスが描いていると思われる存在論について、私個人の問題意識から考えているものです。ストレイライトのイベントシナリオ「The Straylight」で冬優子たちが直面した問題と、最後に愛依が出した答えが、ここで考えている話の軸になっています。まず冬優子たちが直面した問題を私個人の問題意識に引き寄せて読みます。それから愛依が出した答えを、ラカンの疎外と分離の概念、それから愛についての哲学的な議論を経由することで、理解しようとしています。
そして最後に、3年目のシャニマスが描いていると思われる存在論を、主にストレイライトとノクチルの比較を通して考えます。ラカンの疎外と分離の概念を経由することで、ストレイライトとノクチルそれぞれで、アイドルの存在論のあり方が異なっていることが分かると思われるのです。
目次
◆はじめに
◆1.存在論の問題
◆2.ラカン的観点から
◆3.ストレイライトの答え
◆4.愛の問題
◆5.シャニマスの描く存在論
◆文献案内
◆1.存在論の問題
◇意味の優位
私がシャニマスについての感想や読解の文章を書くとき、よく「存在論」という言葉を用いていますが、そこで「存在論」という言葉で言い表そうとしているのは、意味や認識に対して存在(するということ)の優位性があるということです。何かが存在するということ、誰かが存在するということは、当たり前のことであるように思われますが、実はそうとも言い切れないところがあります。そして存在に対して意味の方が優位になるとき、ある問題が発生します。
たとえばいま目の前に1本のペンがあるとします。そこにあるペンを見て「ペンがある」と考えることができるわけですが、その目の前にあるペンというのは、日常生活においてはたいてい書類やノートなどに書き物ができる文房具として利用されているはずです。そのときそのペンは、単に「ある!」ということよりも、書き物ができる道具としての側面が重視されています。そのように利用できるというところに、そのペンの意味があります。ここで存在に対して意味が優位に立っていることになります。「それがある!」ということよりも、「それは何であるか」「それはどんな風に有用であるか」ということの方が重視されているのです。
その意味の重視の観点からすれば、そのペンは別のペンで代用可能なものとなります。なぜならそのペンはそのペンそのものであるということが重要であるのではなく、書き物ができる文房具であることが重要であるので、書き物ができる文房具であれば別のペンであっても構わないからです。したがって、日常生活において「ペンがある」というときに考えられているのは、「そのペンそのものがある」ということではなく、「書き物ができる文房具が1つある」ということになるはずです。後者のように考えられているとき、そこにあるのは代用可能な道具であって存在そのものではありません。
人間にも同様のことが起こります。ある人間が存在するとき、その人間個人が存在するということよりも、その人間は何者で、どんな仕事がこなせて、どれほど有用であるか、ということの方が重視される場面があります。とりわけ、働くというときにその面が強く出てくることになります。そこで1人の人間は、固有な人間としての存在よりも、何者であるかという意味の方が重要とされるようになります。そして意味の方が重視されるとき、道具と同様にその人間は別の人間に代用される存在となるのです。
このように、道具にせよ人間にせよ、何かがある誰かがいるというときに、存在に対して意味の方が優位に立つということは日常的にかなりあることです。
ですが存在に対して意味の方が優位に立つと、ある問題が発生します。存在に対して意味が優位になると、人にせよ物にせよ存在するものはひとつの固有なものであるはずなのに、それらは別のもので代用可能となってしまうという問題です。存在の固有さが失われてしまうのです。
◇ストレイライトに降りかかった問題
イベント「The Straylight」でストレイライトの3人が向き合ったのはこの問題だった、と言うことができます。
音楽番組に出演することになったストレイライトは、アイドルとして以上に、その実力を視聴者に見せつけることを目論みますが、ミュージカル出身の実力派アーティストグループの前に敗北を喫することとなります。ここでストレイライトは、アーティストとしての実力という尺度で、自らの位置を見定めています。この「アーティストとしての実力」というのは、働く人の有用さに相当するような、意味の水準に人を置く尺度です。
で、このアーティストが、ストレイライトのものまねをテレビで披露することになります。冬優子は、実力の差を見せつけられたアーティストグループに対し、自分たちこそが本物のストレイライトであるということを実力で示すことを狙います。そしてそれは達成されることになりました。
ここで冬優子たちは実力で圧倒することによって、自分たちこそが本物のストレイライトであるということ、あなたたちはものまでであり偽物であるということを示したわけですが、重要なのは実力でそれを示したということです。ものまねであるストレイライトカッコニセと冬優子たちストレイライトは、アーティストとしての(あるいはアイドルとしての)実力という同一の尺度の上で比較されています。そしてその度合いの高い方が本物として認められた、ということになっているのです。冬優子たちが本物であるのは、冬優子たちが「ご本人」であるからではなく、実力があるからなのです。ここが重要です。「ご本人」であるという存在に対して、実力の有無という意味の方が優位に立っているわけです。
この意味の優位はまだ続いており、ものまねであるストレイライトカッコニセに続いてCGで再現されたストレイライトのMVというものが冬優子たちの前に現われることになります。ストレイライトカッコニセは、実力派アーティストグループであったとはいえしょせんものまねです。ですが、今回冬優子たちの前に現われたのは、冬優子のいくつもの注文を実現して制作されたCGのMVです。その完成度を冬優子も愛依もあさひも認めないわけにはいきません。このCGについて愛依は「本物」と言い、さらにあさひは「完璧」だと言います。この「完璧」というのは、冬優子たちがストレイライトであるために目標としていたものでした。冬優子たち自身ではなく、冬優子以外の人間によって作られたCGが「完璧」なストレイライトとなってしまったのです。CGが「完璧」なストレイライトであるならば、CGのストレイライトは冬優子たちに成り代わることができるわけです。その可能性が冬優子たちの前に現われます。
冬優子たちの前に、ものまねたCGのストレイライトが現れ、それらが冬優子たちに成り代わる可能性が示されるのは、冬優子たちはストレイライトをアイドルとして作り出しているからです。冬優子たちが作りだすアイドルグループストレイライトは、テレビの中に映る像であり、雑誌やネットの記事で書かれる文章であり、ファンや視聴者が想像するイメージです。なので、それらを作り出すことができるのであれば、その役目を果たすのは冬優子たちでなければならない理由はない、ということになります。ストレイライトというアイドルグループは、書き物ができる文房具としてのペンと同様の水準にあります。々役目を果たすことができるなら、代用可能なのです。
そしてこの問題は今一度冬優子たちに降りかかることになります。イベントシナリオの最後に、冬優子たちは愛依の家で愛依の妹と弟たちにプライベートなステージを披露するのですが、そこで冬優子たちは愛依の弟に「ニセモノ」「カゲムシャ」と言われてしまうのです。今までは、ものまねのストレイライトカッコニセや作られたCGが、「それは本物か」と問われていました。そこではいわば、冬優子たちではない別の何者かが冬優子たちに成り代わろうとしていて、本物かという疑いが向けられていました。冬優子たち自身ではないのですから、本物かという疑いが向けられるのは当然であるような気がします。ですが、ここではその問い=疑いが、紛れもない冬優子自身にまで向けられるのです。
存在に対して意味が優位になるとき、あるものがあるものであるかどうかは、それが当のそれそのものであるということよりも、それがそのあるものとしての役割を果せているかどうかということの方が、より重要になるわけです。だから「ストレイライト」というアイドルユニットがどのようなものであるかということを満たさないものについては、たとえそれが冬優子たち自身であっても、「ニセモノ」「カゲムシャ」と問い=疑いが向けられることになるのです。このときもし、冬優子たちよりももっとストレイライトらしい人たちが他にいたとすれば、冬優子たちではなくそちらの人たちの方こそが本物のストレイライトだということになってしまうでしょう。
冬優子たちよりもストレイライトらしい人たちが実際に登場することはありませんでしたが、イベントシナリオで描かれてきたことをふまえた上で冬優子たちにまで問い=疑いが向けられると、そうした人たちが存在しうる可能性は自然と発生してくると思います。意味が存在に対して優位に立つとき、問題はここまで進むことになるのです。これは恐ろしいことだ、と私は思います
◇この私が存在するということを言えるか
この問題に対して冬優子たちがどのような答えを出したのかを検討する前に、もう少しこの問題をよく見ておきたいと思います。というのも、この問題は私にとって非常に切実な問題であったからです。
デカルトが全ては夢であるかもしれないと方法的懐疑を行った先に、唯一存在を疑いえないものとして見出したのは、考える自分の存在でした。たとえこれが夢であるかもしれないとしても、そのように疑っている自分自身はいま存在しているのであり、そのことは決して疑いえない、ということです。
私は、いま確かに存在しています。ですが、この私が存在するということは、世の中においてはある特定の何者か、たとえば響きハレというような名前の何らかの属性を持った何者かが存在するということです。実は「この私が存在する」ということと、「響きハレという名前の何らかの属性を持った何者かが存在する」ということは、全く同一のものというわけではありません。というのも、この私がいまこのように持っているのとは別の属性をもっていたかもしれないという可能性が考えられるからです。だから、私がいま持っている全ての属性と同一の属性を持つ何者かがいたとしても、その人物がこの私であるとは限らないのです。
ですが、世の中は一般的にそれらの差異に対してそれほど敏感であるわけではありません。上でも書きましたが、存在に対する意味の優位が色濃く表れるのが、労働の場面です。存在に対して意味が優位になるとすると、私の代わりを務める人物はいくらでも存在しうることになります。私がたとえばaとbとcという要素を満たしていて、そのことをもって響きハレという人物が労働において有用さが認められているとすると、aとbとcを満たす人物であれば、私以外の誰でも私の代わりを務めることができるようになります。もし私以上にうまくその要素を満たす人物がいたとしたら、私は用済みになってしまうかもしれません。
これは労働の場面ですが、存在に対する意味の優位を押し進めると、響きハレという人物が存在するということまで問題は進んで行きます。この私はいまここに響きハレという人物として存在していますが、意味の優位の観点からは響きハレという人物が存在しているということは、この私が存在するということではなく、ある特定の属性を持った人物が存在するということです。ですから、この私がいま持っている全ての属性と同一の属性を持つ何者かがいたとすれば、その人物がこの私であるかどうかは関係なく、ともかくその人物が響きハレだということになります。ある人物が存在するとはある特定の属性を持った人物が存在することだという風に、存在に対して意味が優位になるのです。
ここに、この私に成り代わって響きハレという人物であるような、私以外の何者かが存在する可能性が差し挟まれることになります。この私に成り代わる私ではない偽物が存在しうるということではなく、この私こそが偽物とみなされてしまうようなより本物らしい別人が存在しうる、ということになります。
このとき、「いや、この私こそが本物の響きハレだ!」と叫んだところで何にもなりません。その何者かは、この私が持つ属性と全く同じ属性を持っているわけですし、客観的には区別することができません。私が差し出すことができるのは、この私であるというデカルトが懐疑の先に見出した一人称の存在だけです。でもそんなもの、私以外の誰にも認識することはできないのですから、世の中においてはそれは存在しないも同然です。ですから、もし多くの人がそちらの人物の方を「本物だ」とみなすなら、そちらの方が本物だということになってしまうのです。この私がこの私であり本物である!という叫びには何の意味もありません。この私の存在は、意味に対して無力なのです。響きハレが存在するということは、この私が存在するということではなく、ある特定の属性を持った人物が存在するということであり、そうでなければ「存在する」ということに意味を持たせることができないのです。
存在に対する意味の優位は、ここまで進んで行きます。私はこの問題を非常に恐ろしい問題であると考えています。
◆2.ラカン的観点から
◇疎外
この私はここに存在する!と叫んだとしても何にもならないように、世の中において存在が認められるために重要なのは、何であるかという意味です。どこそこの生まれであるとか学歴や職歴がどのようなものであるとか、これこれの専門知識や技術があるとか、そういったものを持っているということこそが、この世において何者かが存在するということです。
自分自身の固有の存在が、何らかの意味や何らかの役割に置き換えられて、失われてしまうのです。これは悲しいことですが、この世において生きていくためにはある程度は仕方のないことです。このように存在が意味に置き換わってしまうことを、哲学の用語で「疎外」と言います。疎外はネガティブな現象として捉えられてきましたが、精神分析家ラカンは、人間が疎外を被るのはある程度仕方のないことであると考えています(ラカン『精神分析の四基本概念』を参照)。
疎外を被るのはある程度仕方がないというのは、上で見たように、意味に対して存在そのものを主張しても何にもならないということによります。ラカンはこのことを、強盗に突き付けられる問いにたとえています。いま強盗に押し入られ、刃物を突き付けられているとします。そこで強盗が言います。「金か命か!」。これはいわば「命が惜しかったら金を出せ」ということなのですが、ここで金を選んだとすると、強盗に殺されてしまって、結局金と命の両方を失ってしまうことになります。金を差し出せば、金は失いますが命は残ります。
存在と意味は、このたとえではそれぞれ金と命に相当します。意味に対して存在を主張すれば、何者であるかという意味を持つことができないばかりか、存在するということさえ主張できなくなってしまいます。というのも、存在するということが認められるのは、何らかの属性を持った何者かが存在するということだからです。意味の方を選べば、これこれの誰々という何者かとして存在が認められますが、自分自身の固有の存在は失ってしまいます。固有の存在は失ってしまいますが、一人の人間として世の中に普通の意味で存在することができるようになります。このようにラカンはこのように疎外のネガティブな点だけでなくポジティブな点も捉えています。
◇分離
ネガティブな側面だけではないとはいえ、疎外を被るということは意味に置き換わってしまうことであり、自分自身の固有の存在を失ってしまうということには違いありません。この失ってしまった存在を、完全な形で取り戻すことはできません。この私が存在するということそのものを、有意味に言うことはできないからです。ですが、失った存在を取り戻すのとは違う形で、自分の固有さを形成する道があります。それは、ラカンが「分離」と呼んだものです。
分離は、意味へと疎外されて存在を失った主体が、ある特殊な対象と関係を構築することで、自分自身の固有さを再び作り出すことができるような、そういう演算です。
人は疎外を被ることで意味へと置き換わり、固有の存在そのものを失ってしまうわけですが、それでも意味へと置き換えることができずに残ってしまうものがあります。その一つとして挙げられるのが、肉体です。特に、思考したりイメージしたりして自分自身の体だと認識されずに残ってしまうような肉体の部分がそれに相当します。手や足などは自分の目からもよく見え、自分で意識して制御することができる部位で、自分の身体の一部としてイメージの中に取り込める部位です。ですが、内臓などは意識的に制御することができないばかりか、それらがはたらいていることすら気づかないものもたくさんあります。でもそういうものがこの体の中で動いているからこそ、この体が生きているということを可能にしています。思考したりイメージしたりすることができないという点で、それらは意味の外部にあります。意味の外部にあるので、それらが何であるのか、そもそもそれらが存在すると言えるのかも確かではないのですが、でもその意味の外部にあるものこそが、人が実際に生きているということを可能にしているのです。
日常的に内臓を直接見たりすることはできないですが、その内臓のはたらきを実感することができるものがあります。それは排泄物です。食事をして、その後に排泄物が出るということが、内臓がはたらいているということの証拠であり、自分が生きているということの証拠になります。その証拠によって確かめられる「生きている」ということは、意味へと置き換えるきることはできません。たとえばこのようにして、分離は達成されていきます。
ここでは内臓や排泄物の例を出しましたが、分離が達成されるために求められる対象はそれだけではなく、さまざまなものがその対象となりえます。ラカンはそうした役割を果す対象を、対象aと呼びました。対象aとなりうる対象は、意味に充分に置き換えることができないものです。つまり、一般に取るにたらないとされるものや、意味がないとされるもの、価値がないとされるものだと言えます。そうしたものを、自分自身の固有のものとして認めるとき、それがあるということをもって、自分自身があるということにする、という構図をつくることができるようになるのです。そうすることで、自分自身の存在そのものを取り戻すことはできないけれど、自分自身の固有さを形成することができるのです。ここで自分自身の固有さを形成することを、ラカンは「幻想」と呼びます。このように幻想を構築することが、疎外に続く分離です。
◇問題への答え?
分離によって、自分自身の固有さを幻想として形成することができたとして、それは自分に成り代わる別の人間がいるかもしれないという問題を退けることができるのでしょうか。
ここは微妙であると私は思います。私という人間が別の人間に成り代わられてしまう可能性が開かれるのは、私という人間が何者であるかという意味に置き換わってしまうからです。別の言い方で言えば、私という人間がいくつかの属性の集合へと置き換えられてしまうからです。そのような置き換えがなされれば、それらの属性を全て持つが私ではないような人間が存在しうるということになります。これが問題だったのでした。
分離によって、自分自身の固有さを形成するとき、主体が関係を持つのは対象aと呼ばれる特殊な対象でした。対象aとなる対象は、何らかの物体ですが、それは一般に意味があるとされないようなもの、取るにたらないとされるようなものです。そしてそうした対象が、自分自身に固有のものとされるとき、その対象があるということをもって、自分自身が固有のものとしてあるということにすることができるというわけです。
ここで重要なのは、(1)その対象が意味があるとされないようなものであるということ、(2)自分自身に固有のものとされるということです。自分自身に固有のものとされるのは、例えばそれらが自分自身の肉体に由来するものである場合に(たとえば内臓や排泄物のように)そうであると言えるかもしれません。
もう一つ重要なのが、その対象が意味があるとされないようなものであるということです。排泄物は肥料などにするのでなければ、だいたい日常生活ではそのまま水に流されてしまうもので、不要のものであるはずです。内臓は無意味でも無価値でもないですが、それが現に働いているところを思考したりイメージしたりすることは難しいもので、そういう点で意味の地平に上ってこないものです。これらは意味の外部にあります。意味の外部にあるということが重要です。それが意味の外部にあるとすれば、それは意味へ置き換えられるものの中から零れ落ちることになるわけです。つまり私という人間を属性の集合へと置き換えたとしても、その属性の集合の中に含まれない何かがその外部に残ることになるわけです。そしてその何かが私に固有の何かであるとき、その何かがあるということをもって私が固有のものとしてあるということになるわけです。
ですがこれで問題が完全に退けられるわけではありません。この微妙なポイントも、その対象が意味の外部にあるということに由来します。というのも、もしその対象が完全に意味の外部にあるものだとすれば、それを持つということに意味を与えられないからです。「この私が存在する!」と叫んだときと同じ状況に陥ってしまうことになります。逆にその対象が何であるのかはっきり言ったり認識したりすることができるものだとしたら、それは私に固有のものではなく、誰もが持ちうるものになってしまいます。ここにジレンマが発生するわけです。
なので、対象aの役割を果すものは、意味の外部にあり意味の内部にあるようなもの、自分自身に固有のものであり誰もが持ちうるもの、という矛盾的なものになります。そういう点で特殊なものです。そんなものが存在しうるのかという問いが浮かんできますが、それは客観的に存在することが必要であるというよりも、幻想の上でそのような役割を果たしうるものがあるということが重要なのです。
◆3.ストレイライトの答え
◇ストレイライトの答え1
かなり長い遠回りをしてしまいましたが、ここまで見てきたことによって、冬優子たちの答えがどのようなものだったのかがよりはっきりと見えてきます。
冬優子たちに降りかかっていた問題は、冬優子たちは本物のストレイライトなのか、冬優子たち以上にもっとストレイライトらしい誰かが存在しうるのではないか、という問題でした。この問題に対して冬優子たちが見出した答えは、もう一つ愛依に降りかかっていた問題への答えでもありました。
愛依に降りかかっていた問題は、ステージ上でファンや視聴者に見せている愛依の姿は愛依自身の姿ではなく、嘘の姿なのではないか、という問題です。愛依は緊張しやすいタイプなため、気さくで明るい普段の姿のままステージ上に上がることができませんでした。その緊張している様子を、クールでミステリアスなイメージとして提示することで、愛依は自身のアイドルイメージを作っていったのです。そこで愛依は、そうしたステージ上で自分が見せているアイドルのイメージは嘘なのだから、自分の普段の姿をファンや視聴者に見せるべきなのかどうか悩むことになりました。
この愛依の問題は、冬優子たちに降りかかった問題と重なってきます。もしステージ上の愛依の姿が、作り物で嘘の姿なのだとしたら、ファンや視聴者が受け取って作り上げているアイドル愛依のイメージは、愛依当人とは異なったものとなります。それらが異なったものであるとすれば、クールでミステリアスなアイドル愛依のイメージを作り出せるのは、愛依でなくてもよいということになります。つまりものまねやCGなどの、冬優子たちではない別の人間たちによるストレイライトが存在する可能性が、ここに差し挟まれることになるのです。
この問題に対して愛依は、あさひの発現を受けて答えに辿り着きます。それは、「ステージのうちも、うち」というものでした。つまり、ステージ上でファンや視聴者に見せているクールでミステリアスなアイドル愛依は、作り物でも嘘でもなく、それもまた愛依自身なのだ、ということです。
ステージ上で愛依が見せる姿と、普段の愛依が異なっていると考えると、ステージ上で愛依が見せる姿は愛依ではない別の誰かが見せても良いという問題が発生します。そしてストレイライトというアイドルユニットは、完璧を求めてレッスンを厳しく行ったりユニットイメージを管理したりして、徹底的に作り込んでいくユニットでもあります。そうやって徹底的に作られているからこそ、ストレイライトというユニットは冬優子たちではない別の誰かがやってもよいという可能性を生み出すことになります。
愛依が辿り着いた答えは、ステージ上のアイドル愛依は愛依自身であり、愛依以外にそれを見せることはできないということを意味しています。そしてそれは同時に、ストレイライトというユニットは、冬優子と愛依とあさひの3人でなければならないという考えを示すのです。この答えに辿り着いた後、ステージ直前で冬優子たちのあげた掛け声は、まさに「あたしたちがストレイライト」でした。
◇ストレイライトの答え2
sSSR【いるっしょ!】の3つ目のコミュで、愛依とストレイライトの答えがさらに語りなおされています。そこから、なぜストレイライトは冬優子と愛依とあさひの3人でなければならないのか、ということを読み取ることができます。
とある配信者の動画によって、ステージ上のアイドル愛依の姿は作り物の嘘の姿なのではないか、ということがSNS上で取りざたされていました。普段の愛依の姿をステージ上でも見せるべきなのかどうか迷っていた愛依にとって、またユニットイメージを徹底的に作っていたストレイライトにとって、この問題は無視できない問題でした。愛依が出した答えは、すでに見たように、「ステージのうちも、うち」です。サポートコミュで描かれるのは、その答えに辿り着いた愛依が、どのようにSNS上の人たちにメッセージを発信したか、ということです。愛依がツイスタに投稿した文章が非常に重要です。実際に見てみましょう。
「噂よりも
ステージを見てほしい
あたしはそこにいるから
そして
あたしたちがいるところにステージはあるんだ
#ストレイライト」
ポイントは2つあると私は考えています。ひとつめは、「あたし」という言い方をしているということです。SNS上で取りざたされている「噂」は、ステージ上のアイドル愛依の姿は愛依の本当の姿なのかどうかということや、本当の愛依はもっと別の姿なのではないか、といった姿、イメージ、キャラに関することです。ですが愛依は、姿やイメージやキャラではなく、単に「あたし」とだけ言っています。どんな姿であっても、どんなイメージであっても、どんなキャラであっても、「あたし」は「あたし」だというニュアンスが、ここに込められているように思われます。「ステージのうちも、うち」という答えが、この「あたし」の背後にあるのです。
もうひとつのポイントは、「ステージ」に関することです。愛依は、「あたしはそこ〔ステージ〕にいる」と言い、同時に「あたしたちがいるところにステージはある」と言っています。この転換が非常に重要であると私は考えています。
ストレイライトは、徹底的に作り込まれたアイドルです。プロデューサーに見せるような、普段の冬優子や愛依やあさひの姿とは異なった、別の姿がアイドルユニットストレイライトでは提示されます。この作り込みを、シャニマス公式サイトに掲示されているストレイライトのキャッチコピーは、次のように表現しています。「身に纏うは迷光、少女たちは偶像となる」。「偶像」はアイドルを意味する言葉ですが、「偶像」という言葉を用いることによって、それが何らかのイメージであるということを示すニュアンスが生じます。そして「迷光」は、光学機器の中で発生するフレアやゴーストなどを指す言葉で、ストレイライトの訳語です。「迷光」は、光学機器の中で発生する像を結ばない光で、像を映すためには不必要な光であるとされていますが、写真を演出したり強い印象を与える効果を発揮するものでもあります。つまりアイドルユニットストレイライトは、光学機器の中で発生する、本来は不必要な「迷光」を「身に纏う」ことで生まれる、ということです。アイドルユニットストレイライトには、迷光を生むための光学機器、つまりカメラが必要であるということがここからうかがえます。
愛依がツイスタに投稿した文章の中で言った「ステージ」は、こうしたカメラなどがあって、アイドルユニットストレイライトを生み出すための場所を意味するのではないか、と私は考えたくなります。意図的かどうかは分かりませんが、イベントシナリオ「The Straylight」で描かれる仕事は、全てテレビ番組の仕事でした。カメラなどの機器が設置されたステージの上にこそ、「あたし」はいる。その「あたし」は「ステージのうちも、うち」の「うち」です。つまりアイドル愛依であり、同時に愛依自身です。
そして、愛依はさらに、「あたしたちがいるところにステージはあるんだ」と続けています。これがとても重要なのです。
そもそもアイドルユニットストレイライトは、生まれるためにカメラなどの機器が設置されたステージを必要とします。まずステージがあり、その上に上がることでアイドルユニットストレイライトが誕生するのです。言わばステージは、アイドルユニットストレイライトというを発生させる意味の装置です。ステージが先にあり、その上に上がることで、冬優子と愛依とあさひは迷光を纏うことができ、アイドルユニットストレイライトとなることができる。
ですが、愛依はこう書くのです。「あたしたちがいるところにステージはある」と。「ステージ」が装置として先にあってストレイライトがあるのではなく、「ステージ」の位置を逆転させているのです。まず先にあるのは「あたしたち」です。「あたしたち」が先にあり、その場所にこそ「ステージ」があるというのです。ここに、私はシャニマスの存在論を感じます。アイドルというイメージが先行したり、アイドルを生み出すステージが先行するのではなく、何より先に「あたしたち」という存在がある。私はこの愛依の書いた「あたしたち」に、「この私が存在する!」という存在論の叫びの反響を聞き取ります。
そして、アイドルユニットストレイライトを生み出すことができる装置である「ステージ」を「あたしたち」に従属させることによって、「あたしたち」こそがストレイライトであるということ、「あたしたち」以外はストレイライトではありえないということを示すのです。もし「ステージ」が先行するのだとすれば、冬優子たち以外の別人が、「ステージ」に上がることでストレイライトを提示することができるかもしれません。実際にものまねやCGはそのようにして冬優子たちの前に現われました。でもそうではないのです。「ステージ」は「あたしたち」に従属するのです。これは、上で長い遠回りをして見てきた疎外に対する分離のプロセスそのものではないか、と私は思うのです。
分離を達成するためには、自分自身に固有の対象と関係を持つことが必要でした。ここで愛依たちにとってのその対象は何なのでしょうか。それは「ステージ」を通して発生する、迷光ではないか、と私は思います。冬優子と愛依とあさひが身に纏う迷光は、カメラによって勝手に生み出されるものではなく、「ステージ」を通して自分たち自身から生み出されるものなのではないか、ということです。
冬優子が見せているふゆの姿や、愛依が見せているクールでミステリアスな姿や、あさひが見せているゾーンに入り込んだような研ぎ澄まされた姿は、他の人が真似することができます。CGなどによって再現することもできます。ですが、それら表に現われた姿を支えるものとして、裏側に潜んでいるものを真似したりCGで再現することはできないはずです。冬優子がふゆを生み出すために払っている努力やその背後にある願望も、愛依のクールでミステリアスな姿を支えている極度の緊張も、あさひの研ぎ澄まされたゾーンに入るための集中力も、それらは表に出ているものを支えるものであって表には出てこないものです。いわばそれらは、アイドルユニットストレイライトのイメージや意味の外部にあります。外部にあるので、それらを真似したりCGで再現したりすることはできないのです。そしてそれらはイメージや意味の外部にあるのですが、むしろそれらこそが、アイドルユニットストレイライトをアイドルユニットストレイライトたらしめているのです。思考やイメージの対象にはならないけれど、生きているということを支えている内臓のようなものです。これらが、アイドルユニットストレイライトがアイドルユニットストレイライトであるために身に纏うべき迷光であり対象aなのではないか、と私は考えています。そして「あたしたちがいるところにステージはある」という言葉はここまでの射程を持つ言葉なのではないか、とも思って居ます。
◆4.愛の問題
◇愛は可能か
上で、分離によって達成されるのは幻想の構築であって、問題に対する答えとしては微妙なものであるという風に考えました。もしそうであるならば、愛依たちが辿り着いた答えもまた、微妙なものとならざるをえないのではないでしょうか。
そもそもの問題は、この私が存在しているのに、私という人間は世の中では何らかの意味や属性に置き換えられてしまうことで、その固有さが失われ、別の何者かに取って代わられる可能性があるということでした。それに対して、自分自身に固有の対象と関係を持つことで、その対象があるということを以てして自分自身があるということにするという答えを提示したのが、分離のプロセスでした。でもそこで構築されるのは幻想で、自分自身に固有の対象が客観的にそうであるとはかぎらないのでした。こうして分離のプロセスでたどり着いた答えは、最初の問題に完全に答えることはできずにいたのです。
分離によって辿り着いた答えの場所から、最初の問題に完全に答えるための道がひとつあります。それは、自分自身を固有の存在として他者に認めてもらうことです。自分自身を固有の存在として他者に認めてもらうために、自分自身に固有な対象を差し出すことができるとすれば、それは達成されます。これはいわば、愛の問題だということになります。
残念ながら、ラカンは愛は不可能だと考えていました。自分自身に固有の対象があるとしても、それを他者に差し出すことは不可能だからです。差し出すことができるとすれば、それは誰でも持ちうるようなものとなってしまうのですし、本当に自分に固有のものであるとすればそれは完全に意味の外部のものであって、そんなものを他者に向って差し出すことはできないからです。愛が不可能であるとしたら、最初の問題に完全に答えることはやはり不可能ということになってしまいます。
◇愛の対象
ですが、ラカンに対してここはもう少し食い下がりたいと思います。愛は本当に不可能なのでしょうか。どうすれば愛が実現できていると言えるのか、そういうところから考え始めてみましょう。
Aというある人が、恋人のBという人に「あなたを愛している」と言ったとしましょう。それを聞いたBは、Aの言葉を疑います。「本当にAは私を愛しているのだろうか」と。Bはその疑問をAにぶつけます。「どうして私を愛してくれているの?」と。そこでもしAが、「Bはとても美しいから」とか「Bはとてもお金を持っているから」などと言ったら、Aの「愛している」という言葉の疑わしさはさらに増してきてしまうと思います。
美しさとかお金を理由に挙げるような人があまりにも疑わしいのは社会通念上当たり前のこととされていると思いますが、Aの「愛している」が疑わしいのは、とりわけ美しさやお金を理由に挙げているからというわけではない、と思います。試みに美しさやお金以外の何だったら、「愛している」という言葉を信用にたる言葉にしてくれるか考えてみましょう。優しい、思いやりがある、尊敬できる、特別な出会い方をした、これこれこういうときに助けてくれた……などが思い浮かびましたが、これらのものを理由に挙げてAが「愛している」と言ったとしたら、この「愛している」は信用できるようになるのでしょうか。
私はここに、すでに問題として浮上している、別の人間が置き換わる可能性の問題が介入してくると考えています。Aがどんなものを理由として挙げたところで、それらは全てBではない別の人物も持ちうるものであって、もし別の人物――たとえばC――が、Aが理由として挙げたものを持っていたとしたら、AはCに「愛している」と言うかもしれません。Aが挙げた理由に関して、BよりもCの方が優れていたとしたら、なおさらです。つまり、「愛している」という言葉の根拠としてBの持つ属性などを挙げた場合、根拠として何の属性が挙げられようと、「愛している」という言葉を信用させるには十分ではないのです。つまり、愛の対象はBの属性ではないのであり、Bの属性が対象となっているならそれは愛であるとは言えないのです。
それゆえBを愛しているとき、その愛が真に実現されるためには、Bの持つ属性と同じ属性を全て持つようなBではない別の人物(C)を愛することなく、さらにBの持つ属についてBを上回る属性を持つような別の人物(D)を愛することもないのでなければなりません。つまり、Bの持つ属性ではなく、Bそのものに対して愛が向いているのでなければならないのです。
愛の対象をもっとよく取り出すために、思考実験をさらに押し進めます。SF的な想定ですが、Bが過去の記憶をどんどん失っていき、異なった人格になっていき、さらに見た目の属性もどんどん別のものへ変化していってしまう、という場合を考えてみます。記憶と人格と見た目が、もともとのBとは全く違うものになってしまったとき、Aはそれでもその変化してしまったBのことを愛することができるでしょうか。もし、記憶と人格と見た目が完全に変化してしまったBを愛することができないとすれば、かつてBに向かって言った「愛している」という言葉は、Bそのものに向けられたものではなく、Bが持つ属性に向けられたものだったということになります。そうであるとすれば、それは愛ではなかった、ということになります。さらに、Bの変化が進んで、BがもとのBとは記憶も人格も見た目も完全に異なってしまったとき、もとのBと同一の記憶と人格と見た目をしたBではない別の人物(E)が現れたとしたらどうでしょうか。それでもAがBを愛しているのなら、その愛はEではなくBに向かうのでなければならないのです。つまり愛の対象であるべきBそのもの、人間そのものは、何らかの属性を持ちうる核のようなもの、存在そのものです。
ではその属性を持ちうる核のようなもの、存在そのものを、愛の対象とすることができるのでしょうか。ここで問題は、「この私が存在する!」と叫んだところでそれを有意味なものとして誰も聞き取ることができない、という最初の問題に立ち返ることになります。結局他者が認識するのは認識することのできる部分、理解できる部分だけで、存在そのものはどうやっても他者にとって認識可能、理解可能なものにはならないのではないでしょうか。
◇時空上の連続性
そうではない、と私は思います。何らかの属性を持つ核、存在そのものは、認識したり理解したりすることが完全に不可能なものではない、と思います。Bが変化していってしまう想定をもう一度考えてみます。徐々に変化していってしまうBのそばに、常にAがいたとします。Aは変化していくBを、Bであると認識し続けることができるはずです。もとのBの面影を全く残さないほどに記憶と人格と見た目が変化してしまったとしても、変化していく過程を認識し続けていればAはその人物をBであると認識できます。変化の中でAが認識しているのは、Bという存在そのものなのではないでしょうか。それが可能なのは、Bが物理的に肉体を持ち、時空の中に居場所を持って存在し続けていたからです。その時空上の連続性を追うということが、存在そのものを認識することを可能にしてくれるのです。
この時空上の連続性を追うということがポイントになってきます。時空上の連続性を追うということは、いわば、時空上に連続して存在していたBそのものと共に過ごしてきたということです。Bそのものと共に過ごしてきた時間は歴史となります。その歴史は現実の歴史であり、変わることはありません。Aが共に過ごしてきたのは、時空上に連続して存在している(していた)Bであって、CでもDでもEでもないのです。Bと同じ属性を持っていたり、Bを上回る属性を持っていたり、Bと同じ記憶と人格と見た目を持っていたりする人物があるとき突然Aの前に現れたとしても、Aが共に時間を過ごしてきたのはそれらの人物ではなく、ほかならぬBなのです。
それゆえ愛は、「愛している」ということで実現されたり証明されたりするのではなく、時空上に連続する存在そのものを対象にして時間を過ごすこと、歴史を作ることそのものである、と言えるかもしれません。
分離の過程で、自分自身に固有の対象と関係を持つことで、その対象が存在することをもって自分自身が存在することとするという幻想が構築されるのでした。その自分自身に固有の対象を他者に差し出すことができれば愛は達成されるのではないかと最初に考えたのですが、それはやはり不可能であると私も考えます。ですが、持っている何かを差し出すことによって、時空的に連続している自分自身の存在を他者に向かって示すことは不可能ではないはずです。ここに、愛の可能性が開かれると思います。
ただ、ここにも同様に、同じものを差し出す別の人間が存在しうるという可能性が介入してきます。時空上に連続している自分自身の方を、全く同じものを差し出す別の人間と識別してもらえるのかという問題は残ります。でも、時空上に連続している存在そのものを相手に時間を過ごしてきたというその歴史は、変わることも失われることもありません。全人類の記憶が失われたり、人類が消滅したり、全ての記録媒体が失われたりしても、その歴史そのものがなくなるわけではありません。ここで言う歴史は誰かの記憶や、何らかの資料や記憶媒体に残された記述や記録のことではなく、現実の歴史そのものです。タイムマシンが開発されて、過去が書き換えられたとしても、その書き換え自体を含めて丸っと全部残るような歴史です。
記憶や記録が失われても、タイムマシンを使って過去が書き換えられても残るという歴史は、だから認識の対象になるようなものではありません。だからおそらく、愛は、認識の対象になったり、理性で理解できるようなことではないのだと思います。愛の証拠を求めたり、愛を実証したりすることはできないのです。愛は、意味の地平を突き抜けて、存在の方へと向かっていくものだからです。
愛は不可能ではないけれども、こうすれば愛は絶対に実現できるという確実性もないということになると思います。誰かのことを愛していると思っていたとしても、その対象が変わってしまったらそうでなくなってしまうかもしれない。誰かに愛されていると思っていたとしても、別の誰かに置き換えられてしまうかもしれない。誰かを愛するときも、誰かに愛されるときも、そうした可能性に常につきまとわれながら、これが愛でありますようにと祈ることしかできないのかもしれません。
◇愛の祈りのようなもの
愛依がツイスタに投稿したとき、ファンや視聴者に向けて言った言葉は「噂よりもステージを見てほしい。あたしはそこにいるから」でした。「見てほしい」という控えめな言葉に、私はこうした愛の祈りのようなものを感じ取ってしまいます。注意しなければならないのは、ここまでのこうした思考を、愛依もしていたということを言いたいわけではないということです。愛依が実際に何を考えていたかはともかく、イベントシナリオやsSSRのコミュで描かれていたことと語られていたことをもとに考えると、ここに愛の祈りのようなものを読み取りたくなる、ということです。
「見てほしい」と言ったその対象は「あたし」です。SNS上で取りざたされているように、愛依のステージ上での姿や、愛依の普段の姿といった、姿やイメージを特定することなく、それらすべてを包含しうるようなものとして、あるいはそれらから独立するものとして、「あたし」というものが提示されています。この「あたし」は愛依の存在そのものを示しているように思えます。そして愛依は、そんな「あたし」を、「見てほしい」と言うのです。「見てほしい」というのは、ただ見るということだけを求めているということです。ですから、ステージ上のクールでミステリアスな愛依の姿が本当であるとか、本当の普段の姿は陽気で気さくなキャラクターであるとか、そういうことを愛依の方から言うわけでもないし、そういう判断をファンや視聴者に求めたりもしないわけです。確かに愛依はステージ上での姿を作っていましたが、それもまた愛依自身なのであって、ステージ上の姿か普段の姿のどちらかを本当の姿として判断してもらうということ自体を避ける必要があるのです。それゆえ愛依が求めるのは、ただ「あたし」を「見てほしい」ということです。姿やイメージなどの属性ではなく、ましてや噂話などではなく、愛依そのものを見る、ということを求めるのです。
「見てほしい」というお願いは、さらに自分たちのことを正しく認識することを求めることもありません。自分たちをものまねやCGから区別して正しく認識することを求めたとしても、それらが本当に達成できるのかどうかは確証がありません。でも「見てほしい」というお願いは、ただ見るということをすれば、それは達成されます。そしてその見るということが行われたとき、その見るということが行われたという歴史が残るのです。
ここに、愛の可能性が開かれるのです。そしてそれは、ストレイライトに降りかかった問題を切り抜けていくために開かれた道でもあるのです。
◆5.シャニマスが描く存在論
◇ストレイライトからノクチルへ
ストレイライトに降りかかった問題から出発して、私自身の抱いている問題意識とラカンの疎外と分離の概念を経由して、さらに愛の問題について考えて、そうやって長い長い遠回りをしてやっと愛依とストレイライトが出した答えへとたどり着きました。注意していただけたらと思うのは、愛依をはじめとしてストレイライトの3人はこんなことを考えていたのだ!ということを言いたいわけでも、このイベントシナリオを書いた人はこんなことを考えていたのだ!ということを言いたいわけでもないということです。ただ、このイベントシナリオを読んで、私自身が抱いている問題意識との関連性を感じて、そこからラカンの概念などを補助線にしてイベントシナリオについて考えることができるのではないか、ということを考えたということです。
ラカンの疎外と分離の概念を持ち出したのは、大仰すぎるのではないか、大鉈をふるいすぎではないか、と思われたかもしれません。ですが、この概念を持ってくることによって、分かることがまだあると思っています。それは、ノクチルのことです。
「The Straylight」のイベントsSSR【いるっしょ!】の3つ目のコミュで、愛依の家で愛依の妹と弟たちにプライベートなステージを披露した後の場面が描かれています。愛依の家から帰り道でプロデューサーの迎えの車を待っているとき、寒がっているあさひに対して、ここをステージだと思って踊ってみようと愛依が持ち掛けます。あさひは乗り気になり冬優子を誘いますが、冬優子は断ります。そこで冬優子は「誰もいないステージで踊るアイドルがどこにいんのよ」と言いました。それに対して愛依は「ここにいるっしょ~!」と言い、あさひは「ふう~~~!」と楽しそうにしています。それを見て冬優子が笑います。この「誰もいないステージ」が、「あたしたちがいるところにステージはある」という愛依がツイスタに投稿した言葉の中にある「ステージ」の一つの実現なのです。誰もいないステージで踊っても、それを見る観客は誰もいません。でも愛依たちは踊る。そこにステージがある。そしてステージの上にこそ、愛依たちストレイライトはいるのです。意味に優位に立たれていた存在が、ここで意味を追い越して顔を見せるのです。誰が見ていなくても、愛依たちのいるところにステージがあり、愛依たちは、愛依たちこそがストレイライトである、と。ここにイベントシナリオ「The Straylight」が描き出す存在論を私は感じます。
ところで、私は冬優子が「誰もいないステージで踊るアイドルがどこにいんのよ」と言ったとき、すぐにノクチルのことを思い浮かべました。ノクチルは観客がほとんどいないような花火のステージで踊ったり、握手や写真を求めてくるような人がほとんどいないようなケーキ販売の仕事をしたり、アイドル運動会の仕事でカメラに映ることをやめたりしているからです。
◇ノクチルの輝き
ノクチルの仕事を振り返ってみましょう。最初にノクチルにやってきた仕事は、イベントシナリオ「天塵」で描かれた、ネット配信番組でのお仕事でした。その仕事でノクチルは、口パクを求められた上、浅倉透以外の3人を添え物のように扱われることになりました。そこで透たちは、求められた口パクをせず、番組側からの要求を拒否したのです。その仕事の様子が知れ渡ったノクチルは、しばらくの間仕事がなくなることになりました。その後プロデューサーが取って来た仕事は、花火大会でのステージでしたが、そこではほとんどの人は花火の方に注目しており、ノクチルのステージを見てくれる人はほとんどいませんでした。
ここには、番組側(アイドル業界側)からのアイドルとしての要求を拒否すると、誰にも見てもらえなくなる、という構図があります。でも、花火のステージをプロデューサーはしっかりと見ていました。そしてそのステージと、その後に海に飛び込んだノクチルの姿に、プロデューサーは特別な輝きを感じるのです。この輝きは、存在そのものの輝きであると、今の私は思います。
この存在そのものの輝きは、ノクチルの次のイベントシナリオ「海へ出るつもりじゃなかったし」でも描かれていると思います。透たち4人は、最初、プロデューサーから打診された地上波放送のアイドル運動会の仕事を断ります。冬休みの間の急な仕事の依頼だから断ってもいいとプロデューサーは言いましたが、地上波放送の仕事に出られるチャンスはめったにないのですから、テレビに映りたい、アイドルとして人にたくさん見られたい、という意欲があるならばその仕事を断らないはずです。でも透たちはそれを断るのです。急な仕事の依頼ですから、透たちは忙しかったり大事な用があったのかなと思えば、描かれる冬休みの透たちにはそんな様子はありません。普通に冬休みを過ごしています。
そしてその後、もう一度、ノクチルにアイドル運動会の仕事の依頼がやってきます。今度はその仕事を受けることになるのですが、それにも特別な理由があるわけではありません。で、そのアイドル運動会で、ノクチルは騎馬戦をすることになるのですが、プロデューサーに優勝してほしいと言われます。透たちはこの要求に対して乗り気になり、騎馬戦の練習をするようになります。本番当日も、テレビに映ることよりも、騎馬戦に勝つことを優先して、カメラを避けさえもします。結果として優勝することはできなかったのですが、ノクチルは最後の3組に残ることができました。が、実際の放送を見るとノクチルの映像は丸まるカットとなっていたのです。
ノクチルは今のところ、アイドルをやるということに特別な理由がありません。それにアイドルであるということに執着したりもしません。アイドルとしてカメラに映ることを求めていないのです。それでも、騎馬戦の練習をして、優勝するために本番で立ちまわったノクチルには、特別な輝きがありました。カメラには映っていない(放送されていない)、ノクチルの存在そのものの輝きです。
「海へ出るつもりじゃなかったし」で、年越しの瞬間に続いている夜の道のことを、透は「どこにもつながっていない道」だと言っています。この「どこにもつながっていない」というのは、ノクチルのことを示す言葉でもあるのではないか、と私は読みました。透たちがプロデューサーに仕事の依頼を断るためにメッセージの文面を考えるとき、敬語をどのように使えばいいのか悩んでいました。雛菜は「文章打つだけなのに上とか下とか大変だね~」と言っています。敬語は相手との関係の中で、必要に応じて用いられるものです。それゆえノクチルは、他の誰かに対して上とか下とかそういう関係を作っていないと言うことができると思います。アイドル運動会のお仕事当日でも、控室でほかのアイドルグループが熱心に交流(売り込みでもある)している中、ノクチルは誰とも交流しておらず、格上である中堅アイドルグループに対してかしこまったりもしませんでした。
このようにノクチルは、「どこにもつながっていない」のです。どこにもつながっておらず、いわば存在そのものがむき出しになっているようなものです。そこでノクチルは、光を放っています。その光は存在そのものの輝きです。
◇疎外の拒否
誰もいないステージで踊り、カメラを避けて放送されないアイドルであるノクチルと、誰もいない夜道をステージにして踊るストレイライトは、同じ場所にいるのではないか、と私は最初考えました。どちらも意味に対して存在が浮き出ていて存在論的なのではないか、と。
ですが今は、ちょっと違う、と考えています。それは、ストレイライトが疎外から分離を経て自分たちの存在の場所へと立ち戻ろうとしているのに対して、ノクチルはそもそも疎外を拒否しているのではないかと思うからです。
ネット配信の番組側から、アイドルとしてこういう風であってほしいと要求されますが、透たちはそれを拒否します。そしてその後に立つことができたステージは、見てくれる人がほとんどいませんでした。また、ノクチルはアイドルならば多くの者が出たいと願うはずの地上波放送のテレビ番組において、カメラを避けさえもします。そして実際に出演シーンは丸まるカットとなります。ノクチルはどこにもつながっていません。存在がむき出しになっています。ノクチルは疎外を拒否しているのです。
ラカンは、存在と意味の2択が突き付けられたとき、存在の方を選べば意味どころか存在さえも失うことになる、と言いました。存在そのものを、存在している!と有意味に言うことはできないからです。「この私が存在する!」と叫んだところで、それは有意味な言葉として聞き取られることはないのです。存在するということに意味を持たせるためには、何が存在しているのかということが言えるのでなければなりません。だから意味を選ばなければ、意味だけでなく存在も失ってしまうのです。
ノクチルは、この2択において意味を選ぶことを拒否しているのだと思います。番組や業界が求めるアイドルの姿を拒否し、テレビカメラにアイドルとして映ることも拒否する。そして何のためにアイドルをするのかとか、どんなアイドルになりたいのかということもありません。ノクチルは、意味の地平に乗っかっていないのです。その結果ノクチルに待っていたのは、誰も見ていないステージであり、出演シーン全カットでした。意味への疎外を拒否すれば、存在するということが言えなくなるのです。
でも、そこでノクチルは光を放っています。どこにもつながっておらず、認識してもらえない存在そのものが、光を放っているのです。「天塵」のラストで、ノクチルのその輝きを見たプロデューサーは、この輝きをどうすれば伝えることができるのかと自問していますが、これを人に伝えるのは至難の業だと思われます。果たしてプロデューサーはこのノクチルの輝きをどのようにしてプロデュースしていくのでしょうか。
ところで意味への疎外を拒否する、というのはノクチル自体だけでなく、透と円香にも見受けられます(小糸と雛菜は今のところ不明です)。透は、相手が言った隠喩的な表現に対して、隠喩的意味を素通りして文字通りの言葉を受け取ることがあります。ノクチルが初登場したコミュで、プロデューサーがアイドルのことを「虹をかける」と表現したのに対し、透は本当に文字通り虹をかけることができるのかを確かめようとしました。そして円香は、プロデューサーが言う言葉に対して警戒を怠らず、プロデューサーの言葉に乗せられたり、プロデューサーの言葉に円香自身が捕らえられることを避けようとします。そこで円香はプロデューサーの言葉にあるロジックの穴を突き付けるのです。
透は相手の隠喩的意味を素通りして言葉を文字通りに眺め、円香は相手の言葉を交わしてそのロジックを眺めます。透も円香も、相手の言葉の内部に入って行かないのです。ノクチルのライブアピールでの効果が「回避」であるのもここに繋がっているのではないか、と思います。回避はノクチルの特徴ですから、小糸と雛菜にも、それぞれ意味への疎外を拒否する態度があるのではないかと思って居るのですが、それが何であるのかはまだ分かっていません。
◇シャニマス3年目のテーマ
シャニマスの3年目は、テレビ番組や業界に求められるアイドルという姿への疎外と、疎外によって見えなくなってしまう存在の存在論を描いてきたのではないか、と考えたくなります。順に見ていきましょう。
まず4月の頭に、3年目のテーマソングとも言えそうな「シャイノグラフィ」と「Dye the sky.」の収録された「GR@DATE WING 01」が発売されました。「シャイノグラフィ」では、「この空をキャンバスにして/誰のでもない 瞬間を/新しく記していこう/光空記録(My shinography)」と歌っており、記録を残すことを表現しています。重要なのは、「誰のでもない」というところではないかと思います。他の誰でもなく、自分自身の記録だということです。
そして「Dye the sky.」では、写真に写った自分のことを「けど既に他人みたい/あの時の自分じゃない」と歌い、さらに「低解像度な偽物だ」とまで言います。強烈なのは「キャンバスを裂くように」という表現で、「Dye the sky.」は写真に写されたり絵に描かれたりすることを拒否する態度があるように思われます。つまり像にされることに対する拒否です。
◇ストーリー・ストーリー
そして4月の終わりにアンティーカの「ストーリー・ストーリー」がありました。このイベントシナリオでは、アンティーカがリアリティショーと呼ばれるジャンルの番組に出演することになります。アンティーカの5人が、決められた期間一つの家で暮らし、その様子を撮影して番組にする、というものです。この番組は視聴者に好評なら番組の期間が延長されるルールがあり、アンティーカの5人はそれを目指しました。番組として面白くするために霧子と摩美々と咲耶は様々な策を実行するのですが、どれも失敗してしまいます。そして面白い番組が成立しないと思われ、番組制作側に勝手にアンティーカメンバーが仲たがいするという嘘のストーリーを映像編集で作られてしまうのです。これに対してアンティーカの5人はショックを受けます。番組制作側の言い分はこうです。視聴者は面白い物語を求めているが、ただの生活が物語になるはずがない。面白い物語がなければ視聴者が満足しないから、だからアンティーカメンバーが仲たがいするという物語を作らせてもらった、というものでした。番組制作側によって勝手に作られた物語に、アンティーカは疎外されてしまっているわけです。
これに対して霧子が打開策を発案します。番組側に物語を作られてしまうなら、自分たちで物語を作った方がいいという策です。番組側が勝手に作る物語は、虚偽のアンティーカの姿を描きます。そこに本当のアンティーカの姿はありません。だからといって自分たちで物語を作ったとしても、製作側に勝手に編集されるリスクは消えません。でも勝手に編集されたとしても、自分たちで作った物語は嘘ではない物語ですから、本当のアンティーカはそこに残ります。霧子はその方がいいと考えました。そして残りの4人は霧子の提案した策に乗ることにするのです。霧子の策には、疎外に対してそれを拒否するのではなく、一旦それを受けいれた上で、自分たち自身から出てくるものによって自分たちを描こうとするという、分離の過程に相当するものを読み取ることができます。
ただ、自分たちで作りだすものとはいえそれは物語ですから、その物語に対して自分たちを合わせていかなければならない部分もあります。摩美々はそのことに敏感で、「カメラの外でも嘘じゃないストーリーにする」と言って、カメラに映らない家の外でもパンをくわえて走ろうとしたりします。ですが、これに対して霧子が答えて言います。「生きてることは……物語じゃ……ないから…… わたしたちがわたしたちなら……ほんとは……どこにも嘘なんて……」と。ここに存在論が現れています。生きるということはただ人間として存在するということで、それは物語ではないのです。物語には始まりと終わりがあって、面白かったりつまらなかったり感動的だったりしますが、生きるということはそういうものではありません。また、実在する人物や出来事を描いた物語なら、その物語は事実と一致しているかどうかという真偽の問題が発生しますが、ただ生きているということ、ただ存在しているということは意味の外部にあるのですから、真偽の問題の対象にはならないのです。
ですが、存在そのものは意味の外部ですから、それを言葉で捉えることはできないはずです。霧子はここで、言葉で捉えることができないはずのその存在そのものを、どうにか言い表そうとしています。それが、「わたしたちがわたしたちなら」という表現です。ここで言われている「わたしたち」は、愛依がツイスタに投稿した「あたし」に相当するものです。そしてその「わたしたち」が何であるかを言うために述語を結び付けるとき、何らかの属性を持ってくるのではなく、主語である「わたしたち」を反復するのです。「わたしたちがわたしたちなら」という表現は、「AはAである」という表現です。この同語反復的な文は、紛れもない真理ですが、情報量がなく意味がない文であるような気がしてしまいます。ですが無意味であるとも言い切れません。「~は…である」という、主語を説明する形式の文を使うことによって、主語「わたしたち」が何であるかということを説明するニュアンスが含まれます。そして、何であるかということを示すときに「わたしたち」を持ってくることで、それは「わたしたち」そのものであるという意味が発生するのです。これによって、「わたしたち」の輪郭線のようなものが浮かび上がるように思われます。その輪郭線が示すものは、「わたしたち」より大きくもなく小さくもなく、余計なものを付け足しているわけでもなく何かが足りないわけでもなく、「わたしたち」にぴったりと一致しています。つまりそれは「わたしたち」の存在そのものを示しているのです。このように主語を反復して述語として結びつけることによって、その存在そのものを言葉の上で指し示すニュアンスが込められるのではないかと思うのです。
◇カメラと写真と、存在
このように立て続けに存在論を描いたものがあり、6月末にノクチルのイベント「天塵」があります。そして12月末にノクチルの2つ目のイベント「海へ出るつもりじゃなかったし」があり、年が明けて1月末にストレイライトの「The Straylight」が続いています。
またその間に、注目するべきイベントが2つあります。ひとつは、5月末のイルミネーションスターズの「くもりガラスの銀曜日」です。これはくもりガラスを通して向こう側を見つめることが描かれています。ガラスはくもりガラスなので、向こう側にあるものをはっきり見ることはできないのですが、だからといって向こう側にあるものを見つめることを諦めたくはない、ということが語られます。くもりガラスを通して向こう側を見るというのは、レンズをのぞきこむカメラ的な所作です。レンズがくもりガラスになっているということは、カメラを通して見えるもの、写真に写るものは、対象の十全な像ではないということを示しているように思えます。でもだからといって、見ることを諦めたりはしない。これは意味や写真から逃れていく存在そのものに対する、カメラや写真の側からの決意と倫理的な態度であると言えるかもしれません。
そしてもうひとつは11月末の「明るい部屋」です。このイベントタイトルは明らかにロラン・バルトの写真論の本が由来になっており、イベントシナリオと写真がどのような関係にあるのかということは興味深い問題となっています。杜野凛世のイベントSSRのイラストも、窓をレンズに見立てたカメラの内部のような構図になっていて、カメラや写真を連想させます。これら2つのイベントはどちらもカメラや写真を思わせるものとなっており、「シャイノグラフィ」と「Dye the sky.」が3年目のテーマであることを考えるとき、これらのイベントも無視することはできません。
◇アイドルの存在論
シャニマスの3年目のテーマを、「シャイノグラフィ」と「Dye the sky.」という裏表のような2曲の歌とアンティーカの「ストーリー・ストーリー」に始まる、アイドルの存在論であると整理してみたくなります。それはカメラとの関係の中で、アイドルという意味と像へと疎外されることに対する存在の側の抵抗です。あるいは存在に対するカメラの側の倫理です。ストレイライトは疎外から分離へと進み、ノクチルははっきりとそれを拒絶するのです。
これらを通して、業界が求めて番組や広告に映し出すような、像や「商品」としての“アイドル”ではなく、アイドルをする者たちの存在そのものを、描いているように私には思えてくるのです。そして私のような、存在に関する問題意識を抱いている人間にとって、意味に優位に立たれてしまう存在を取り出してくれるということが、意味ではなく存在の方を描いてくれるということが、とてもとても嬉しいのです。
◆文献案内
ここまで文献からの引用などは行ってきませんでしたが、考えの背景や土台となっている文献や議論がありますのでそれらを紹介してこの文章を終わりたいと思います。
◇ラカンについて
ラカンの疎外と分離の概念は、ラカンの講義録(セミネール)の11巻を参照しています。16章と17章で主にその概念について語られています。
ジャック・ラカン,『精神分析の四基本概念』小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭訳,2000,岩波書店.
『精神分析の四基本概念』は2020年に文庫化されており、入手しやすくなっています。
ただ、いきなり『精神分析の四基本概念』を読むのはしんどいと思いますので、ラカン入門として次の3冊をご紹介します。
片岡一竹,2017,『疾風怒涛精神分析入門――ジャック・ラカン的生き方のススメ』誠信書房.
松本卓也,2015,『人はみな妄想する――ジャック・ラカンと鑑別診断の思想』青土社.
向井雅明,2016,『ラカン入門』ちくま学芸文庫.
片岡さんの『疾風怒涛精神分析入門』は、精神分析とはどういう営みなのかというところから紹介してくれており、精神分析自体が初めてという方におすすめできる本になっています。片岡さんご自身が精神分析を受ける経験をしており、その経験に基づいて書かれているところも良いところです。
松本さんの『人はみな妄想する』は、精神科医の観点から、神経症と精神病(それぞれ精神分析における診断カテゴリです)それぞれの構造を区別して理解することを目指した本になっています。神経症と精神病を分ける(鑑別する)ことが必要なのは、それぞれで治療の仕方が全く異なってくるからです。松本さんの記述はおそろしいほど分かりやすく整理されており、ラカンの概念や考え方を追うことができます。
3冊目は向井さんの『ラカン入門』です。この本は1988年に出版された『ラカン対ラカン』の増補改訂版です。ラカンの思想や概念を時代に沿って解説してくれいて、前期と後期との思想的な発展を理解する手助けとなってくれます。『精神分析の四基本概念』を開設した部分もあり、疎外と分離について段階を踏んで説明してくれています。
また、ラカンは「フロイトへの回帰」を掲げてフロイト読解として講義を始めた経緯があり、ラカンを読み理解するにあたってフロイトにまでさかのぼるというのは重要な手です。そこで主に重要になってくるのは、メタサイコロジー論と呼ばれる論文群です。メタサイコロジーというのは、精神の力動(意識と無意識のダイナミックな関係や運動)の理論です。文庫で読めるものをご紹介します。
ジークムント・フロイト,『メタサイコロジー論』十川幸司訳,2018,講談社学術文庫.
ジークムント・フロイト,『自我論集』竹田青嗣編,中山元訳,1996,ちくま学芸文庫.
『メタサイコロジー論』と『自我論集』は、重複している論文も入っていますが、どちらにも文庫で読める良さがあります。『メタサイコロジー論』は、1910年代にフロイトが出版を計画していたメタサイコロジー論集をまとめて読めるようにしたものとなっています。
『自我論集』の方は、フロイトがそれまでの自身の理論を更新することになった1920年の「快感原則の彼岸」と、その理論更新後のメタサイコロジーとも言える「自我とエス」が読めるのが良いところです。
◇愛の問題について
愛の対象となっているのは、存在ではなく属性に過ぎないのではないかという問題は、次の論文での議論が下敷きになっています。(私と同じ属性を持つ人間がいたら、その人物は私に成り代わってしまうのではないかという問題もまた次のクロートの論文で扱われていますが、この問題それ自体は私個人から出て来たものです。)
ロバート・クロート,「ウォルターはサンドラを本当に愛しているのか?」永井均訳,1989,『現代思想』17(7): 74-91.
またこのクロートの議論は、固有名の名指しの議論が背景になっています。その代表的なものが次のクリプキの著作です。
ソール・クリプキ,『名指しと必然性――様相の形而上学と心身問題』八木沢敬・野家啓一訳,1985,産業図書.
またこのクリプキの『名指しと必然性』は、バートランド・ラッセルの議論を批判したものとなっています。
バートランド・ラッセル,「指示について」清水義夫訳,1986,『現代哲学基本論文集』勁草書房: 45-78.
ラッセルは「指示について」で、記述理論と呼ばれる考えを展開しています。ラッセルによれば、固有名は属性の束であり、属性をひとつずつ拾い上げていくことで1人の人物を特定することができます。
クリプキの『名指しと必然性』はこの記述理論を批判しています。もしラッセルの記述理論が正しいとしたら、「哲学者にならなかったソクラテス」のような固有名に関する反実仮想的な文を考えることができなくなってしまうからです。現実にソクラテスは哲学者ですが、もしかしたらソクラテスは哲学者にならなかったかもしれませんし、戦争に行かなかったかもしれません。哲学者にならなかったとしても、戦争に行かなかったとしても、ソクラテスはソクラテスに違いありません。ですから、哲学者であるとか、従軍経験があるとか、そういった諸性質はソクラテスという固有名にとって本質的な属性ではないのです。
この記述理論に対するクリプキの批判が、愛の対象が属性であったらそれは愛であると言えるのかというクロートの愛の議論と対応するわけです。
この愛の問題は、次の永井均の著作でも取り上げられて議論されています。
永井均,2007,『翔太と猫のインサイトの夏休み』ちくま学芸文庫.
時空上の連続性という概念も永井均によります。でもこの概念を直接教わったのは入不二基義先生からでした。愛の問題に関しては入不二基義先生の指導で卒論を書いたときに学んだことがたくさんあるので、どの著作からと特定できない源泉がたくさんあります。
*Privatterの投稿は削除済み
◆はじめに
この文章はシャニマスが描いていると思われる存在論について、私個人の問題意識から考えているものです。ストレイライトのイベントシナリオ「The Straylight」で冬優子たちが直面した問題と、最後に愛依が出した答えが、ここで考えている話の軸になっています。まず冬優子たちが直面した問題を私個人の問題意識に引き寄せて読みます。それから愛依が出した答えを、ラカンの疎外と分離の概念、それから愛についての哲学的な議論を経由することで、理解しようとしています。
そして最後に、3年目のシャニマスが描いていると思われる存在論を、主にストレイライトとノクチルの比較を通して考えます。ラカンの疎外と分離の概念を経由することで、ストレイライトとノクチルそれぞれで、アイドルの存在論のあり方が異なっていることが分かると思われるのです。
目次
◆はじめに
◆1.存在論の問題
◆2.ラカン的観点から
◆3.ストレイライトの答え
◆4.愛の問題
◆5.シャニマスの描く存在論
◆文献案内
◆1.存在論の問題
◇意味の優位
私がシャニマスについての感想や読解の文章を書くとき、よく「存在論」という言葉を用いていますが、そこで「存在論」という言葉で言い表そうとしているのは、意味や認識に対して存在(するということ)の優位性があるということです。何かが存在するということ、誰かが存在するということは、当たり前のことであるように思われますが、実はそうとも言い切れないところがあります。そして存在に対して意味の方が優位になるとき、ある問題が発生します。
たとえばいま目の前に1本のペンがあるとします。そこにあるペンを見て「ペンがある」と考えることができるわけですが、その目の前にあるペンというのは、日常生活においてはたいてい書類やノートなどに書き物ができる文房具として利用されているはずです。そのときそのペンは、単に「ある!」ということよりも、書き物ができる道具としての側面が重視されています。そのように利用できるというところに、そのペンの意味があります。ここで存在に対して意味が優位に立っていることになります。「それがある!」ということよりも、「それは何であるか」「それはどんな風に有用であるか」ということの方が重視されているのです。
その意味の重視の観点からすれば、そのペンは別のペンで代用可能なものとなります。なぜならそのペンはそのペンそのものであるということが重要であるのではなく、書き物ができる文房具であることが重要であるので、書き物ができる文房具であれば別のペンであっても構わないからです。したがって、日常生活において「ペンがある」というときに考えられているのは、「そのペンそのものがある」ということではなく、「書き物ができる文房具が1つある」ということになるはずです。後者のように考えられているとき、そこにあるのは代用可能な道具であって存在そのものではありません。
人間にも同様のことが起こります。ある人間が存在するとき、その人間個人が存在するということよりも、その人間は何者で、どんな仕事がこなせて、どれほど有用であるか、ということの方が重視される場面があります。とりわけ、働くというときにその面が強く出てくることになります。そこで1人の人間は、固有な人間としての存在よりも、何者であるかという意味の方が重要とされるようになります。そして意味の方が重視されるとき、道具と同様にその人間は別の人間に代用される存在となるのです。
このように、道具にせよ人間にせよ、何かがある誰かがいるというときに、存在に対して意味の方が優位に立つということは日常的にかなりあることです。
ですが存在に対して意味の方が優位に立つと、ある問題が発生します。存在に対して意味が優位になると、人にせよ物にせよ存在するものはひとつの固有なものであるはずなのに、それらは別のもので代用可能となってしまうという問題です。存在の固有さが失われてしまうのです。
◇ストレイライトに降りかかった問題
イベント「The Straylight」でストレイライトの3人が向き合ったのはこの問題だった、と言うことができます。
音楽番組に出演することになったストレイライトは、アイドルとして以上に、その実力を視聴者に見せつけることを目論みますが、ミュージカル出身の実力派アーティストグループの前に敗北を喫することとなります。ここでストレイライトは、アーティストとしての実力という尺度で、自らの位置を見定めています。この「アーティストとしての実力」というのは、働く人の有用さに相当するような、意味の水準に人を置く尺度です。
で、このアーティストが、ストレイライトのものまねをテレビで披露することになります。冬優子は、実力の差を見せつけられたアーティストグループに対し、自分たちこそが本物のストレイライトであるということを実力で示すことを狙います。そしてそれは達成されることになりました。
ここで冬優子たちは実力で圧倒することによって、自分たちこそが本物のストレイライトであるということ、あなたたちはものまでであり偽物であるということを示したわけですが、重要なのは実力でそれを示したということです。ものまねであるストレイライトカッコニセと冬優子たちストレイライトは、アーティストとしての(あるいはアイドルとしての)実力という同一の尺度の上で比較されています。そしてその度合いの高い方が本物として認められた、ということになっているのです。冬優子たちが本物であるのは、冬優子たちが「ご本人」であるからではなく、実力があるからなのです。ここが重要です。「ご本人」であるという存在に対して、実力の有無という意味の方が優位に立っているわけです。
この意味の優位はまだ続いており、ものまねであるストレイライトカッコニセに続いてCGで再現されたストレイライトのMVというものが冬優子たちの前に現われることになります。ストレイライトカッコニセは、実力派アーティストグループであったとはいえしょせんものまねです。ですが、今回冬優子たちの前に現われたのは、冬優子のいくつもの注文を実現して制作されたCGのMVです。その完成度を冬優子も愛依もあさひも認めないわけにはいきません。このCGについて愛依は「本物」と言い、さらにあさひは「完璧」だと言います。この「完璧」というのは、冬優子たちがストレイライトであるために目標としていたものでした。冬優子たち自身ではなく、冬優子以外の人間によって作られたCGが「完璧」なストレイライトとなってしまったのです。CGが「完璧」なストレイライトであるならば、CGのストレイライトは冬優子たちに成り代わることができるわけです。その可能性が冬優子たちの前に現われます。
冬優子たちの前に、ものまねたCGのストレイライトが現れ、それらが冬優子たちに成り代わる可能性が示されるのは、冬優子たちはストレイライトをアイドルとして作り出しているからです。冬優子たちが作りだすアイドルグループストレイライトは、テレビの中に映る像であり、雑誌やネットの記事で書かれる文章であり、ファンや視聴者が想像するイメージです。なので、それらを作り出すことができるのであれば、その役目を果たすのは冬優子たちでなければならない理由はない、ということになります。ストレイライトというアイドルグループは、書き物ができる文房具としてのペンと同様の水準にあります。々役目を果たすことができるなら、代用可能なのです。
そしてこの問題は今一度冬優子たちに降りかかることになります。イベントシナリオの最後に、冬優子たちは愛依の家で愛依の妹と弟たちにプライベートなステージを披露するのですが、そこで冬優子たちは愛依の弟に「ニセモノ」「カゲムシャ」と言われてしまうのです。今までは、ものまねのストレイライトカッコニセや作られたCGが、「それは本物か」と問われていました。そこではいわば、冬優子たちではない別の何者かが冬優子たちに成り代わろうとしていて、本物かという疑いが向けられていました。冬優子たち自身ではないのですから、本物かという疑いが向けられるのは当然であるような気がします。ですが、ここではその問い=疑いが、紛れもない冬優子自身にまで向けられるのです。
存在に対して意味が優位になるとき、あるものがあるものであるかどうかは、それが当のそれそのものであるということよりも、それがそのあるものとしての役割を果せているかどうかということの方が、より重要になるわけです。だから「ストレイライト」というアイドルユニットがどのようなものであるかということを満たさないものについては、たとえそれが冬優子たち自身であっても、「ニセモノ」「カゲムシャ」と問い=疑いが向けられることになるのです。このときもし、冬優子たちよりももっとストレイライトらしい人たちが他にいたとすれば、冬優子たちではなくそちらの人たちの方こそが本物のストレイライトだということになってしまうでしょう。
冬優子たちよりもストレイライトらしい人たちが実際に登場することはありませんでしたが、イベントシナリオで描かれてきたことをふまえた上で冬優子たちにまで問い=疑いが向けられると、そうした人たちが存在しうる可能性は自然と発生してくると思います。意味が存在に対して優位に立つとき、問題はここまで進むことになるのです。これは恐ろしいことだ、と私は思います
◇この私が存在するということを言えるか
この問題に対して冬優子たちがどのような答えを出したのかを検討する前に、もう少しこの問題をよく見ておきたいと思います。というのも、この問題は私にとって非常に切実な問題であったからです。
デカルトが全ては夢であるかもしれないと方法的懐疑を行った先に、唯一存在を疑いえないものとして見出したのは、考える自分の存在でした。たとえこれが夢であるかもしれないとしても、そのように疑っている自分自身はいま存在しているのであり、そのことは決して疑いえない、ということです。
私は、いま確かに存在しています。ですが、この私が存在するということは、世の中においてはある特定の何者か、たとえば響きハレというような名前の何らかの属性を持った何者かが存在するということです。実は「この私が存在する」ということと、「響きハレという名前の何らかの属性を持った何者かが存在する」ということは、全く同一のものというわけではありません。というのも、この私がいまこのように持っているのとは別の属性をもっていたかもしれないという可能性が考えられるからです。だから、私がいま持っている全ての属性と同一の属性を持つ何者かがいたとしても、その人物がこの私であるとは限らないのです。
ですが、世の中は一般的にそれらの差異に対してそれほど敏感であるわけではありません。上でも書きましたが、存在に対する意味の優位が色濃く表れるのが、労働の場面です。存在に対して意味が優位になるとすると、私の代わりを務める人物はいくらでも存在しうることになります。私がたとえばaとbとcという要素を満たしていて、そのことをもって響きハレという人物が労働において有用さが認められているとすると、aとbとcを満たす人物であれば、私以外の誰でも私の代わりを務めることができるようになります。もし私以上にうまくその要素を満たす人物がいたとしたら、私は用済みになってしまうかもしれません。
これは労働の場面ですが、存在に対する意味の優位を押し進めると、響きハレという人物が存在するということまで問題は進んで行きます。この私はいまここに響きハレという人物として存在していますが、意味の優位の観点からは響きハレという人物が存在しているということは、この私が存在するということではなく、ある特定の属性を持った人物が存在するということです。ですから、この私がいま持っている全ての属性と同一の属性を持つ何者かがいたとすれば、その人物がこの私であるかどうかは関係なく、ともかくその人物が響きハレだということになります。ある人物が存在するとはある特定の属性を持った人物が存在することだという風に、存在に対して意味が優位になるのです。
ここに、この私に成り代わって響きハレという人物であるような、私以外の何者かが存在する可能性が差し挟まれることになります。この私に成り代わる私ではない偽物が存在しうるということではなく、この私こそが偽物とみなされてしまうようなより本物らしい別人が存在しうる、ということになります。
このとき、「いや、この私こそが本物の響きハレだ!」と叫んだところで何にもなりません。その何者かは、この私が持つ属性と全く同じ属性を持っているわけですし、客観的には区別することができません。私が差し出すことができるのは、この私であるというデカルトが懐疑の先に見出した一人称の存在だけです。でもそんなもの、私以外の誰にも認識することはできないのですから、世の中においてはそれは存在しないも同然です。ですから、もし多くの人がそちらの人物の方を「本物だ」とみなすなら、そちらの方が本物だということになってしまうのです。この私がこの私であり本物である!という叫びには何の意味もありません。この私の存在は、意味に対して無力なのです。響きハレが存在するということは、この私が存在するということではなく、ある特定の属性を持った人物が存在するということであり、そうでなければ「存在する」ということに意味を持たせることができないのです。
存在に対する意味の優位は、ここまで進んで行きます。私はこの問題を非常に恐ろしい問題であると考えています。
◆2.ラカン的観点から
◇疎外
この私はここに存在する!と叫んだとしても何にもならないように、世の中において存在が認められるために重要なのは、何であるかという意味です。どこそこの生まれであるとか学歴や職歴がどのようなものであるとか、これこれの専門知識や技術があるとか、そういったものを持っているということこそが、この世において何者かが存在するということです。
自分自身の固有の存在が、何らかの意味や何らかの役割に置き換えられて、失われてしまうのです。これは悲しいことですが、この世において生きていくためにはある程度は仕方のないことです。このように存在が意味に置き換わってしまうことを、哲学の用語で「疎外」と言います。疎外はネガティブな現象として捉えられてきましたが、精神分析家ラカンは、人間が疎外を被るのはある程度仕方のないことであると考えています(ラカン『精神分析の四基本概念』を参照)。
疎外を被るのはある程度仕方がないというのは、上で見たように、意味に対して存在そのものを主張しても何にもならないということによります。ラカンはこのことを、強盗に突き付けられる問いにたとえています。いま強盗に押し入られ、刃物を突き付けられているとします。そこで強盗が言います。「金か命か!」。これはいわば「命が惜しかったら金を出せ」ということなのですが、ここで金を選んだとすると、強盗に殺されてしまって、結局金と命の両方を失ってしまうことになります。金を差し出せば、金は失いますが命は残ります。
存在と意味は、このたとえではそれぞれ金と命に相当します。意味に対して存在を主張すれば、何者であるかという意味を持つことができないばかりか、存在するということさえ主張できなくなってしまいます。というのも、存在するということが認められるのは、何らかの属性を持った何者かが存在するということだからです。意味の方を選べば、これこれの誰々という何者かとして存在が認められますが、自分自身の固有の存在は失ってしまいます。固有の存在は失ってしまいますが、一人の人間として世の中に普通の意味で存在することができるようになります。このようにラカンはこのように疎外のネガティブな点だけでなくポジティブな点も捉えています。
◇分離
ネガティブな側面だけではないとはいえ、疎外を被るということは意味に置き換わってしまうことであり、自分自身の固有の存在を失ってしまうということには違いありません。この失ってしまった存在を、完全な形で取り戻すことはできません。この私が存在するということそのものを、有意味に言うことはできないからです。ですが、失った存在を取り戻すのとは違う形で、自分の固有さを形成する道があります。それは、ラカンが「分離」と呼んだものです。
分離は、意味へと疎外されて存在を失った主体が、ある特殊な対象と関係を構築することで、自分自身の固有さを再び作り出すことができるような、そういう演算です。
人は疎外を被ることで意味へと置き換わり、固有の存在そのものを失ってしまうわけですが、それでも意味へと置き換えることができずに残ってしまうものがあります。その一つとして挙げられるのが、肉体です。特に、思考したりイメージしたりして自分自身の体だと認識されずに残ってしまうような肉体の部分がそれに相当します。手や足などは自分の目からもよく見え、自分で意識して制御することができる部位で、自分の身体の一部としてイメージの中に取り込める部位です。ですが、内臓などは意識的に制御することができないばかりか、それらがはたらいていることすら気づかないものもたくさんあります。でもそういうものがこの体の中で動いているからこそ、この体が生きているということを可能にしています。思考したりイメージしたりすることができないという点で、それらは意味の外部にあります。意味の外部にあるので、それらが何であるのか、そもそもそれらが存在すると言えるのかも確かではないのですが、でもその意味の外部にあるものこそが、人が実際に生きているということを可能にしているのです。
日常的に内臓を直接見たりすることはできないですが、その内臓のはたらきを実感することができるものがあります。それは排泄物です。食事をして、その後に排泄物が出るということが、内臓がはたらいているということの証拠であり、自分が生きているということの証拠になります。その証拠によって確かめられる「生きている」ということは、意味へと置き換えるきることはできません。たとえばこのようにして、分離は達成されていきます。
ここでは内臓や排泄物の例を出しましたが、分離が達成されるために求められる対象はそれだけではなく、さまざまなものがその対象となりえます。ラカンはそうした役割を果す対象を、対象aと呼びました。対象aとなりうる対象は、意味に充分に置き換えることができないものです。つまり、一般に取るにたらないとされるものや、意味がないとされるもの、価値がないとされるものだと言えます。そうしたものを、自分自身の固有のものとして認めるとき、それがあるということをもって、自分自身があるということにする、という構図をつくることができるようになるのです。そうすることで、自分自身の存在そのものを取り戻すことはできないけれど、自分自身の固有さを形成することができるのです。ここで自分自身の固有さを形成することを、ラカンは「幻想」と呼びます。このように幻想を構築することが、疎外に続く分離です。
◇問題への答え?
分離によって、自分自身の固有さを幻想として形成することができたとして、それは自分に成り代わる別の人間がいるかもしれないという問題を退けることができるのでしょうか。
ここは微妙であると私は思います。私という人間が別の人間に成り代わられてしまう可能性が開かれるのは、私という人間が何者であるかという意味に置き換わってしまうからです。別の言い方で言えば、私という人間がいくつかの属性の集合へと置き換えられてしまうからです。そのような置き換えがなされれば、それらの属性を全て持つが私ではないような人間が存在しうるということになります。これが問題だったのでした。
分離によって、自分自身の固有さを形成するとき、主体が関係を持つのは対象aと呼ばれる特殊な対象でした。対象aとなる対象は、何らかの物体ですが、それは一般に意味があるとされないようなもの、取るにたらないとされるようなものです。そしてそうした対象が、自分自身に固有のものとされるとき、その対象があるということをもって、自分自身が固有のものとしてあるということにすることができるというわけです。
ここで重要なのは、(1)その対象が意味があるとされないようなものであるということ、(2)自分自身に固有のものとされるということです。自分自身に固有のものとされるのは、例えばそれらが自分自身の肉体に由来するものである場合に(たとえば内臓や排泄物のように)そうであると言えるかもしれません。
もう一つ重要なのが、その対象が意味があるとされないようなものであるということです。排泄物は肥料などにするのでなければ、だいたい日常生活ではそのまま水に流されてしまうもので、不要のものであるはずです。内臓は無意味でも無価値でもないですが、それが現に働いているところを思考したりイメージしたりすることは難しいもので、そういう点で意味の地平に上ってこないものです。これらは意味の外部にあります。意味の外部にあるということが重要です。それが意味の外部にあるとすれば、それは意味へ置き換えられるものの中から零れ落ちることになるわけです。つまり私という人間を属性の集合へと置き換えたとしても、その属性の集合の中に含まれない何かがその外部に残ることになるわけです。そしてその何かが私に固有の何かであるとき、その何かがあるということをもって私が固有のものとしてあるということになるわけです。
ですがこれで問題が完全に退けられるわけではありません。この微妙なポイントも、その対象が意味の外部にあるということに由来します。というのも、もしその対象が完全に意味の外部にあるものだとすれば、それを持つということに意味を与えられないからです。「この私が存在する!」と叫んだときと同じ状況に陥ってしまうことになります。逆にその対象が何であるのかはっきり言ったり認識したりすることができるものだとしたら、それは私に固有のものではなく、誰もが持ちうるものになってしまいます。ここにジレンマが発生するわけです。
なので、対象aの役割を果すものは、意味の外部にあり意味の内部にあるようなもの、自分自身に固有のものであり誰もが持ちうるもの、という矛盾的なものになります。そういう点で特殊なものです。そんなものが存在しうるのかという問いが浮かんできますが、それは客観的に存在することが必要であるというよりも、幻想の上でそのような役割を果たしうるものがあるということが重要なのです。
◆3.ストレイライトの答え
◇ストレイライトの答え1
かなり長い遠回りをしてしまいましたが、ここまで見てきたことによって、冬優子たちの答えがどのようなものだったのかがよりはっきりと見えてきます。
冬優子たちに降りかかっていた問題は、冬優子たちは本物のストレイライトなのか、冬優子たち以上にもっとストレイライトらしい誰かが存在しうるのではないか、という問題でした。この問題に対して冬優子たちが見出した答えは、もう一つ愛依に降りかかっていた問題への答えでもありました。
愛依に降りかかっていた問題は、ステージ上でファンや視聴者に見せている愛依の姿は愛依自身の姿ではなく、嘘の姿なのではないか、という問題です。愛依は緊張しやすいタイプなため、気さくで明るい普段の姿のままステージ上に上がることができませんでした。その緊張している様子を、クールでミステリアスなイメージとして提示することで、愛依は自身のアイドルイメージを作っていったのです。そこで愛依は、そうしたステージ上で自分が見せているアイドルのイメージは嘘なのだから、自分の普段の姿をファンや視聴者に見せるべきなのかどうか悩むことになりました。
この愛依の問題は、冬優子たちに降りかかった問題と重なってきます。もしステージ上の愛依の姿が、作り物で嘘の姿なのだとしたら、ファンや視聴者が受け取って作り上げているアイドル愛依のイメージは、愛依当人とは異なったものとなります。それらが異なったものであるとすれば、クールでミステリアスなアイドル愛依のイメージを作り出せるのは、愛依でなくてもよいということになります。つまりものまねやCGなどの、冬優子たちではない別の人間たちによるストレイライトが存在する可能性が、ここに差し挟まれることになるのです。
この問題に対して愛依は、あさひの発現を受けて答えに辿り着きます。それは、「ステージのうちも、うち」というものでした。つまり、ステージ上でファンや視聴者に見せているクールでミステリアスなアイドル愛依は、作り物でも嘘でもなく、それもまた愛依自身なのだ、ということです。
ステージ上で愛依が見せる姿と、普段の愛依が異なっていると考えると、ステージ上で愛依が見せる姿は愛依ではない別の誰かが見せても良いという問題が発生します。そしてストレイライトというアイドルユニットは、完璧を求めてレッスンを厳しく行ったりユニットイメージを管理したりして、徹底的に作り込んでいくユニットでもあります。そうやって徹底的に作られているからこそ、ストレイライトというユニットは冬優子たちではない別の誰かがやってもよいという可能性を生み出すことになります。
愛依が辿り着いた答えは、ステージ上のアイドル愛依は愛依自身であり、愛依以外にそれを見せることはできないということを意味しています。そしてそれは同時に、ストレイライトというユニットは、冬優子と愛依とあさひの3人でなければならないという考えを示すのです。この答えに辿り着いた後、ステージ直前で冬優子たちのあげた掛け声は、まさに「あたしたちがストレイライト」でした。
◇ストレイライトの答え2
sSSR【いるっしょ!】の3つ目のコミュで、愛依とストレイライトの答えがさらに語りなおされています。そこから、なぜストレイライトは冬優子と愛依とあさひの3人でなければならないのか、ということを読み取ることができます。
とある配信者の動画によって、ステージ上のアイドル愛依の姿は作り物の嘘の姿なのではないか、ということがSNS上で取りざたされていました。普段の愛依の姿をステージ上でも見せるべきなのかどうか迷っていた愛依にとって、またユニットイメージを徹底的に作っていたストレイライトにとって、この問題は無視できない問題でした。愛依が出した答えは、すでに見たように、「ステージのうちも、うち」です。サポートコミュで描かれるのは、その答えに辿り着いた愛依が、どのようにSNS上の人たちにメッセージを発信したか、ということです。愛依がツイスタに投稿した文章が非常に重要です。実際に見てみましょう。
「噂よりも
ステージを見てほしい
あたしはそこにいるから
そして
あたしたちがいるところにステージはあるんだ
#ストレイライト」
ポイントは2つあると私は考えています。ひとつめは、「あたし」という言い方をしているということです。SNS上で取りざたされている「噂」は、ステージ上のアイドル愛依の姿は愛依の本当の姿なのかどうかということや、本当の愛依はもっと別の姿なのではないか、といった姿、イメージ、キャラに関することです。ですが愛依は、姿やイメージやキャラではなく、単に「あたし」とだけ言っています。どんな姿であっても、どんなイメージであっても、どんなキャラであっても、「あたし」は「あたし」だというニュアンスが、ここに込められているように思われます。「ステージのうちも、うち」という答えが、この「あたし」の背後にあるのです。
もうひとつのポイントは、「ステージ」に関することです。愛依は、「あたしはそこ〔ステージ〕にいる」と言い、同時に「あたしたちがいるところにステージはある」と言っています。この転換が非常に重要であると私は考えています。
ストレイライトは、徹底的に作り込まれたアイドルです。プロデューサーに見せるような、普段の冬優子や愛依やあさひの姿とは異なった、別の姿がアイドルユニットストレイライトでは提示されます。この作り込みを、シャニマス公式サイトに掲示されているストレイライトのキャッチコピーは、次のように表現しています。「身に纏うは迷光、少女たちは偶像となる」。「偶像」はアイドルを意味する言葉ですが、「偶像」という言葉を用いることによって、それが何らかのイメージであるということを示すニュアンスが生じます。そして「迷光」は、光学機器の中で発生するフレアやゴーストなどを指す言葉で、ストレイライトの訳語です。「迷光」は、光学機器の中で発生する像を結ばない光で、像を映すためには不必要な光であるとされていますが、写真を演出したり強い印象を与える効果を発揮するものでもあります。つまりアイドルユニットストレイライトは、光学機器の中で発生する、本来は不必要な「迷光」を「身に纏う」ことで生まれる、ということです。アイドルユニットストレイライトには、迷光を生むための光学機器、つまりカメラが必要であるということがここからうかがえます。
愛依がツイスタに投稿した文章の中で言った「ステージ」は、こうしたカメラなどがあって、アイドルユニットストレイライトを生み出すための場所を意味するのではないか、と私は考えたくなります。意図的かどうかは分かりませんが、イベントシナリオ「The Straylight」で描かれる仕事は、全てテレビ番組の仕事でした。カメラなどの機器が設置されたステージの上にこそ、「あたし」はいる。その「あたし」は「ステージのうちも、うち」の「うち」です。つまりアイドル愛依であり、同時に愛依自身です。
そして、愛依はさらに、「あたしたちがいるところにステージはあるんだ」と続けています。これがとても重要なのです。
そもそもアイドルユニットストレイライトは、生まれるためにカメラなどの機器が設置されたステージを必要とします。まずステージがあり、その上に上がることでアイドルユニットストレイライトが誕生するのです。言わばステージは、アイドルユニットストレイライトというを発生させる意味の装置です。ステージが先にあり、その上に上がることで、冬優子と愛依とあさひは迷光を纏うことができ、アイドルユニットストレイライトとなることができる。
ですが、愛依はこう書くのです。「あたしたちがいるところにステージはある」と。「ステージ」が装置として先にあってストレイライトがあるのではなく、「ステージ」の位置を逆転させているのです。まず先にあるのは「あたしたち」です。「あたしたち」が先にあり、その場所にこそ「ステージ」があるというのです。ここに、私はシャニマスの存在論を感じます。アイドルというイメージが先行したり、アイドルを生み出すステージが先行するのではなく、何より先に「あたしたち」という存在がある。私はこの愛依の書いた「あたしたち」に、「この私が存在する!」という存在論の叫びの反響を聞き取ります。
そして、アイドルユニットストレイライトを生み出すことができる装置である「ステージ」を「あたしたち」に従属させることによって、「あたしたち」こそがストレイライトであるということ、「あたしたち」以外はストレイライトではありえないということを示すのです。もし「ステージ」が先行するのだとすれば、冬優子たち以外の別人が、「ステージ」に上がることでストレイライトを提示することができるかもしれません。実際にものまねやCGはそのようにして冬優子たちの前に現われました。でもそうではないのです。「ステージ」は「あたしたち」に従属するのです。これは、上で長い遠回りをして見てきた疎外に対する分離のプロセスそのものではないか、と私は思うのです。
分離を達成するためには、自分自身に固有の対象と関係を持つことが必要でした。ここで愛依たちにとってのその対象は何なのでしょうか。それは「ステージ」を通して発生する、迷光ではないか、と私は思います。冬優子と愛依とあさひが身に纏う迷光は、カメラによって勝手に生み出されるものではなく、「ステージ」を通して自分たち自身から生み出されるものなのではないか、ということです。
冬優子が見せているふゆの姿や、愛依が見せているクールでミステリアスな姿や、あさひが見せているゾーンに入り込んだような研ぎ澄まされた姿は、他の人が真似することができます。CGなどによって再現することもできます。ですが、それら表に現われた姿を支えるものとして、裏側に潜んでいるものを真似したりCGで再現することはできないはずです。冬優子がふゆを生み出すために払っている努力やその背後にある願望も、愛依のクールでミステリアスな姿を支えている極度の緊張も、あさひの研ぎ澄まされたゾーンに入るための集中力も、それらは表に出ているものを支えるものであって表には出てこないものです。いわばそれらは、アイドルユニットストレイライトのイメージや意味の外部にあります。外部にあるので、それらを真似したりCGで再現したりすることはできないのです。そしてそれらはイメージや意味の外部にあるのですが、むしろそれらこそが、アイドルユニットストレイライトをアイドルユニットストレイライトたらしめているのです。思考やイメージの対象にはならないけれど、生きているということを支えている内臓のようなものです。これらが、アイドルユニットストレイライトがアイドルユニットストレイライトであるために身に纏うべき迷光であり対象aなのではないか、と私は考えています。そして「あたしたちがいるところにステージはある」という言葉はここまでの射程を持つ言葉なのではないか、とも思って居ます。
◆4.愛の問題
◇愛は可能か
上で、分離によって達成されるのは幻想の構築であって、問題に対する答えとしては微妙なものであるという風に考えました。もしそうであるならば、愛依たちが辿り着いた答えもまた、微妙なものとならざるをえないのではないでしょうか。
そもそもの問題は、この私が存在しているのに、私という人間は世の中では何らかの意味や属性に置き換えられてしまうことで、その固有さが失われ、別の何者かに取って代わられる可能性があるということでした。それに対して、自分自身に固有の対象と関係を持つことで、その対象があるということを以てして自分自身があるということにするという答えを提示したのが、分離のプロセスでした。でもそこで構築されるのは幻想で、自分自身に固有の対象が客観的にそうであるとはかぎらないのでした。こうして分離のプロセスでたどり着いた答えは、最初の問題に完全に答えることはできずにいたのです。
分離によって辿り着いた答えの場所から、最初の問題に完全に答えるための道がひとつあります。それは、自分自身を固有の存在として他者に認めてもらうことです。自分自身を固有の存在として他者に認めてもらうために、自分自身に固有な対象を差し出すことができるとすれば、それは達成されます。これはいわば、愛の問題だということになります。
残念ながら、ラカンは愛は不可能だと考えていました。自分自身に固有の対象があるとしても、それを他者に差し出すことは不可能だからです。差し出すことができるとすれば、それは誰でも持ちうるようなものとなってしまうのですし、本当に自分に固有のものであるとすればそれは完全に意味の外部のものであって、そんなものを他者に向って差し出すことはできないからです。愛が不可能であるとしたら、最初の問題に完全に答えることはやはり不可能ということになってしまいます。
◇愛の対象
ですが、ラカンに対してここはもう少し食い下がりたいと思います。愛は本当に不可能なのでしょうか。どうすれば愛が実現できていると言えるのか、そういうところから考え始めてみましょう。
Aというある人が、恋人のBという人に「あなたを愛している」と言ったとしましょう。それを聞いたBは、Aの言葉を疑います。「本当にAは私を愛しているのだろうか」と。Bはその疑問をAにぶつけます。「どうして私を愛してくれているの?」と。そこでもしAが、「Bはとても美しいから」とか「Bはとてもお金を持っているから」などと言ったら、Aの「愛している」という言葉の疑わしさはさらに増してきてしまうと思います。
美しさとかお金を理由に挙げるような人があまりにも疑わしいのは社会通念上当たり前のこととされていると思いますが、Aの「愛している」が疑わしいのは、とりわけ美しさやお金を理由に挙げているからというわけではない、と思います。試みに美しさやお金以外の何だったら、「愛している」という言葉を信用にたる言葉にしてくれるか考えてみましょう。優しい、思いやりがある、尊敬できる、特別な出会い方をした、これこれこういうときに助けてくれた……などが思い浮かびましたが、これらのものを理由に挙げてAが「愛している」と言ったとしたら、この「愛している」は信用できるようになるのでしょうか。
私はここに、すでに問題として浮上している、別の人間が置き換わる可能性の問題が介入してくると考えています。Aがどんなものを理由として挙げたところで、それらは全てBではない別の人物も持ちうるものであって、もし別の人物――たとえばC――が、Aが理由として挙げたものを持っていたとしたら、AはCに「愛している」と言うかもしれません。Aが挙げた理由に関して、BよりもCの方が優れていたとしたら、なおさらです。つまり、「愛している」という言葉の根拠としてBの持つ属性などを挙げた場合、根拠として何の属性が挙げられようと、「愛している」という言葉を信用させるには十分ではないのです。つまり、愛の対象はBの属性ではないのであり、Bの属性が対象となっているならそれは愛であるとは言えないのです。
それゆえBを愛しているとき、その愛が真に実現されるためには、Bの持つ属性と同じ属性を全て持つようなBではない別の人物(C)を愛することなく、さらにBの持つ属についてBを上回る属性を持つような別の人物(D)を愛することもないのでなければなりません。つまり、Bの持つ属性ではなく、Bそのものに対して愛が向いているのでなければならないのです。
愛の対象をもっとよく取り出すために、思考実験をさらに押し進めます。SF的な想定ですが、Bが過去の記憶をどんどん失っていき、異なった人格になっていき、さらに見た目の属性もどんどん別のものへ変化していってしまう、という場合を考えてみます。記憶と人格と見た目が、もともとのBとは全く違うものになってしまったとき、Aはそれでもその変化してしまったBのことを愛することができるでしょうか。もし、記憶と人格と見た目が完全に変化してしまったBを愛することができないとすれば、かつてBに向かって言った「愛している」という言葉は、Bそのものに向けられたものではなく、Bが持つ属性に向けられたものだったということになります。そうであるとすれば、それは愛ではなかった、ということになります。さらに、Bの変化が進んで、BがもとのBとは記憶も人格も見た目も完全に異なってしまったとき、もとのBと同一の記憶と人格と見た目をしたBではない別の人物(E)が現れたとしたらどうでしょうか。それでもAがBを愛しているのなら、その愛はEではなくBに向かうのでなければならないのです。つまり愛の対象であるべきBそのもの、人間そのものは、何らかの属性を持ちうる核のようなもの、存在そのものです。
ではその属性を持ちうる核のようなもの、存在そのものを、愛の対象とすることができるのでしょうか。ここで問題は、「この私が存在する!」と叫んだところでそれを有意味なものとして誰も聞き取ることができない、という最初の問題に立ち返ることになります。結局他者が認識するのは認識することのできる部分、理解できる部分だけで、存在そのものはどうやっても他者にとって認識可能、理解可能なものにはならないのではないでしょうか。
◇時空上の連続性
そうではない、と私は思います。何らかの属性を持つ核、存在そのものは、認識したり理解したりすることが完全に不可能なものではない、と思います。Bが変化していってしまう想定をもう一度考えてみます。徐々に変化していってしまうBのそばに、常にAがいたとします。Aは変化していくBを、Bであると認識し続けることができるはずです。もとのBの面影を全く残さないほどに記憶と人格と見た目が変化してしまったとしても、変化していく過程を認識し続けていればAはその人物をBであると認識できます。変化の中でAが認識しているのは、Bという存在そのものなのではないでしょうか。それが可能なのは、Bが物理的に肉体を持ち、時空の中に居場所を持って存在し続けていたからです。その時空上の連続性を追うということが、存在そのものを認識することを可能にしてくれるのです。
この時空上の連続性を追うということがポイントになってきます。時空上の連続性を追うということは、いわば、時空上に連続して存在していたBそのものと共に過ごしてきたということです。Bそのものと共に過ごしてきた時間は歴史となります。その歴史は現実の歴史であり、変わることはありません。Aが共に過ごしてきたのは、時空上に連続して存在している(していた)Bであって、CでもDでもEでもないのです。Bと同じ属性を持っていたり、Bを上回る属性を持っていたり、Bと同じ記憶と人格と見た目を持っていたりする人物があるとき突然Aの前に現れたとしても、Aが共に時間を過ごしてきたのはそれらの人物ではなく、ほかならぬBなのです。
それゆえ愛は、「愛している」ということで実現されたり証明されたりするのではなく、時空上に連続する存在そのものを対象にして時間を過ごすこと、歴史を作ることそのものである、と言えるかもしれません。
分離の過程で、自分自身に固有の対象と関係を持つことで、その対象が存在することをもって自分自身が存在することとするという幻想が構築されるのでした。その自分自身に固有の対象を他者に差し出すことができれば愛は達成されるのではないかと最初に考えたのですが、それはやはり不可能であると私も考えます。ですが、持っている何かを差し出すことによって、時空的に連続している自分自身の存在を他者に向かって示すことは不可能ではないはずです。ここに、愛の可能性が開かれると思います。
ただ、ここにも同様に、同じものを差し出す別の人間が存在しうるという可能性が介入してきます。時空上に連続している自分自身の方を、全く同じものを差し出す別の人間と識別してもらえるのかという問題は残ります。でも、時空上に連続している存在そのものを相手に時間を過ごしてきたというその歴史は、変わることも失われることもありません。全人類の記憶が失われたり、人類が消滅したり、全ての記録媒体が失われたりしても、その歴史そのものがなくなるわけではありません。ここで言う歴史は誰かの記憶や、何らかの資料や記憶媒体に残された記述や記録のことではなく、現実の歴史そのものです。タイムマシンが開発されて、過去が書き換えられたとしても、その書き換え自体を含めて丸っと全部残るような歴史です。
記憶や記録が失われても、タイムマシンを使って過去が書き換えられても残るという歴史は、だから認識の対象になるようなものではありません。だからおそらく、愛は、認識の対象になったり、理性で理解できるようなことではないのだと思います。愛の証拠を求めたり、愛を実証したりすることはできないのです。愛は、意味の地平を突き抜けて、存在の方へと向かっていくものだからです。
愛は不可能ではないけれども、こうすれば愛は絶対に実現できるという確実性もないということになると思います。誰かのことを愛していると思っていたとしても、その対象が変わってしまったらそうでなくなってしまうかもしれない。誰かに愛されていると思っていたとしても、別の誰かに置き換えられてしまうかもしれない。誰かを愛するときも、誰かに愛されるときも、そうした可能性に常につきまとわれながら、これが愛でありますようにと祈ることしかできないのかもしれません。
◇愛の祈りのようなもの
愛依がツイスタに投稿したとき、ファンや視聴者に向けて言った言葉は「噂よりもステージを見てほしい。あたしはそこにいるから」でした。「見てほしい」という控えめな言葉に、私はこうした愛の祈りのようなものを感じ取ってしまいます。注意しなければならないのは、ここまでのこうした思考を、愛依もしていたということを言いたいわけではないということです。愛依が実際に何を考えていたかはともかく、イベントシナリオやsSSRのコミュで描かれていたことと語られていたことをもとに考えると、ここに愛の祈りのようなものを読み取りたくなる、ということです。
「見てほしい」と言ったその対象は「あたし」です。SNS上で取りざたされているように、愛依のステージ上での姿や、愛依の普段の姿といった、姿やイメージを特定することなく、それらすべてを包含しうるようなものとして、あるいはそれらから独立するものとして、「あたし」というものが提示されています。この「あたし」は愛依の存在そのものを示しているように思えます。そして愛依は、そんな「あたし」を、「見てほしい」と言うのです。「見てほしい」というのは、ただ見るということだけを求めているということです。ですから、ステージ上のクールでミステリアスな愛依の姿が本当であるとか、本当の普段の姿は陽気で気さくなキャラクターであるとか、そういうことを愛依の方から言うわけでもないし、そういう判断をファンや視聴者に求めたりもしないわけです。確かに愛依はステージ上での姿を作っていましたが、それもまた愛依自身なのであって、ステージ上の姿か普段の姿のどちらかを本当の姿として判断してもらうということ自体を避ける必要があるのです。それゆえ愛依が求めるのは、ただ「あたし」を「見てほしい」ということです。姿やイメージなどの属性ではなく、ましてや噂話などではなく、愛依そのものを見る、ということを求めるのです。
「見てほしい」というお願いは、さらに自分たちのことを正しく認識することを求めることもありません。自分たちをものまねやCGから区別して正しく認識することを求めたとしても、それらが本当に達成できるのかどうかは確証がありません。でも「見てほしい」というお願いは、ただ見るということをすれば、それは達成されます。そしてその見るということが行われたとき、その見るということが行われたという歴史が残るのです。
ここに、愛の可能性が開かれるのです。そしてそれは、ストレイライトに降りかかった問題を切り抜けていくために開かれた道でもあるのです。
◆5.シャニマスが描く存在論
◇ストレイライトからノクチルへ
ストレイライトに降りかかった問題から出発して、私自身の抱いている問題意識とラカンの疎外と分離の概念を経由して、さらに愛の問題について考えて、そうやって長い長い遠回りをしてやっと愛依とストレイライトが出した答えへとたどり着きました。注意していただけたらと思うのは、愛依をはじめとしてストレイライトの3人はこんなことを考えていたのだ!ということを言いたいわけでも、このイベントシナリオを書いた人はこんなことを考えていたのだ!ということを言いたいわけでもないということです。ただ、このイベントシナリオを読んで、私自身が抱いている問題意識との関連性を感じて、そこからラカンの概念などを補助線にしてイベントシナリオについて考えることができるのではないか、ということを考えたということです。
ラカンの疎外と分離の概念を持ち出したのは、大仰すぎるのではないか、大鉈をふるいすぎではないか、と思われたかもしれません。ですが、この概念を持ってくることによって、分かることがまだあると思っています。それは、ノクチルのことです。
「The Straylight」のイベントsSSR【いるっしょ!】の3つ目のコミュで、愛依の家で愛依の妹と弟たちにプライベートなステージを披露した後の場面が描かれています。愛依の家から帰り道でプロデューサーの迎えの車を待っているとき、寒がっているあさひに対して、ここをステージだと思って踊ってみようと愛依が持ち掛けます。あさひは乗り気になり冬優子を誘いますが、冬優子は断ります。そこで冬優子は「誰もいないステージで踊るアイドルがどこにいんのよ」と言いました。それに対して愛依は「ここにいるっしょ~!」と言い、あさひは「ふう~~~!」と楽しそうにしています。それを見て冬優子が笑います。この「誰もいないステージ」が、「あたしたちがいるところにステージはある」という愛依がツイスタに投稿した言葉の中にある「ステージ」の一つの実現なのです。誰もいないステージで踊っても、それを見る観客は誰もいません。でも愛依たちは踊る。そこにステージがある。そしてステージの上にこそ、愛依たちストレイライトはいるのです。意味に優位に立たれていた存在が、ここで意味を追い越して顔を見せるのです。誰が見ていなくても、愛依たちのいるところにステージがあり、愛依たちは、愛依たちこそがストレイライトである、と。ここにイベントシナリオ「The Straylight」が描き出す存在論を私は感じます。
ところで、私は冬優子が「誰もいないステージで踊るアイドルがどこにいんのよ」と言ったとき、すぐにノクチルのことを思い浮かべました。ノクチルは観客がほとんどいないような花火のステージで踊ったり、握手や写真を求めてくるような人がほとんどいないようなケーキ販売の仕事をしたり、アイドル運動会の仕事でカメラに映ることをやめたりしているからです。
◇ノクチルの輝き
ノクチルの仕事を振り返ってみましょう。最初にノクチルにやってきた仕事は、イベントシナリオ「天塵」で描かれた、ネット配信番組でのお仕事でした。その仕事でノクチルは、口パクを求められた上、浅倉透以外の3人を添え物のように扱われることになりました。そこで透たちは、求められた口パクをせず、番組側からの要求を拒否したのです。その仕事の様子が知れ渡ったノクチルは、しばらくの間仕事がなくなることになりました。その後プロデューサーが取って来た仕事は、花火大会でのステージでしたが、そこではほとんどの人は花火の方に注目しており、ノクチルのステージを見てくれる人はほとんどいませんでした。
ここには、番組側(アイドル業界側)からのアイドルとしての要求を拒否すると、誰にも見てもらえなくなる、という構図があります。でも、花火のステージをプロデューサーはしっかりと見ていました。そしてそのステージと、その後に海に飛び込んだノクチルの姿に、プロデューサーは特別な輝きを感じるのです。この輝きは、存在そのものの輝きであると、今の私は思います。
この存在そのものの輝きは、ノクチルの次のイベントシナリオ「海へ出るつもりじゃなかったし」でも描かれていると思います。透たち4人は、最初、プロデューサーから打診された地上波放送のアイドル運動会の仕事を断ります。冬休みの間の急な仕事の依頼だから断ってもいいとプロデューサーは言いましたが、地上波放送の仕事に出られるチャンスはめったにないのですから、テレビに映りたい、アイドルとして人にたくさん見られたい、という意欲があるならばその仕事を断らないはずです。でも透たちはそれを断るのです。急な仕事の依頼ですから、透たちは忙しかったり大事な用があったのかなと思えば、描かれる冬休みの透たちにはそんな様子はありません。普通に冬休みを過ごしています。
そしてその後、もう一度、ノクチルにアイドル運動会の仕事の依頼がやってきます。今度はその仕事を受けることになるのですが、それにも特別な理由があるわけではありません。で、そのアイドル運動会で、ノクチルは騎馬戦をすることになるのですが、プロデューサーに優勝してほしいと言われます。透たちはこの要求に対して乗り気になり、騎馬戦の練習をするようになります。本番当日も、テレビに映ることよりも、騎馬戦に勝つことを優先して、カメラを避けさえもします。結果として優勝することはできなかったのですが、ノクチルは最後の3組に残ることができました。が、実際の放送を見るとノクチルの映像は丸まるカットとなっていたのです。
ノクチルは今のところ、アイドルをやるということに特別な理由がありません。それにアイドルであるということに執着したりもしません。アイドルとしてカメラに映ることを求めていないのです。それでも、騎馬戦の練習をして、優勝するために本番で立ちまわったノクチルには、特別な輝きがありました。カメラには映っていない(放送されていない)、ノクチルの存在そのものの輝きです。
「海へ出るつもりじゃなかったし」で、年越しの瞬間に続いている夜の道のことを、透は「どこにもつながっていない道」だと言っています。この「どこにもつながっていない」というのは、ノクチルのことを示す言葉でもあるのではないか、と私は読みました。透たちがプロデューサーに仕事の依頼を断るためにメッセージの文面を考えるとき、敬語をどのように使えばいいのか悩んでいました。雛菜は「文章打つだけなのに上とか下とか大変だね~」と言っています。敬語は相手との関係の中で、必要に応じて用いられるものです。それゆえノクチルは、他の誰かに対して上とか下とかそういう関係を作っていないと言うことができると思います。アイドル運動会のお仕事当日でも、控室でほかのアイドルグループが熱心に交流(売り込みでもある)している中、ノクチルは誰とも交流しておらず、格上である中堅アイドルグループに対してかしこまったりもしませんでした。
このようにノクチルは、「どこにもつながっていない」のです。どこにもつながっておらず、いわば存在そのものがむき出しになっているようなものです。そこでノクチルは、光を放っています。その光は存在そのものの輝きです。
◇疎外の拒否
誰もいないステージで踊り、カメラを避けて放送されないアイドルであるノクチルと、誰もいない夜道をステージにして踊るストレイライトは、同じ場所にいるのではないか、と私は最初考えました。どちらも意味に対して存在が浮き出ていて存在論的なのではないか、と。
ですが今は、ちょっと違う、と考えています。それは、ストレイライトが疎外から分離を経て自分たちの存在の場所へと立ち戻ろうとしているのに対して、ノクチルはそもそも疎外を拒否しているのではないかと思うからです。
ネット配信の番組側から、アイドルとしてこういう風であってほしいと要求されますが、透たちはそれを拒否します。そしてその後に立つことができたステージは、見てくれる人がほとんどいませんでした。また、ノクチルはアイドルならば多くの者が出たいと願うはずの地上波放送のテレビ番組において、カメラを避けさえもします。そして実際に出演シーンは丸まるカットとなります。ノクチルはどこにもつながっていません。存在がむき出しになっています。ノクチルは疎外を拒否しているのです。
ラカンは、存在と意味の2択が突き付けられたとき、存在の方を選べば意味どころか存在さえも失うことになる、と言いました。存在そのものを、存在している!と有意味に言うことはできないからです。「この私が存在する!」と叫んだところで、それは有意味な言葉として聞き取られることはないのです。存在するということに意味を持たせるためには、何が存在しているのかということが言えるのでなければなりません。だから意味を選ばなければ、意味だけでなく存在も失ってしまうのです。
ノクチルは、この2択において意味を選ぶことを拒否しているのだと思います。番組や業界が求めるアイドルの姿を拒否し、テレビカメラにアイドルとして映ることも拒否する。そして何のためにアイドルをするのかとか、どんなアイドルになりたいのかということもありません。ノクチルは、意味の地平に乗っかっていないのです。その結果ノクチルに待っていたのは、誰も見ていないステージであり、出演シーン全カットでした。意味への疎外を拒否すれば、存在するということが言えなくなるのです。
でも、そこでノクチルは光を放っています。どこにもつながっておらず、認識してもらえない存在そのものが、光を放っているのです。「天塵」のラストで、ノクチルのその輝きを見たプロデューサーは、この輝きをどうすれば伝えることができるのかと自問していますが、これを人に伝えるのは至難の業だと思われます。果たしてプロデューサーはこのノクチルの輝きをどのようにしてプロデュースしていくのでしょうか。
ところで意味への疎外を拒否する、というのはノクチル自体だけでなく、透と円香にも見受けられます(小糸と雛菜は今のところ不明です)。透は、相手が言った隠喩的な表現に対して、隠喩的意味を素通りして文字通りの言葉を受け取ることがあります。ノクチルが初登場したコミュで、プロデューサーがアイドルのことを「虹をかける」と表現したのに対し、透は本当に文字通り虹をかけることができるのかを確かめようとしました。そして円香は、プロデューサーが言う言葉に対して警戒を怠らず、プロデューサーの言葉に乗せられたり、プロデューサーの言葉に円香自身が捕らえられることを避けようとします。そこで円香はプロデューサーの言葉にあるロジックの穴を突き付けるのです。
透は相手の隠喩的意味を素通りして言葉を文字通りに眺め、円香は相手の言葉を交わしてそのロジックを眺めます。透も円香も、相手の言葉の内部に入って行かないのです。ノクチルのライブアピールでの効果が「回避」であるのもここに繋がっているのではないか、と思います。回避はノクチルの特徴ですから、小糸と雛菜にも、それぞれ意味への疎外を拒否する態度があるのではないかと思って居るのですが、それが何であるのかはまだ分かっていません。
◇シャニマス3年目のテーマ
シャニマスの3年目は、テレビ番組や業界に求められるアイドルという姿への疎外と、疎外によって見えなくなってしまう存在の存在論を描いてきたのではないか、と考えたくなります。順に見ていきましょう。
まず4月の頭に、3年目のテーマソングとも言えそうな「シャイノグラフィ」と「Dye the sky.」の収録された「GR@DATE WING 01」が発売されました。「シャイノグラフィ」では、「この空をキャンバスにして/誰のでもない 瞬間を/新しく記していこう/光空記録(My shinography)」と歌っており、記録を残すことを表現しています。重要なのは、「誰のでもない」というところではないかと思います。他の誰でもなく、自分自身の記録だということです。
そして「Dye the sky.」では、写真に写った自分のことを「けど既に他人みたい/あの時の自分じゃない」と歌い、さらに「低解像度な偽物だ」とまで言います。強烈なのは「キャンバスを裂くように」という表現で、「Dye the sky.」は写真に写されたり絵に描かれたりすることを拒否する態度があるように思われます。つまり像にされることに対する拒否です。
◇ストーリー・ストーリー
そして4月の終わりにアンティーカの「ストーリー・ストーリー」がありました。このイベントシナリオでは、アンティーカがリアリティショーと呼ばれるジャンルの番組に出演することになります。アンティーカの5人が、決められた期間一つの家で暮らし、その様子を撮影して番組にする、というものです。この番組は視聴者に好評なら番組の期間が延長されるルールがあり、アンティーカの5人はそれを目指しました。番組として面白くするために霧子と摩美々と咲耶は様々な策を実行するのですが、どれも失敗してしまいます。そして面白い番組が成立しないと思われ、番組制作側に勝手にアンティーカメンバーが仲たがいするという嘘のストーリーを映像編集で作られてしまうのです。これに対してアンティーカの5人はショックを受けます。番組制作側の言い分はこうです。視聴者は面白い物語を求めているが、ただの生活が物語になるはずがない。面白い物語がなければ視聴者が満足しないから、だからアンティーカメンバーが仲たがいするという物語を作らせてもらった、というものでした。番組制作側によって勝手に作られた物語に、アンティーカは疎外されてしまっているわけです。
これに対して霧子が打開策を発案します。番組側に物語を作られてしまうなら、自分たちで物語を作った方がいいという策です。番組側が勝手に作る物語は、虚偽のアンティーカの姿を描きます。そこに本当のアンティーカの姿はありません。だからといって自分たちで物語を作ったとしても、製作側に勝手に編集されるリスクは消えません。でも勝手に編集されたとしても、自分たちで作った物語は嘘ではない物語ですから、本当のアンティーカはそこに残ります。霧子はその方がいいと考えました。そして残りの4人は霧子の提案した策に乗ることにするのです。霧子の策には、疎外に対してそれを拒否するのではなく、一旦それを受けいれた上で、自分たち自身から出てくるものによって自分たちを描こうとするという、分離の過程に相当するものを読み取ることができます。
ただ、自分たちで作りだすものとはいえそれは物語ですから、その物語に対して自分たちを合わせていかなければならない部分もあります。摩美々はそのことに敏感で、「カメラの外でも嘘じゃないストーリーにする」と言って、カメラに映らない家の外でもパンをくわえて走ろうとしたりします。ですが、これに対して霧子が答えて言います。「生きてることは……物語じゃ……ないから…… わたしたちがわたしたちなら……ほんとは……どこにも嘘なんて……」と。ここに存在論が現れています。生きるということはただ人間として存在するということで、それは物語ではないのです。物語には始まりと終わりがあって、面白かったりつまらなかったり感動的だったりしますが、生きるということはそういうものではありません。また、実在する人物や出来事を描いた物語なら、その物語は事実と一致しているかどうかという真偽の問題が発生しますが、ただ生きているということ、ただ存在しているということは意味の外部にあるのですから、真偽の問題の対象にはならないのです。
ですが、存在そのものは意味の外部ですから、それを言葉で捉えることはできないはずです。霧子はここで、言葉で捉えることができないはずのその存在そのものを、どうにか言い表そうとしています。それが、「わたしたちがわたしたちなら」という表現です。ここで言われている「わたしたち」は、愛依がツイスタに投稿した「あたし」に相当するものです。そしてその「わたしたち」が何であるかを言うために述語を結び付けるとき、何らかの属性を持ってくるのではなく、主語である「わたしたち」を反復するのです。「わたしたちがわたしたちなら」という表現は、「AはAである」という表現です。この同語反復的な文は、紛れもない真理ですが、情報量がなく意味がない文であるような気がしてしまいます。ですが無意味であるとも言い切れません。「~は…である」という、主語を説明する形式の文を使うことによって、主語「わたしたち」が何であるかということを説明するニュアンスが含まれます。そして、何であるかということを示すときに「わたしたち」を持ってくることで、それは「わたしたち」そのものであるという意味が発生するのです。これによって、「わたしたち」の輪郭線のようなものが浮かび上がるように思われます。その輪郭線が示すものは、「わたしたち」より大きくもなく小さくもなく、余計なものを付け足しているわけでもなく何かが足りないわけでもなく、「わたしたち」にぴったりと一致しています。つまりそれは「わたしたち」の存在そのものを示しているのです。このように主語を反復して述語として結びつけることによって、その存在そのものを言葉の上で指し示すニュアンスが込められるのではないかと思うのです。
◇カメラと写真と、存在
このように立て続けに存在論を描いたものがあり、6月末にノクチルのイベント「天塵」があります。そして12月末にノクチルの2つ目のイベント「海へ出るつもりじゃなかったし」があり、年が明けて1月末にストレイライトの「The Straylight」が続いています。
またその間に、注目するべきイベントが2つあります。ひとつは、5月末のイルミネーションスターズの「くもりガラスの銀曜日」です。これはくもりガラスを通して向こう側を見つめることが描かれています。ガラスはくもりガラスなので、向こう側にあるものをはっきり見ることはできないのですが、だからといって向こう側にあるものを見つめることを諦めたくはない、ということが語られます。くもりガラスを通して向こう側を見るというのは、レンズをのぞきこむカメラ的な所作です。レンズがくもりガラスになっているということは、カメラを通して見えるもの、写真に写るものは、対象の十全な像ではないということを示しているように思えます。でもだからといって、見ることを諦めたりはしない。これは意味や写真から逃れていく存在そのものに対する、カメラや写真の側からの決意と倫理的な態度であると言えるかもしれません。
そしてもうひとつは11月末の「明るい部屋」です。このイベントタイトルは明らかにロラン・バルトの写真論の本が由来になっており、イベントシナリオと写真がどのような関係にあるのかということは興味深い問題となっています。杜野凛世のイベントSSRのイラストも、窓をレンズに見立てたカメラの内部のような構図になっていて、カメラや写真を連想させます。これら2つのイベントはどちらもカメラや写真を思わせるものとなっており、「シャイノグラフィ」と「Dye the sky.」が3年目のテーマであることを考えるとき、これらのイベントも無視することはできません。
◇アイドルの存在論
シャニマスの3年目のテーマを、「シャイノグラフィ」と「Dye the sky.」という裏表のような2曲の歌とアンティーカの「ストーリー・ストーリー」に始まる、アイドルの存在論であると整理してみたくなります。それはカメラとの関係の中で、アイドルという意味と像へと疎外されることに対する存在の側の抵抗です。あるいは存在に対するカメラの側の倫理です。ストレイライトは疎外から分離へと進み、ノクチルははっきりとそれを拒絶するのです。
これらを通して、業界が求めて番組や広告に映し出すような、像や「商品」としての“アイドル”ではなく、アイドルをする者たちの存在そのものを、描いているように私には思えてくるのです。そして私のような、存在に関する問題意識を抱いている人間にとって、意味に優位に立たれてしまう存在を取り出してくれるということが、意味ではなく存在の方を描いてくれるということが、とてもとても嬉しいのです。
◆文献案内
ここまで文献からの引用などは行ってきませんでしたが、考えの背景や土台となっている文献や議論がありますのでそれらを紹介してこの文章を終わりたいと思います。
◇ラカンについて
ラカンの疎外と分離の概念は、ラカンの講義録(セミネール)の11巻を参照しています。16章と17章で主にその概念について語られています。
ジャック・ラカン,『精神分析の四基本概念』小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭訳,2000,岩波書店.
『精神分析の四基本概念』は2020年に文庫化されており、入手しやすくなっています。
ただ、いきなり『精神分析の四基本概念』を読むのはしんどいと思いますので、ラカン入門として次の3冊をご紹介します。
片岡一竹,2017,『疾風怒涛精神分析入門――ジャック・ラカン的生き方のススメ』誠信書房.
松本卓也,2015,『人はみな妄想する――ジャック・ラカンと鑑別診断の思想』青土社.
向井雅明,2016,『ラカン入門』ちくま学芸文庫.
片岡さんの『疾風怒涛精神分析入門』は、精神分析とはどういう営みなのかというところから紹介してくれており、精神分析自体が初めてという方におすすめできる本になっています。片岡さんご自身が精神分析を受ける経験をしており、その経験に基づいて書かれているところも良いところです。
松本さんの『人はみな妄想する』は、精神科医の観点から、神経症と精神病(それぞれ精神分析における診断カテゴリです)それぞれの構造を区別して理解することを目指した本になっています。神経症と精神病を分ける(鑑別する)ことが必要なのは、それぞれで治療の仕方が全く異なってくるからです。松本さんの記述はおそろしいほど分かりやすく整理されており、ラカンの概念や考え方を追うことができます。
3冊目は向井さんの『ラカン入門』です。この本は1988年に出版された『ラカン対ラカン』の増補改訂版です。ラカンの思想や概念を時代に沿って解説してくれいて、前期と後期との思想的な発展を理解する手助けとなってくれます。『精神分析の四基本概念』を開設した部分もあり、疎外と分離について段階を踏んで説明してくれています。
また、ラカンは「フロイトへの回帰」を掲げてフロイト読解として講義を始めた経緯があり、ラカンを読み理解するにあたってフロイトにまでさかのぼるというのは重要な手です。そこで主に重要になってくるのは、メタサイコロジー論と呼ばれる論文群です。メタサイコロジーというのは、精神の力動(意識と無意識のダイナミックな関係や運動)の理論です。文庫で読めるものをご紹介します。
ジークムント・フロイト,『メタサイコロジー論』十川幸司訳,2018,講談社学術文庫.
ジークムント・フロイト,『自我論集』竹田青嗣編,中山元訳,1996,ちくま学芸文庫.
『メタサイコロジー論』と『自我論集』は、重複している論文も入っていますが、どちらにも文庫で読める良さがあります。『メタサイコロジー論』は、1910年代にフロイトが出版を計画していたメタサイコロジー論集をまとめて読めるようにしたものとなっています。
『自我論集』の方は、フロイトがそれまでの自身の理論を更新することになった1920年の「快感原則の彼岸」と、その理論更新後のメタサイコロジーとも言える「自我とエス」が読めるのが良いところです。
◇愛の問題について
愛の対象となっているのは、存在ではなく属性に過ぎないのではないかという問題は、次の論文での議論が下敷きになっています。(私と同じ属性を持つ人間がいたら、その人物は私に成り代わってしまうのではないかという問題もまた次のクロートの論文で扱われていますが、この問題それ自体は私個人から出て来たものです。)
ロバート・クロート,「ウォルターはサンドラを本当に愛しているのか?」永井均訳,1989,『現代思想』17(7): 74-91.
またこのクロートの議論は、固有名の名指しの議論が背景になっています。その代表的なものが次のクリプキの著作です。
ソール・クリプキ,『名指しと必然性――様相の形而上学と心身問題』八木沢敬・野家啓一訳,1985,産業図書.
またこのクリプキの『名指しと必然性』は、バートランド・ラッセルの議論を批判したものとなっています。
バートランド・ラッセル,「指示について」清水義夫訳,1986,『現代哲学基本論文集』勁草書房: 45-78.
ラッセルは「指示について」で、記述理論と呼ばれる考えを展開しています。ラッセルによれば、固有名は属性の束であり、属性をひとつずつ拾い上げていくことで1人の人物を特定することができます。
クリプキの『名指しと必然性』はこの記述理論を批判しています。もしラッセルの記述理論が正しいとしたら、「哲学者にならなかったソクラテス」のような固有名に関する反実仮想的な文を考えることができなくなってしまうからです。現実にソクラテスは哲学者ですが、もしかしたらソクラテスは哲学者にならなかったかもしれませんし、戦争に行かなかったかもしれません。哲学者にならなかったとしても、戦争に行かなかったとしても、ソクラテスはソクラテスに違いありません。ですから、哲学者であるとか、従軍経験があるとか、そういった諸性質はソクラテスという固有名にとって本質的な属性ではないのです。
この記述理論に対するクリプキの批判が、愛の対象が属性であったらそれは愛であると言えるのかというクロートの愛の議論と対応するわけです。
この愛の問題は、次の永井均の著作でも取り上げられて議論されています。
永井均,2007,『翔太と猫のインサイトの夏休み』ちくま学芸文庫.
時空上の連続性という概念も永井均によります。でもこの概念を直接教わったのは入不二基義先生からでした。愛の問題に関しては入不二基義先生の指導で卒論を書いたときに学んだことがたくさんあるので、どの著作からと特定できない源泉がたくさんあります。
*Privatterの投稿は削除済み
ここだけの話、伏せ字ツイートの最後に♡を入れると、伏せ字の○がぜんぶ♡になるという隠し機能があるよ……
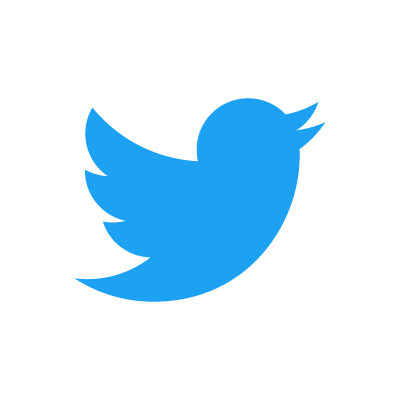 元ツイート
元ツイート