一次創作・恋愛小説『佐渡那奈と恋愛マスター!』
1話『斎と那奈』です。どなたでもご覧いただけます。
文字数:10,447字
1話『斎と那奈』です。どなたでもご覧いただけます。
文字数:10,447字
<1.斎と那奈>
「ゲームセット!ウォンバイ・紫電、6-2!」
審判のコールが会場に響く。陽を浴びて青紫色に輝く髪が、ガッツポーズでさらりと揺れた。
「よっし!!」
「よっしゃあーー!!」
「いいぞ!いいぞ!紫電!!」
「紫電!紫電!!」
観客たちの歓声が木霊する。テニスコート上の相手は悔しそうに顔を歪めながらも、対戦相手に敬意を示して、互いに握手を交わした。青地に黒のユニフォームに身を包み、観客に向かってラケットを掲げる紫電 斎(しでん いつき)は、観客の応援に感謝しながら、きょろきょろと辺りを見渡した。紫電の黒い髪が、陽の光を浴びてわずかに青紫色に見える。紫電は視線を彷徨わせ、目的の人を見つけると、ぱっと顔を輝かせた。
その視線の先には、ひとりの少女。紺色の髪をまとめ、手にしたスケッチブックへ一心不乱に何かを描いている。ふと、少女が顔をあげると、紫電に向かって満面の笑顔を向けた。
「斎くん!!」
その声が、紫電にはっきり聞こえた。紫電は大好きな彼女の笑顔に、つられて自分も笑顔を返した。
春の東京都。高校テニスの地区大会で、紫電 斎は難なく勝利をおさめた。
紫電の所属する市立清音(せいおん)高校は、テニス部の実力はまだまだ伸び盛りだが、2年生にしてエースの紫電の実力は頭ひとつ抜きん出ていた。スピードもスタミナも申し分なく、正確に打ち込まれるショットに相手は次第に疲弊し、スタミナ切れをおこしていく。今日の試合も、相手は汗だくにも関わらず、紫電は涼しい顔をしていた。
コートを降りてベンチに座り、紫電はチームメイトからスポーツドリンクをもらう。それを飲みながら、先ほどのスケッチブックを持った紺色の髪の少女に視線を向けた。
少女は視線を感じて、紫電の方を見る。少女は再び笑顔を向けて、口の動きで言葉を伝えた。
(おめでとう、斎くん!)
紫電はその言葉ににっと笑って、口を動かした。
(ありがとう、那奈)
紫電 斎と少女、佐渡 那奈(さわたり なな)は、恋人同士である。
+
「はぁ~あ……斎はいいよね、那奈と仲良しで」
ある日の清音高校。2年B組の教室で、明神 八雲(みょうじん やくも)は机に突っ伏した。前の席に座る紫電がため息をつく。
「またダメだったのか?」
「ダメっていうか……タイミングが悪かった……」
明神が黒いくせ毛の頭をがっくりと垂れる。この明神には好きな女子がいる。奥津城 千穂(おくつき ちほ)という同い年の幼馴染だ。明神は高校1年の冬から奥津城に告白しようと機を伺っているのだが、毎回失敗しているうちにずるずると高校2年に進学してしまっていた。その失敗も、たいていは告白しようとして周囲の環境に邪魔されているというもので、ここまでくるといっそこいつは一生告白できないのかもしれない、と紫電は内心でため息をついた。
「お前はいつもタイミングを伺うよな。ヘタにカッコつけるより、ストレートに言った方が絶対いいって」
「そうは言うけどさあ……そういうことできるの斎だけだよ……言う方はめちゃめちゃ緊張するんだからさ……」
「まあ心の準備が要るのはわかるけどな……」
いつもこんなやりとりを繰り返している。あまり機を伺って心を削るのも明神の心身によくない、早く決着がつけられればいいのに。そう思いながら、紫電は明神のくせ毛をぽんぽんと撫でた。
「まあ、諦めずにやってこうな。今日はオフだから、今日こそチャレンジしてみなよ」
「ううう……」
明神はのそりと起き上がって、帰り支度をする。今日は部活も休みの日、みんな早めに帰れる日だ。紫電も帰り支度を整えると、少し離れた席から佐渡が歩み寄ってきた。
「八雲くん、またダメだったの?」
「やっほー那奈……いろいろダメだったよ……」
「八雲くんも大変だねえ。今度こそ、うまくいくといいね」
「ありがと……ねえ、斎と那奈って、なんでそんなに仲がいいの?」
紫電と佐渡は、きょとんと明神に視線を向けた。
「中2の頃から付き合ってたよね?もう付き合って3年?学生の恋愛にしては、びっくりするくらい長続きしてるじゃん。ケンカとかしなかったの?」
明神の素朴な疑問に、紫電と佐渡は互いに顔を見合わせた。そして、ふたりでふふっと笑った。
「そりゃあ、ケンカもしたさ。けどそれ以上に、俺は那奈が好きだからな」
「私も、斎くんが大好きだから。ケンカもしたけど、ちゃんと仲直りしてるんだよ」
それを聞くと、明神はぐでり、と椅子の上で溶けた。
「はぁ~うらやましい……」
「はいはい。じゃあな八雲、お先に。がんばれよ」
「がんばってね八雲くん!応援してるよ!!」
「ありがとぉ……」
紫電と佐渡はふたり並んで、教室をあとにした。その背中に手を振って、明神は一人呟いた。
「……ぼくもがんばらなきゃなあ」
+
校門を出て、曲がり角に差し掛かる。紫電はいつものように、佐渡と一緒に帰路についていた。
「昨日の大会、いい成績でよかったね!」
佐渡がうれしそうに笑いかける。佐渡はいつもご機嫌だ。その機嫌よさそうな笑顔に、紫電もつられて笑顔になった。
「そうだな。次の大会も絶対勝つ」
「大将戦、惜しかったねえ。神堂部長もがんばったけど、やっぱり雪月さんは強いや」
「ああ、神堂さんもすごい人だけどな。北辰(ほくしん)の雪月さんは世界で戦えるくらい強い人だ、一筋縄じゃいかないんだよな」
「絶対負けられない相手だよね。がんばらないと!」
佐渡はまるで自分のことのように意気込んだ。彼女は美術部でテニスはからっきしだが、自分も一緒に戦っている気になっているらしい。清音高校のテニス部長・神堂 亮介と、昨日の試合の対戦相手だった私立北辰高校のテニス部長・雪月 哲也。部長同士の一騎打ちだったが、清音高校は僅差で敗れた。雪月はスポーツ雑誌にたびたび取り上げられるほどの注目選手である。並大抵の努力で勝てる相手ではないが、だからこそ挑み甲斐があるのだった。
「今度こそ、リベンジしたいね!」
「ああ、本当に」
全身に力をこめる佐渡を見て、紫電はふふっと笑う。角を曲がって少し歩くと、後ろから声をかけられた。
「やあ、ちょっといいかな」
自分たちのことかと思い、紫電と佐渡が振り返る。そこには、自分たちに視線を向ける、ふたりの男子高校生の姿があった。
片方は、西欧圏のような整った顔立ちに金色の髪、柔和な雰囲気を持った高校生。もう片方は鋭い目つきの厳格な雰囲気を醸し出す高校生。紫電と佐渡は、厳格な生徒を見てはっとした。昨日の大会で戦ったばかりの、雪月 哲也本人だった。金髪の生徒も、記憶に新しい。同じ北辰高校のテニス部員だ。
「北辰の、雪月さん!?と、あなたは……」
「こうやって話すのは初めてだね。僕は待宵(まつよい)スバル。突然ごめんね、君たちに用事があって」
「私たちに用事、ですか?」
「そうなんだ、この哲也がね。君たちにどうしても尋ねたいことがあって」
待宵が手で指す雪月は、少し緊張したような面持ちをしていた。紫電と佐渡は高校2年生、相手の2人は3年生。ひとつ上の先輩だ。その先輩たちが、自分たちになんの用だろう。
「とりあえず、場所を変えよう。どこか喫茶店に入ろうか。付き合ってもらってもいいかな。時間、大丈夫?」
「は、はい。大丈夫です。お供します」
「私も、いいんですか?」
「うん。君たちふたりがいいんだ」
頷くと、待宵は近くの喫茶店へ案内した。紫電と佐渡はついていきながら、互いに顔を見合わせた。
+
待宵は席につくと、紫電と佐渡に飲み物を勧めた。連れ回しているのはこちらだから、代金は自分たちが持つと言い、佐渡にはケーキも勧めた。ふたりは遠慮したが、待宵たちに「奢るから、先輩の顔を立てて」と言われると断れず、お礼を言いながら飲み物とケーキをいただいた。
コーヒーや紅茶、佐渡のチーズケーキが運ばれてくると、待宵は話を切り出した。
「さて、君たちに用事がある、ということなんだけど……
実はね、君たちのこと、北辰でウワサになってるんだ」
「えっ?」
「ウワサ……ですか?」
紫電と佐渡はふたりで驚く。待宵は続けた。
「うん。君たちの中学時代のクラスメイトが北辰に進学していてね、彼の話したことが北辰で広まっているんだ。
なんでも、君たちは中学2年の頃から今もずっと付き合っていて、とても仲がいいと。
そして、中学の頃は恋愛に関して相談事も承っていて、それがけっこう好評だったと聞いているよ」
「あ、あー……」
紫電はなるほど、と内心頷いた。
紫電と佐渡の仲の良さは、中学時代でも評判だった。学生の恋愛は1年続けば長持ちする方だが、紫電と佐渡は表立ってケンカもせず、いつもふたり仲良く寄り添っていた。
その姿が評判を呼び、いつしか中学校の生徒たちが紫電と佐渡に恋愛相談を持ちかけるようになっていた。その恋愛相談はたしかに好評で、不思議なほどいろいろな生徒から相談を受けたことをふたりは覚えている。中にはこうして、他校から相談にやってくる生徒もいたほどだった。
「……たしかに、いろんな人から相談はいただいていました。といっても、俺たちだってただの学生です。役に立てたかはわかりませんけど……」
「そうだよね。でも、その彼曰く、君たちが相談に乗ってくれたおかげで、好きな人と気持ちが結ばれたり、たとえ実らなくても前向きになれたりと、いろいろな人が君たちに感謝しているという話だったよ」
「そうなんですねえ。それならよかったんですけど……でも私たち、そんなに大したこと、してなくて」
「君たちにとっては、そうかもしれない。でも、中学の頃から付き合い始めて、今も関係が続いているなんて、すごいことだと思うよ。
で……君たちにとっては飽き飽きしているかもしれないんだけど、この雪月 哲也の相談にも、乗ってほしいと思っているんだ」
「雪月さん、ですか?」
紫電と佐渡は驚いて雪月の方を見る。雪月は緊張しているようで、少し視線を泳がせていた。
「そうなんだ。ほら哲也、お膳立てはしたよ。あとは自分で言う」
「う、うむ……」
雪月は待宵に急かされて、だいぶ固い声を出した。どうやら、かなり緊張しているらしい。紫電はその気持ちを察すると、自分から切り出した。
「雪月さんにも、好きな人がいるんですね」
「……ああ。同じ北辰の……テニス部の、マネージャーだ」
「マネージャーさん……お名前は?」
「……佐倉 絢(さくら あや)という。隣のクラスの、女子生徒だ」
「同じ学年なんですね」
紫電は佐渡に視線を向けた。佐渡も頷いた。ふたりとも、このやや堅物な部長の相談に乗りたいという気持ちで固まっていた。それを互いに確認し、本格的に相談に乗ることにした。
「わかりました。じゃあまず、佐倉さんについて、わかる範囲でいいので教えてください」
「ああ、助かる」
「ごめんね、ありがとう」
「いえいえ!困った時はお互い様ですよ」
佐渡がそう言って笑うと、雪月は少し緊張を和らげたようだった。
「まず、佐倉さんとの出会いは、いつからですか?」
「高1の春、テニス部に入った時に初めて顔を合わせた。最初は、部員とマネージャーという立場だった」
「なるほど。その時は、部員とマネージャーとして交流していた感じですか?」
「ああ、そうだ。北辰は部員が多く、その分仕事も多かったが、彼女は文句ひとつ言わずよく働いた。部員たちのデータをまとめるのも上手く、頭の回転の速い女性だと感じた」
「ふむふむ……お仕事はきっちりされる方なんですね」
「ああ、彼女の仕事は俺も信頼している。部員たちも、同じ気持ちだ」
「きちんとした仕事をしてくれる人は貴重ですよね。俺も中学の頃、テニス部にマネージャーさんいましたけど、本当によくサポートしてくれました」
「ああ、彼女の仕事には感謝している」
佐倉の話をする雪月の表情は、あまり変わらないように見えて、その実とてもうれしそうに見えた。その表情を見て、紫電もそっと微笑んだ。
「雪月さんが、佐倉さんを好きだな、と感じたのは、どういう時でしたか?」
紫電がそう聞くと、雪月は少し考えた。
「……そうだな……いつしか……気が付けば、彼女を目で追うようになっていた気がする。
佐倉が他の男子生徒に告白されていると聞いた時に、どうにも心が乱れてやまなかった。それをこの待宵に相談したら……それは恋というものではないか、と」
「この哲也、今まで勉強とテニスばかりで、恋をしたことがないんだって。佐倉さんが初恋なんだってさ。
だから自分でそういう自覚もなくて、自覚した今もどうしていいかわからないみたいなんだよね」
「初恋……ステキですねえ」
きゃー、と小さく声をもらしながら、佐渡は両手を頬にあてる。厳格な印象のある雪月だが、その容姿は割と整っている方である。こんなにカッコいい人に好かれる佐倉さんは幸せ者だなあ。佐渡は幸せな気持ちになった。
「うん、本当に。ステキなことだと思います。
佐倉さんが男子生徒に告白されたってことですけど、佐倉さんは断ったんですか?」
「そうみたいだよ。僕から彼女に聞いてみたんだけれど、今は恋愛をしている余裕はない、と言っていてね」
「なるほど……」
紫電も佐渡も頷いた。学業や部活の忙しさに流されて、いつしか恋愛をする余裕がなくなってしまう。高校生なら、よくある話である。
「じゃあ、雪月さんが今回、俺たちに相談したいと思ったのは、どういうことが気になっている感じですか?」
紫電が聞くと、雪月は視線を落とした。
「……お前たちにとっては、ありきたりな答えかもしれないが……
もしも断られてしまった時、どう気持ちを立て直せばよいものかと、思ってな……」
その答えに、紫電と佐渡はゆっくりと頷いた。
「……そうですよね。勇気が要りますよね」
「うんうん。相手の気持ちもありますし、断られたら、って思うと、怖いですよねえ」
「ああ。……テニスの時と違い、どうにも踏ん切りがつかない……俺自身の、弱さなのだろうか」
少し落ち込んだように、雪月がそう言葉をこぼす。その様子を見て、紫電は口を開いた。
「じゃあ、雪月さん。今からちょっと、難しい質問をします」
「む?」
雪月は少し身を引き締める。紫電は、質問を投げかけた。
「雪月さんは、仮に佐倉さんに告白して、もしそれを受け入れてもらえて気持ちが結ばれたら、どんな関係でありたいですか」
雪月は、少し目を見開いた。紫電が続ける。
「たとえば俺なら、一言で言えば『那奈とずっと一緒にいたい』と思っています。
俺は、那奈が好きです。那奈はいつも機嫌がよくて、自分の幸せを他人に分けることができる。そんな那奈の優しさが好きです。
那奈はその優しさで、たびたび俺を癒してくれました。だから俺も、那奈に自分の好きな気持ちをたくさん伝えて、ふたりで幸せになりたい。そう思っています。
……雪月さんは、佐倉さんと恋人になったら、どんなことがしたいですか。
映画館に行きたいとか、カフェに行きたい、水族館に行きたい、こんなデートがしたい、こんな風に一緒にいたい。その具体的なイメージを、言葉にしたら、どうなりますか」
雪月はそれを聞き、じっくりと考えた。思ってもいなかった質問だった。もし、もしも自分が佐倉と結ばれたら。自分は、何がしたいだろうか。
雪月はじっくり考えて、やがて、口を開いた。
「……佐倉と……絢とふたりで、同じものが見たい。
俺は、何かを学ぶことが好きだ。やはり俺は堅物なのだろう、ただ漫然と生きるより、常に何かを学んで生きていたい、そう思っている。
そして彼女も、あの仕事熱心で頭のいい彼女なら、俺と一緒に同じものを見てくれる、そう思っている……
水族館や博物館などにふたりで行って、展示品の前で話をしたい。展示を見終わってカフェに行って、ふたりで感想を言い合ったり、そんな付き合いが、したい」
雪月は絞り出すように、ゆっくりと言葉を紡いだ。紫電と佐渡は、その言葉を最後まで聞き届けた。そして、ふたりで頷いた。
「いいですねえ、ステキなことですね」
「ああ、本当に。
雪月さん。今言ってくれたその気持ちが、雪月さんの本心です。雪月さんが本当に、佐倉さんを好きだと思う気持ち。
まずはその気持ち、人を好きになった自分を、大切にしてほしいと思います。
人を好きになる気持ち、恋というものは自分に本当の余裕がないと持てない気持ちです。
誰かを好きになることができた、それは充分、称賛に値します。まずは、人を好きになれた自分をほめてあげてほしいです」
「うんうん!そうですね。踏ん切りがつかない自分に焦ったりするかもしれませんけど、それは相手の気持ちもちゃんと考えてあげられているからこそのものです」
「俺たち学生というのは、まだまだ子供です。まだまだワガママな子供です。どうしても自分のことばかり先立って、相手のことをなかなか考えられないことが多いです。
自分が認められたい、自分の気持ちを通したい、相手を自分のものにしたい。自分中心に考えがちです。だからほとんどの人は、さっきの俺の質問に答えることができないんですよ。
でも、雪月さんはそうじゃない。佐倉さんと一緒に幸せな時間を過ごしたいと考えている。自分だけじゃなくて、相手のことをきちんと思っている。
当たり前のように感じるかもしれませんけど、それはとてもすごいことなんです。まずはその気持ちを、素直に受け止めて、大事にしてほしいと思います」
紫電と佐渡の言葉が、雪月の心の中にすとん、すとんと落ちていく。焦る気持ちが音を立てて消えていく。
自分が本当に、心から佐倉が好きだという気持ちを、からかわずに真剣に受け止めてくれる。たったそれだけのことだが、雪月にとってはそれが何よりもうれしかった。
「そうして自分の気持ちを大事にしたうえで、今言ってくれた気持ちを、佐倉さんにそのままストレートに伝える。それで充分だと思います。
俺たち子供は、言葉に酔いがちです。カッコいい言葉を並べ立てて、それが本心だと思い込みがちです。カッコつけた自分こそが本物だと思いがちです。
でも、そんなものはニセモノだと、相手にはすぐにわかります。それでは、本当の気持ちは伝わらない。
飾らず、素直に、気持ちを伝えてください。自分の気持ちを素直に受け止めて、大事にすることができれば、自然と気持ちを伝えたくなります。
難しいことですけど、雪月さんなら絶対できます。テニスだって、カッコつけてるやつはだいたい弱いじゃないですか。
ストイックで飾らない雪月さんなら、絶対に大丈夫です。
あとは、佐倉さんの気持ち次第。でも雪月さんが全力であたれば、佐倉さんだってきっと真剣に考えてくれます。
お互いに本気で出した答えなら、自然と受け入れられるものです。大丈夫。自分に自信を持ってください」
紫電は雪月をまっすぐ見据えて、そう言った。雪月はその言葉を、ひとつひとつ、胸におさめた。飾らず、素直に。ありのままの自分でいい。紫電と佐渡が心から応援してくれるその気持ちに触れて、雪月は心に力が満ちるような心地を覚えた。自分を受け入れてくれたような気がした。雪月は目の前の後輩の存在に、心から感謝した。
「……ああ。ありがとう。憑き物が落ちたような気分だ……
明日、絢に告白しよう。結果は必ず伝える。絢の気持ち次第だが……お前に相談する前とは違い、たとえ絢の気持ちに添えなくても、前を向けるような気がしている。
それは諦めのようなものではないことも、わかる。明日、絢に告白することで、きっと俺自身も、人間として一歩成長できる。そんな気がしている」
晴れやかに微笑んで、雪月はそう言った。その表情に、紫電も佐渡もうれしそうに笑った。
「役に立てたならよかったです!」
「がんばってください!!応援してますね!!」
「ああ、感謝する」
雪月と紫電は、互いに握手を交わす。その様子を、待宵はどこかうれしそうに見ていた。
+
翌日。北辰高校、昼休み。雪月は人気のない資料室に佐倉を呼び出した。
「……雪月さん、本日はどうされました。このような人気のないところに……」
濃いブラウンの長い髪を耳にかけて、佐倉は尋ねた。雪月は内心、心臓が高鳴って仕方がなかったが、意を決して言葉をかけた。
「突然このようなことを言って、お前を困らせるかもしれない。
だが……お前に、伝えたいことがある」
「……?はい、なんでしょう」
佐倉はきょとんとしている。雪月は佐倉の顔をまっすぐに見て、言った。
「佐倉 絢。俺は―――お前が、好きだ」
「…………!」
佐倉は、はっと息を呑んだ。
「俺は……お前と、絢と、恋仲になりたい。
俺は絢と、ふたりで、同じものが見たい。ふたりで、同じ気持ちを共有して―――ともに、すごしたい。
……お前の気持ちは、いかがだろうか。正直に、教えてほしい」
佐倉は大きく目を見開いて、両手で口をおさえていた。
「……本当、に?」
「ああ。……二言はない」
「……………………」
佐倉はしばらく驚いていた。しかし、やがて状況を理解すると、その大きな瞳からぽろり、ぽろりと涙がこぼれた。
「あ、絢?!」
雪月はぎょっとして、咄嗟にハンカチを差し出した。佐倉はすみません、と何度か謝って、涙を拭いながら言った。
「す、すみません……あの、まさか雪月さんから、そのようにおっしゃっていただけるなんて……思っても、いなくて……」
「す、すまない……やはりその……嫌だった、だろうか」
「そ、そのようなことは!!」
佐倉は雪月の言葉を、全力で否定した。
「あ、あの、私……雪月さんを好きだと思ってから、この恋は絶対に叶わないと思っていて……!」
「…………!」
「雪月さんは勉学にテニスに、常に全力でいらっしゃって、恋をするヒマなどないだろうと思っておりました。
私も、あなたが好きです。でも、雪月さんの努力の邪魔をしたくなくて……そのまま卒業まで、持って行こうと思って……」
「……そうだったか……」
雪月はそっと、佐倉の背中を撫でた。佐倉も、自分に寄り添ってくれた。恋焦がれた人物が、自分の胸におさまるように寄り添ってくれる。うれしさのあまり泣き出してしまった佐倉には申し訳ないと思ったが、雪月にとっては、望外の喜びだった。
「ありがとう。感謝する。俺のような堅物に目をかけてくれたこと。……気持ちを受け入れてくれたこと。至上の喜びだ。この気持ちは、何にも代えがたい……
絢。改めて言おう。……俺と、付き合ってくれるだろうか」
雪月が、手を差し出す。佐倉はその手を、喜んでとった。
「―――はい!喜んで!!」
佐倉はそう言って、満面の笑みを浮かべた。その笑顔は雪月にとって、生まれて初めて見た、何よりも美しいと感じる笑顔だった。
+
その日の放課後。部活を終えた帰り、雪月と佐倉はふたり並んで帰路についていた。
「……哲也さん。本日は、本当にありがとうございました。
今こうして、あなたと一緒にいられるのが、夢のようです」
そう言って、佐倉は笑いかける。固い表情の多い雪月も、想いの通じた恋人の前では柔らかく微笑んだ。
「ああ、俺もだ。ありがとう、絢。
……実を言うと、お前に気持ちを伝えるまでに、かなり悩んでな……ウワサになっていた清音のふたりに頼ったくらいなのだ」
「清音の?……というと、校内でウワサになっている、あの?」
「ああ、紫電と佐渡だ。紫電斎は先日も、大会で顔を合わせただろう。清音の2年エース。中学2年次から佐渡と付き合い、今も良好な関係を続けている……」
「まあ……そうだったのですね。……うふふ、なんだかうれしいです」
「む……そうか?少し、みっともない話だったかもしれないが……」
「そんなことはありませんよ。他校の生徒に頼ってでも、私に気持ちを伝えようとしてくださったのです。うれしいに決まっておりますとも。
自分にウソをついて逃げた私の方が、よっぽどみっともないです」
佐倉は心から、うれしそうに笑う。美しい笑顔が、自分のために向けられている。それが雪月にとっては、今まで味わったことのないような幸福であった。
「……そのようなことはない。俺を想ってくれたその気持ちは、尊く、美しく、ありがたいものだ」
「うふふ……ありがとうございます。
では、あのおふたりにはお礼を言わなければなりませんね」
「ああ。メッセージの連絡先はもらっている、取り急ぎメッセージで伝えるが……近いうちに必ず会って、直接礼を言おう」
「はい、お供します」
佐倉がそっと、雪月の手に自分の手を絡める。雪月はその手をとって、ふたり手をつないで帰路についた。
夕焼けを浴びて、歩道に影が映る。ふたり仲良く歩道を往く、歩み始めの影だった。
+
夜。雪月からメッセージを受けた紫電と佐渡は、寝る前に電話で話していた。
『雪月さん、よかったねえ!お付き合いできるようになって!』
「ああ、めでたいことだよ。今度、お祝いしに行こうか」
『行く行く!!雪月さんなら、きっとずっと、佐倉さんを大事にしてくれるよね』
「ああ、俺もそう思う。ふふ、これからあのふたりとは、テニスだけじゃない付き合いになりそうだな」
『だねえ!えへへっ、私までうれしくなっちゃった』
「那奈は本当に、いつもゴキゲンだな」
『えへへー、人の幸せを浴びると私も幸せになる~』
「お前のものも俺のもの、的な?」
『それは違う~!!』
冗談めかして言うと、佐渡が笑いながら抗議する。そのふざけたやりとりもおもしろくて、電話越しにふたりで笑いあった。
『ねえ、斎くん』
「うん?」
『私も、斎くんのこと、大好きだよ!』
佐渡は素直にそう言った。紫電の瞼の裏に、大好きな彼女の笑顔が容易に浮かんでくるのだった。
「ああ、俺も。那奈、大好きだよ。ありがとう」
『えへへっ!うれしい!!』
「ふふ。じゃあ、そろそろ寝ようか」
『うんっ!今日はいい夢が見れそう』
「いつもだろ」
『そのとおり!!』
「ふふっ……おやすみ、那奈」
『うん!おやすみ!また明日ね!!』
「ああ、また明日」
そっと電話を切る。スマートフォンの電源を切りながら、紫電は耳に残る彼女の声の余韻を感じて、ふっと幸せそうに笑った。
「ゲームセット!ウォンバイ・紫電、6-2!」
審判のコールが会場に響く。陽を浴びて青紫色に輝く髪が、ガッツポーズでさらりと揺れた。
「よっし!!」
「よっしゃあーー!!」
「いいぞ!いいぞ!紫電!!」
「紫電!紫電!!」
観客たちの歓声が木霊する。テニスコート上の相手は悔しそうに顔を歪めながらも、対戦相手に敬意を示して、互いに握手を交わした。青地に黒のユニフォームに身を包み、観客に向かってラケットを掲げる紫電 斎(しでん いつき)は、観客の応援に感謝しながら、きょろきょろと辺りを見渡した。紫電の黒い髪が、陽の光を浴びてわずかに青紫色に見える。紫電は視線を彷徨わせ、目的の人を見つけると、ぱっと顔を輝かせた。
その視線の先には、ひとりの少女。紺色の髪をまとめ、手にしたスケッチブックへ一心不乱に何かを描いている。ふと、少女が顔をあげると、紫電に向かって満面の笑顔を向けた。
「斎くん!!」
その声が、紫電にはっきり聞こえた。紫電は大好きな彼女の笑顔に、つられて自分も笑顔を返した。
春の東京都。高校テニスの地区大会で、紫電 斎は難なく勝利をおさめた。
紫電の所属する市立清音(せいおん)高校は、テニス部の実力はまだまだ伸び盛りだが、2年生にしてエースの紫電の実力は頭ひとつ抜きん出ていた。スピードもスタミナも申し分なく、正確に打ち込まれるショットに相手は次第に疲弊し、スタミナ切れをおこしていく。今日の試合も、相手は汗だくにも関わらず、紫電は涼しい顔をしていた。
コートを降りてベンチに座り、紫電はチームメイトからスポーツドリンクをもらう。それを飲みながら、先ほどのスケッチブックを持った紺色の髪の少女に視線を向けた。
少女は視線を感じて、紫電の方を見る。少女は再び笑顔を向けて、口の動きで言葉を伝えた。
(おめでとう、斎くん!)
紫電はその言葉ににっと笑って、口を動かした。
(ありがとう、那奈)
紫電 斎と少女、佐渡 那奈(さわたり なな)は、恋人同士である。
+
「はぁ~あ……斎はいいよね、那奈と仲良しで」
ある日の清音高校。2年B組の教室で、明神 八雲(みょうじん やくも)は机に突っ伏した。前の席に座る紫電がため息をつく。
「またダメだったのか?」
「ダメっていうか……タイミングが悪かった……」
明神が黒いくせ毛の頭をがっくりと垂れる。この明神には好きな女子がいる。奥津城 千穂(おくつき ちほ)という同い年の幼馴染だ。明神は高校1年の冬から奥津城に告白しようと機を伺っているのだが、毎回失敗しているうちにずるずると高校2年に進学してしまっていた。その失敗も、たいていは告白しようとして周囲の環境に邪魔されているというもので、ここまでくるといっそこいつは一生告白できないのかもしれない、と紫電は内心でため息をついた。
「お前はいつもタイミングを伺うよな。ヘタにカッコつけるより、ストレートに言った方が絶対いいって」
「そうは言うけどさあ……そういうことできるの斎だけだよ……言う方はめちゃめちゃ緊張するんだからさ……」
「まあ心の準備が要るのはわかるけどな……」
いつもこんなやりとりを繰り返している。あまり機を伺って心を削るのも明神の心身によくない、早く決着がつけられればいいのに。そう思いながら、紫電は明神のくせ毛をぽんぽんと撫でた。
「まあ、諦めずにやってこうな。今日はオフだから、今日こそチャレンジしてみなよ」
「ううう……」
明神はのそりと起き上がって、帰り支度をする。今日は部活も休みの日、みんな早めに帰れる日だ。紫電も帰り支度を整えると、少し離れた席から佐渡が歩み寄ってきた。
「八雲くん、またダメだったの?」
「やっほー那奈……いろいろダメだったよ……」
「八雲くんも大変だねえ。今度こそ、うまくいくといいね」
「ありがと……ねえ、斎と那奈って、なんでそんなに仲がいいの?」
紫電と佐渡は、きょとんと明神に視線を向けた。
「中2の頃から付き合ってたよね?もう付き合って3年?学生の恋愛にしては、びっくりするくらい長続きしてるじゃん。ケンカとかしなかったの?」
明神の素朴な疑問に、紫電と佐渡は互いに顔を見合わせた。そして、ふたりでふふっと笑った。
「そりゃあ、ケンカもしたさ。けどそれ以上に、俺は那奈が好きだからな」
「私も、斎くんが大好きだから。ケンカもしたけど、ちゃんと仲直りしてるんだよ」
それを聞くと、明神はぐでり、と椅子の上で溶けた。
「はぁ~うらやましい……」
「はいはい。じゃあな八雲、お先に。がんばれよ」
「がんばってね八雲くん!応援してるよ!!」
「ありがとぉ……」
紫電と佐渡はふたり並んで、教室をあとにした。その背中に手を振って、明神は一人呟いた。
「……ぼくもがんばらなきゃなあ」
+
校門を出て、曲がり角に差し掛かる。紫電はいつものように、佐渡と一緒に帰路についていた。
「昨日の大会、いい成績でよかったね!」
佐渡がうれしそうに笑いかける。佐渡はいつもご機嫌だ。その機嫌よさそうな笑顔に、紫電もつられて笑顔になった。
「そうだな。次の大会も絶対勝つ」
「大将戦、惜しかったねえ。神堂部長もがんばったけど、やっぱり雪月さんは強いや」
「ああ、神堂さんもすごい人だけどな。北辰(ほくしん)の雪月さんは世界で戦えるくらい強い人だ、一筋縄じゃいかないんだよな」
「絶対負けられない相手だよね。がんばらないと!」
佐渡はまるで自分のことのように意気込んだ。彼女は美術部でテニスはからっきしだが、自分も一緒に戦っている気になっているらしい。清音高校のテニス部長・神堂 亮介と、昨日の試合の対戦相手だった私立北辰高校のテニス部長・雪月 哲也。部長同士の一騎打ちだったが、清音高校は僅差で敗れた。雪月はスポーツ雑誌にたびたび取り上げられるほどの注目選手である。並大抵の努力で勝てる相手ではないが、だからこそ挑み甲斐があるのだった。
「今度こそ、リベンジしたいね!」
「ああ、本当に」
全身に力をこめる佐渡を見て、紫電はふふっと笑う。角を曲がって少し歩くと、後ろから声をかけられた。
「やあ、ちょっといいかな」
自分たちのことかと思い、紫電と佐渡が振り返る。そこには、自分たちに視線を向ける、ふたりの男子高校生の姿があった。
片方は、西欧圏のような整った顔立ちに金色の髪、柔和な雰囲気を持った高校生。もう片方は鋭い目つきの厳格な雰囲気を醸し出す高校生。紫電と佐渡は、厳格な生徒を見てはっとした。昨日の大会で戦ったばかりの、雪月 哲也本人だった。金髪の生徒も、記憶に新しい。同じ北辰高校のテニス部員だ。
「北辰の、雪月さん!?と、あなたは……」
「こうやって話すのは初めてだね。僕は待宵(まつよい)スバル。突然ごめんね、君たちに用事があって」
「私たちに用事、ですか?」
「そうなんだ、この哲也がね。君たちにどうしても尋ねたいことがあって」
待宵が手で指す雪月は、少し緊張したような面持ちをしていた。紫電と佐渡は高校2年生、相手の2人は3年生。ひとつ上の先輩だ。その先輩たちが、自分たちになんの用だろう。
「とりあえず、場所を変えよう。どこか喫茶店に入ろうか。付き合ってもらってもいいかな。時間、大丈夫?」
「は、はい。大丈夫です。お供します」
「私も、いいんですか?」
「うん。君たちふたりがいいんだ」
頷くと、待宵は近くの喫茶店へ案内した。紫電と佐渡はついていきながら、互いに顔を見合わせた。
+
待宵は席につくと、紫電と佐渡に飲み物を勧めた。連れ回しているのはこちらだから、代金は自分たちが持つと言い、佐渡にはケーキも勧めた。ふたりは遠慮したが、待宵たちに「奢るから、先輩の顔を立てて」と言われると断れず、お礼を言いながら飲み物とケーキをいただいた。
コーヒーや紅茶、佐渡のチーズケーキが運ばれてくると、待宵は話を切り出した。
「さて、君たちに用事がある、ということなんだけど……
実はね、君たちのこと、北辰でウワサになってるんだ」
「えっ?」
「ウワサ……ですか?」
紫電と佐渡はふたりで驚く。待宵は続けた。
「うん。君たちの中学時代のクラスメイトが北辰に進学していてね、彼の話したことが北辰で広まっているんだ。
なんでも、君たちは中学2年の頃から今もずっと付き合っていて、とても仲がいいと。
そして、中学の頃は恋愛に関して相談事も承っていて、それがけっこう好評だったと聞いているよ」
「あ、あー……」
紫電はなるほど、と内心頷いた。
紫電と佐渡の仲の良さは、中学時代でも評判だった。学生の恋愛は1年続けば長持ちする方だが、紫電と佐渡は表立ってケンカもせず、いつもふたり仲良く寄り添っていた。
その姿が評判を呼び、いつしか中学校の生徒たちが紫電と佐渡に恋愛相談を持ちかけるようになっていた。その恋愛相談はたしかに好評で、不思議なほどいろいろな生徒から相談を受けたことをふたりは覚えている。中にはこうして、他校から相談にやってくる生徒もいたほどだった。
「……たしかに、いろんな人から相談はいただいていました。といっても、俺たちだってただの学生です。役に立てたかはわかりませんけど……」
「そうだよね。でも、その彼曰く、君たちが相談に乗ってくれたおかげで、好きな人と気持ちが結ばれたり、たとえ実らなくても前向きになれたりと、いろいろな人が君たちに感謝しているという話だったよ」
「そうなんですねえ。それならよかったんですけど……でも私たち、そんなに大したこと、してなくて」
「君たちにとっては、そうかもしれない。でも、中学の頃から付き合い始めて、今も関係が続いているなんて、すごいことだと思うよ。
で……君たちにとっては飽き飽きしているかもしれないんだけど、この雪月 哲也の相談にも、乗ってほしいと思っているんだ」
「雪月さん、ですか?」
紫電と佐渡は驚いて雪月の方を見る。雪月は緊張しているようで、少し視線を泳がせていた。
「そうなんだ。ほら哲也、お膳立てはしたよ。あとは自分で言う」
「う、うむ……」
雪月は待宵に急かされて、だいぶ固い声を出した。どうやら、かなり緊張しているらしい。紫電はその気持ちを察すると、自分から切り出した。
「雪月さんにも、好きな人がいるんですね」
「……ああ。同じ北辰の……テニス部の、マネージャーだ」
「マネージャーさん……お名前は?」
「……佐倉 絢(さくら あや)という。隣のクラスの、女子生徒だ」
「同じ学年なんですね」
紫電は佐渡に視線を向けた。佐渡も頷いた。ふたりとも、このやや堅物な部長の相談に乗りたいという気持ちで固まっていた。それを互いに確認し、本格的に相談に乗ることにした。
「わかりました。じゃあまず、佐倉さんについて、わかる範囲でいいので教えてください」
「ああ、助かる」
「ごめんね、ありがとう」
「いえいえ!困った時はお互い様ですよ」
佐渡がそう言って笑うと、雪月は少し緊張を和らげたようだった。
「まず、佐倉さんとの出会いは、いつからですか?」
「高1の春、テニス部に入った時に初めて顔を合わせた。最初は、部員とマネージャーという立場だった」
「なるほど。その時は、部員とマネージャーとして交流していた感じですか?」
「ああ、そうだ。北辰は部員が多く、その分仕事も多かったが、彼女は文句ひとつ言わずよく働いた。部員たちのデータをまとめるのも上手く、頭の回転の速い女性だと感じた」
「ふむふむ……お仕事はきっちりされる方なんですね」
「ああ、彼女の仕事は俺も信頼している。部員たちも、同じ気持ちだ」
「きちんとした仕事をしてくれる人は貴重ですよね。俺も中学の頃、テニス部にマネージャーさんいましたけど、本当によくサポートしてくれました」
「ああ、彼女の仕事には感謝している」
佐倉の話をする雪月の表情は、あまり変わらないように見えて、その実とてもうれしそうに見えた。その表情を見て、紫電もそっと微笑んだ。
「雪月さんが、佐倉さんを好きだな、と感じたのは、どういう時でしたか?」
紫電がそう聞くと、雪月は少し考えた。
「……そうだな……いつしか……気が付けば、彼女を目で追うようになっていた気がする。
佐倉が他の男子生徒に告白されていると聞いた時に、どうにも心が乱れてやまなかった。それをこの待宵に相談したら……それは恋というものではないか、と」
「この哲也、今まで勉強とテニスばかりで、恋をしたことがないんだって。佐倉さんが初恋なんだってさ。
だから自分でそういう自覚もなくて、自覚した今もどうしていいかわからないみたいなんだよね」
「初恋……ステキですねえ」
きゃー、と小さく声をもらしながら、佐渡は両手を頬にあてる。厳格な印象のある雪月だが、その容姿は割と整っている方である。こんなにカッコいい人に好かれる佐倉さんは幸せ者だなあ。佐渡は幸せな気持ちになった。
「うん、本当に。ステキなことだと思います。
佐倉さんが男子生徒に告白されたってことですけど、佐倉さんは断ったんですか?」
「そうみたいだよ。僕から彼女に聞いてみたんだけれど、今は恋愛をしている余裕はない、と言っていてね」
「なるほど……」
紫電も佐渡も頷いた。学業や部活の忙しさに流されて、いつしか恋愛をする余裕がなくなってしまう。高校生なら、よくある話である。
「じゃあ、雪月さんが今回、俺たちに相談したいと思ったのは、どういうことが気になっている感じですか?」
紫電が聞くと、雪月は視線を落とした。
「……お前たちにとっては、ありきたりな答えかもしれないが……
もしも断られてしまった時、どう気持ちを立て直せばよいものかと、思ってな……」
その答えに、紫電と佐渡はゆっくりと頷いた。
「……そうですよね。勇気が要りますよね」
「うんうん。相手の気持ちもありますし、断られたら、って思うと、怖いですよねえ」
「ああ。……テニスの時と違い、どうにも踏ん切りがつかない……俺自身の、弱さなのだろうか」
少し落ち込んだように、雪月がそう言葉をこぼす。その様子を見て、紫電は口を開いた。
「じゃあ、雪月さん。今からちょっと、難しい質問をします」
「む?」
雪月は少し身を引き締める。紫電は、質問を投げかけた。
「雪月さんは、仮に佐倉さんに告白して、もしそれを受け入れてもらえて気持ちが結ばれたら、どんな関係でありたいですか」
雪月は、少し目を見開いた。紫電が続ける。
「たとえば俺なら、一言で言えば『那奈とずっと一緒にいたい』と思っています。
俺は、那奈が好きです。那奈はいつも機嫌がよくて、自分の幸せを他人に分けることができる。そんな那奈の優しさが好きです。
那奈はその優しさで、たびたび俺を癒してくれました。だから俺も、那奈に自分の好きな気持ちをたくさん伝えて、ふたりで幸せになりたい。そう思っています。
……雪月さんは、佐倉さんと恋人になったら、どんなことがしたいですか。
映画館に行きたいとか、カフェに行きたい、水族館に行きたい、こんなデートがしたい、こんな風に一緒にいたい。その具体的なイメージを、言葉にしたら、どうなりますか」
雪月はそれを聞き、じっくりと考えた。思ってもいなかった質問だった。もし、もしも自分が佐倉と結ばれたら。自分は、何がしたいだろうか。
雪月はじっくり考えて、やがて、口を開いた。
「……佐倉と……絢とふたりで、同じものが見たい。
俺は、何かを学ぶことが好きだ。やはり俺は堅物なのだろう、ただ漫然と生きるより、常に何かを学んで生きていたい、そう思っている。
そして彼女も、あの仕事熱心で頭のいい彼女なら、俺と一緒に同じものを見てくれる、そう思っている……
水族館や博物館などにふたりで行って、展示品の前で話をしたい。展示を見終わってカフェに行って、ふたりで感想を言い合ったり、そんな付き合いが、したい」
雪月は絞り出すように、ゆっくりと言葉を紡いだ。紫電と佐渡は、その言葉を最後まで聞き届けた。そして、ふたりで頷いた。
「いいですねえ、ステキなことですね」
「ああ、本当に。
雪月さん。今言ってくれたその気持ちが、雪月さんの本心です。雪月さんが本当に、佐倉さんを好きだと思う気持ち。
まずはその気持ち、人を好きになった自分を、大切にしてほしいと思います。
人を好きになる気持ち、恋というものは自分に本当の余裕がないと持てない気持ちです。
誰かを好きになることができた、それは充分、称賛に値します。まずは、人を好きになれた自分をほめてあげてほしいです」
「うんうん!そうですね。踏ん切りがつかない自分に焦ったりするかもしれませんけど、それは相手の気持ちもちゃんと考えてあげられているからこそのものです」
「俺たち学生というのは、まだまだ子供です。まだまだワガママな子供です。どうしても自分のことばかり先立って、相手のことをなかなか考えられないことが多いです。
自分が認められたい、自分の気持ちを通したい、相手を自分のものにしたい。自分中心に考えがちです。だからほとんどの人は、さっきの俺の質問に答えることができないんですよ。
でも、雪月さんはそうじゃない。佐倉さんと一緒に幸せな時間を過ごしたいと考えている。自分だけじゃなくて、相手のことをきちんと思っている。
当たり前のように感じるかもしれませんけど、それはとてもすごいことなんです。まずはその気持ちを、素直に受け止めて、大事にしてほしいと思います」
紫電と佐渡の言葉が、雪月の心の中にすとん、すとんと落ちていく。焦る気持ちが音を立てて消えていく。
自分が本当に、心から佐倉が好きだという気持ちを、からかわずに真剣に受け止めてくれる。たったそれだけのことだが、雪月にとってはそれが何よりもうれしかった。
「そうして自分の気持ちを大事にしたうえで、今言ってくれた気持ちを、佐倉さんにそのままストレートに伝える。それで充分だと思います。
俺たち子供は、言葉に酔いがちです。カッコいい言葉を並べ立てて、それが本心だと思い込みがちです。カッコつけた自分こそが本物だと思いがちです。
でも、そんなものはニセモノだと、相手にはすぐにわかります。それでは、本当の気持ちは伝わらない。
飾らず、素直に、気持ちを伝えてください。自分の気持ちを素直に受け止めて、大事にすることができれば、自然と気持ちを伝えたくなります。
難しいことですけど、雪月さんなら絶対できます。テニスだって、カッコつけてるやつはだいたい弱いじゃないですか。
ストイックで飾らない雪月さんなら、絶対に大丈夫です。
あとは、佐倉さんの気持ち次第。でも雪月さんが全力であたれば、佐倉さんだってきっと真剣に考えてくれます。
お互いに本気で出した答えなら、自然と受け入れられるものです。大丈夫。自分に自信を持ってください」
紫電は雪月をまっすぐ見据えて、そう言った。雪月はその言葉を、ひとつひとつ、胸におさめた。飾らず、素直に。ありのままの自分でいい。紫電と佐渡が心から応援してくれるその気持ちに触れて、雪月は心に力が満ちるような心地を覚えた。自分を受け入れてくれたような気がした。雪月は目の前の後輩の存在に、心から感謝した。
「……ああ。ありがとう。憑き物が落ちたような気分だ……
明日、絢に告白しよう。結果は必ず伝える。絢の気持ち次第だが……お前に相談する前とは違い、たとえ絢の気持ちに添えなくても、前を向けるような気がしている。
それは諦めのようなものではないことも、わかる。明日、絢に告白することで、きっと俺自身も、人間として一歩成長できる。そんな気がしている」
晴れやかに微笑んで、雪月はそう言った。その表情に、紫電も佐渡もうれしそうに笑った。
「役に立てたならよかったです!」
「がんばってください!!応援してますね!!」
「ああ、感謝する」
雪月と紫電は、互いに握手を交わす。その様子を、待宵はどこかうれしそうに見ていた。
+
翌日。北辰高校、昼休み。雪月は人気のない資料室に佐倉を呼び出した。
「……雪月さん、本日はどうされました。このような人気のないところに……」
濃いブラウンの長い髪を耳にかけて、佐倉は尋ねた。雪月は内心、心臓が高鳴って仕方がなかったが、意を決して言葉をかけた。
「突然このようなことを言って、お前を困らせるかもしれない。
だが……お前に、伝えたいことがある」
「……?はい、なんでしょう」
佐倉はきょとんとしている。雪月は佐倉の顔をまっすぐに見て、言った。
「佐倉 絢。俺は―――お前が、好きだ」
「…………!」
佐倉は、はっと息を呑んだ。
「俺は……お前と、絢と、恋仲になりたい。
俺は絢と、ふたりで、同じものが見たい。ふたりで、同じ気持ちを共有して―――ともに、すごしたい。
……お前の気持ちは、いかがだろうか。正直に、教えてほしい」
佐倉は大きく目を見開いて、両手で口をおさえていた。
「……本当、に?」
「ああ。……二言はない」
「……………………」
佐倉はしばらく驚いていた。しかし、やがて状況を理解すると、その大きな瞳からぽろり、ぽろりと涙がこぼれた。
「あ、絢?!」
雪月はぎょっとして、咄嗟にハンカチを差し出した。佐倉はすみません、と何度か謝って、涙を拭いながら言った。
「す、すみません……あの、まさか雪月さんから、そのようにおっしゃっていただけるなんて……思っても、いなくて……」
「す、すまない……やはりその……嫌だった、だろうか」
「そ、そのようなことは!!」
佐倉は雪月の言葉を、全力で否定した。
「あ、あの、私……雪月さんを好きだと思ってから、この恋は絶対に叶わないと思っていて……!」
「…………!」
「雪月さんは勉学にテニスに、常に全力でいらっしゃって、恋をするヒマなどないだろうと思っておりました。
私も、あなたが好きです。でも、雪月さんの努力の邪魔をしたくなくて……そのまま卒業まで、持って行こうと思って……」
「……そうだったか……」
雪月はそっと、佐倉の背中を撫でた。佐倉も、自分に寄り添ってくれた。恋焦がれた人物が、自分の胸におさまるように寄り添ってくれる。うれしさのあまり泣き出してしまった佐倉には申し訳ないと思ったが、雪月にとっては、望外の喜びだった。
「ありがとう。感謝する。俺のような堅物に目をかけてくれたこと。……気持ちを受け入れてくれたこと。至上の喜びだ。この気持ちは、何にも代えがたい……
絢。改めて言おう。……俺と、付き合ってくれるだろうか」
雪月が、手を差し出す。佐倉はその手を、喜んでとった。
「―――はい!喜んで!!」
佐倉はそう言って、満面の笑みを浮かべた。その笑顔は雪月にとって、生まれて初めて見た、何よりも美しいと感じる笑顔だった。
+
その日の放課後。部活を終えた帰り、雪月と佐倉はふたり並んで帰路についていた。
「……哲也さん。本日は、本当にありがとうございました。
今こうして、あなたと一緒にいられるのが、夢のようです」
そう言って、佐倉は笑いかける。固い表情の多い雪月も、想いの通じた恋人の前では柔らかく微笑んだ。
「ああ、俺もだ。ありがとう、絢。
……実を言うと、お前に気持ちを伝えるまでに、かなり悩んでな……ウワサになっていた清音のふたりに頼ったくらいなのだ」
「清音の?……というと、校内でウワサになっている、あの?」
「ああ、紫電と佐渡だ。紫電斎は先日も、大会で顔を合わせただろう。清音の2年エース。中学2年次から佐渡と付き合い、今も良好な関係を続けている……」
「まあ……そうだったのですね。……うふふ、なんだかうれしいです」
「む……そうか?少し、みっともない話だったかもしれないが……」
「そんなことはありませんよ。他校の生徒に頼ってでも、私に気持ちを伝えようとしてくださったのです。うれしいに決まっておりますとも。
自分にウソをついて逃げた私の方が、よっぽどみっともないです」
佐倉は心から、うれしそうに笑う。美しい笑顔が、自分のために向けられている。それが雪月にとっては、今まで味わったことのないような幸福であった。
「……そのようなことはない。俺を想ってくれたその気持ちは、尊く、美しく、ありがたいものだ」
「うふふ……ありがとうございます。
では、あのおふたりにはお礼を言わなければなりませんね」
「ああ。メッセージの連絡先はもらっている、取り急ぎメッセージで伝えるが……近いうちに必ず会って、直接礼を言おう」
「はい、お供します」
佐倉がそっと、雪月の手に自分の手を絡める。雪月はその手をとって、ふたり手をつないで帰路についた。
夕焼けを浴びて、歩道に影が映る。ふたり仲良く歩道を往く、歩み始めの影だった。
+
夜。雪月からメッセージを受けた紫電と佐渡は、寝る前に電話で話していた。
『雪月さん、よかったねえ!お付き合いできるようになって!』
「ああ、めでたいことだよ。今度、お祝いしに行こうか」
『行く行く!!雪月さんなら、きっとずっと、佐倉さんを大事にしてくれるよね』
「ああ、俺もそう思う。ふふ、これからあのふたりとは、テニスだけじゃない付き合いになりそうだな」
『だねえ!えへへっ、私までうれしくなっちゃった』
「那奈は本当に、いつもゴキゲンだな」
『えへへー、人の幸せを浴びると私も幸せになる~』
「お前のものも俺のもの、的な?」
『それは違う~!!』
冗談めかして言うと、佐渡が笑いながら抗議する。そのふざけたやりとりもおもしろくて、電話越しにふたりで笑いあった。
『ねえ、斎くん』
「うん?」
『私も、斎くんのこと、大好きだよ!』
佐渡は素直にそう言った。紫電の瞼の裏に、大好きな彼女の笑顔が容易に浮かんでくるのだった。
「ああ、俺も。那奈、大好きだよ。ありがとう」
『えへへっ!うれしい!!』
「ふふ。じゃあ、そろそろ寝ようか」
『うんっ!今日はいい夢が見れそう』
「いつもだろ」
『そのとおり!!』
「ふふっ……おやすみ、那奈」
『うん!おやすみ!また明日ね!!』
「ああ、また明日」
そっと電話を切る。スマートフォンの電源を切りながら、紫電は耳に残る彼女の声の余韻を感じて、ふっと幸せそうに笑った。
伏せ太のLINEスタンプ販売中。スタンプショップ内を「伏せ太」で検索してね
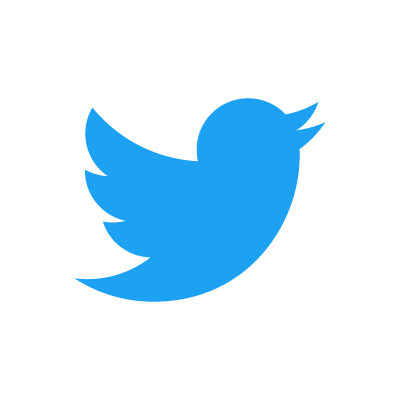 元ツイート
元ツイート